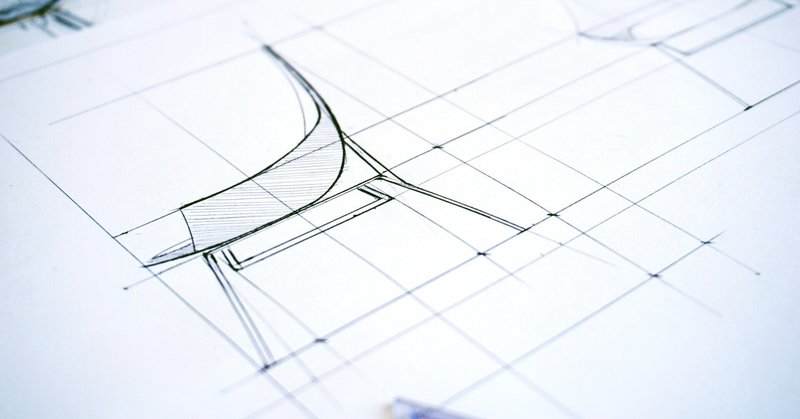
mignを創業した経緯
原風景としての幼少期

母が画家だったこともあり、デザインに小さいころから興味がありました。
小学生のころ、建築家の黒川紀章さんの作品の特集をテレビで見たときに、スケールが大きくて美しいものを世界中でつくっていくことに携わりたいと感じるようになりました。
小学校の卒業文集にも将来は建築家になりたいと書いた覚えがあります。(恥ずかしくて言えませんでしたが当時の第一希望はプロ野球選手でした)
建築・都市・土木を学んだ学生時代

高校卒業後は芸大の建築学科に入りたいと思っていましたが、合格できず、浪人をすることになりました(いま思うとデッサンや模型作成の技術が全く足りていませんでした)。
結局、芸大には進学できませんでしたが、学部は土木、大学院は都市計画、ダブルスクールの専門学校で建築を学びました。

歴代の巨匠のように大学教授をやりながら建築事務所を主宰するような働き方をしたいと思い、博士課程に進みました。
博士課程では、建築・土木領域のデータ解析をつかった研究内容で博士号を取得しました。
起業のきっかけだった虚無感

大学院での学術研究が起業のきっかけでした。
大学院の修士課程、博士課程では学位取得のために論文執筆や学会発表の研究成果が求められ、心配性のぼくは、普通の学生より数倍速いスピードで研究成果を上げることに全てを注いでいました。
結果として、博士課程修了までに審査付論文10本以上、国際会議論文等その他の研究成果を30本以上を発表しました。
修士課程のうちから建設系分野で有名な国際学術誌に論文が掲載され、都市計画学会や地理情報学会での論文賞、工学系研究科博士課程副代表修了などの受賞等をしました。
しかし、全くというほどに満足感を得られず、常に虚無感を感じていました。
自分の研究成果は、狭い分野の専門家のみに評価され、誰かの役に立っていると感じられなかったからです。
修士課程の2年目から自分の研究活動に疑問を感じ、研究内容をいろいろと変化させながら、どうにか社会の役に立つことができないか、試行錯誤しましたが、大御所と言われる教授の方々に、君は何がしたいんだ、一つの分野に絞って研究を深めなさい、と咎められるのみで、自分の研究が社会の役に立っているということが実感できないまま博士課程を修了しました。
大学の研究者としての身分だと、いろんな制約があり、誰かの役に立つ、社会をより良くすることに純粋に関わりにくいと感じたことが、起業のきっかけです。
日本の大学の研究者の評価(KPI)は論文の数や質に概ね依存し、人事も大学内の研究者によって決定されることによって、本来、社会に貢献するというベクトル(≒GDP向上)に、学術研究が少しずれてしまっていることが問題です。
ぼくはそれらの制約に縛られない身分として、純粋に社会をより良くすることに取り組みたいと思い、株式会社(mign・マイン)を創業しました。
大学院にいたときから博士課程修了後の前職の大学助教をつとめて退職するまで、いくつかテストで事業を立ち上げつつ、ずっと準備していました。
組織としての目標

mignの創業にあたり、近い将来の目標と、少し遠い将来の目標があります。
近い将来の目標は、ぼくがこれまで長く学んで好きだった建築・土木領域を中心としてグローバルなスケールで学術界との連携を図りつつ最先端の技術を導入していくこと、そしてそれをぼく(経営者)が何もしなくても再現し、自律的にリスクを回避しつつ、成長し続けることができる組織(PERが無限大に近い組織)をつくることです。
少し遠い将来の目標は、世界の人々の生活を豊かにすること、自分の贔屓チームであり、小さい頃から両親が重い病で働けない中でも生活を支えてくれ、わがままなほどにぼくに勉強をする機会を与えていただけた日本や荒川区をより良くすることです。
他社はマーケットを取り合う競合と言われつつも社会をより良くしていくチームだと思っています。
人類の生活は300万年前にチンパンジーと種を分岐してから、多くの人々の協力と効率化によって、ますます豊かになっています。
かつてはがんばって狩りをして捉えた獲物が、いまではスーパーで食べやすく加工された上で売っているどころか、年配の方や病気などの方にも社会保障によって働かずとも生活できる社会になっています。
今後、ほとんど働かずとも生活できる社会に近づいていくはずなので、競合企業を含めたみなさまと切磋琢磨しながら、餓死や戦争がない社会に近づくことに貢献したいです。
最後に

mignの意味の一つはMinecraftです。
専門性のない小さい子供が楽しんで家やまちをつくっているところを見て、とても感動しました。
ぼくが小さいころに感じた家づくり、まちづくりの憧れや楽しさを、一緒にサービスをつくるメンバーや、サービスのユーザーと共に感じながら、成長していきたいと思います。
まだまだ勉強不足で未熟者ですが、応援していただけるとうれしいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
