
今週末はこれを使え!〜BG Adventureパーフェクトガイド〜
2020/02/04追記
この記事は元々2019年のGP名古屋のフォーマットだった当時のスタンダードについて書いた有料記事でしたが、禁止改訂や新弾の発売で当時から環境が大きく変わった現在では旬が過ぎた内容になっているので無料で公開させていただきます。
他に公開している有料記事はこれ以上の文量、情報量で書かせていただいてるので有料部分の内容が気になって購入するか悩んでいるという方はまずこちらを参考にして頂けると助かります。
また今後書く記事に関しては公開後に価格を変更する予定はありませんが、情報の性質上旬が過ぎたと思われるものや、需要が少なくなったものに関してはこちらの判断で変更する場合がございます。ご了承ください。
※編注 この記事は10/21日の禁止改訂以前に執筆されたものになります。《死者の原野》禁止以前の環境を中心に話していますが、基本的な動きやノウハウは変わらないのでほぼ原文のまま掲載しています。購入の際はご了承ください。
また、追記に新環境版の最新リストを載せてありますのでそちらも参考にしていただけますと幸いです。
はじめに
初めまして。SWDと申します。
まずは簡単な自己紹介から。5年ほど前からマジックを始め、現在は石川でMagicOnlineやMTGArenaを中心に、日々PT権利の獲得を目指しているしがない競技プレイヤーです。
今回は、今週末(10/27〜28)に行われるアリーナMC予選、及び11/1~3日に開催されるGP名古屋に向けて現在進行形で調整しているBGアドベンチャー(以下BG)の戦略記事を書いていきます。
はじめに、筆者は特別公式で結果を残しているプレイヤーではなく、普段からスタンダードを熱心にプレイしているわけでもない、せいぜいMOPTQでいつも一勝が足りずトップ8に残れない程度の実力であることは前提に置いてください。
そんな自分ですが、一つのデッキタイプを回し続け理解度を深めていくことには自信があります。実際に2週間ほどこのデッキだけを使い続けた結果、特に苦戦することなくミシックランクに到達でき、プラチナ帯からスプレッドシートに記録してきたランクマッチでの勝率は70%越えを維持できています。

スタンダードの大型イベントが複数控える中、国内の戦略記事(特にサイドボードガイド)が足りないと感じているプレイヤーは多いのではないでしょうか。(自分もその中の一人です)
というわけでせっかくならばと言語化の練習も兼ねて、今回の調整で得たノウハウを共有したいと思い筆を取った次第です。
この記事では、BO3をBGで通算100マッチ以上プレイしてきた自分の現在のリストとサイドインアウト、各マッチアップに対するプランニングなどに触れていきます。詳細な分、長い内容になりますがよろしくお願いします。
また、今回は試験的に前半のメインデッキの解説を無料、後半のサイドボードの解説やマッチアップガイドの部分を有料として公開させていただきます。
前半部分を読んでこのデッキに興味を持ったり、よりこのデッキを理解したいと感じたら是非記事を購入していただけると幸いです。
現在のデッキリスト
さて、前置きが長くなってしまったが、現在自分が使用しているリストは以下のものとなる。メタゲームに応じて細かなカード選択など改善の余地はあると思うが、同アーキタイプの構成としてオススメできることは確かだ。

MPL所属のプロプレイヤーであるkanisterことPiotr GlogowskiがMC5に持ち込んだリストが原型となっているが、現在のアリーナのメタゲームに合わせて細かな調整を施してある。メインボードで特筆すべき点は、主に《むかしむかし》の不採用と、《アーク弓のレインジャー、ビビアン》の採用だろう。
こちらについても追々解説していくが、そもそも多種多様なデッキが存在する現在のスタンダード環境で、なぜわざわざBGを選ぶのか?について話したいと思う。BGの強みは大きく分けて3つほどある。
それは
・手が付けられないほどのブン回りが存在する
・トップメタの二種に対して強い
・サイドボードの潤沢さ
の3点だ。順に説明していく。
まずはブン回りについてだ。言うまでもなく《エッジウォールの亭主》絡みのドロー連鎖によるものだが、特に序盤から2体以上並んだ時の動きはすさまじく、相手の全体除去から即座に復帰することも容易な程だ。
しかしながら特定のキーカードに依存した構築というわけではなく、マナカーブに沿ってパワーカードを連打していくミッドレンジとしても成立しているのがこのリストの強みで、従来型の《幸運のクローバー》等を採用したコンボチックなリストとの明確な違いだろう。
次に、トップメタの二種に強い点。
現在のスタンダード環境は5cゴロスとシミックフードの2強環境と言われているが、BGはその2種のデッキに対して五分〜微有利ほどの相性があると感じている。
ゴロスには2種の回避能力付き速攻クリーチャーでゾンビの群れを乗り越えてライフを削りにいくプランが成立しやすいし、シミックにはスタッツに優れた生物群とメインサイドで都合7枚採用されている《残忍な騎士》と《害悪な掌握》によってPWマウントを取られづらい。
例えば赤単アグロは序盤の干渉手段が少ないゴロス相手には圧倒的な勝率を叩き出すかもしれないが、食物トークンや《ハイドロイド混生体》のライフゲイン、盤面の支配に優れた《意地悪な狼》要するシミックには覆せない相性差があるだろう。軸が違うこの2種のデッキに対してどちらにも対等に渡り合えるデッキは中々存在しないと言っていい。
だからといってTire2以下のデッキに不利かというとそうではない。メインから4枚採用された《恋煩いの野獣》や《穢れ沼の騎士》のおかげで雑多なアグロデッキ全般に非常に勝率が高いのもこのデッキの特徴だ。総じて、BGは絶対的に不利なデッキが環境に少ない、「丸い」デッキなのだ。
そして上記の勝率、丸さを担保しているのはサイドボードの潤沢さだ。
環境でも随一の汎用性を誇る色対策カードである《夏の帳》と《害悪な掌握》を無理なく採用できるのは勿論、対ゴロスのキラーカードである《夢を引き裂く者、アショク》やアグロデッキ全般に刺さる《軍団の最期》の追加も採れる上、《アーク弓のレインジャー、ビビアン》の存在によってメインからシルバーバレット的にサイドボードに触れることさえできてしまう。1枚ずつ散らされている《虐殺少女》等は主にその用途で使用する。
今回は採用していないが(理由は後述する)コントロールが多いメタなら各種ハンデス、アグロへのガードを高めたいなら《見栄え損ない》など、2色ながら環境に応じて柔軟に採用カードを選択できるのも強みだ。
メインボード
さて、順番が前後してしまったが、ここからは採用したカードについて順に触れていきたいと思う。
《エッジウォールの亭主 》×4
《穢れ沼の騎士》×4
《残忍な騎士》×4
《恋煩いの野獣》×4
デッキの核となる出来事生物達。
《エッジウォールの亭主》は相手に軽量除去があったり全体除去で流されそうな場合は手札に溜めておいて出来事生物と一緒に展開するのが有効。
《穢れ沼の騎士》は3マナ1ドローのモードが活きるマッチも存在するので相手のデッキが分からない先手1t目に出すかはよく考えよう。
《真夜中の騎士団》×3
同じく出来事生物の枠だが、このカードは通常2枚程度の採用が多いと思ったので別で書くことにした。
元々は《採取/最終》を2枚採用していたのだがやや受け身なカードであり、2t目にクロックとして出すこともできるこちらを増量。
6マナから4マナの速攻生物を回収し即投げる動きと除去された5マナから《エッジウォールの亭主》を回収し同時に展開する動きが強力。対アグロではブロッカーにならないためよくサイドアウトする。
《楽園のドルイド》×3
従来は《むかしむかし》だった枠だが、4マナ域の増量、特に後述する《アーク弓のレインジャー、ビビアン》の採用によってマナベースにかかった負荷を軽減する目的で入れ替えられている。
そもそも《エッジウォールの亭主》のドローが回り始めればマナの使い道はいくらでもあるデッキだし、3t目に《探索する獣》を投げるようなブン回りパターンにも寄与することから《むかしむかし》よりも感触が良く、この変更には納得している。
《軍団の最期》×2
ゴロスのゾンビトークンをまとめて流したり、《ハイドロイド混生体》を後続までシャットアウトできる汎用性の高い除去であり、最早メイン採用を疑問視する者はいないだろう。環境次第で3枚目を検討。
《悪ふざけの名人、ランクル》×3
《探索する獣》×3
4マナの速攻生物枠。獣4のランクル2や、獣4のランクル4なども試したが、複数嵩張った時の弱さやそれぞれの性質の違い(獣は地上デッキ同系で強くなく、ランクルは後手時に出しづらい)等を考慮した結果、この比率に落ち着いた。基本はこの二種を連打することによる押し付けをメインにゲームを進めていくことになるが、サイド後は前述の性質を理解し適切にサイドアウトしていく必要がある。
《アーク弓のレインジャー、ビビアン》×3
デッキ内ほぼ全ての生物とシナジーする最強PW。このデッキをネクストレベルに押し上げた1枚。特に《探索する獣》とのシナジーが強烈で、+で摂死トランプル警戒の怪物を作るも良し、-で接死ビームを飛ばしても良しと八面六臂の活躍を見せる。大マイナスの効果は正直おまけだが、《虐殺少女》による大逆転など、不可能を可能にすることも稀によくあるのでインクの染みと思わず常にプレイの選択肢に入れておこう。
《世界を揺るがす者、ニッサ》×1
《呪われた狩人、ガラク》×1
フィニッシャー枠は散らしている。生物のサイズが小さい相手に対処を迫り、行動回数を増やす《世界を揺るがす者、ニッサ》とやや重いものの地上デッキ対決では圧倒的な制圧力を誇る《呪われた狩人、ガラク》、どちらもそれぞれ強力だが性質が違うカードのため必要なマッチと不必要なマッチを見極めてサイドアウトしていきたい。
《採取/最終》×1
出来事生物を2体回収する動きが消耗戦で強力だが、基本前のめりなデッキの性質と合っているかは疑問が残るところでもある。‐4/-4のモードが劇的に刺さる場面もあるため散らしているが、除去や《真夜中の騎士団》の追加でも構わないだろう。
続いて、サイドボードと不採用となったカードについて触れていく。
サイドボード
《夏の帳》×2
《害悪な掌握》×3
定番の色対策。同系やコントロールが増えれば帳を、シミック系が増えれば掌握をそれぞれ増量することもありうる。
《軍団の最期》×1
メインの追加。先手後手で強さが変わるカードなので後手番を捲るためにもメインサイド合わせて3枚は欲しいと感じる。
《クロールの銛撃ち》×3
パッと見「何に対して入れるの?」と感じるだろうし、最初は自分も懐疑的だった枠。だが使えば使うほど今のメタゲームにフィットしているカードなのが分かると思う。
具体的にはシミック系の《金のガチョウ》と《ハイドロイド混生体》がターゲットだが、黒系アグロの《悪ふざけの名人、ランクル》や《騒乱の落とし子》、シミックフラッシュの《厚かましい借り手》、《幽体の船乗り》など意外と対象は多い。
単純にアグロ全般に対する序盤の相打ち要員として《真夜中の騎士団》と入れ替えても良く、2枚は入れておきたい。
《夢を引き裂く者、アショク》×3
ゴロス相手は様々なサイドカードを試したが、結局は早期にこれを立てて相手を減速させ、殴り切るプランが一番勝率が良かった。勿論先手2tらせん、3t迂回路のようなブン回りに無力なのも確かだが、ゴロスから原野を複数サーチされなくなるだけで相当展開が楽になるため、ほぼ専用サイドだが安定してキャストするために3枚採用している。《敬虔な命令》には注意。
《打ち壊すブロントドン》×1
《虐殺少女》×1
《夜の騎兵》×1
主に《アーク弓のレインジャー、ビビアン》からサーチする目的で散らしているが、マッチアップによっては勿論普通にサイドインすることもある。
特に《夜の騎兵》は環境に後腐れなく除去できるカードがほぼ存在しない対アグロの最終兵器ともいえる性能で、黒黒黒と緑緑緑を共存させてでも使う価値がある一枚だ。
緑同系で《虐殺少女》を入れたくなる気持ちは分かるが、こちらの盤面も吹き飛んでしまうため積極的にサイドインしたいというほどではなく後手時の捲り手段として検討する程度にした方が良い。
不採用カードとその理由
《むかしむかし》
1t目に《エッジウォールの亭主》を探す動きだけは強いのだが、それ以降は重めのサーチスペルになりがちで速度が大事な現環境ではテンポロスが大きいと感じ不採用。前述の通り《楽園のドルイド》の方が総合的に見て序盤の事故を軽減できている。
《グレートヘンジ》
メインに1枚入っているリストを散見するし、実際一度定着してしまえば無双する性能ではあるのだが、如何せんトップメタ2種に対して弱いのが気になって今は不採用としている。
そもそもデッキ内の最大パワーが《恋煩いの野獣》の5で、フル軽減できて4マナ。出すために1tを丸々費やすこともザラで、返しに《時を解す者、テフェリー》でバウンスされたり《王冠泥棒、オーコ》で鹿にされると目も当てられない。
全体除去を要する相手にはそもそも出す前に盤面を一掃されて手札で腐ったりとろくなことがないので少なくともメインには入れない方が無難だ。
《暗殺者の戦利品》
万能除去と言えば聞こえはいいが、現環境では相手に先んじて高マナ域をプレイされてしまうデメリットが大きすぎる。
そもそも《残忍な騎士》で大抵のパーマネントは処理できるため、必要性を感じない。
・各種ハンデス
《強迫》
《ドリルビット》
《はぐれ影魔道士、ダブリエル》
サイドインする相手はエスパースタックス、ジェスカイ(orグリクシス)創案の火、5cゴロスだが、前2つのデッキはそもそものリソース差のつけ易さやPWへの対処のしやすさから元々有利寄りの認識でわざわざサイドを用意する必要がなく、主な標的は5cゴロスになる。
しかし、一番落としたい全体除去がクリーチャーである《王国まといの巨人》に寄っている以上《強迫》は役に立たず、《ダブリエル》に関しては他のハンデスと併用する前提で、サイドボードの枠を大きく消費することになってしまう。
そもそも対ゴロスは長引けば長引くほど相手がトップデッキしていいカードが増えるうえ、序盤は全体除去の前にライフをいかに削っておけるかが重要なので、ちょっと強い《精神腐敗》をプレイできるほど悠長ではないのだ。
どうしてもサイドにハンデスが無いと落ち着かないという人は《ドリルビット》を2~3枚程度入れることをオススメする。
序盤の軽いクロックが多いこのデッキなら、ほぼライフ損失のない《思考囲い》として運用できるはずだ。
《見栄え損ない》
アグロ相手には元々相性が良く、ややオーバーボードな印象を受ける。
しかし後手時に相手のブン回りに対抗できる札であることは間違いないので、生物での受けが成立しづらいアグロ(具体的には接死やコンバットトリックが多いマルドゥ騎士など)が流行れば一考の余地はある。
《戦慄衆の将軍、リリアナ》
《害悪な掌握》が当たらないPWということで主に同系戦で活躍が期待できると思っていたが、《残忍な騎士》が当たることは変わりなく、+のゾンビトークン生成も-の2体エディクトも押されている盤面ではインパクトが弱すぎると感じた。
横並びで盤面を押し返せ、奥義のプレッシャーをかけ続けられるガラクの方が個人的には好みだ。
《壮大な破滅》《意地悪な狼》を2マナで後腐れなく処理できる。ただそれだけ。脳内では緑同系の最強サイドカードだったが対象が意外と狭い上に《軍団の最期》と併用することで発生する裏目に耐えられず数回プレイして抜いてしまったが、試す価値はあると思う。
サイドボーディング&マッチアップガイド
ここからは現環境における各マッチアップの戦い方について解説していく。
前提としてサイドボーディングは水物であり、相手のデッキ構成やプラン、先手後手の変化などで柔軟に対応していく必要があることは理解してほしい。
よって、筆者自身も毎回決まったサイドボーディングを行っているわけではないのだが、それでも不要なカードと必要なカードはある程度選定しているつもりだ。その上で可能な限り主要マッチアップにおける要点を言語化していければと思う。
・5cゴロス
in
+3《夢を引き裂く者、アショク》
+1《軍団の最期》
out
‐1《世界を揺るがす者、ニッサ》
‐1《採取/最終》
‐2《残忍な騎士》
・予想されるサイドカード
《敬虔な命令》《霊気の疾風》
全体除去、《裏切りの工作員》の追加など
メインはアグロVSコントロールの構図になり、全体除去が飛んでくる4~5t目までにどれだけライフを詰められるかが焦点だ。通常のコントロール戦と違うのは、消耗戦を仕掛けるとズルズルと相手が有利になっていく点で、基本的には短期決着を目指す。
一度全体除去を食らった返しに都合6枚の速攻クリーチャーを連打し残り数点を詰めていくのが最もよくある勝ち筋となる。
4マナ域の優先度は《アーク弓のレインジャー、ビビアン》>《探索する獣》>《悪ふざけの名人、ランクル》の順だ。《ビビアン》は序盤に展開した生物を後押ししつつ、全体除去に流されず、後続の速攻クリーチャーを強化できるので最優先で出す。また、《探索する獣》は後出しのゴロスにチャンプされ時間を稼がれてしまうのでダメージを入れられるうちに出すのが無難だ。逆に《悪ふざけの名人、ランクル》はゾンビトークン+ゴロスのような盤面からでもお互いドローのモードと合わせて4点を叩き込むことができる唯一のカードだ。最後の詰めとして使うのが良いだろう。
サイド後も基本的な方針は変わらないが、ゴロス側が更に除去を増やしてくることが予想されるので、息切れを防ぐ《エッジウォールの亭主》や初動を減速させる《夢を引き裂く者、アショク》あたりがキープ基準となる。
3/3サイズがトークンの群れの前で無力な《世界を揺るがす者、ニッサ》と単体除去として微妙な《残忍な騎士》を減らすのは確定として、《呪われた狩人、ガラク》を残すかは難しいところだ。
現状は奥義の影響力の高さやアショクでグダらせている間にすぐ勝てるカードとして残しているが、《裏切りの工作員》で逆に利用されるリスクもあるため他のカードでも問題はない。
ゲーム2で《裏切りの工作員》やカウンターを複数見たなら《夏の帳》を入れてもいいし、《王冠泥棒、オーコ》などのPWを見たなら《残忍な騎士》を多めに残しても良いだろう。
また、先手後手に関わらず純粋な2/3/2の殴り手として《クロールの銛撃ち》を入れてみるのも面白い。この辺りは相手のプランと相談というところか。
・シミック(バント)フード
in
+3《害悪な掌握》
+3《クロールの銛撃ち》
out
‐3《楽園のドルイド》
-1《採取/最終》
-1《探索する獣》
‐1《世界を揺るがす者、ニッサ》
・予想されるサイドカード
《冷気の疾風》《夏の帳》《大食のハイドラ》《探索する獣》など
地上は相手の《意地悪な狼》とこちらの《恋煩いの野獣》《探索する獣》の睨み合いになりやすく、基本はPWと回避能力持ちがゲームを決める展開になる。メインボードは相手の合計8枚のPWに対処できる札が《残忍な騎士》4枚のみなのでやや苦戦するが、サイド後は《害悪な掌握》でかなり改善される。
リソースを獲得する手段は基本《ハイドロイド混成体》のみで、《ニッサ》絡みの爆発的なドローさえなければ消耗戦でこちらに分がある。後半役に立たないマナクリーチャーを除去に変え、相手の息切れを狙うプランがいいだろう。
《採取/最終》や《虐殺少女》などのスイーパーは個人的には入れない方がいいと考えている。何故なら、対シミック戦は盤面を構築しつつ、2種のPWとXマナ生物をどう対処するかが鍵で、無理やり盤面を流せたとしてもPWさえ残っていれば復帰されてしまうからだ。特に《最終》はX5以上の《ハイドロイド混生体》や2回パンプした狼を流せず、期待外れの性能となることが多い。
《軍団の最期》はPWや《意地悪な狼》でのマウントに抵抗できないことから2枚のみの採用としているが、サイド後は《大食のハイドラ》が増えるため、対象に困ることは少ない。
《クロールの銛撃ち》の3枚目はやや過剰なので、ここは先手後手によって《楽園のドルイド》を少し残したり、《軍団の最期》の追加にしても良いかもしれない。
バント型とはまだ殆どマッチアップしたことがないため確証を持てていないが、《拘留代理人》のために《夏の帳》を入れるかは難しいところだ。
ただシミックバント両方に言えるが《軽蔑的な一撃》などのカウンターはあからさまに構えている場合(《むかしむかし》で手札に加えたクリーチャーを展開せずにターンを返してくる等)を除いて基本的にノーケアでいい(《冷気の疾風》は少し意識しておいた方がいいくらい)し、そのためだけに《夏の帳》をサイドインするのはあまりオススメしない。
こちらのデッキ全体が軽く、序盤からお互いにフルタップで脅威を展開するゲームになるのでサイドアウトされる前提でいいだろう。
・ミラーマッチ
in
+2《夏の帳》
+3《害悪な掌握》
out
‐3《楽園のドルイド》
-1《採取/最終》
‐1《世界を揺るがす者、ニッサ》
対シミックと似たようなゲームになるが、お互いに除去が豊富なため《残忍な騎士》をどう消費させるかが焦点になる。《エッジウォールの亭主》や《探索する獣》で除去を誘い、飛行クリーチャーかPWが完走する展開が理想だ。
ゲームを決めるのは主に《エッジウォールの亭主》《アーク弓のレインジャー、ビビアン》《悪ふざけの名人、ランクル》だ。
特に《アーク弓のレインジャー、ビビアン》は膠着した地上をトランプル付与で突破できるのは勿論、相手の《夏の帳》をかわしながら除去を撃つこともできるので最重要カードと言ってもいい。(この動きは対シミックやグルール戦などでも応用できる)
また、《軍団の最期》と《害悪な掌握》を両方かわせる飛行クロックである《悪ふざけの名人、ランクル》は膠着した盤面で出すとそのまま勝ててしまうほどに強力で、相手の飛行に対するブロッカーとしても機能するため後手でも減らすことはない。
《軍団の最期》は《エッジウォールの亭主》を後腐れなく除去するため残しているが、シミックと違いかなり対象が限定される。先手時は全抜きして《楽園のドルイド》や《採取/最終》に変えてしまうのも一考だ。
・赤単アグロ
in
+3《クロールの銛撃ち》
+1《軍団の最期》
+1《打ち壊すブロントドン》
+1《夜の騎兵》
+1《虐殺少女》
out
‐3《真夜中の騎士団》
‐3《楽園のドルイド》
‐1《採取/最終》
・予想されるサイドカード
《溶岩コイル》《実験の狂乱》《無頼な扇動者、ティボルト》など
メインに《朱地洞の族主、トーブラン》が4入っていて、生物中心に攻めてくるタイプを想定している。
火力が多めに入っているタイプには少し苦戦するものの《恋煩いの野獣》《探索する獣》のラインが強く、メインサイド合わせてマッチを落とすことはほぼ無いだろう。
《残忍な騎士》は《朱地洞の族主、トーブラン》以外に除去モードで撃ちたい対象がおらず、ハンドに複数ある場合は最初から生物モードで出してしまって構わない。《稲妻の一撃》が落ちた関係で一枚で除去できるカードはメインでは《殺戮の火》くらいしかなく、十分な脅威となるはずだ。
サイド後はブロックに回しづらい生物を除去やよりタフな生物に入れ替え、ライフレースを有利に進めていく。
《悪ふざけの名人、ランクル》は前述の通りインスタントで除去されるカードがほぼ無く、ハンデスモードで反撃の芽を摘む動きが強力なため後手でも残すようにしている。
《呪われた狩人、ガラク》については意見が分かれるところかもしれないが、サイド後は《実験の狂乱》によるリソース負けもありうるため、一枚で盤面を押し返せてゲームに勝てるカードが欲しく、現状は残している。
・騎士系アグロ
in
+1《軍団の最期》
+1《打ち壊すブロントドン》
+1《夜の騎兵》
+1《虐殺少女》
out
‐3《真夜中の騎士団》
‐1《悪ふざけの名人、ランクル》
・予想されるサイドカード
《害悪な掌握》など
接死持ちや《エンバレスの宝剣》を含めた各種コンバットトリックを受けきるのは非常に難しく、アグロの中では苦戦する部類となる。
パワー2以上の生物が多く相打ちを繰り返していれば勝てるという類のデッキでもないので《クロールの銛撃ち》は入れず、《楽園のドルイド》でより早く上のマナ域にアクセスし、ライフレースを仕掛けた方が良いだろう。
白が濃いタイプなら《害悪な掌握》も候補に入るが大抵の場合本質は赤黒のデッキなので入れない方が無難。
このマッチを改善したいならインスタントタイミングでコンバットトリックや《エンバレスの宝剣》に抵抗できる《見栄え損ない》《打ち壊すブロントドン》等を増量すると良いだろう。
・グルールアグロ
in
+1《打ち壊すブロントドン》
+1《夜の騎兵》
+3《害悪な掌握》
out
‐3《真夜中の騎士団》
‐1《採取/最終》
‐1《世界を揺るがす者、ニッサ》
・予想されるサイドカード
《夏の帳》《溶岩コイル》《ドムリの待ち伏せ》など
同じく《エンバレスの宝剣》デッキの亜種だが、こちらは《害悪な掌握》をサイドインできる分比較的相性がいい部類だ。
各種速攻クリーチャーと《エンバレスの宝剣》の関係で常にライフを高く維持するのが重要。リソースを得るカードもほぼ存在しないため負け筋をケアし続けながら動けばいずれ勝つ。
赤単同様地上クリーチャーを《アーク弓のレインジャー、ビビアン》でバックアップしてライフレースを優位に進めていくか、《悪ふざけの名人、ランクル》でリソースを摘み取っていくのが主な勝ち筋となるが、《争闘/壮大》で《悪ふざけの名人、悪ふざけの名人、ランクル》が除去されてしまうのには注意。
《軍団の最期》は《生皮収集家》《ザル=ターのゴブリン》くらいにしか当たらないものの、後手番では必須。
《クロールの銛撃ち》は《スカルガンのヘルカイト》に触れられて序盤の相打ち要員にもしやすいが、《砕骨の巨人》の2点火力でついでに除去されてしまう弱さもあるのでサイドインするかはよく考えよう。
創案の火(ジェスカイ、グリクシス)
in
+1《打ち壊すブロントドン》
+2《夏の帳》
out
‐2《軍団の最期》
‐1《楽園のドルイド》
・予想されるサイドカード なし(《願いのフェイ》型が主流のため)
サイドボードの部分で少し触れたとおり、環境に母数が多くなく、マッチを通してそこまで不利に感じたこともないため現状ではほぼサイドカードを割いていない。
全体除去が《轟音のクラリオン》や《煤の儀式》など限定的なものが多く、除去された《エッジウォールの亭主》を墓地回収で拾い再展開していればリソースは尽きず、PWは《探索する獣》や《残忍な騎士》で比較的簡単に対処できるためだ。とはいえ《覆いを割く者、ナーセット》でドローを進められなくされたり最速で《創案の火》+《抽象からの抽出》のような展開をされるとやはり厳しいものがあるので、今後数を増やすようであればサイドにハンデスを追加したい。
おわりに
さて、ここまで駆け足で現在のスタンダード環境におけるBGの立ち位置を纏めてきたが、以上が自分の所感となる。
アリーナMC予選直前に公開しようと考えていたため、突然禁止改定時期の変更がアナウンスされた時は驚いたが、おそらく禁止の影響を受けないアーキタイプであり、新環境でも通用するノウハウは伝えられると感じたので公開に踏み切った次第だ。MC5はグルールの優勝で終わったが、今後スタンダード環境がどう変容していくのか楽しみだ。
明日までには禁止改定が発表される。間違いなくゴロスかシミック、もしくはその両方にメスが入ることになると思われるため、近日中に改定後の最新リストや簡単な所感を追記できればと思う。
10/22追記 禁止改訂後の環境予想と最新デッキリスト
10/21日、《死者の原野》がスタンダードで禁止となった。
https://magic.wizards.com/en/articles/archive/news/october-21-2019-banned-and-restricted-announcement?s
大方予想通りではあったものの、環境の多くのアグロデッキを殺しているシミック系にノータッチだったのは意外なところだ。
これにより《死者の原野》に殺されていたコントロール系デッキが復権し、環境はますます中速~低速化されると思われる。
反対に《死者の原野》に対するアンチデッキとして存在していた赤単アグロやグルールアグロは数を減らしていくのではないかと予想する。
もしアグロを使うのであれば、サイドに《強迫》《害悪な掌握》を採用できる黒+何かのものが良いだろう。
アリーナでの適用がまだなので参考になるかは不明だが、この構成でBO3を5戦回して4-1とまずまずの結果を得られたので最後に禁止改訂後の最新リストを貼っておく。

メインボードの構成には概ね満足しているので大きな変更は無い。サイドの枠が足りなかったのと後手時の勝率を上げたかったので《採取/最終》を解雇し《軍団の最期》の3枚目をメインに移しているくらいだ。
主な変更点はサイドボードだ。まず、ゴロス専用のサイドカードだった《夢を引き裂く者、アショク》を抜き《強迫》を採用した。これは環境が低速化し《創案の火》系やエスパースタックスなどのコントロールが増えることが予想されるためだ。
ここは《ドリルビット》でもいいが、《王国まといの巨人》や《不屈の巡礼者、ゴロス》を落とす必要がなくなったため、1t目からキャストできてゲームメイクを楽に進められる《強迫》の方が無難だろう。
そしてシミックがトップメタになることが予想されるので《害悪な掌握》を4に増量した。元々有利なマッチアップではあるものの、《夏の帳》を複数持たれていたりすると押し負けることもよくあるので、取りこぼさないためにもフル投入が良い。
《戦慄衆の将軍、リリアナ》は緑同系とコントロールに強い枠としてお試しで入れているが、《呪われた狩人、ガラク》と併用するとデッキが重くなりすぎるのでここは《アーク弓のレインジャー、ビビアン》でもサーチできる《真夜中の死神》等でも良いかもしれない。また新たなフィードバックがあればMC予選の直前にでも追記したいと思う。
10/26追記 アップデート版リスト ~今週末にBGを使うなら~

あれから数日ありとあらゆる構成やサイドボードを試したが、この構成をベースにBO3を16戦回して12勝4敗(勝率75%)と悪くない勝率で、初めてミシックランクの二桁台に到達することができた。

サイドボード含め、一周して元のリストに戻ってしまった感があるが、メインの《世界を揺るがす者、ニッサ》を解雇し《楽園のドルイド》《呪われた狩人、ガラク》を増量した点はかなり好感触だ。
そもそも《楽園のドルイド》型の強みはシンボルのきつい4マナ域のパワーカード(特にトリプルシンボルがきつく、頭数を並べることが重要な《アーク弓のレインジャー、ビビアン》)を安定して強く使えることと、メインから5マナ6マナ以上の重いカードを無理なく使える点で、ならばその強みを伸ばしていくのが《むかしむかし》型との差別化になると感じたからだ。
環境から短期決着型のデッキが減り、重めのパワーカードを連打するミッドレンジが主流になっているのも追い風だろう。
サイドボードは奇を衒わない、シンプルなものとなった。
前回の追記で少し触れた《真夜中の死神》は3マナのアイツに鹿にされて真顔になるだけだったので、間違えてもデッキに入れてはいけない。
同型やシミックの増加により色対策カードを増量し、《強迫》は直近16戦でコントロールらしいコントロールがジェスカイ《創案の火》と一戦当たった程度で環境に合っていないと感じたので数を減らした。
理論に勝率がついてきて、概ねアリーナ予選及びリアルで行われるPTQもこのリストで出るだろうと思っていた。思っていたのだが……
10/26、予選直前になって勝率がガタ落ち。
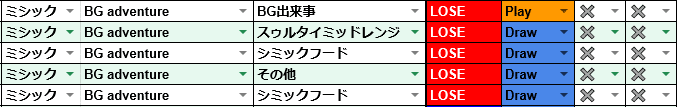
盛り一切抜きで0-10(スト負け×5)を経験し、直近12戦を4-8と散々なものだった。
単純にマリガンを繰り返しデッキが回らず一種のティルト状態に陥っていたのも要因としてあると思うが、主な理由としては以下のことが考えられる。
・黒絡みのデッキがメインから《害悪な掌握》を積み始めたこと。
・シミック系が同系を意識して《裏切りの工作員》や《集団強制》を積み始めたこと。
・《死者の原野》が退場したことでサイドのカウンターが減り、その枠が追加の《夏の帳》に変わっていること。
の3点だ。現在のミシック帯のメタゲームではシミック(+X)のデッキ群が同系を意識しまくった結果、「緑同系をいかにして出し抜くか?」という構築が横行し、そのあおりをBGも受けてしまっている、というのが残念ながら現状だ。
だが、このままでは今週末にこのデッキを使うべきではないという結論になりタイトル詐欺だと言われてしまうので、それでもBGを使いたいというこの記事の読者に、直近のランクマッチで使用していたリストを元に緑同系のカギを3点、改めて伝えようと思う。

1.《エッジウォールの亭主》を大事にしろ!
同系も対シミックも散々やってきたが、結局はこのカードをどれだけ引けたか、定着させられたかで決まる。特にシミックはメインに効果的な対処手段が限られる以上、このカードで枚数差をつけて消耗戦に持ち込めるかが勝負となる。マナが余っているからと出したところで《意地悪な狼》の餌にされているようでは消耗戦に持ち込む前にPWに押しつぶされてしまう。時には我慢し手札に温存しておく勇気も必要だ。
また、除去があるだけの弱いハンドをキープしてもいけない。あくまでもこちらが押し付ける側で、除去はビートダウンのサポート程度に考える方が良いだろう。1マリガン分くらいは《エッジウォールの亭主》が余裕で取り返してくれるのがこのデッキの強みだ。自分のデッキの性質を理解し、勇気を持ってマリガンしよう。
2.勝負を決めるのは回避能力!
地上は《意地悪な狼》や《恋煩いの野獣》ですぐ膠着するので、《探索する獣》はサイド後に真っ先に抜く筆頭だ。
消耗戦の末にゲームを決めるのはやはり回避能力持ちで、相手の飛行に対処する手段、自分の飛行を守る手段を両方入れていないと勝ち切ることはできない。
自分はメインサイド合わせてどうしても《悪ふざけの名人、ランクル》を4枚取りたくてサイドに4枚目を用意したがこれは悪くないバランスだと思う。緑同系では劇的な活躍をするものの、マッチアップや先手後手によっては枚数を調節したいからだ。
《真夜中の騎士団》も《エッジウォールの亭主》を回収しつつ飛行を展開できる唯一無二のカードなので3枚目を入れたいところだが、どうしても枠が見つからなかった。あれだけ力説しておいてなんだが、《楽園のドルイド》の4枚目はやはりデッキ全体がフラッドしやすくなり過剰かもしれないので変えるとしたらそこだろう。
3.色対策でハマる構成にするな!
現在のミシック帯のメタはメインから《害悪な掌握》や《冷気の疾風》が積まれていることもザラで、構築段階やサイドボーディングでいかにそれらのカード群をかわせるかがカギとなる。
自分はメインのPW枠を《呪われた狩人、ガラク》から《戦慄衆の将軍、リリアナ》に変更した。理由は単純で緑同系に強い枠として採用していたにも関わらず同系やスゥルタイの《害悪な掌握》に簡単に対処されてしまうからだ。
カード単体の性能としては勿論《呪われた狩人、ガラク》が上だが、現在のメタではその対処のされにくさから《戦慄衆の将軍、リリアナ》を使うことをオススメする。(盤面を捲る類のカードではないので2枚は過剰かもしれないが)
そして黒い除去を多用することから《夏の帳》に非常に弱いのもBGというデッキの特徴で、前述の理由で採用枚数自体が増えていることもあり、最近は対シミックであっても黒い除去をフル投入するようなサイドはしないようにしている(勿論相手のプランと要相談ではあるが)
また、それをかわしながら除去を撃てたり膠着しがちな地上クリーチャーを回避能力持ちに強化させられる《アーク弓のレインジャー、ビビアン》を複数採用できているのはやはりこの構築の強みだと感じた。
以上が、《楽園のドルイド》型のBGを使い続けた所感だ。
他にもメインの《害悪な掌握》は本当に入れるべきなのか?とかマナベースに黒マナもう一枚欲しい問題とか色々語るべきことはあるのだが、如何せん時間が足りな過ぎた。
2枚目のリストは発展途上のもので、ミシック帯のメタには合っているのかもしれないがアリーナ予選やGPのように雑多なデッキに当たることが予想されるフィールドでは1枚目のリストを使用することをオススメする(何より勝率が証明している)
10/31日追記 BGの変遷~GP名古屋でBGを使うなら~
先週末、アリーナMC予選及びリアルPTQに参戦し、それぞれ4-2drop、3-3予選落ちと振るわない成績だった。
フード系デッキの隆盛により《害悪の掌握》や《冷気の疾風》といった色対策がメインから積まれるようになってしまった現状では従来の構成は余りにも時代遅れで、大幅なリスト変更を余儀なくされた。
そんな中、ちょうどMC予選で好成績だったリストが出回っていたこともあり、様々な構成を試した結果行き着いたのが現在のリストになる。金曜PTQ及びGP名古屋も概ねこの構成で出場する予定だ。

日本のプラチナプロである井川良彦氏のリストとMC予選をBGで唯一抜けたプレイヤーのリストの合いの子といった感じだが、従来のリストより中~長期戦を見据えた構成になっており、直近15戦で11-4と悪くない成績だ。BGというデッキの是非はともかく、現在のメタゲームにフィットしているのは確かだ。
メインボードで特筆すべきは《探索する獣》の不採用だろう。雑多なアグロやPW要する《創案の火》系には若干弱くなるものの、元々緑同系では《恋煩いの野獣》や《意地悪な狼》でビタ止まりしてしまうサイドアウト率の高いカードだっただけにこの変更には納得している。《悪ふざけの名人、ランクル》に関しては適当にサクりやすい生物が多いこのデッキでは八面六臂の活躍をし、他のシミック系との差別化にもなるため残している。
そしてメインの《害悪な掌握》を増やし更にPWに触りやすくなったことで《世界を揺るがす者、ニッサ》の3/3土地や《意地悪な狼》をまとめて流せる《虐殺少女》《採取/最終》の評価は上がった。《戦慄衆の将軍、リリアナ》が場にいれば自軍が壊滅するデメリットも帳消しにでき、対シミック系の勝ち筋の一つとなる。
また、採用カードの変化によってマナベースにも手を加えた。4マナ域を早いターンに展開する重要性が減り、序盤のスクリューが致命的な構成なため土地25、《楽園のドルイド》2のバランスに落ち着いた。
フラッドのリスクを軽減するため《ロークスワイン城》を2枚採用しているが森や神殿土地と重ね引いた時のタップイン地獄も馬鹿にならないためここは各々で最適なバランスを探し出してほしい。
黒の比率が増えたことで、《アーク弓のレインジャー、ビビアン》が安定して出せなくなるのでは?という疑問もあると思うが、以前のように最速で出す展開を想定していないため、現状はあまり困っていない。
ここは最近流行りの《ゴルガリの女王、ヴラスカ》の追加でもいいが、食物トークンをサクれるスゥルタイと違いプラスがあまり強くないので自分はこの比率の方が好みだ。
メインがサイド後のような構成なため、サイドボードは苦手なコントロール系に対して厚く取っている。《強迫》は以前までは2で回していたが、リアルでのトーナメントはアリーナのようにフード系に偏ったメタではないと予想され、《ティムール再生》や《青白コントロール》等の新しいデッキも登場しているため嗜みとして4枚の採用をオススメする。
《軍団の最期》はメインとサイドで1枚ずつ散らしているがここは《害悪の掌握》と入れ替えても構わない。ただ、所詮は単体除去でしかなく、1対1交換だけを繰り返していると《ハイドロイド混生体》連打で負けたりもするし、最近はメイン《害悪の掌握》をかわすことが目的のラクドスアリストクラッツなども増えているのでリスクを少しでも軽減するため今週末に《害悪な掌握》メイン4で突っ込むのはあまりオススメしない。
《古呪》はサイド後重PWコントロールのように変化するスゥルタイを見て直前に採用したが、ややオーバーボード気味な気もするのでここは《打ち壊すブロントドン》の追加などでもいいかもしれない。
私自身も言語化できていない部分が多いまま殴り書きしてしまったので見辛い文章になってしまったかもしれないが、何か質問があればこの記事のコメントか、ツイッターアカウント(@BWD_shine)にリプライを飛ばしてくれればできる限り対応する。
また、仕事の都合で不定期にはなるが、稀にTwitch(twitch.tv/azatoyellow)で配信もしているので、そこでの質問も大歓迎だ。
というわけで、最後まで読んでくれてありがとう。この記事を読んだ君が、GP名古屋で好成績を残してくれれば幸いだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
