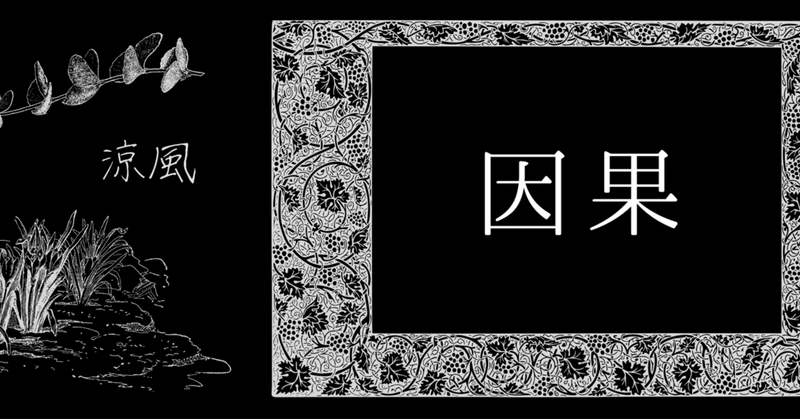
因果
走馬灯シアター
「B-6」2列目、中央やや左、それとなく確認し席に着こうとすると、カーペットに吸音されながらも微かに、軽い足音が響いてきた。
「一人かと思いました、映画とかよく観られますか」
「いや、私は」
歯切れ悪そうに答えると、目線を前の方に落とした。
スクリーンの下には、小さい映画館ながら、試写会などで役者が立つような段があり、前列にいると確かについ目をやってしまう。その無作為な仕草に少し見覚えがあった。
「あれ、どこかでお会いした事ありましたっけ」
「そういう手法を使ってたんですね」
手には資料を抱えている。
「手法とかじゃなくてホンマに、あ、そのスタッフの方ですかね」
「スタッフというか、その、アレです」
「アレっていうのは」
「いやあの、まあその、死神、的な」
黙ってはいけないと思ったが、上手い言葉も出ないまま、謝ってしまった。
「ちがうちがう、だからあんまり言いたくなかったんですよね」
「全然全然」
笑いを堪えきれなかった。
「良くないですよ」
「別になんとも思ってないですって」
笑いを堪えきれないままそう言った。
「いや、そういうところなんじゃないですか」
「何がですか」
「死因」
ただ音としてしか捉えられず、意味がわからなかった。
「そういう人をすぐ馬鹿にするところが死に繋がったんじゃないですかね、わかんないですけど」
この人がいわゆるな人であれば合点がいく。
「馬鹿にされたから殺そうとしてます?一旦落ち着きましょうか」
とにかく距離を取らなければと思ったその時、
「あなたが落ち着いて下さい、あなたはもう、死んでいます」
もし本当に意表をつかれて、認識より先に死んでしまったとしたら、トムとジェリーのトムが崖から落ちる時のように、まず自分の死を認識して、そこから引っ張られるようにして死んでいくのかもしれない。
「あなたはもう現世で死んでいて、だから今ここにいるんですよ、ちょっと前の事思い出してみて下さい」
自分でも不思議な事に、本当にその時まで、それを自覚していなかった。
「それが、ここに来てからの事は覚えてるんですけど、それより前の事はあんまり思い出せないんですよね」
「死んでますからね」
「死んだら記憶ってなくなるもんなんですか」
「まあ、記憶残ったまま現世離れるのも辛いでしょ」
確かになと思ったし、それがまた信憑性を増させたが、受け入れられる訳も無く「なんで?」と口からこぼれていた。
「なんでかは知らないです」
「知らないですって、あなた要は神様ってことでしょ」
「だからずっと別に神様では無いって言ってるじゃないですか」
その神様が言っている事は何も間違ってなかった。だからこそ、なるほど僕は死んだんだと自覚した。こんな感じかと思った。寂しかった。
「じゃああれは、走馬灯、普通死に際に走馬灯見るって言うじゃないですか、僕そんなんもなく気付いたらここにいたんですけど」
「今から見るんですよ、最期に」
ここは走馬灯シアター、僕の20過ぎからの要約した人生が上映された。
凶器
出囃子が鳴る。スクリーンに映る自分の多くはお笑い芸人をしていた。僕には相方がいた。変な奴だった。関わる人の中でも相方というのは特別で、その一挙一動が面白く、時に腹立たしかった。僕は思っていることが表面に溢れ出てしまう。ことお笑いにおいては輪をかけてそうだった。そのせいで相方が何人か飛んで行ったことがある。きっとこの人も。気付けばそう考えるようになっていた。自分は自分を大好きになろうとした。僕さえ凄ければと思っていた。
「いやでも、平場とかもうちょっと頑張って欲しいかな、今日とかもなんも喋れへんかったから大変やってんな、まあ俺やからなんとかするけど、逆に俺おるねんから、もう何も考えんととりあえずなんかゆうたらいいから」
「ナイフ」
「まあこれから頑張ってな」
「うん、じゃあお疲れ」
「え、ネタ合わせは?」
「あ、そうか」
「忘れてたん?信じられへん新ネタ2本やで」
その内1本は珍しく相方が書いてきたネタだったので、とても不安で、余計に気が立った。
「いや、忘れてただけ」
「忘れへんやろ普通、なんかそういうところやで、ええけど」
「ハンマー」
「俺がネタ書いてんねんから気持ちだけは持っといてくれんと」
「爪切り」
苛立ちを言葉ではなく、凶器に変えて僕に伝えてきた。確かに、感情に任せて暴言を吐くと争いになるし、黙っていると悔しいので、合理的ではあるなと思った。相方にはそういうところがあって、そういうところが面白い。その時僕は、今難波にいることを思い出した。
「そういえば最近ニュース見た?この辺らしいな」
連日ニュースでやっていた、通り魔事件のことだ。今まで似たようなニュースを見ても、世の中に対する恐怖感とか、きっとこういうことは無くならないんだろうなとか、どこか少し達観していたけれど、難波という音の響きに耳がゾワゾワとし、恐怖がより近く、もう肌が当たっているような感覚になっていた。
それからしばらく、相方の粗相がある度に、僕は嫌味を言い、相方は凶器で返した。僕の電話が鳴った。相手は、女性からだった。先月高校の同窓会があって、その人とはそこで知り合った。高校時代は見たことも無い人だったけど、その人自身も、この2年で色々変わったからと言っていた。初めは知らないギャルがいると用心していたが、話すと聞いてみたいことがたくさんあった。彼女は東京に住んでいた。僕が知らない、見えていない事を知っていたし、見ていた。そこから、彼女と会うのがとても楽しみになった。隙をついて電話をするようになった。電話口で4月から大阪に住むと言った。嬉しかった。彼女と電話をすると、つられて標準語のギャルっぽい話し方になる。
「魚雷」
聞こえないフリをした。
「こないだの同窓会の子?」
どこかで話したような気もしたが思い出せず言葉を濁した。
「その、良くないで」
「いや別に、あれやから普通に」
「彼女さんは知ってんの?」
「知ってるわけないやん」
「まあ私はどうなってもええけど」
じゃあ別に良くない?と思い、語気を強めてしまった。
「これはこっちの話やから」
「・・・ボイスレコーダー。」
友達
5年来の友達がいた。親友では無いくらいがちょうど良かったし、だからこそ5年も、なんだかんだ友達でいたのだと思う。しかし、時間が経てば経つほど、友達はただ「友達」という関係性を差す言葉になっていった。1年半ほど前に、バイトを勢いで辞めてしまい、貯金も底をつき途方に暮れていた時に、プライドの高い僕でも唯一頭を下げれたのがその友達だった。ライブには来たことは無いが、芸人活動は応援してくれていた。高校時代は歌手になろうとしていたし、卒業して専門学校に進学したが、今は薬局で正社員として働いている。そこまで頻繁にお金を借りていたわけでは無いが気付けばその金額は着々と大きくなっていた。
「頼むわ、来月にはめどが立つから」
僕は決まってそう言うし、その瞬間においては割と本気でそう思っている。
いつもは適当に返事をされたあとお金を天満まで貰いに行くのだが、その日は違った。やけに渋っていた。当然といえば当然の事だけれど、続けて返して欲しいと言ってきた。おかしい。理由を聞いた。
「俺来月、結婚すんねんな」
金の貸し借りの話の時に1番聞きたくない言葉だったので、一瞬たじろいだが、「おめでとう」と言えた。
その友達には高校からずっと付き合っている彼女がいた。存在はなんとなく知っていたが1度も会ったことが無いし、名前すら知らない。そういえばその彼女は、東京の大学に行くので遠距離になると聞いていた。会わせたくないから適当に嘘をついているのかとも思ったが、そんな軽薄な嘘をつくようなやつでも無いので、恐らく本当だった。
「なんでまたこのタイミングで?」
「いやまあ、同棲するから」
「転勤とか?」
「仕事は結構前に辞めてて、今はバイト。でも来月からこっちで就職決まったらしい」
「そうなんや」
僕が喜ぶのが意外だったのか、めずらしく饒舌になり、色々な事を話しだした。そのどれもが彼女の事で、仕事辞めてギャルになって心配だとか、結婚式の余興をやって欲しいとか、僕のLINEを念のため彼女に教えときたいとか。僕にはそんなことよりも大事な用を思い出した。
「お金は借りられへん感じ?」
「え?」
「いやその、俺は返されへん感じやねんけど、借りられへん感じかな?」
「・・・いや」
危ないと思いすぐ話を戻した。借りられないならばせめて返さない感じにしなければ。ライブを理由に何度も電話を切ろうとしたが、そのたび向こうは話を続けようとし、攻防が続いたが、なんとか適当にかわして切った。
もうあまり関わることは無いだろうなと思った。確かに5年来の友達だったけど、そこには「5年」という時間を差す言葉と、寂しさだけが残った。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
