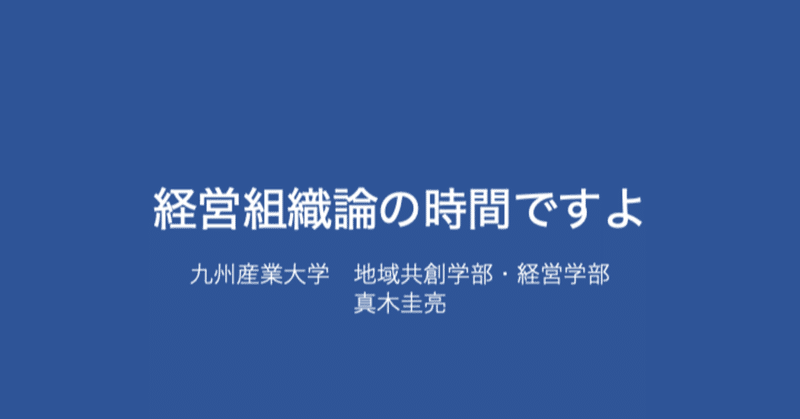
第5回(2020/06/01) 経営組織論 人間はどうやったらやる気になるのでしょうか?(2)
1.はじめに
このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第5回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。ちなみに「そのまま文字起こし」って書いてますけど,最初に適当にそう書いたからそのまま書いているだけで,実際は毎回ゼロから書いています。書き下ろし原稿です。わりと頑張ってるんですよ!
こんにちは。ようやくCOVID-19も落ち着いたと思ったら,また感染者が増えているようで,まだまだ予断を許さない状況です。対面講義もいくつか再開されていますが,通学・登校が不安な場合は講義担当教員のお話をよく聞いておきましょう。対面講義を再開しても,受講生の状況によっては遠隔講義にも対応できるように,というのが九州産業大学の基本方針です。なお,どの講義が対面で実施されるのかは5月26日付でK's Lifeを通じて発信されています。必ずそちらを確認し,何が対面講義かわからないという状況がないようにしましょう。
いつもならここで余談に入るところですが,後述するように今回の講義noteには「補論」があります。この補論は「本格的な余談」みたいなものなので,今回の寄り道はそちらに譲ることにしますね。「その補論とやらを余談で話せばいいやんけ」と思うでしょうが,ちょっと文章量が多くバランスが悪くなるので最後にお話しします。
2.前回の振り返り
前回講義では,大きく分けて次の2つについて学びました。1つめは,モチベーションについて学ぶ意義です。組織は協働体系です。組織目的を達成するために,リーダーは組織メンバー間の協働をより良いものとするべくメンバーに働きかけます。そのとき,メンバーが何に,どのように動機づけられるかを考えることなしに,メンバーの協働を促すことは困難です。したがって,リーダーはメンバーのモチベーションについて考えなければなりません。その時の助けとなるのが,モチベーションに関する理論です。これを学び,それを活かしていくことで,リーダーはより適切にメンバーの協働を促すことができます。これがモチベーションについて学ぶ意義の1つです。
もう1つは,モチベーションの内容理論です。モチベーションに関する理論は,「何が人を動機づけるのか?」について考える「内容理論」と,「どのようにして人は動機づけられるのか?」について考える「過程理論」の2つに分けられます。前回講義では,内容理論について学びました。
内容理論として紹介したのは,欲求階層説,ERG理論,マクレランドの欲求理論,内発的動機づけ理論の4つでした。これらの詳細については前回の講義noteを参照してください。いずれの理論も,今では当たり前に思える内容かもしれません。
しかし,これらの理論が提唱された後のモチベーションに関する理論は,これらの理論を基礎として発展してきています。基礎を理解していなければ,新しい理論の言わんとしているところや,その理論の価値を十分に理解することは困難です。その意味で,あなたは前回の講義を通じてモチベーションについて考えていくための基本的な武器を手に入れることができたと言えるでしょう。
3.前回の課題へのフィードバック
<課題>
「4.講義内容:人間ってどうやったらやる気を抱くのでしょうか?」に書かれている内容を踏まえて,あなたなりに人間の欲求をいくつかに分類し,それについて説明してください(400字程度)。
人間が仕事をする上での欲求を3つに分類して考えてみたいと思います。1つ目の欲求は「自分のために働く」という欲求です。自分のために働くということは、「自分の社会で生活していく上で必要なお金を稼ぐために働く」「自分がその仕事が好きだから働く」という意味で、とにかく自分を中心に考えて、自分の欲求を満たすためだけに働く。また、「良い仕事をして、上司や同僚に良い人間だと思われたい」というような、自分が得を得たいという欲望を満たすために働くという考え方です。
2つ目の欲求は、「人のために働く」という欲求です。1つ目の欲求の「自分のために働く」であっても、結果としては誰かの役に立っているかもしれません。しかし、ここでいう「人のために働く」とは、自分の欲求や欲望は二の次に考えて、社会貢献や、自分が頑張ることで会社のイメージをあげたいというような、純粋に自分以外の人のためになりたいから働くという考え方です。
3つ目の欲求は、「階級や役職のために働く」という欲求です。階級や役職のために働くということは、階級や役職の名誉汚さないために、それに見合った仕事をするということです。ある程度人の上に立つ階級や役職は、多くの人が憧れ、目指しているポジションだと思います。そういった階級や役職に就いた以上は、それに恥じない働きをしようと考えるはずです。階級や役職というのは、1人の個人に与えられるものであり、出世や昇給にも関わるため、1つ目の欲求の「自分のために働く」と似ているかもしれませんが、3つ目の欲求はあくまでも階級や役職の権威を守るために働くという考え方です。
欲求を,それが向けられる対象で分けるのはとてもおもしろいですね。特に3つめの「階級や役職のために働く」という欲求は,なるほどなと感じました。この回答者にはそういった経験があるのかもしれませんね。メンバーがあるポジションに憧れ,そのポジションに就くことができたら誇りを持って働く。これはとても素晴らしいことだと思います。もちろん,そのポジションに期待されるあり方が,他者を不幸にしないものであるということが前提ですが。
では,メンバーがこういった欲求を自然ともつようになる組織をつくるには,どのような工夫が必要だと考えますか?そういった工夫を考えて組織をつくっていくのって,とてもおもしろいですよね。少し考えてみてくださいな。最終レポートに活かすことができると思いますよ。
まず、現代は多くの人が毎日帰る家もあり、ある程度自由に食事を摂れていると思います。なので現代人のほぼ全員が承認欲求(自尊欲求)を持っていると思います。今回のFBで1つ目に取り上げられていた様に現代社会はSNSが日常生活に完全に溶け込んでいます。いわゆる「映え」や「バズる」といった言葉、YouTuberが動画の最後に言う「チャンネル登録と高評価お願いします」も全て元をただせば承認欲求です。
私が考える現代人はまずそこが満たされて初めて余裕ができ、様々な欲求が出現し、満たしていくのではないかと考えました。
もちろん仕事の面で見ても承認欲求は人間のベースの部分に存在していると思います。ですが仕事の際に人間の中に承認欲求と同居しているのが権力動機だと思います。
突然ですが私はどんな組織でも上に立つ人間は2パターンの人間しかいないと思っています。それは、自分の理想があり、実現のために上に立ちたい人間と、部下に全てを丸投げして楽をしたい人間です。もちろんこの2つのパターンの人間は考え方も全く違います。ですが権力動機を以って行動している点は全く同じです。欲求や動機が同じでもその組織が生き残り続けれるかどうかは上に立った人間の志の違いだと思います。
承認欲求が重要であるとするのは,一見するとマズローの欲求階層説と同様です。しかし,マズローが承認欲求を5つある欲求のうちの上から2番目という高位に位置付けていたのに対して,この回答では現代人は承認欲求が基礎にあるのではないか,とされています。生理的欲求や安全欲求は満たされているとしているので,社会的欲求と承認欲求の関係性に疑問を投げかけているとも言えますね。そうすると,なぜそのように考えたのかを知りたくなります。今,回答に書かれているのは,承認欲求が重要であると考えた根拠であって,理屈ではありません。その理屈について回答者自身が考えてみること。それが今後の人間観の形成に大きく寄与するように思います。ぜひトライしてみてください。
私なりに考えた人間の欲求は五つある。一つ目は、生存欲求だ。これは、今回の講義でも取り上げられていたように、人として生物として生きていく中で必要とされている物を行うための欲求で、これは本当に必要と思った。
二つ目は、集団作成・加入の欲求。これは、自身がどこかの団体やグループに存在したい、入りたいと思うものだと考える。また、そのグループ内での助け合いなどを行っていったりする上で必要になってくると思う。
三つ目は、循環欲求。これは、依存に近いものだと思う。ゲームをやりたいや動画を見たい、あの講義を受けたいなどと考えて実現し欲求が満たされたが、時間が経つにつれてもう一回,などと考えてまた欲求を解消していくようなものがあると考える。
四つ目は、差別的欲求。これは学校や職場などで発生することがある虐め、差別などをしてやると思ってしまうものであると思う。これには権力動機にすこしだけ関わってるのではないかと思う。誰かより優越な立場で下の物を罵倒し続けたりすることがあると考えたからだ。
五つ目は、自己実現欲求だと思う。講義で述べていた内容そのものの様になってしまうが、将来の夢を持っている時点でこの欲求はあると考える。いくら叶うことができなくたってかなえようと努力をする。達成してもできなくてもどうにかして夢に道をつなげようと努力するからそう考えた。このように、私は人間の欲求は五つに分類できると考えた。
5つの欲求を挙げてくれていますが,ここでは4つめの欲求として挙げた差別的欲求について考えていきます。歴史的に見ても,人類は自分とは異なると認知した存在を差別したり攻撃したりしてきました。そしてそれは,悲しいことですが今でも続いています。このように見ると,差別的行為(差別に基づく攻撃的行為)は,たしかに人間の本性に基づくものであると考えることができます。
他方で,別の可能性も考えられます。差別的行為は,何か別の欲求を充足するために遂行されたものである可能性です。たとえば,自分が所属する社会の外にいる存在からの攻撃は,自分が所属する社会を破壊する可能性があります。自分が所属する社会が破壊されると,安全欲求や社会的欲求が充足されなくなる可能性があります。それを防ぐためには,自分が所属する社会や集団を守る必要があります。差別的行為は,そのために遂行される行動である可能性も否定できません。もしそうだとするならば,「差別はダメだ!」と言っても効果はないように思えます。
個人的には,その行為の背後に,その行為への直接的欲求があることを当たり前のように前提としない方がいいように思います。その行為がなぜ遂行されるのかをもう一歩踏み込んで考えてみることは,とても価値があるのではないでしょうか。少しだけ回り道をして考えてみることも楽しいですよ。
4.講義内容:人間はどうやったらやる気になるのでしょうか?(2)
ここからは今回の講義内容に入っていきます。本日お話しする内容は次の2つです。1つはモチベーションの過程理論について。そしてもう1つはモチベーションに関する補論です。メインは過程理論についての説明ですが,補論でも考える価値がありそうなことについてお話しします。「補論とはなんぞや?」とか「本筋と関係ない話をするんかい!」と思うでしょうが,補論の意味合いについては「5.補論:承認欲求への注目」でお話しします。
ということで,まずは過程理論についてお話をしていきます。過程理論は,人々が動機づけられる心的な過程を明らかにすることを目的としたものです。前回の講義noteで内容理論がwhatを問うものであったのに対して,過程理論はwhyやhowを問うものと考えるとわかりやすいです。
前回は内容理論について割とガッツリ説明しましたが,実は近年主流になっているのは過程理論です。モチベーションの内容ももちろん重要ですが,内容にばかり気を取られてしまうと,「人は○○によって強く動機づけられる → じゃあ○○を刺激すれば人は行動するんだ!」という極めて単純な図式で物事を考えてしまうかもしれません。この図式を経済人モデルに当てはめると「人はお金によって強く動機づけられる → じゃあお金をたくさん与えれば人は行動するんだ!」となりますし,社会人モデルに当てはめると「人は人間関係によって強く動機づけられる → じゃあ職場の人間関係を良好にすれば人は行動するんだ!」となります。時と場合にもよりますが,僕たちはそれほど単純に動機づけられてはいないでしょう。僕たちが動機づけられるその複雑さを理解するのが過程理論であると言えるでしょう。そう考えると,内容理論よりも過程理論に焦点が当てられてきていることも納得できます。
過程理論に分類される考え方はいくつもあります。この講義noteではその中でも代表的な公平論,期待理論の2つについて紹介します。
公平理論
公平理論とは,「人間は自分と他者を比較して不公平さを感じた場合に,それを是正するための行動に動機づけられる」というものです。イメージしづらいかもしれないので,具体的な状況を想定して考えてみましょう。
あなたは飲食店でアルバイトをしています。そのアルバイト先では,仕事ぶりを認められると時給が10円ずつアップしていきます。あなたはとても真面目に働いていて,とうとう時給をアップしてもらうことができました。お金をたくさんもらえることももちろん嬉しいですが,目に見える形で評価してもらえるのはさらに嬉しいものですよね。
ですが,納得のいかないこともあります。あなたと同じアルバイト先に,Aさんがいます。Aさんはあなたと同じタイミングでアルバイトを始めましたが,あなたから見ると仕事の覚えが遅く,また熱心に仕事をしているようにも見えません。しかし,それにも関わらず,あなたの時給が10円アップしたのと同じタイミングでAさんの時給も10円アップしたのです!こんちくしょー。
あなたがこのような状況に直面したら,どのように感じるでしょうか。所詮Aさんは他人ですから,気にしても仕方がないとも言えます。しかし,やはりどこか納得できないのではないでしょうか。「こんなに努力した自分と,大して努力していないAさんが同じ評価なの?」と感じるのではないでしょうか。要するに,不公平だと感じるのではないでしょうか。不公平だと感じたとき,人々はどうするのでしょうか。この点から人々の動機づけと行動を考えたのが,公平理論です。
こうしたときの人々の行動について,公平理論では次のように考えます。まず,あることを達成するために自分(a)が投入したすべて(努力,経験,スキル,時間など)をI(a)とします。「I」は投入を意味する「Input」の頭文字です。そのI(a)によって自分が得られるすべて(報酬,昇給,昇進,評価など)をO(a)とします。「O」は成果を意味する「Outcome」の頭文字です。これに対して,あることを達成するために他者(b)が投入した努力や時間などをI(b),それによって自分が得られる報酬をO(b)とします。人々の行動への動機づけは,投入したIに対して得ることができたOが見合っているか否か,要するに「努力と報酬が割りに合っているか否か」をどのように感じたかによって左右されます。
公平理論で重要なのは,自分が得ているOが割りに合っているか否かは,Oの客観的な総体ではなく,他者との比較を通じて主観的に知覚される,という点です。つまり,O(a)/I(a)とO(b)/I(b)を比較することで初めて,人々は自分がきちんと評価されているかを判断します。O(a)/I(a)とO(b)/I(b)を比較するとき,以下の3つのパターンを想定できます。

①は,自分(a)と他者(b)の間に是正すべき不公平がない状態です。不公平がないので,当然ですがそれを是正する行動に動機づけられることはありません。むしろ,公平感を覚えているので,モチベーションが向上します。きちんと評価されるのは嬉しいですよね。
②は,自分(a)よりも他者(b)のほうが評価されていると感じている状態です。自分(a)が不公平を感じている状態ですね。このとき,自分(a)は①の状態に近づけるための行動に動機づけられます。③は②とは逆に自身の評価が過剰であると知覚している状態ですが,その場合でも①の状態に近づけるための行動に動機づけられます。
②・③の状態を①の状態に近づけるための行動とは,O(a),I(a),O(b),I(b)のそれぞれを変化させることです。②の状態を①に近づけるためには,O(a)を増やすこと,I(a)を減らすこと,O(b)を減らすこと,I(b)を増やすことのいずれか,あるいはこれらを組み合わせることが必要です。③の状態から①の状態に近づけるには,これとは逆のことが必要です。
ここでは②の状態を①の状態に近づけることを考えてみます。たとえば,O(a)を増加させるためには,報酬を増やしてもらうように上司や組織に要請するでしょう。I(a)を減らすために,手を抜いたりするかもしれません。O(b)を減らすために「あいつ,もらいすぎですぜ」と上司や組織に働きかけたり,I(b)を増加させるために他者(b)の足を引っ張るなどするかもしれません。ほら。不公平を是正するために,特定の行動に動機づけられましたね?これが公平理論です。
ただ,O(a),I(a),O(b),I(b)は実際に変化させなくても構わない可能性があります。先ほどから何度か「知覚」という言葉が出てきていますが,これは「そのように感じる,思う,認識する,評価する」とかそういう意味です。要するに,O(a),I(a),O(b),I(b)は客観的に測定されるのではなく,あくまで主観的な評価でしかないということです。ならば,これらに対する自分自身の認識を改めていくという変化のさせ方もあります。たとえばO(a)を増加させるというアプローチをとるときのことを考えてみましょう。実際にお給料を増やしてもらうという方法もあります。しかし,これとは別に,自分が得ているものはなんなのかを自分なりに考えて,そこに価値を見出す,ということも方法もあり得ます。「よくわからないけどやらなければいけないこと」に直面したときに,やりがいとか,将来に役立ちそうとか,これができたらモテそうだとか,自分なりに意味を見出したりしたこともありませんか?これが,自分の認識を改めるということです。

しかし,どうやっても②・③の状態を①の状態に近づけられないことがあります。そのときの行動として2つの可能性が考えられます。1つは,その場から離脱することです。会社であれば退職することです。どう考えても不公平なのにその状況を改善することができず,さらにその状況に我慢できないのであれば,そこから離脱するしかありません。
もう1つの行動は,比較対象を変えることです。公平か否かは,特定の誰かと自分を比較しないことには知覚されません。その特定の誰かは,あくまで自分が(無意識的に)選んだ相手です。したがって,その比較相手を変えてしまうことで,知覚する公平感も変わります。
たとえば,会社のお偉いさんの強力なコネで入社した同僚がいるとしましょう。その同僚は,とんでもなく無能で,しかも仕事をしません。でも,強力なコネのおかげであなたよりもずっと早く出世していきます。あなたが社内での出世に興味がある場合に限られますが,これはもうやってられないでしょう。そんなときは嫌気がさして退職を検討するかもしれません。あるいは,そんなスペシャルな相手と自分を比較しても意味がないので,スペシャルな背景を持たない同期を改めて比較対象とするかもしれません。
ここまで見てきたように,公平理論は内容理論で紹介した理論よりもいくらか複雑です。内容理論に分類されるものの多くは,ある欲求を抱いたら,それを充足するために行動するということが前提とされていました。あるいは,そもそも特定の動機を持つがゆえに,それに応じた特定の行動をとるという説明がされていました。
これに対して公平理論では,人々がなぜある行動につながる動機を抱くのか,というレベルから検討をしていました。人々の心的なプロセスにより深くアプローチしていると言えるでしょう。
期待理論
過程理論として紹介するもう1つの理論は,期待理論です。期待理論とは,「ある人がある行為を遂行するように作用する力は,その行為がいくつかの結果をもたらす期待と,それぞれの結果がもっている報酬の積の和である」というものです。書いといてなんですが,よくわかりません。ですので,図で説明します。なお,期待理論にはかなりバリエーションがあり,複雑で精緻なモデルもあるのですが,今回は非常に単純化したモデルを通じて期待理論を説明します。

まず,人々が何かの行為を遂行します。そうすると,何かしらの結果が生じます。その結果は1つのこともあれば,非常に多岐にわたることもあります。そして,それぞれの結果に応じて,何かしらを得ることができます(何かしらばかり)。要するに,行為の結果(1次の結果)として得られると知覚される望ましい結果(2次の結果)への期待の総和が大きいほど,その行為に強く動機づけられる,というのが期待理論です。行為の結果として期待できるものが大きく,かつそれを得られる確率が十分に高いとき,人々は強くその行為に動機づけられます。

相変わらずよくわからないので,「大学生が積極的に学習する」という行為への動機づけについて考えてみましょう。上の図はそれを示したものであり,厳密性はまったくありませんが,期待理論の骨子さえつかめればそれで構いません。
積極的な学習は,いくつかの結果(1次の結果)をもたらします。たとえば,積極的に学ぶことで良い成績を可能性は高まります。豊富な知識も得られるでしょう。さらに,学習していく中であれやこれや考える経験を経て創造力が強化されるかもしれません。
こういった結果は,さらに別の結果(2次の結果)をもたらします。良い成績を上げることで,就職活動において評価される可能性は高まります。豊富な知識を得ることは,就職活動時に優位に働くだけではなく,就職後にも役立つでしょう。創造力を高めることは,働く上での優位性だけではなく,人間的な豊かさをもたらしてくれるかもしれません。
ここまで見てくると,「勉強っていいことばかりやんけ。よっしゃ勉強したろ!」となりそうですが,残念ながらあまりそうなってはいません。積極的に学習する学生もいれば,そうではない学生もいます。いつの時代だってそうです。積極的に学ぶ学生とそうではない学生の違いとはなんなのでしょうか?積極的な学習に動機づけられる人々とそうでない人々の違いとはなんなのでしょうか?それは,「結果として得られるものをどれだけ手にしたいか」と,「それを得られる主観的な確率」が人によって異なるからです。
積極的に学習しているある学生は,どうしても入社したい,憧れの企業があり,是が非でも就職活動を有利に進めたいと考えています。そのためには良い成績を収めることが必要条件であり,これまで努力をしてきたので良い成績を取ることにも自信があります。つまり,この学生は成果として得られる就職活動の優位性に非常に魅力を感じており,そのために必要な良い成績を高い確率で得られると信じています。得られるものに大きな魅力を感じており,それを得られる確率が一定以上ありそうだと知覚したとき,人はそのための行動に強く動機づけられます。
これとは逆に,積極的に学習をしないある学生は,2次の結果には関心がないのかもしれません。だから,それにつながる1次の結果を得ようせず,1次の結果をもたらす積極的な学習にも動機づけられません。あるいは,2次の結果には関心があっても,それが1次の結果によってもたらされるとは信じていない可能性もあります。さらには,積極的に学習をしても,良い成績などの1次の結果を得られる可能性があまり高くないと考えているのかもしれません。得られるものに魅力を感じていなかったり,魅力を感じていてもそれを得られる可能性が低いと考えている場合に,人々はそのための行動にそれほど強く動機づけられません。
これが期待理論の基本的な論理です。要するに「ある行為によって得られる報酬の総和」と「それを得られる期待」を掛け合わせたものが大きければ大きいほど,人はその行為に強く動機づけられる,ということです。ものすごく簡単に言うと,「得られるものが魅力的なら頑張るけど,あんまりそれが得られそうになかったら頑張らない」ってことです。これを数式で表すと以下のようになります。

ここで改めて確認しておきたいのは,報酬の大きさも,それを得られる期待も,あくまで主観的なものであるということです。公平理論と同様ですね。ある報酬は誰かにとっては魅力的でも,別の誰かには魅力的ではないかもしれません。ある報酬は,誰かにとっては確実に得られるものかもしれないけど,別の誰かはそれを得ることを難しいと感じるかもしれません。期待理論に基づいて誰かを動機づけようとするとき,その人が何にどれほどの魅力を感じているのかを理解しなければいけません。そして,その魅力を感じているものを手にするのは不可能ではなく,努力によって得られるんだということも,合わせて伝えていかなければいけません。「自分が好きなことは相手も好き」と早合点したり,具体的な方法に触れるでもなしに「大丈夫!できるできる!」という無責任な声かけをすることからはほとんど効果が見込めない,ということですね。
たしかに僕たちは,期待が大きければ積極的に行動しますし,そうでなければそれほどやる気が出ません。期待理論は,そのことを前提とし,どのようなときに期待が高まり動機づけられるについて理論化したものです。この講義noteではかなり簡潔に説明していますが,より精緻なモデルもあるので,ぜひさらに理解を深めてください。
5.補論:承認欲求への注目
さて。前回と今回の2回を用いてモチベーションについてお話ししてきました。この節では,この2回の講義内容と関連して,あなたに少し考えてほしい話題の提供をします。その前に,なぜ「補論」を設けるのかについて説明させてください。
この講義で紹介している内容は,経営組織論の多くのテキストで紹介されている代表的な理論ばかりです。それらはどちらかと言えば古い理論で,「そんな古い理論が役に立つのかしらん?」と思うかもしれません。しかし,現代でもテキストに掲載されている古い理論は,その後の研究の基礎になっているからこそ,長い歴史の中で淘汰されず,今でもテキストに掲載されているのです。ですから,経営組織論の初学者であるあなたにこれらの理論から紹介することは適切であると,僕は考えています。
他方で,あるいはその代償として,この講義では最近の議論についてあまり触れていません。その理由は,最近の議論は現代的な問題意識に基づく刺激的なものですが,まだ提唱されて日が浅いこともあり,たしかな知識として講義で紹介することに僕が抵抗を覚えるからです。
ただ,あなたの興味・関心などを考慮すると,やはり少しは最近の議論にも触れておきたいとも思います。そこで,必ずしもテキストには掲載されていないけれども意義のあるトピックを,「補論」という形で取り上げ紹介します。
今回の補論で検討するのは,マズローの欲求階層説でも触れた「自尊欲求」あるいは「承認欲求」と呼ばれるものです。人は誰かに自分という存在を評価し認めてもらいたがっている,という欲求ですね。自尊よりも承認の方がイメージが伝わりやすいので,この補論では「承認欲求」で統一します。前回の課題に対する回答の中で,承認欲求に触れたものが多かったため,承認欲求をめぐる最近の議論を取り上げることにしました。
少し復習しましょう。前回の講義noteでも紹介しましたが,下の図は欲求階層説が想定している欲求の階層性を示したものです。

欲求階層説では最上位の欲求として自己実現欲求が配置されています。そのため,その1つ下の次元にある承認欲求(自尊欲求)については見過ごされがちです。しかし,この承認欲求こそが,実は日本人にとっては重要なのではないかという主張があります。同志社大学の太田肇先生は,その代表的な論者として承認欲求に関する多くの書籍を執筆されています。以下のリンクで紹介しているのはその一例です。
あまりそういった印象はないかもしれませんが,実は経営学も科学です。科学は基本的に現象の普遍的な説明を目指します。普遍的というのは,いつでもどこでも当てはまる,ということです。僕の家と隣の家で電気の性質が異なるなんてことはおそらくありません。あったら困ります。日本とブラジルでも,きっと同じでしょう。自然科学ではこの普遍性はかなりの程度,保証されるという前提が置かれています。
他方で,経営学が含まれる社会科学でも同様かというと,僕はよくわかりません。ただ,暫定的に僕の考えを述べるのであれば,自然科学ほどの普遍性はない,というものになります。普遍的に語ることのできない現象にこそ,僕の関心はあると言ったほうがいいかもしれません。
なぜそういった現象に関心があるかというと,人間は社会的につくられていく存在であり,そして経営はその社会的につくられた人々による行為だからです。「人間が社会的につくられる」というのは,僕たち人間は,他者や歴史,文化と関わり合うことなく生きていくことが不可能である,という意味です。僕たち人間は成長していく中で,好むと好まざるとも,意図的にも意図せざるとも,直接的にも間接的にも,それら社会的なものと関わり合いながら成長していきます。だから僕たちは,社会的につくられる存在なのだと考えられます。
経営という行為は,社会的につくられた僕たちによるものです。したがって,どのようにすれば経営がうまくいくかという問いに対する答えも,極めて社会的な文脈に依存したものであると言えるのではないでしょうか。僕はその文脈を踏まえた上で,企業の行動を理解し,解き明かしていきたいと考えています。その上で,それでもなお多くの企業に共通することを発見することができれば,それが最高です。そこを目指していきたいと考えています。これはあくまで僕のスタンスであり,正しいというわけではありません。誰にだって信念はあります。ただ,僕はこのようなスタンスである,ということはご理解ください。
ここで,承認欲求に話を戻します。日本人にとって承認欲求が重要なのではないかという議論がなされているとお話ししましたね。僕は前述のスタンスなので,日本人に特有のモチベーションがあるという主張に違和感を覚えません。むしろそうだろうと思います。
では,なぜ日本人にとって承認欲求が重要なのでしょうか?ここからのお話しは,太田肇先生の論考を中心にまとめたものです。太田先生は日本の組織には「表の承認」と「裏の承認」があるとしています。「表の承認」とは,大きな成果を上げて称賛されるとか,自分の能力や個性を認めてもらうことを意味します。これに対して「裏の承認」とは何かと言うと,和を乱さないとか,規律を守るとか,義理を果たすなどです。表の承認が加点評価であるのに対し,裏の承認は減点評価されないためのものと理解するとわかりやすいでしょう。
詳細は太田先生の各著作を読んでいただきたいのですが,日本企業は歴史的にこの裏の承認を重視してきたとされます。そのため,表の承認が十分にされず,さらには「出る杭は打たれる」という言葉があるように,表の承認を受けにくい状況になってしまっています。
かつては,裏の承認だけでも満足できる時代でした。しかし,現代は個性の尊重や創造性などが重視される時代です。それらを発揮するように人々は振る舞いたいのに,企業がそうさせてくれない。人々はこれまでの日本企業の文脈を理解しているので,「自分を評価してくれ!」と声高に言うことができない。だから人々は承認欲求に飢えていて,自己実現欲求よりも承認欲求をまず満たすことが日本企業では重要ではないか。これが太田先生が承認欲求を重視する論理です。この承認欲求を刺激するユニークな施策の事例を見つけたので,以下のリンク先をご覧ください。
紹介されている株式会社匠工芸という会社では,同僚や顧客から褒められると,社長からコインを1枚もらえます。そのコイン1枚で,社内にあるガチャガチャを1回だけ引くことができるのですが,そのガチャガチャには100円から1000円が入っていて,ガチャガチャを引いた社員はそれをもらうことができます。
「なんだたいした額じゃないやんけ」と思うでしょう。金額的にはその通りなのですが,ガチャガチャを引くとき,結構職場が盛り上がるそうです。また,金額は小さいけれども,「自分が認められた」とか「自分は人の役に立っている」などと感じられるそうです。まさに承認欲求が満たされるわけです。詳しくはリンク先をご覧いただきたいのですが,なかなかおもしろい施策ですよね。
今回の補論では承認欲求について考えました。冒頭にもお話しした通り,余談にするにはちょっと長めでしたね。あなたは,承認欲求についてどう考えますか?これを考えることは,あなたなりの人間観を形成することにつながっていきます。大学の4年間には様々な側面がありますが,僕は自分なりの世界観や人間観,モノの見方を形にしていく期間だと考えています。なかなか答えが出ないでしょうし,そもそも答えがあるのかもわかりませんが,だからこそ考える価値がある問いであるとも言えます。じっくり時間をかけて考えていってもらえると嬉しいです。
6.終わりに
僕自身はモチベーションについて研究しているわけではなく,特段モチベーションに詳しいということはありません。それでも,2回の講義を使ってモチベーションについてお話ししたのは,繰り返しになりますが組織は人々が協働する場だからです。第2回講義note「「経営組織論」ではそもそも何を学ぶのか?」にも書きましたが,組織というのは企業や病院など,具体的な協働体系の共通点を抽出したものです。協働がなされていなければ組織ではなく,その意味では経営組織論の1つの目的は,「どのようにすれば組織において人々はより良く協働するのかを考えること」であると言えます。
このことについて考えていくためには,そもそも人はどのような存在であるのかを考えていく必要があります。これは第3回講義note「人間ってどんな存在だと思いますか?」でお話ししましたね。それに加えて,人は何に,そしてどのように動機づけられていくのかも考えなければいけません。多くの場合,人々は何かしらの理由やきっかけがあって行動します。つまり,人々を動かすにはその「何かしらの理由やきっかけ」を理解し,そこに働きかけなければなりません。組織メンバーの共同を促進させるのがリーダーの役割だとするならば,人々のモチベーションについて考え,理解するという姿勢がリーダーには求められます。
繰り返し述べていますが,僕はあなたにはぜひ組織のリーダーになってほしいと願っています。人々のモチベーションを考えられるようになることは,リーダーの必要条件です。ですから,モチベーションについて時間をかけてお話ししました。ぜひぜひ,誰かの行動を眺めるとき,あるいは自分自身の行動について考えるとき,この講義で学んだモチベーションの視点を活用してもらえると幸いです。
さて。ここからは次回予告です。この講義で紹介したモチベーションについての理論は,個人に関するものがほとんどでした。次回は,議論のレベルを1つ上げて,組織の集団心理的側面に焦点を当てます。具体的には「組織文化」についてお話しをしていきます。相変わらず抽象的な話が多くなると予想されますが,次回もゆっくりじっくり時間をかけて講義noteを読んでいただければ幸いです。
ではでは。
7.課題
<課題>
今回の講義noteで学んだ期待理論を用いて,あなたがこれまで高いモチベーションで臨んだ経験と,低いモチベーションしか抱けなかった経験について,それぞれ説明してください(400字程度)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
