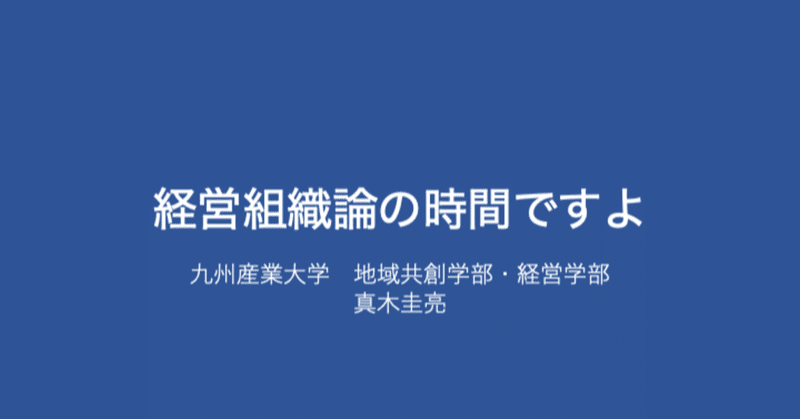
第4回(2020/05/25) 経営組織論 人間はどうやったらやる気になるのでしょうか?(1)
1.はじめに
このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第4回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。
こんにちは。ここ数日は福岡県内におけるCOVID-19感染者数も0人となっており,ずいぶんと落ち着いてきた印象がありますね。それに伴い,九州産業大学でも徐々に対面講義へと戻っていくようです。この経営組織論は,6月2週目の講義まではこの講義noteを活用した形式で進行します。その後については状況を見ながら判断していきます。ちなみに少なくともこの講義については,遠隔講義でも対面講義でも課題の量は変わりません。やったね!(やってない)
さあ,今日もいつもの余談から始めていきましょう。あなたは,企業においてどのような人が高い成果を上げられると思いますか?学歴の高い人?能力の高い人?見た目が良い人?人脈が豊富な人?上司に可愛がられる人?もちろん,業種や職種,職位,企業の状況にもよるので,一概に「○○な人!」というのは難しいでしょう。いろんな可能性が考えられますね。
成果を上げることができる人材像についてはいろいろなことが言われていますが,これといった統一的な見解はありません。ですが,何にでも流行というものはあって,かつて主にアメリカのビジネススクール(ビジネスパーソンがビジネスを学ぶために通う大学院です)で流行した人材像があります。それは「Happy Worker Model」というものです。これは,従業員の満足度と生産性が比例する,という考え方です。要するに,満足している従業員はより頑張って働くので高い成果を上げるけれど,満足していない従業員は頑張らないので低い成果にとどまってしまう,ということです。なんとなく,そんな気もしますよね。たしかに満足している人のほうが積極的に仕事に取り組む印象があります。実際に,Happy Worker Modelに基づいて従業員満足を向上させる取り組みを導入している企業もあります。
他方で,やはりHappy Worker Modelは素朴すぎるようにも思います。Happy Worker Modelの背後には,「満足すると人はさらなる満足を得るために行動し,その行動が成果に結びつく」という論理があります。下のような関係性ですね。

この関係性は,自明なもの,当たり前なものなのでしょうか。たとえば,満足してしまったらもう行動しないかもしれません。「もうこれくらいでいいや」となることってありますよね。また,行動が成果に結びつくとも限りません。その行動は成果とは無関係かもしれません。その行動が成果に結びつくか否かは状況によるかもしれません。さらに,「従業員が満足しているから成果が上がる」のではなく,「成果が上がっているから従業員が満足している」という可能性も指摘されており,実際にこれを支持する研究もあります。いずれにせよ,Happy Worker Modelはわかりやすいですが,正しいとは限らないようです。
僕もHappy Worker Modelを初めて知ったとき,「そんな単純なことがあるかいな」と感じました。経営学を学んでいると,組織の成果は非常に多様な要因からなる複雑な関係が生み出したものであることがよくわかります。ですので,「○○だけすればあなたの会社の成果は上がります!」みたいな書籍などの売り文句はまったく信用しません。何か1つを変えたところで組織の成果が劇的に変わるなどありえないし,仮にあったとするならば,見えているのがその1つに過ぎないというだけです。Happy Worker Modelに対しても,同様に感じていました。
最近ではHappy Worker Modelという言葉を聞かなくなりました。その代わりに耳にするようになったのは「Frightened Worker Model」という言葉です。Frightened Workerとは「怯える従業員」という意味で,人々を行動に駆り立てるのは満足ではなく,減給や降格,解雇などに対する恐れであると考えるのが,Frightened Worker Modelです。組織が成果を上げるには,そのための行動をメンバーにしてもらわなければなりません。そのためにはメンバーを方向づける規律が必要であり,規律を守らせるにはそれを破った場合の罰が必要です。Frightened Worker Modelには多少の息苦しさを覚えますが,これはこれで筋が通っています。
ただ,最近,思うんです。「Happy Worker Modelは科学的には正しくなさそうだけれど,でもHappy Workerであること自体はとても大事」だと思うんです。日本では社会人になると,だいたい最低でも1日8時間は働きます。1日の1/3は仕事をしているわけです。考えてみたら,1日の1/3を怯えて過ごすなんて異常です。満足し,幸せに過ごすほうがいいに決まっています。そうでないと心の健康を維持できません。たしかに人は放っておくと怠けてしまう弱い存在かもしれません。したがって,Frightened Worker Modelを前提としたほうが,組織的な成果は上げやすいのかもしれません。でも,僕個人としては,働く人々が満足することをまず前提とし,その上でどのように経営をしていくのかを考えるべきではないか,それが当たり前ではないかと考えています。
この講義を受講しているあなたの世代の人々は想像できないかもしれませんが,かつての日本企業は従業員を大切にしていると言われていました。しかし,ブラック企業をめぐる報道の印象が強すぎて,働くということ自体をネガティブに捉えてしまってはいませんか?もちろん,働くことはいつだって無条件に楽しいわけではありません。やりたくない仕事もあるし,うまくいかないこともあるし,苦悩し葛藤することもあります。でも,それらを含めて,全体としては満足できるような仕事のあり方,組織のあり方を考えつくっていくことができるようなリーダーになってほしいと,僕はこの経営組織論を受講しているあなたに願い,期待しています。それは「かつての日本企業に戻れ!」という懐古主義ではありません。それはもはや難しいでしょう。だから,あなたにはこれからの時代において働く人々が幸せになることができる組織を考えてほしいのです。そのために,初回の講義noteでお伝えした最終レポートのテーマを設定しているのです。

2.前回の振り返り
ここからは,前回の講義内容を振り返っていきましょう。前回は「そもそも人間とはどんな存在なのか?」がテーマでしたね。
協働体系である組織のリーダーは,組織目的を達成するためにメンバーの行動を方向づけていくが仕事の1つです。そのためには,どのようにすればメンバーを動かすことができるのかを考えなければなりませんが,他方でメンバーは多様です。そのため,「多くのメンバーはきっとこういうことを考えるだろう」という前提を置く必要があり,前回講義ではそれを人間モデルと呼びました。
これまでの研究を整理すると,人間モデルは以下の4つに分類することができます。
・経済人モデル
・社会人モデル
・自己実現モデル
・複雑人モデル
それぞれのモデルの内容については前回資料をご参照ください。このうち複雑人モデルは,「人間には様々な側面があり,それらは併存している」と考えるモデルです。たしかに,経済的報酬も人間関係も自己実現もどれも重要で,人間はそれらをすべて併せもっています。その複雑性を受け入れていくことが重要なのではないかと述べました。
以上が前回の内容です。人間モデルの中心には「人々は何に動機づけられるのか?」という問いがあります。今回は,その動機づけ,つまりモチベーションについて,より詳しく考えていきます。
3.前回の課題へのフィードバック
現代の人々は、他人に自分の経験価値を認められることに動機づけられると考えます。現代人は、snsなどで自分の経験を友達や家族のみならず、世界中の人々に発信しています。自分が見た景色や食べた食べ物を、シンプルに人々に紹介したいという動機で発信している人ももちろんいると思いますが、その投稿を見た人の評価ばかりを気にする人も多くいると思います。また、何人の人から「いいね!」をもらえたか、短期間でどれだけ爆発的に話題になった(バズった)かなどということで自分の価値を測っている人もいるように感じられます。自分が他人からどうされているかを評価を気にして、他人から認められたい。つまり現代人は自己顕示欲が高いと言えるでしょう。
私が組織のリーダーであったら、部下のモチベーションを上げるために、良い仕事をしたら、世間の人々が自分たちを認めてくれる。悪い仕事をしたら、世間の人々は自分たちに興味を持ってもらえなくなるという意識を持ってもらいます。世間から良い企業だと認めてもらうためには、良いサービスや商品を提供することであり、良いサービスや商品を提供できれば、世間の人々に認めてもらえるという意識を部下が持てば、部下のモチベーションは上がり、仕事の効率も上がると考えたからです。
SNSの隆盛から,現代の人々は自己顕示欲が強いと考えてくれました。そして,それを前提とすると,メンバーの仕事が世間とどのように関わっているのかについて意識づけをすることがリーダーにとって重要な仕事ではないか,となるわけですね。この背後には「自分が所属している企業が認めてもらえたら,自分も認めてもらえたように感じられる」という考えがあるように見受けられます。この「メンバーは自分が所属している組織と自分自身をオーバーラップさせ同一視する」という考えは,「組織的同一化(organizational identification)」と呼ばれ研究されています。とても重要な考えなので,また別の回で少しお話ししますね。
現代的なモデルとしては近年「社会人モデル」に近い会社が多いように思う。大体どの会社も社員同士の交流や、会社と地域の人々との交流を大事にしている印象を受ける。ただし、雇用される側はあまりそこに重きを置いていない様に思う。もちろんメンバー同士の円滑なコミュニケーションは魅力的であるし、そういう会社のほうが働きたいと思うだろう。しかし、最近はライフワークバランスを重要視している人が多いように思う。
今までの様に仕事で全力を出し切って休日はゆっくり英気を養う、というより、自分の趣味のための休日を楽しく過ごすために仕事をこなす、という考え方のほうが身近だ。人間だれしもいろんなモデルが自分の中で混在しているが仕事に対する動機づけが仕事に関わらないことであることが近年のモデルであると考える。それに伴い自分の仕事の範囲がきっちり決まっているほうが今の人たちは働きやすいのではないかと考える。自分がリーダーであればそこの振り分けを明確に行う。仕事の目標が明確であれば自分の休日を確保するために仕事に取組み、きちんと成果を上げ、休日に思いっきりリフレッシュできるからだ。
現代的な人々のモデルと,それに対する組織の認識がズレているのではないか,という重要な示唆ですね。組織は「社会人モデル」を前提とした各種施策を実施しているけれど,メンバーはそれに魅力を感じず,ワークライフバランスを重視している。したがって,仕事は仕事,プライベートはプライベートときっちり分かれていて,仕事の範囲も明確に決められているのが良いのではないかということ。なるほどな,と感じます。
働き方改革が叫ばれていることもあって,こうした働き方に関する議論は盛んに行われています。その中でワークライフバランスについても議論されていますが,以下のリンク先のようなことも言われているようです。これが正しいというわけではありませんが,どのように感じますか?またご意見など聞かせてもらえると幸いです。
毎回,書いている気もしますが,また望ましくない回答についてお伝えしておきます。ご存知でしょうが,この講義では講義内容を要約する<課題1>と,講義内容を踏まえて経験を振り返ったり,あなた自身の考えを書く<課題2>を毎回の課題としています。毎回,提出された課題を見ると,<課題2>の回答欄に講義内容をなぞった内容を書いているものが散見されます。これは無意味なのでやめてください。意図は不明ですが,必要文字数を埋めるために適当にしているようにしか見えません。僕は「努力した上でできない」ことには寛容ですが,ウソをついたり手を抜いたりすることを許容するつもりはありません。それが教育であり,また僕の職業倫理に反するからです。こういった手を抜いたように見える課題を提出した場合は採点対象外となるので注意してください。
4.講義内容:人間ってどうやったらやる気を抱くのでしょうか?
モチベーションについて考える意義
今回のテーマは「人々が働く上でのモチベーション(動機づけ)」についてです。モチベーションとは,平たく言うと「やる気」です。このモチベーションについては内容が盛り沢山なので,今回と次回の2回を使ってお話ししていきます。
組織目的は,組織のメンバーがその達成に貢献してくれない限りは達成できません。したがって,組織のリーダーは組織目的に対するメンバーの貢献を引き出してあげる必要があります。
ですが,メンバーはタダでは働きません。そりゃそうです。あなただって「本当に申し訳ないんだけど,今月のお給料,無しでいい…?」とかアルバイト先の店長に言われたら,さすがに「おいおい正気か」と思うでしょう。組織で働くことで何かを得ることができるからこそ,メンバーはその組織で働きます。つまり,メンバーは自分が組織に対して果たしている貢献に対して組織から得られるもの(誘引)が同程度か,あるいは大きいときに,組織目的に貢献します。メンバーの貢献を引き出すために,メンバーが望む誘引を提示・提供することも,リーダーの重要な仕事の1つと言えるでしょう。

上の数式は,あるメンバーが組織から得ている誘引(I)と,組織に果たしている貢献(C)の関係の3つのパターンを示したものです。誘引は英語でincentive,貢献はcontributionなので,それぞれの頭文字をとってIとCとしています。①はIとCが釣り合っていますね。したがって,①のときはこのメンバーは組織に留まり,共通目的に貢献します。しかし,IとCがまったくの同程度なので,少しIが小さくなったり,他の組織から得られるCが大きそうに感じたら,その組織を離れる可能性があります。比較的不安定な状態と言えますね。
②は,CよりもIが大きい状態です。この場合はメンバーは積極的に組織に残り,共通目的に貢献します。過剰な誘因を与えるわけにはいきませんが,望ましい状態と言えるでしょう。
②とは逆の状態,すなわちIよりもCが大きい状態が③です。「なんでこんなに頑張っているのに/こんなに成果を出しているのに,これだけしか評価されないの…?」という状態ですね。当たり前ですが,こういった状況ではメンバーがその組織に留まり続ける理由はないので,遅かれ早かれ離脱するでしょう。

このIとCのバランスをうまくとり,メンバーの貢献を引き出すことで組織目的を達成していくことが,リーダーには求められます。そのためには,リーダーはメンバーがどのようなことに,どのようにして動機づけられるのかを理解する必要があります。前回の内容とも関係しますが,リーダーにはメンバーの内面への深い理解(あるいは理解しようとする姿勢)が求められるのです。これが,モチベーションについて学ぶ意義の1つです。
ここで,この誘引と貢献について,あなた自身の経験から考えてみましょう。5分程度でワーク①に取り組んでみてください。

いかがでしょうか?きっと,頑張る気になった組織もあれば,そうなることができなかった組織もあったかと思います。あなたが参加していた組織は,この誘引と貢献の設計がうまくいっていたでしょうか?学んだことを使って振り返ることができるようになるといいですね。
モチベーション論の2つの分類
ここまで,モチベーションについて学ぶ意義をお話ししてきました。「モチベーションに関する理論」は大きく2つに分けることができます。1つは,「人々は何に動機づけられるのか?」や「人々がもつ欲求とはどのようなものであるのか?」を解き明かすことを目的にした「内容理論」です。そしてもう1つは,人々が動機づけられていくプロセスを解き明かすことを目的とした「過程理論」です。今回はこの2つのうち,内容理論に関する主要な理論を見ていきましょう。
<モチベーションの内容理論:欲求階層説>
モチベーションの内容理論としてまず紹介するのは,エイブラハム・ハロルド・マズロー(Abraham Harold Maslow)による欲求階層説です。マズローは人間の欲求は5つに分類でき,そしてその5つの欲求は階層を成しているしています。それを簡潔に示したのが下の図です。なお,前回の講義noteでは「自己実現については第4回講義noteで詳細に述べる」と書きましたが,想像していた以上に文章量が多くなってしまったので,別の講義noteに補論として書くことにします。

この欲求階層説にはいくつかポイントがあります。1つめのポイントは,前述したとおり,人間の欲求は5つに分けることができるということです。ここではこの欲求の5つの分類を見ていきましょう。
人間がもつ1つめの欲求は「生理的欲求」です。これは食欲は睡眠欲,性欲など,僕たちが他の動物と同様に生物として生きていくために満たそうとする欲求です。
2つめの欲求は安全欲求です。生命を脅かされないように安全なところで生きていきたいとか,現代社会で生きていくためにはお金が必要なので経済的安定性を求めるなどが,これに該当します。
3つめの欲求は社会的欲求です。これは,集団に所属したいであるとか,誰かから友情や愛情を受けたい,などといった欲求です。前回講義でお話しした社会人モデルの内容に近しいですね。
4つめの欲求は自尊欲求です。これは,誰かに認められたいとか,尊敬してほしいなどといった欲求です。前回の課題で「現代人は自己顕示欲が強い」と考えた回答を取り上げましたが,それもこの自尊欲求の現れであると考えられます。
5つめの欲求は自己実現欲求です。これは,自分が持つ可能性を最大限に発揮して,創造的に何か大きな目的を達成したいという欲求です。たとえば,これまでの大活躍によりすでに高い評価を得ており,お金も十分に持っているスポーツ選手であっても,それでもなお厳しいトレーニングを重ねてより高みを目指すことがあります。さらに高い社会的評価を得たいだけではないかという可能性もあり,それへの反論は難しいですが,おおよそ自己実現とはこういったイメージだと思ってください。
このように,人間の欲求は5つに分類できますが,これらは階層を成しています。これが欲求階層説の2つめのポイントです。まず,私たちは生きるために生理的欲求を抱き,それを満たすように行動します。それが満たされると,次は安心・安全を求めます。この2つの欲求が満たされると余裕を持って生きていくことができるようになるので,心の充足のために他者とのつながりを求めます。すると今度は,その中で自分という存在を高く評価してほしいという欲求を抱きます。他者からの高い評価を十分に得ると,最後は自分という存在がもつ可能性を最大限に発揮しないと達成できないような大きな目標を抱き,それを達成したいと考えるようになります。
生理的欲求がもっとも低いレベル,自己実現欲求がもっとも高い欲求であるとすると,人間は低いレベルの欲求が満たされて初めて,1つ上のレベルの欲求を抱くようになります。そして,レベルの低い欲求から順に満たしていき,最終的にもっとも高いレベルである自己実現欲求を抱くようになります。安全欲求が満たされたら社会的欲求を飛び越して自尊欲求を抱くということはありません。1つひとつ,階段を登るように,高いレベルの欲求を抱くようになるとされています。
欲求を抱くということ,そして欲求が階層を成しているということについて,もう少し補足しておきます。前述の通り,欲求階層説では低いレベルから順に欲求を抱くとされていますが,それは低いレベルの欲求が満たされて初めて次のレベルの欲求がその人の内部に生じるということではありません。もともと,人の内部には5つの欲求がすべてあります。しかし,ある欲求が満たされていないと,行動がその欲求に支配されてしまう,ということです。たとえば,あなたはとてもお腹が空いているとしましょう。そうしたときになにかしようと思っても,頭をよぎるのは「お腹空いたな…今日は何を食べようかな…」ということばかり。なかなか集中できません。そんな経験はありませんか?僕はそんなことばっかりです。これが,欲求が行動を支配する,という意味です。同様に,他者からの愛情に飢えている人は,それを充足することに重きを置くでしょう。自分が評価されていないと感じている人は,自分を認めてもらうことが動機づけとなるでしょう。自己実現欲求とは,こういった相対的に低次の欲求が満たされていないことによる行動の支配から逃れ,自分自身とはどういう存在なのか,本当に自分自身がしたいことは何であるのかを純粋に考えられるようになって初めて到達する段階です。単に「○○がしたい!」とは異なることを留意しておいてください。
少し話がそれましたが,欲求階層説の3つめのポイントは,自己実現欲求は満たされることはないということです。自己実現欲求以外の生理的欲求,安全欲求,社会的欲求,自尊欲求は,満たされたら解消されます。これらはまとめて「欠乏欲求」と呼ばれます。欠乏しているからそれを満たそうとするわけですね。
これに対して自己実現欲求は「成長欲求」と呼ばれ,満たされることはありません。自己実現を追求し成長していくと,見える範囲が広がったり,関心が強化され,さらなる成長への意欲をかき立てます。
例として僕の話をしましょう。僕は経営学者のはしくれです。僕が研究をする動機は,「経営に関する人類の知識を少しでもアップデートしたい」ということに尽きます。「人類をアップデート云々」については,僕が自分の記憶を捏造していない限りは落合陽一氏よりも前から言っていたはずなのに誰も信じてくれないので僕は少し悲しんでいるのですが,これは自己実現欲求であるといって差し支えないと思います。
研究を進めていく中で,僕は多くの書籍や論文,あるいは調査から新しい知識を獲得してきました。新しい知識は僕の問題意識を解決してくれますが,同時にさらに知らないことを増やします。知識を得たのに知らないことが増えるとはどういうことなのか。それは,新しい知識を得ることで,その知識が位置付けられている,僕にとって未知の研究領域の存在を知るということです。要するに「まだこんなに知らないことがあったのか!」ということです。その領域の存在を知ってしまった以上は,無視することはできません。終わりの見えない洞窟の中を一筋の光を求めながら探検していて,ようやく外に出たと思ったらそこはこれまでいた洞窟の何倍もの広大な大地だった,みたいなことを繰り返しているのが学者であると言えるでしょう。難儀な商売ですね(でも好き…)。
ここまで,モチベーションの内容理論として代表的な欲求階層説についてお話ししてきました。比較的わかりやすい理論かと思いますが,さらに理解を深めるためにワークをしてみましょう。欲求階層説では人間の欲求を5つに分類していましたが,その中にはお金などの経済的な欲求は入っていません。これは,マズローが経済的欲求を無視していたということではありません。欲求階層説で挙げられている5つの欲求と経済的欲求はレベルが違うものであると考えるのが妥当です。それを踏まえて,以下のワーク②に取り組んでください。

いかがでしょうか?ワーク②には特にこれといった答えはありませんので自由に考えてください。現代社会においてはお金がなければ食べ物を買えないので,経済的報酬は生理的欲求を満たすためにある,と考える人もいるでしょう。あるいは,安全欲求で触れた経済的安定性との関係を考える人もいるかもしれません。他者や組織,社会から認められた証拠として経済的報酬を捉える人もいるかもしれませんね。経済的報酬は,様々な欲求に関係しそうです。
このことは,経済的報酬が万能であるということを意味しているわけではありません。報酬として同じものを与えられても,人によってその解釈や意味づけは異なります。そのため,その人にとって経済的報酬にはどんな意味があるのか,その人は経済的報酬によってどのような欲求を満たしているのかを考えた上で,それでは満たすことができない欲求をどのようにすれば満たしていくことができるのかを考えることが,リーダーには求められると言えるでしょう。
<モチベーションの内容理論:ERG理論>
続いて紹介するのは,クレイトン・アルダーファ(Clayton Alderfer)によるERG理論です。なんだかカッコいい名前ですね。このERG理論はマズローの欲求階層説を修正したものです。2つの理論を比較しながら,ERG理論についてお話ししていきます。

まず,ERG理論が想定している人間の欲求とはなんなのか。それは,存在欲求(existence),関係欲求(relatedness),成長欲求(growth)の3つです。存在欲求とは,人間として生きていくための欲求です。欲求階層説における生理的欲求と安全欲求に該当します。関係欲求とは,他者との人間関係に関わる欲求です。欲求階層説では社会的欲求と自尊欲求に該当します。そして成長欲求はその名の通り,成長することで自分が望むことを実現したいという欲求です。これは欲求階層説における自尊欲求の一部と自己実現欲求に該当します。欲求の内容については,ほぼマズローの欲求段階説を踏襲していると言えるでしょう。
ですが,ERG理論には欲求階層説とは違う2つの側面があります。1つめの違いは,欲求がどのように存在するのか,あるいは表面化するのか,という点です。欲求階層説では低いレベルの欲求が解消されて初めて次のレベルの欲求が抱かれるようになるとされています。
これに対してERG理論では,存在欲求,関係欲求,成長欲求の3つの欲求が併存するとされています。存在欲求と成長欲求の2つに同時に突き動かされることもある,ということです。
2つめの違いは,欲求を抱く順序です。欲求階層説では,低いレベルから1つずつ,順に欲求を抱くとされています。そして,一度満たされた欲求を再度満たすことは想定されていません。
これに対してERG理論では,高いレベルの欲求が十分に満たされないと,低いレベルの欲求を抱くことがある,とされています。たとえば関係欲求を抱いている人がいるとします。関係欲求が満たされれば,その人は1つ上のレベルである成長欲求を抱きます。しかし,関係欲求が十分に満たされなければ,その人は関係欲求を抱きながら,同時に1つ下のレベルの存在欲求を抱きます。
ERG理論は欲求階層説を踏襲しつつ,欲求を抱くメカニズムについてはそれを洗練させたものであると言えるでしょう。
<モチベーションの内容理論:マクレランドの欲求理論>
アメリカの心理学者であるデイビッド・クラレンス・マクレランド(David Clarennsu McClelland)は,人間の動機・欲求を3つに分類しています。1つめは達成動機です。この動機は,何かを成し遂げたいという動機です。この動機を強く持つ人は,前回よりも高い成果を上げるための成長の努力や,効率化のための創意工夫を惜しみません。達成動機を強く持つ人は,仕事それ自体に非常に強く動機づけられていると言えるでしょう。
2つめは親和動機です。これは欲求階層説では社会的欲求,ERG理論では関係欲求と類似した動機です。同じ職場で働く同僚と密接かつ良好な関係を築き,維持するために仕事に取り組みます。この動機が強い人は,必ずしも仕事それ自体に動機づけられているわけではありませんが,同僚の役に立ちたいという思いから仕事に打ち込みます。
3つめは権力動機です。これは他者よりも高い地位に立ち,自分よりも下位の人々に影響力を行使してコントロールしたいという動機です。少しだけ,欲求階層説の自尊欲求に近しいかもしれません。高い地位に登り詰めるためには仕事で評価される必要があるので,仕事にも熱心に取り組みます。
どの動機が強いにせよ,それらはいずれも仕事に向かわせるものであるというのがマクレランドの理論の特徴です。しかし,それでもやはり動機の重要性には差があります。マクレランドが整理した3つの動機のうち,もっとも重視されたのは達成動機です。その理由は,達成動機を強く持つ人は,親和動機や権力動機を強く持つ人よりも高い仕事の成果を上げることに意欲的だからです。
でも,達成動機が高い人がいつでも仕事に熱心に取り組むかというと,必ずしもそうではありません。彼ら/彼女らがその高い動機を行動に結びつけるにはいくつかの条件があります。1つめの条件は,自分の高い能力が必要とされていることです。必ずしも自分ではなくてもいい仕事や,それほど高い能力を求められない仕事だと,彼ら/彼女らはあまり気乗りしません。
2つめの条件は,それほど競争が激しくないことです。達成動機を強く持つ人は,自分個人としての仕事に興味・関心を抱いており,社内の競争には力を注ぎたくないと考えます。
3つめの条件は,その仕事の成功確率が中程度であることです。達成動機を強く持つ人は,あまりに簡単な仕事,誰でも確実にできる仕事には興味を持ちません。他方で,あまりに困難な仕事,どう考えても成功確率ほとんどないような仕事にも,同様に興味を持ちません。達成できない可能性が高いからです。そのため,彼ら/彼女らは,真剣に取り組んだ上での成功確率が中程度の仕事を好みます。
4つめの条件は,仕事に対して同僚や上司からのフィードバックが頻繁に得られることです。フィードバックがあれば,それがポジティブなものであれネガティブなものであれ,自分の仕事への取り組みの改善につながります。逆にそれがなかったり,あまりにも頻度が少ないと,成長機会が限られてしまいます。
欲求階層説やERG理論は,主に人間の基礎的な欲求について扱っていました。これに対してマクレランドの欲求理論,その中でも達成動機は仕事に直結したものでした。さらに,どのような状況であれば達成動機が行動につながるのかを明らかにしており,議論がより洗練されてきたと言えます。少しずつ,「経営」組織論で扱う内容に近づいてきていることがわかりますね。
<モチベーションの内容理論:内発的動機づけ理論>
だいぶ長くなりましたが,本日紹介する理論はこれで最後です。もうひと頑張りしましょう!
達成動機が強い人は,その仕事に取り組み達成することや,さらに効率的に仕事を進めることに喜びを見出していました。要するに仕事が好きだから熱心に取り組んでいるわけです。この「好きなことに取り組むことそれ自体に動機づけられること」を内発的動機づけと言います。これに対して給与やボーナス,他者からの称賛などといった外部からの報酬による動機づけを外発的動機づけと言います。純粋にその科目の内容に興味があるから学んでいるのであれば,それは内発的に動機づけられた状態です。他方で,単位や卒業,就職のためであれば,それは外発的に動機づけられた状態です。
予定調和的ではありますが,結論から述べると,基本的には外発的動機づけよりも,内発的動機づけの方が重要です。さらに踏み込むと,外的な報酬は内発的動機づけを阻害することがあります。これを発見したのは心理学者であるエドワード・デシ(Edward Deci)です。
デシは,当時(1960年代)流行していたSOMAパズルというパズルを用いて,外的報酬と内発的動機づけの関係に関する実験を行いました。これがSOMAパズルです。ちなみにデシもSOMAパズルが大好きだったそうです。

実験に先立ち,被験者はこのSOMAパズルに十分に親しんでおり,このパズルで遊ぶことに喜びを見出していました。つまり,被験者はSOMAパズルに取り組むことに対して内発的に動機づけられていたわけですね。これが前提です。
実験の内容は,絵に描かれた立体物を,このSOMAパズルを組み立てて再現するというごくシンプルなものでした。被験者にはこの実験に取り組んでもらうわけですが,デシは被験者を2つのグループに分け,以下のように複数回の実験を行いました。各セッションでは4つのお題に取り組み,2つめと3つめのお題の間には短時間の休憩が設定されていました。

この3回のセッションのうち,グループ1に対しては第2セッションのみ,出来上がったパズルの数に応じて報酬を与えました。それ以外の条件はすべて同様です。すると,次のような光景が観察されました。報酬を支払われたグループ1の被験者は,第3セッションの休憩時間中は部屋にあった雑誌を読むなど,手元にSOMAパズルがあるにも関わらず,それには触れませんでした。これに対して無報酬のグループ2は,休憩時間でもSOMAパズルで遊んでいました。つまり,一度でも報酬をもらったグループは,それがもらえなくなると内発的動機を低下させたのに対して,報酬がないグループは内発的動機を維持し続けたということです。通常であれば,外的報酬があったほうがさらに真剣に取り組みそうなものです。なぜこのようなことが起きたのでしょうか?これを説明したのが下の一連の図です。

まず,①で示された内発的に動機づけられた状態とは,職務を遂行すること(SOMAパズルに取り組むこと)と,それから満足を得ること(SOMAパズルを楽しむこと)が切り離されていない状態です。仕事自体が喜びなのですから,これらは切っても切り離すことができないわけですね。

しかし,職務の遂行に対して金銭的報酬などの外的報酬が得られるようになると話が変わります。②で示しているように,①では不可分だった職務遂行と職務満足との間に金銭的報酬が割り込んできます。職務遂行と職務満足が切り離されてしまったわけです。こうなると,職務遂行と職務満足は金銭的報酬を介してしかつながらなくなってしまいます。

そのような状態になってから金銭的報酬を支払わなくするとどうなるでしょうか?職務遂行と職務満足を唯一つないでいた金銭的報酬がなくなってしまうので,職務遂行と職務満足が分断され,職務遂行から職務満足を得ることができなくなってしまいます。そうなると,誰も職務に積極的に取り組まなくなります。デシのパズル実験で起きたのはまさにこの現象です。
こうした,「外的報酬によって内発的動機が低下する」ことを,アンダーマイニング効果(抑制効果)と呼びます。このアンダーマイニング効果について,以下のサイトではとてもわかりやすく説明しています。一読しておいてください。
他方で,いつでも外的報酬が内発的動機を低下させるかというと,そういうわけでもありません。金銭や商品など形がある外的報酬ではなく,賞賛や承認などの形がない外的報酬は内発的動機を高めることがあります。これを「エンハンシング効果」と呼びます。外発的報酬が内発的動機に与える影響については,状況や対象によって変わると言えそうです。
5.終わりに
今日は働く上でのモチベーションについてお話ししてきました。最初はかなりシンプルでしたが,最後のほうになるとかなり複雑になってきましたね。ただ,今日お話しした内容は,モチベーションに関する理論の古典中の古典です。近年ではより問題意識の範囲が限定された詳細な研究が数多く行われています。次回は,近年のモチベーション研究についてお話しします。
働く上でのモチベーションを理解することは,どのような進路に進むにせよ重要です。ここでの「重要」には2つの意味があります。1つは,繰り返し述べてきたように,組織のリーダーにとって重要であるという意味です。そしてもう1つは,あなた個人にとって重要という意味です。
僕は,自分の機嫌を自分で取ることができるのはとても重要な能力あるいはスキルだと思っています。組織において,必ずしもあなたのモチベーションは最優先事項ではありません。要するに,他者があなたの機嫌を取ってくれるわけではないということです。そこまでの余裕がある組織ばかりではないからです。そうしたとき,不貞腐れるのではなくて,自分で自分を動機づけていくことが重要になります。それが内発的動機につながり,仕事自体を楽しいものにさせてくれます。他者に期待しつつ,過剰には期待しないこと。自分で自分を動機づけていくことができること。あなたにはこの2つができる人材,セルフコントロールができる人材になってほしいと願っています。
ではでは。
6.課題
最近,みなさんお疲れ気味なようなので,今回は課題を以下の1題に留めておきます。そのうちにまた2題に戻るので,それまでは英気を養っておいてくださいね。
<課題>
「4.講義内容:人間ってどうやったらやる気を抱くのでしょうか?」に書かれている内容を踏まえて,あなたなりに人間の欲求をいくつかに分類し,それについて説明してください(400字程度)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
