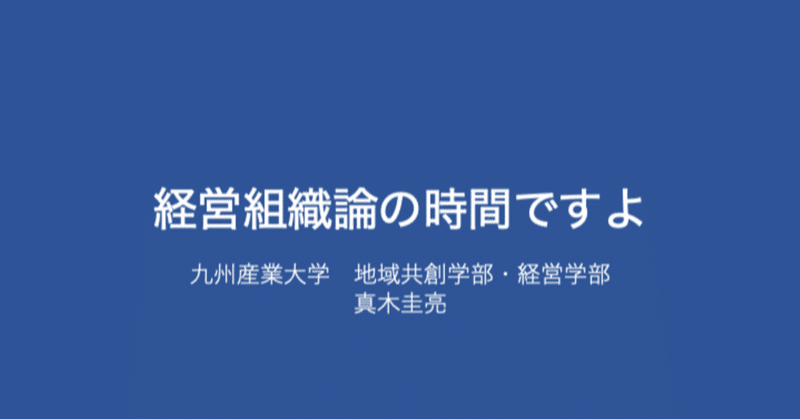
第9回(2020/06/29) 経営組織論 官僚制
1.はじめに
このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第8回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。
こんにちは。今日も余談から入りましょう。いきなりですが,まずはリンク先の記事をお読みください。
製菓大手のカルビーが,原則としてテレワークを基本的な働き方とし,またこれに伴い業務に支障がなければ単身赴任をしなくてもよいという方針の変更をしたそうです。ずいぶんと大胆な方針転換ですね。あなたはこのカルビーの方針をどのように評価しますか?僕はカルビーの強い意志を感じます。
まず,テレワークを基本的な働き方として定め,社員がそれに順応した場合,再びこれまでと同じ出社勤務に戻すことは極めて困難になります。働き方は,生活の他の部分と独立しているわけではありません。相互に依存しています。たとえば,出社しての勤務だったときは子どもを保育園に預けるしか選択肢がなかったけれど,テレワークで働くことができるようになると自宅で育児ができたり,幼稚園に通わせることができるようになったりします。そのようになってからまた出社勤務に戻そうとすると,これは大変です。社員はまた保育園を探さなければいけなくなります。もしかすると社員からの不満が出るかもしれません。働き方が変わることに伴って生じる生活のその他の部分での変化は,不可逆であると考えられます。
また,単身赴任を止めることに伴い,カルビーの社内で様々な変化が生じるはずです。企業は気まぐれで社員に単身赴任を命じていたわけではありません。単身赴任は必要な人材を必要なときに必要な場所に配置するためのものです。つまり,単身赴任は「社員という経営資源の再配置」として捉えることができます。もちろん,「業務に支障がなければ」ということではあるので,単身赴任がゼロになるわけではないでしょうが,きっと単身赴任をする社員はこれまでよりは減少するでしょう。そうすると,必要な人材を必要なときに必要な場所に配置できなくなるわけです。これは困りますよね。
これをカバーするために,各支社や営業所単位で中途採用を中心とした採用活動が拡大する可能性があります。本社に集中していた人事関係の機能が分散していくかもしれません。
しかし,中途で外部から採用された人材と,これまでであれば単身赴任をしていた社内の人材では,たとえスキル面で同等であっても,社内の文脈の理解に差があります。もし中途採用の増加が不可避であるならば,その差を無くすために,仕事を可能な限り文脈と切り離すようになるのではないでしょうか。つまり,社内の文脈を知らなくても仕事ができるように,細かな情報までも文書化され共有されるようになるのではないでしょうか。
これらはすべて僕の妄想なので,本当にそのようになるかはまったくわかりません。しかし,今回のカルビーの方針転換が及ぼす可能性のある影響は,パッと考えただけでもいくつも思い浮かびます。カルビーがそれを想定していないわけがありません。それらのめんどくさい影響を考慮した上での今回の方針転換であるでしょうから,冒頭で「今回の方針転換からはカルビーの強い意志を感じる」と述べたわけです。
繰り返しになりますが,あなたはこのカルビーの方針をどのように評価しますか?1つの変化が連鎖的に与える影響をあれこれ考えてみるのも楽しいものですよ。それをうまくできる人が,いわゆる未来を見通す人と呼ばれるのでしょうね。そんな人になれたら素敵じゃないですか?そのために,論理的に物事を考える力を身につけましょう。論理的に物事を考えることを積み重ね,いくつもの変化とその影響のパターンをストックし,それらを組み合わせたりつなげていくことで,未来を見通す人に少しだけ近づけるのだと思います。天才ではない人々は,小さな成長を積み重ねていくしかありません。この講義のレポートは論理性も評価します。あなたの小さな成長に少しでも貢献できれば幸いです。
2.前回の振り返り
前回のテーマは「組織社会化」でした。組織社会化とは,荒っぽく言えば「その組織の人っぽくなる」ということです。その組織のメンバーとして必要な技能やスキル,考え方や振る舞いを身につけることが組織社会化です。
この組織社会化は組織にとっても個人にとっても重要です。この講義では一貫して「協働」をキーワードにしていますが,組織社会化はスムーズな協働に寄与します。組織社会化によって,組織メンバーは必要なスキルを身につけ戦力化されます。必要なスキルがなければ,協働以前にそもそも働くことができないですからね。また,その組織特有の考え方を身につけることで,細かいコミュニケーションを逐一とることなく連携することができます。さらに,組織社会化を通じてその組織の一員として認められることで,その組織に対するコミットメントや働く上でのモチベーションが向上します。いかに新しい組織メンバーを組織社会化していくかは,組織にとっての重要な課題の1つであると言えるでしょう。
組織社会化は,研修やOJT(On the Job Training)など,組織に入ってから促されます。しかし,組織社会化が生じるのは組織に入ってからだけではありません。組織に入る前にも生じます。それを予期的社会化と呼びます。内定者など,組織に参入することが決まった人に対しては,入社前研修などを通じて社会化が促されます。さらに,この予期的社会化の段階においては,は,組織に参入することが決まった人が組織に対して抱く過剰な期待を抑制することも必要となります。過剰な期待を抱いたままに組織に参入してしまうと,期待と現実のギャップに幻滅するリアリティ・ショックに直面します。それを防ぐために事前に組織のリアルな情報を伝える現実的職務予告(Realistic Job Preview:RJP)が実施されることがあります。
3.前回課題のフィードバック
<前回の課題>
あなたは企業の採用担当者です。あなたはRJPを行いますか?行いませんか?理由を含めてお答えください。また,それぞれの場合で生じるデメリットをカバーする方法についても,合わせてお答えください。
前回の課題に対して,ほとんど全員が「RJPを採用する」と答えました。今年は不採用と回答したのは5名程度(全体の7%ほど)で,例年よりも大幅に少ない結果となっています。まず採用とした意見の中から特徴的なものを2つ紹介し,次いで不採用とした意見を1つ紹介しますね。
なお,不採用という意見が少ないからと言って,それが間違いであるということはまったくありません。就職活動中,あるいは就職活動を控えた学生の立場からすると,RJPを採用すると答えるのが順当です。ブラック企業は回避したいですからね。他方で,企業には企業の立場もあります。不採用と答えた人は,学生としてだけではなく,企業の立場を考えた結果であるとも言えます。今回の課題は「企業の採用担当者として考える」ものですからね。もちろん,RJPを採用するとした人が企業の立場から考えられていないというわけではありません。今の自分の立場を離れて,意図的に異なる立場から想像することが大事だということです。これも協働においてはとても重要です。
私であればRJPを行います。ですが、行うとしても小出しにしていく必要があると思います。採用説明会などの初期段階からRJPを公にするのもそれはそれでよいと思います。なぜなら、少なからず「この会社は自分にぴったりだ!ここの内定が欲しい!」と思う人もある一定数いると思われるからです。ですがその割合より多くの人材が欲しい場合はこのやり方では人材を必要数確保できません。その為RJPをまずは少しだけ公開する形にし、ある程度自分の会社に欲しい人材をふるいにかけるべきだと思います。その段階を乗り越えた採用候補者にはまた更にRJPを行います。段階的に情報を公開していくことで理想と現実の落差が、入社して気づいたときには取るに足らないほどの差になっているのではないかと考えました。
ですが注意するポイントはやはり、どの程度の情報をうまく小出しにするか、という点だと思います。今回のnoteにもあったようにRJPを先走るのもダメですし、逆にRJPを小出しにしすぎる(RJPを行っても行わなくても変わらない内容)のも後々「詐欺じゃん」と言われる可能性があります。私が今回述べた方法はその匙加減が肝になると考えます。
「RJPを採用するかしないか」だけではなく,「どのようにするのか」まで踏み込んで考えてくれています。とても良い回答のスタンスです。
回答者自身も書いてくれていますが,どのような情報をどのようなタイミング,どのような順序で公開すれば,組織への参加を希望する人を極力減らすことなく,しかしリアリティ・ショックも最小限に抑えることができるのかを考えることはとても重要ですね。ゼミナールでの研究や卒業論文のテーマにしてもいいかもしれません。同じような研究があるのかしらと思い,日本の学術論文を検索できるwebサイトであるJ-STAGEで「RJP 段階」と検索してみたところ,以下のような論文がヒットしました。企業におけるRJPを含めた採用活動について書かれた論文です。ご興味があればご一読ください。データでダウンロードもできますよ。
私が企業の採用担当者だったら、RJP(現実的職務予告)を行います。これは企業に採用された人材が自分の企業イメージと実際に働いてみた現実とのギャップを小さくする効果があり、近年問題になっている新入社員の早期退職問題の解決にも繋がるのではないかと考えたからです。
しかし、いくらギャップを小さくしたとしても、それは人それぞれの捉え方で異なるため、企業に対して悪いイメージを抱く人が全くいないとは言えません。そこで、RJPを行う企業は現状の会社内をクリーンにすることが先決だと思います。今回の題で争点になっているのは、RJPを行うことはネガティヴな情報も与えるから難しいという所であるため、デメリットの解決策として会社内の働き方改革を行い、クリーンな会社にすることで、RJPを行ってもネガティヴな情報がそもそも出てこないのではないかと考えました。そうした上でのRJPは就職活動をしている人にとっても、企業のブランディングにとっても、非常に魅力的な方法だと思います。
RJPは行うけども,そもそもの前提として社内にネガティヴな側面が少なければ,RJPをしても問題がないという考えですね。たしかにそのとおりです。また,RJPを入社希望者や採用候補者に対するもの,すなわち外部者に対するものとだけとらえるのではなく,それを内部の変革のテコにするというのは良い考えですね。
私はRJPを行わない。なぜなら、仕事とはキツく辛いことばかりではなく楽しいこともあるため、少なからず自社に対して興味を持ち、立候補してくれたのなら、多少キツく辛いことがあっても簡単に辞めることは無いというのがRJPを行わない理由である。また、予め何人か辞めることを想定して多くの立候補者を採用しておくことで良い人材が見つかる可能性も高くなる。
RJPを行わないデメリットとして、内定後にリアリティ・ショックを受け辞める人が増えるという点が予想されるが、採用段階で予め多くの人材を採用しておくことでカバーは可能だと考えた。ただし、辞めなかった時の支払う人件費のことを考えて定員数の+10人ほど多く採用するのがいいのではないだろうか。
今度は反対に「RJPを採用しない」という意見です。たしかに,回答の多くはネガティヴな情報について注目していますが,仕事には楽しさもあるということにはあまり触れられていませんでした。仕事の楽しさはやってみないとわかりませんが,辛さは比較的簡単にイメージできてしまいます。結婚や子育てみたいなものかもしれませんね。したらしたで確実に良いことはあるけれど,経験していない人に言語化して伝えるのが困難なので,悪い側面ばかりが伝わってしまうことってあります。あまり事前にネガティヴ情報を伝えすぎるとポジティヴな面が覆い隠されてしまうかもしれません。伝えるのって難しいですよね。
ここまで3つの意見を紹介してきました。みなさんに1つ考えてほしいことがあります。それは,社内の人々にとってのポジティヴ/ネガティヴな情報と,社外の人々にとってのポジティヴ/ネガティヴな情報は同じなのか,という点です。昔,こういうことがありました。僕の知人が就職活動の結果,2社から内々定をもらいました。1つは外資系のメーカーで,もう1つは日系の化学メーカーです。世間的な知名度も給与も圧倒的に前者の方が高く,多くの人が彼はそちらに入社するだろうと考えていました。
でも,彼は後者の化学メーカーに入社しました。その理由を聞くと,彼はこう言いました。「前者はすぐにバリバリ働けることをすごく前面に押し出している。もちろん,仕事を早く任せてもらえるのは嬉しいけど,入社までただの学生に過ぎない自分が,そんなにすぐに戦力になることができるとは思えない。それに対して後者はいわゆる伝統的な日本企業で,すぐには仕事を任せてはもらえない。それに物足りなさもあるのかもしれないけど,それは若手を前線に投入しなくても余裕があることを示しているのだろうし,何より顧客の前に中途半端な社員は出さないということだから,企業として真摯であるように思える。だから自分は後者の方が企業として信頼できる。」
ある人にとってはポジティヴになることも,別の人にとってはそうではないことがあります。逆もまた然りです。RJPを実施するとき,このズレを企業として認識できるかはとても重要ですね。思わぬ反応を巻き起こしてしまうかもしれません。
4.講義内容:官僚制
ルールによるコントロール
この講義では一貫して協働をキーワードにしていますが,協働を促すには組織メンバーの行動を望ましい方向に向かわせる(コントロールする)必要があります。ここ数回の講義では,モチベーションや組織文化,社会化など,組織での協働に対して組織メンバーの心理的な側面からアプローチするものでした。たしかに,人々の心にアプローチすることでその行動をコントロールできれば,協働はスムーズに進みますね。
他方で,心理的なアプローチからしか人々の行動をコントロールできないわけではありません。人々の心をそもそもコントロールできるのか,という疑問もありますしね。心へのアプローチではない人々のコントロール,それはルールによるコントロールです。
ここで,ルールによる行動のコントロールについて,ワークを通じて考えてみましょう。まず,1つめのワークは以下のものです。考えてみましょう。

家族や学校,部活,アルバイトなど,これまで様々な組織に所属したと思います。それらには明示的か否かはともかく,きっとルールがあったでしょう。その中には人によっては思い出したくもないくらい嫌なルールもあったかもしれません。嫌かもしれませんが,まあちょっと思い出してみてください。
充分に思い出すことはできたでしょうか。それでは続いて次のワークに取り掛かりましょう。

ルールが人々の行動をコントロールするものであるならば,行動を向かわせる方向,つまり目的があるはずです。いかんせん理不尽なルールを挙げてもらっているので感情的にはそのルールを肯定的には捉えられないかもしれませんが,いったん感情は脇に置いておいて考えてみましょう。
ちなみに,僕も理不尽なルールを経験したことがあります。僕は中学生のときにソフトテニス部に所属していたのですが,そこは理不尽感満載でした。ここで書けないような理不尽な出来事もあったのでマイルドなものを挙げると,「サーブ練習でミスをするとテニスコート(4面)を全速力で規定時間内に一周しなければならない」というものがありました。罰走ですね。おまけに顧問から怒鳴られ,ラケットで殴られもしました。よく毎日あんなにあの人は怒鳴っていたなと思います。喉,枯れないのかな。僕は近距離パワー型(ぽっちゃり体型)であったためスタミナに乏しく,サーブの精度にも難があったため,本当にこのルールが嫌で仕方がありませんでした。正直なところ,当時のソフトテニス部顧問には憎悪以外の感情をもっていません。20年以上経過した今でもです。書きながら胃のあたりがムカムカしてきましたよ。世界一かわいいうちの猫を撫でて,心の平穏を取り戻そうと思います。
嫌でたまらなかったこのルールですが,自分の心に鞭打ってねらいを考えてみると,きっと「練習でも試合と同じような緊張感をもって臨ませる」というものだったのだろうと思います。ミスが許されない試合を常に意識した練習をすることは,たしかに試合で実力を存分に発揮するためには必要かもしれません。
では,このルールが目的達成のために効果的だったかというと,まったくそんなことはなかったように思います。部員はサーブミスによる罰走が嫌で,力を抜いてサーブ練習をするようになりました。ただミスをしないように縮こまってしかサーブを打てなくなりました。もちろん,ミスをしてもヘラヘラしていいわけではありません。ミスを少なくできるように改善に取り組む必要があります。しかし,サーブミスをするのは緊張感がないからではなく,単純に技術的な問題です。根本的に問題設定が間違っています。これではいつまでたっても問題解決なんてしません。僕はこのときの経験が嫌で仕方がなかったので,以降は一度も部活や体育系の組織に入ったことがありません。運動も体育会系全般も嫌いになりました。少なくとも僕にとってはその後の人生を歪められた最悪なルールであったと言えます。
さて。僕の恨み言はこれくらいにして,あなたはこれまで経験した理不尽なルールに対してどのように意味づけをしましたか?このワークのねらいは,一見すると理不尽だったり無意味に見えるルールの背後にあるねらいや機能を想像することにあります。今回の講義内容はルールによる行動のコントロールです。そこで紹介するルールはとても窮屈そうに見えます。しかし,そこで考えを止めるのではなく,それが果たす機能まで考えていくと視界が一変します。今回の講義を通じてその経験をしてもらえると嬉しいです。
求められる効率性と安定性
第2回講義noteにも記したように,企業にせよ自治体にせよ,組織はメンバー個人では達成できない困難な目標を達成するために存在します。困難な目標は,長期的な活動を通じてしか達成できません。したがって,いかなる組織も,程度の差こそあれ一定以上の期間にわたって活動を続けられる必要があります。そのためには組織には何が求められるのでしょうか?今回の講義では,議論をシンプルにするために企業に焦点を当ててお話していきます。
雇用の創出も重要ですが,何より企業は製品・サービスの提供を通じて社会に貢献します。製品・サービスを開発し生産するには,それを作るための知識や技術,製品・サービスの元となる原材料や働いてくれる従業員,そしてそれらを買ったり雇用するための資金が必要です。こういった経営に活用できるもの全般のことを「経営資源」と言います。経営資源は具体的には様々ですが,概ね「ヒト・モノ・カネ・情報」と整理されます。経営資源については後期の「経営戦略論」で詳しくお話しするので,ここで詳細な説明は省きますね。企業は経営資源を投入して製品・サービスを生産し,その対価として売上や利益を獲得します。これらを用いてまた原材料を購入し,人々を雇用して製品・サービスを生産します。
製品・サービスの対価として企業が得るのはお金だけではありません。優れた製品・サービスを提供することで顧客が満足すると,「あの会社は良い製品・サービスをつくっているぞ!」という社会的な評価も獲得します。高い社会的評価を得ると,より良い人材が集まる可能性が高まります。また,株主からの評価が上がり,株価が上がる可能性も高まります。株価が上がると,銀行などから有利な条件で融資を受けることができ,さらに資金を集めることができます。
さらに,企業は自身の行動の結果から学習することで,知識を獲得します。ある製品・サービスを生産すると,より効率的な生産方法について企業は学習します。製品・サービスを販売し顧客の手に渡ると,顧客の反応からどのような製品・サービスが受け入れられるのか/受け入れられないのかを企業は学習します。
ここまでの内容を図示したものが下の図です。企業はインプットをアウトプットへと変換するものであると言うことができます。企業が長期的に活動を続けていくためには,この図で示されている流れを効率的かつ安定的に循環させていく必要があります。効率的でなければ,他の企業に経営資源の獲得競争で負けてしまう可能性があり,また生産する製品・サービスの質や量が不安定だと,顧客や社会から信頼されず,十分な経営資源を獲得できないからです。

官僚制とは
では,このサイクルを効率的かつ安定的に循環させていくにはどうすればよいでしょうか?それをもっとも突き詰めたものとして,「官僚制」と呼ばれるものがあります。この官僚制組織は,ドイツ(プロイセン)の社会学者であるマックス・ウェーバー(Max Weber)によって概念化されています。ウェーバーは20世紀を代表する社会学者であり,彼の著作はその後の社会科学に大きな影響を与えています。すぐに理解するのは難しいかとは思いますが,学生のうちに彼の著作を少し読んでおくことをオススメします。なお,今回の講義noteでは,ウェーバーが官僚制について言及したその経緯について詳細には述べません。理由は,それを理解するには前提となる知識がいくつも必要であり,それらをすべて説明しようとすると15,000字〜20,000字と定めている1回の講義noteでは収まらなくなるからです。したがって,今回は官僚制とはどのようなものであるのかを簡潔にお話ししていきます。
官僚制とは,簡単に言うと「すべての意思決定や行動が,制定されたルールに基づくシステム」のことです。まさにルールによる行動のコントロールですね。この官僚制には以下の6つの特徴があります。
①ルールに基づく職務の遂行
人々にはそれぞれ個性がありますが,その個性に基づいて仕事をしてもらうのではなく,あくまで組織のルールとして定めた進め方で仕事をしてもらう,ということです。
②文書に基づく遂行
何事も文書を通じて行われることです。あなたのアルバイト先にも「マニュアル」ってあるのではないでしょうか。まさにそれのことです。また,行われた活動は文書として記録し残されます。
③明確な職務権限の原則
誰がどの仕事をするのかが,ルールによって明確に定められているということです。
④階層的な権限体系
官僚制組織には階層性があります。階層性を図示すると以下のようになります。

階層性と企業で考えると,一番上にまず社長がいます。その下に事業部長がいて,その下に部長がいて,さらにその下に課長がいて・・・というイメージです。重要なのは,個人としてではなく職位に権限がある,ということです。A課長はB部長の指示にしたがいますが,それはあくまでB部長が上司だからであって,B部長が人格的に優れているからとかではありません。
⑤専門的訓練
ある仕事の担当になったら,その役割を十分に果たすことができるように徹底して専門的な訓練が施される,ということです。
⑥フルタイム勤務
職務に専念するために副業や兼業を禁止する,というものです。
6つも挙げといてなんですが,別にこれらを一言一句,正確に記憶する必要はありません。誤解を恐れずこれらの官僚制の特徴を一言でまとめると,「可能な限り,インプットをアウトプットに変換する際のブレを小さくする」ものであると言えるでしょう。もし,仕事のやり方が定められていなかったら,人によって仕事の仕方が大きく異なってしまいます。そうすると,毎回違うアウトプットが生み出されてしまう可能性がありますよね。仕事内容を文書で記録しなかったら,「言った言わない」で揉めごとが起きます。仕事の範囲が明確に定められていないと,ある人があるときはその仕事に取り組み,またあるときは取り組まない,ということが生じます。専門的な訓練を受けないと,個人間の能力差がダイレクトにアウトプットの質や量に影響します。
こう考えてみると,組織がインプットをアウトプットに変換する際のブレは,組織メンバー間の違いと,成果の不確実性に起因していると考えられます。官僚制は,組織メンバー間の違いを出来るだけ平準化すると同時に,組織メンバーの取り組みを予測可能なものにしている,極めて合理的なものであると言えるでしょう。これによって企業をはじめとする組織は効率性と安定性を確保できているのです。
ところで,官僚という言葉は,日本においては国家公務員を指すことがほとんどです。したがって,省庁を含むいわゆる「役所」が代表的な官僚制組織であると考えられがちです。たしかにほとんどの役所には官僚制の側面が強くあります。
しかし,官僚制の側面を有する組織は役所だけではありません。現代における一定以上の規模の組織は,程度の差こそあれほぼすべて官僚制組織です。この官僚制こそが,現代の組織の基本的な土台であると言えます。むしろ,官僚制の側面を有する組織のことを現代的な組織である言った方がいいかもしれません。だからこそ,官僚制について理解することが重要となるのです。
官僚制の逆機能
あなたは「お役所仕事」という言葉にどのようなイメージを抱きますか?きっと「融通が利かない」など,ネガティヴなイメージを抱くことでしょう。そうなんです。ここまで官僚制について肯定的にお話ししてきましたが,実は官僚制にも問題があります。それらを「官僚制の逆機能」と呼びます。ルールや制度には,それが果たす機能があります。しかし,他方でそれによって生じる好ましくない機能もあります。逆機能とはそういったものを指します。
官僚制の逆機能としてまず挙げられるのが,手段の目的化です。本来,ルールを守ることは,組織がインプットをアウトプットに変換するプロセスを円滑にすることが目的です。つまり,その目的に対してルールを守ることは手段であると言えます。
しかし,時が経つにつれて,ルールを守ることが過剰に重視され,目的化されます。そうなると,組織メンバーは組織が成果を上げていなくても規則さえ守っていればいいと考え始め,できる限りの努力をしなくなります。これを最低許容行動と言います。最低許容行動が組織に蔓延すると,その組織の顧客の不満足を招きます。顧客を満足させることが目的ではなくなってしまっていますから当然ですね。
手段の目的化は,いわゆる前例主義につながります。これまでのやり方と同じか否かでしか物事を評価できなくなる,ということです。そうなると,新しいものを評価することが不可能になります。新しいものは前例にありませんからね。こうした組織は自らを革新できず,環境の変化に対応できなくなります。このような組織のメンバーは官僚制組織の一員としてはよく訓練されているものの,それによって自分の頭で何が適切かを考え行動することができなくなる,訓練された無能となります。
ここまで官僚制の逆機能についてお話ししました。ここで誤解しないでほしいのは,官僚制に逆機能があるからと言って,官僚制がそのものが悪いというわけではないということです。官僚制の逆機能は,前述の官僚制の6つの特徴が強調されすぎたり,形だけ遵守されたりした結果として生じています。官僚制の逆機能はあくまで不適切な組織のコントロールが原因であると言えます。
しかし,現実としては「官僚制=悪」のように考える人々もいます。現代のほとんどの組織に官僚制の側面があることを理解できていればそのような考えには至らないはずなのですが…
これはきっと,官僚に対する好ましくないイメージが影響しているように思います。現役大学生のあなたにとっては意外かもしれませんが,一定以上の世代の人々は必ずしも「官僚」という言葉に対して好ましいイメージを抱いてはいません。僕の世代もそうではないでしょうか。官僚という言葉が連想させるのは,本来であれば国家公務員です。彼/彼女のほとんどがとても優秀な人材であることは間違いありません。
そんな彼/彼女に対して好ましくないイメージが抱かれてしまったのは,かつて世間を賑わせた「官官接待」が大きく影響しているように思います。官官接待とは,予算や補助金などの面で自分が務める自治体に有利になるように,地方公務員が国家公務員を公費で飲食などのもてなしをすることを指します。1990年代前半から中頃にかけてだったと記憶していますが,この官官接待は強く批判されました。このときのイメージに引っ張られて官僚制組織を勘違いする人が今でもいるように思います。
ですが,前述したように,たしかに行き過ぎた官僚制はたしかによくないけれども,それは官僚制そのものが悪いことを意味してはいません。この点はよく理解しておいてください。官僚制は現代組織の仕組みの基礎です。この基礎がなければ,組織は業務を円滑に行うことはできません。
5.終わりに
今回の講義を通じてもっとも意識してほしいのは,組織で定められているルールのねらいや機能を考える姿勢です。あなたはいずれ,それなりの規模の組織に入ることでしょう。そこにはきっと様々なルールがあります。中には意味のよくわからないルールや,理不尽なルールもあるでしょう。それらに直面したときに思考停止するのではなく,「なぜそういったルールがあるのか?」や「そのルールがあることで組織にどのような影響があるのか?」などを考えられるようになってほしいと,僕は考えています。
僕はあなたに組織のリーダーになることを期待しています。組織のリーダーは組織メンバーの協働を促進させる役割を担っています。そのためには組織文化をつくり共有していくことに加えて,ルールの設定によって組織メンバーの行動を方向づけることも必要です。どのようなルールがどのように組織メンバーを方向づけるのか。常にこのことを意識し,組織メンバーを自然と協働に導くことができるリーダーになりましょう。
6.課題
<課題1>
あなたが経験した理不尽なルールについて述べてください。そして,そのルールには何の目的があり,その目的達成のためにそのルールは妥当であったかを評価してください(要するにワーク①とワーク②で考えた内容を教えてください)。
<課題2>
本日の講義noteでお話しした「官僚制の逆機能」から1つを選び,それによる組織への悪影響を極力小さくするにはどのようにすればよいか,あなたの考えを400字程度で述べてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
