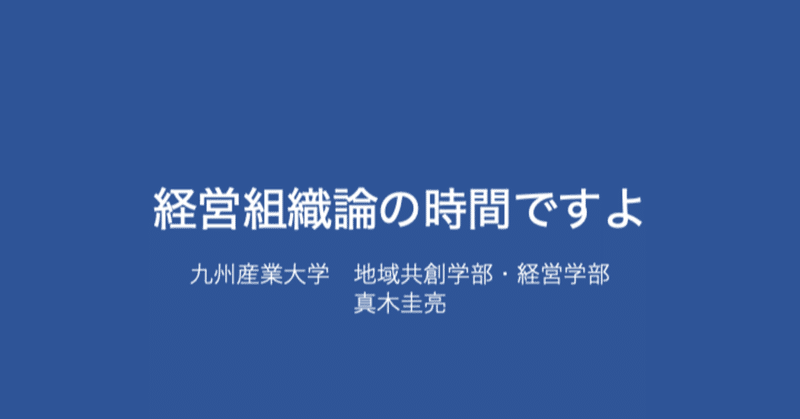
第7回(2020/06/15) 良い組織文化って何?
1.はじめに
このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第7回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。
こんにちは。いくつかお知らせがあります。まず,当初予定した評価方法から,いくつか変更が生じました。具体的な内容はnoteで公開するようなことではないため,改めてK's Lifeを通じてご連絡します。なお,変更内容は単位取得に不利になるものではありませんのでご安心ください(楽になるとも言っていない)。
もう1つは残念なお知らせです。初回講義noteに明記していますが,この講義では毎回の課題の未提出回数が6回になった時点で,最終レポートの提出資格がなくなります。今回の講義で7回目ですが,すでに初回講義から連続して6回,課題を提出していない学生が複数名います。この講義は最終レポートを提出しないと単位を取得できませんので,課題の未提出回数が6回を超えた学生は,その時点で単位を取得できません。課題の提出状況は自分で確認できるはずですので,不安であれば確認しておいてください。なお,学年に関係なく一切の救済はありません。例年であれば課外活動や就職活動など,考慮すべき要因がありましたが,今年はそれらはほぼストップしているので学業への影響はごく小さいはずです。何より課題提出にはかなりの期間を設けているので,僕が考慮しなければならない理由はありません。
さて。のっけから気の滅入る話題でしたが,気を取り直していきましょう。今日はリモートワークと組織文化の関係についての余談です。現在,COVID-19の影響により,企業がリモートワークを導入しています。導入率についてはいろいろな数字があり,どれを信頼すべきか今ひとつわからないのでここでは示しませんが,少なくともCOVID-19の流行以前よりはリモートワークを導入する企業は増えていると言えそうです。
このリモートワークが一過性のものとして終わるのではなく,組織に根付いたとしたら,組織文化にどのような影響を与えるでしょうか?要するに,直接的な人的接触が極端に減った状況において,組織文化は形成されるのでしょうか?あるいは,その形成過程や形成される組織文化に大きな変化はあるでしょうか?
これに対する答えはとても難しいです。根本的な難しさは,リモートワークが通常の勤務体制になった場合,「組織」というものの認識自体が変わってくる可能性があることに起因します。理論的にどうかは置いておいて,リモートワーク以前は「物理的な意味で同じ職場にいる人々」を組織として理解していた傾向があるように思います。組織は眼前にある目に見えるものであり,手触りのあるものでした。
しかし,リモートワークが進んでいる現在,その手触りは急速に失われていっていると言ってもいいでしょう。そうすると,組織というものはどのように捉えられるようになるのでしょうか?手触りのない組織に,人々は深くコミットするのでしょうか?人々が深くコミットしない組織において,組織文化は人々の内面深くに共有されるのでしょうか?
仮にリモートワークが通常の勤務体制となるのであれば,それまでの組織をリモートワークでもそのまま再現することは放棄すべきでしょう。これまでの組織の在り方に固執するのではなく,新しい組織観をつくっていくべきでしょう。組織への人々のコミットメントも,これまでとはまったく別の尺度で測るべきでしょう。リモートワークの導入を真面目に考えると,これほどの大転換が求められると僕は感じています。あなたはどのように考えますか?
after coronaあるいはwith coronaの世界がどのようになるかはわかりません。元通りになるかもしれないし,ならないかもしれない。ですが,想定すべきは元通りにならなかった場合のことです。元通りになるのであれば何の備えも必要ではないので,そもそも考えることが何もないからです。これは自明なことです。それなのに元通りになる前提を勝手においてそれ以外の可能性を考えないのは,自らをafter coronaあるいは with coronaの世界への適応に大きく出遅れてしまう人間に押しやっている行為だと思ってください。
2.前回の振り返り
前回と今回の講義noteでは,組織文化をテーマとしてお話ししています。前回はその前半として,組織文化とはどのような概念であるのかに触れました。組織文化は様々な研究者によって様々に定義されますが,この講義においては「組織内で共有されている価値観,規範,信念」と定義しました。
この定義から一歩踏み込み,さらに組織文化を理解するための枠組みとして,多くの経営組織論のテキストに記載されているエドガー・ヘンリー・シャインの枠組みを紹介しました。以下の図がその枠組みです。

前述の定義では,組織文化は価値観や信念のような人々の内面の考え方に限定されていました。しかし,「文化」と聞くと,食文化や伝統芸能,音楽のような,必ずしも人々の内面にあるものに限定されない印象があります。シャインの枠組みは,人々の内面にあるもの,すなわち見えないものに限定せず,目に見えるものまで含めて組織文化としています。他にも組織文化に関する枠組みはありますが,この包括性から,この講義ではシャインの枠組みを代表的なものとして紹介しました。
シャインの枠組みの特長は,組織文化を「人工物」,「共通価値」,「基本的仮定」の3つの階層に分けて考えている点です。目に見えるものも文化の一部だけれど,その背後にはその文化圏で生きる人々に共通する価値があり,さらにその背後には彼ら/彼女らにとっての「当たり前」が潜んでいる,というのがシャインの枠組みの骨子であると言えるでしょう。
文化という概念は,国や地域のような大きなレベルだけではなく,日々を過ごしている組織という単位でも成立します。その意味で,僕たちにとって組織文化はとても身近なものと言えるでしょう。
しかし,前回講義を通じて感じてもらえたかと思うのですが,僕たち自身があまり自覚的でないため,組織文化を考えることはかなり難しいです。それでも,組織文化が組織メンバーの行動を方向付け,彼ら/彼女らの協働を左右するものであることを考えると,なんとかして理解しなければいけない。シャインの枠組みにとどまる話ではありませんが,理論や枠組みはそのためにあります。それを使ったところで個別事例について完全な理解はできないけど,それでも理解するための1つの切り口を得るためのものとして,理論や枠組みはあります。その目的に対しては,理論や枠組みは有用です。シャインの枠組みを知ったからといって,それだけでインスタントに,オートマティックにあなたの組織の文化を理解することはできません。でも,これをきっかけに現象の尻尾を掴むことはできます。理論や枠組みは抽象度が高いですが,そのようなものとしてご理解ください。
3.前回の課題へのフィードバック
<前回の課題>
シャインの示した組織文化に関する理論枠組みに沿って,あなたがこれまで所属した,あるいは現在所属している組織の組織文化について,400字程度で分析してください。
前回の課題のポイントは次の2つです。1つめのポイントは,シャインの枠組みの理解が正確であること。こちらはわかりやすいですね。そしてもう1つは,人工物,共通価値,基本的仮定の3つを貫く説明ができていることです。こちらはわかりにくいので,もう少し説明します。これは「○○という習慣があり,これは人工物であると考えられる。その裏には××な共通価値があり,それは△△という基本的仮定に基づいていると考えられる」という,人工物,共通価値,基本的仮定が相互に関係したものとして捉える,ということです。提出された課題を見ると,おおよそ1つめのポイントはクリアできています。ただ,2つめのポイントについては不十分なものが多く見受けられます。改めて,前回の講義noteの大学教育の例を見直してください。以下に取り上げる回答は,2つめのポイントを良く理解できていたものです。
私がこれまでに所属した組織であるインターアクトクラブの組織文化について考えた時、まず他人へ対する思いやりと、他人の力になる心構えの奨励と実践というスローガンや、インターアクトクラブに加入していることを示すピンバッジが人工物にあたると考えた。これらは目に見えるものであり、スローガンは入部したときに渡された書類に記載されていた。
これらの人工物を産み出した理念は、上部組織であるロータリークラブでも共通して掲げられる「奉仕の理想」で、具体的には「最も良く奉仕する人こそが、最も多く報いられる」という考え方である。実際積極的な奉仕活動は、他者の為だけでなく自分のためと多くの所属メンバーが考えていたため、これは共通認識に当てはまると考えた。
最後に、これらの理念の背景にあるのは「インターアクトクラブは青少年に奉仕の心を学んで貰う場である」前提と、「他者への奉仕を行うことは社会の発展に貢献する」という基本的仮定であると感じた。
模範的な回答です。非常に良く書けていますね。人工物,共通価値,基本的仮定がそれぞれどのようなものであるのか,そしてそれらはどのように関係しているのかがとても読み取りやすく書かれています。
インターアクトクラブとは,主にボランティアなどの奉仕活動を行う青少年の組織です。そのような活動を行う組織であるため,価値観や理念を大事にしているのかもしれませんね。
4.講義内容:良い組織文化って何?
先週の講義noteでは,組織文化とは何かについて学びました。今週は,もう一歩踏み込んで組織文化について考えてみましょう。今週のテーマは「良い組織文化とは何か?」です。ここでの「良い」とは「組織的成果に好影響を与える」という意味です。「良い組織文化」について理論や枠組みから説明する前に,あなたの経験に即して「良い組織文化」について考えるワークをしてみましょう。

いかがでしょうか?いろんな答えがあり得ますが,このワークで重要なのは,ただ好影響を与えていたと思われる組織文化を挙げるだけではありません。その組織文化が具体的にどのような組織的成果に好影響を与えていたのか,そしてそれはなぜ好影響を与えることができたのかも考えてみましょう。ぼんやりとではなく,原因と結果,そしてそれらをつなぐ道筋を明確に考えることが重要ですよ。
先週の講義noteで,1980年代半ば頃に組織文化論が爆発的に流行したとお話ししました。そのきっかけとなった研究や書籍は,実はこの「良い組織文化」について書かれたものがほとんどです。今回の講義noteでは,その中でも代表的な書籍である『エクセレント・カンパニー』(原題:"In Search of Excellence")を取り上げ,良い組織文化がどのように考えられたのかをお話しします。
この『エクセレント・カンパニー』はトム・ピーターズ(Tomas J. Peters)とロバート・ウォーターマン(Robert H. Waterman Jr.)という2人のコンサルタントによって書かれた書籍です。コンサルタントとは,クライアント(顧客)が抱える経営上の課題について調査した上で適切な助言をしたり,場合によってはクライアントと共に改革を実行していくことを職業とした人々のことです。外部者でありながら,その組織の置かれている状況を正確に理解することが求められるので,極めて高い情報処理能力や学習能力が求められる職業です。
ピーターズ&ウォーターマンはマッキンゼーというコンサルティング会社に所属しており,そこで超優良企業が持つ特徴とはどのようなものであるのかについて調査していました。調査対象は43社,調査方法は丹念なインタビュー調査です。その調査の中で彼らは超優良企業に共通する組織文化を発見するのですが,実は彼らは当初から組織文化に注目していたわけではありません。彼らは,組織の構造(分業や階層のあり方)や戦略において,超優良企業に共通する要素を見つけることを目的に調査をスタートをしています。その結果として,組織文化の共通性を見出したわけですが,この流れは第3回講義で紹介したホーソン実験と似ていますよね。最適な物理的作業環境を明らかにすることを目的としてスタートし,結果として人間関係の重要性を発見したのがホーソン実験です。ホーソン実験も『エクセレント・カンパニー』も,発見できたことは当初のねらいとは異なっても,柔軟に方針を転換し,その予想外の発見を読み解いていくことで新たな発見をしたわけです。何事にもねばりが重要ですね。
さて,話を戻しましょう。ピーターズ&ウォーターマンは調査の結果,超優良企業に共通する8つの文化的特徴を抽出しました。それらをまとめたものが以下の表です。

<行動の重視>
「まずはやってみよう!」という姿勢です。意思決定のために競合他社や顧客,自社を取り巻く環境を分析することは確かに大事です。しかし,組織が巨大化すると,往々にして組織内のメンバーを説得するための分析が必要になります。分析に時間をかけると機会を逃してしまったり,分析と実行に時間的な距離が生じてしまい,分析結果があてにならないことがあります。また,実行して初めてわかることもあります。分析を目的化せず,行動を重視することで機会を逃さず,さらに様々なことを学習することができます。
<顧客に密着する>
顧客の声を大事にし,そこからさらなる機会を見出そうという姿勢です。どれだけ強い思い入れでつくった製品・サービスであっても,それを購入し使用するのは顧客です。彼ら/彼女らがその製品・サービスに何かしらの魅力を感じなければ,それらを購入することはありません。顧客に密着し,彼ら/彼女らが何を感じているのかを丁寧に把握することは,さらに魅力的な製品・サービスの実現につながります。
<自主性と企業家精神>
組織メンバーが自主的に挑戦することを何よりも奨励する姿勢です。誰かに言われたことをするだけでは,最低水準しか満たすことができません。また,そのような姿勢では,次々と新しい取組みに対しても消極的になりがちです。組織が継続的に改善していったり新たなものを生み出していくには,組織メンバーの自主性を高めると同時に,挑戦を奨励する必要があります。そのためには失敗を叱責したり罰するのではなく,ねらいがあり,かつ目標達成に近づいた失敗であればそれが成功するように支援します。
<ひとを通じての生産性向上>
組織全体に関わる重要な意思決定をするのは経営陣です。その意味で,経営陣はとても重要なのですが,しかし,実際に製品・サービスを生み出し顧客に提供するなど,経営陣の決定を実行するのは現場で働く従業員たちです。「ただ経営陣の指示に従って働くだけの存在」として彼ら/彼女らを軽視するのではなく,彼ら/彼女らこそが自社を担っており,その彼ら/彼女らの働きによって生産性が大きく変わると,超優良企業は考えています。
<価値観に基づく実践>
その企業が大事にしている価値観に基づいて日々の活動が行われていることを指します。これはダイレクトに組織文化の重要性を示していますね。企業特有の価値観は様々であり,その内容の良し悪しを判断することは難しいですが,内容を問わずその価値観が組織メンバーに浸透していると行動の一貫性を確保できるなど,協働に良い影響を与えます。
<基軸から離れない>
新しい製品・サービスを開発するときや,新しい事業に進出するときに,既存の製品・サービスや既存事業と大きく離れないことを意味します。たとえば農家が八百屋をやることは直観的に「近い」と感じますよね。農家として培ってきた美味しい野菜を生産するノウハウがあるので,それを直接販売する八百屋ビジネスに進出することは妥当に見えます(農協とか近隣農家とのめんどくさい関係はここでは無視します)。
しかし,農家が独力で月まで届くロケットを飛ばしたいとなると,これはちょっと遠い。ノウハウも何もないですからね。たぶんできません。あるいは,できたとしてもやらないほうがいい,ということもあります。もう流行は終わりましたが,農家がタピオカミルクティーを売ることはできないわけではありません。ものすごくこだわった商品を提供する場合を除き,タピオカミルクティーの製造・販売にそこまで複雑なノウハウは必要ないですから。でも,農業とタピオカミルクティーのビジネスには共通点があまりありません。農業で培ったノウハウをタピオカミルクティーのビジネスに活かすことも,タピオカミルクティーでの経験を農業に活かすことも,あまりできなさそうです。それよりも,お互いに良い影響を与え合える事業に進出した方がいい,ということですね。関係ないことに気を取られすぎて,本業がおろそかになってしまうこともあります。
<単純な組織・小さな本社>
組織が直面する環境が複雑になると,それに応じて組織も複雑な形になるとされています。また,これは企業組織に限定されますが,組織が巨大化し部門や支社,営業所の数が増えると,それらで重複する機能が生まれます。たとえば営業所ごとに人事部門があり,それらが個別に採用活動をするとなると無駄ですよね。その無駄を省くために,重複した機能は本社にまとめられます。
これは全体的な効率を向上させるために必要なことなのですが,組織が複雑になったり本社に多くの機能が集約されると,部門や支社,営業所レベルでの意思決定が遅れ,それに伴い実行も遅れます。それを防ぐために,組織はシンプル,本社もミニマム,ということですね。
<厳しさと緩やかさの両面を同時に持つ>
組織には守ってほしい価値観があります。しかし,それの遵守を強制すると,現場レベルの組織メンバーは自主性を失ってしまう可能性があります。だからと言って,現場や個人の自由を優先すると,今度は組織としてのまとまり感がなくなります。これは難しい言葉で言うと「自律と統制の両立・使い分け」ですが,超優良企業はこれを実践しています。
超優良企業に共通する8つの文化的特徴を見てきたわけですが,いかがですか?比較的納得のできるものが多いのではないでしょうか。この8つの文化的特徴は,言われてみたら当たり前のことが多いですよね。そうなんです。超優良企業だからといって,すごく優秀な人材がいなければできないことや,すごくお金がたくさんなければできないことをしているわけではないんです。それらはあくまで結果であって,その結果はこういった当たり前に思えることをとことん追求し実践できているから,実現できているのはないかと考えられます。そうしたことを示したのも,この『エクセレント・カンパニー』をはじめとする組織文化論が流行した理由の1つかもしれませんね。
ただ,この講義noteを書きながらこの8つの文化的特徴を眺めていたのですが,本当にこの整理でいいのかという疑問がないわけではありません。たとえば「基軸から離れない」という特徴は,戦略の基本方針であるように思えます。また「単純な組織・小さな本社」は明らかに組織構造に関わる事柄です。戦略や組織構造のあり方も組織文化の一部であると言えばそれまでなのですが,そうすると組織のほぼすべてが組織文化であるということになります。そういった考えもないわけではありません。「組織文化は組織が保有するもの」として捉えるのではなく,「組織は組織文化そのもの」として捉える考え方です。このどちらの考えが妥当なのかはわかりませんし,そもそも妥当か否かを議論する性質なのかもわかりませんが,組織文化というコントロールが難しいものを原因や基礎とすると,結局何も変えられないという結論に行き着く可能性があります。組織文化の存在感をどのように評価するのかは,慎重に考えていきたいところです。ちなみに僕は「組織文化はとても好きだし重要だと思うけど,それだけですべてを説明しようとするのは妥当だとは思えない」というスタンスです。
さらに,この8つの特徴がすべて文化的特徴であるならば,「価値観に基づく実践」は,他の7つとは明らかにレベルが異なります。7つの文化的特徴には価値観に分類できるものがありますから,それらに基づく実践というのはより基礎のレベルにあると考えられます。
このように『エクセレント・カンパニー』の内容には少し荒い部分もありますが,組織文化に光を当てたことは企業経営において非常に大きな意義があります。前回の講義noteでお話ししたように,僕たちは文化と無縁で生きていくことはできません。それが組織生活においても同様であり,組織における協働,そしてその結果としての組織的成果に組織文化が影響を与えるということを示したのは,『エクセレント・カンパニー』やそれに続く研究が果たした大きな貢献であると言えるでしょう。
「良い組織文化」はいつでも同じ?
前節では『エクセレント・カンパニー』を題材に,良い組織文化について考えました。前述したように,『エクセレント・カンパニー』は超優良企業43社を調査対象としていましたが,この43社がその後どうなったかというと,必ずしもすべての企業がその地位を維持し続けたわけではありません。『エクセレント・カンパニー』の出版後2年間のうちに,実に43社中14社が経営不振に陥ったと言われています。その理由は企業によって様々ですが,考えられる1つの可能性は,「どのようなときでも良い組織文化は同じとは限らない」というものです。
テレンス・ディール(Terrence E. Deal)とアラン・ケネディー(Allan A. Kennedy)はその著書『シンボリック・マネジャー』(原題:"Corporate Cultures: The Rites And Rituals Of Corporate Life")の中で,ビジネスのタイプと組織文化の関係について論じています。

上の図が,ディール&ケネディによる組織文化の4類型です。彼らは縦軸に1つひとつの意思決定のリスクの大きさを,横軸にビジネスの結果が分かるまでの時間的長さを置いて,組織文化を4つに類型化しています。
<会社を賭ける文化>
意思決定のリスクが大きく,その結果が分かるまでの時間が長い企業でよく見られる文化を指します。たとえば石油会社は,石油を掘り当てるために大規模な投資が必要です。しかし,確実に石油を掘り当てることはできませんし,しかも掘り始めてすぐに石油が出るわけでもありません。このようなビジネスでは失敗が許されません。投資額が大きいために,1つの失敗で企業の経営が傾く可能性があるからです。したがって,リスクが高く,結果もすぐにはわからないビジネスの意思決定は,常に長期的な視点に立ったものとなります。収集した情報を集団で検討した上で,段階ごとに慎重な意思決定がなされます。
<手続きの文化>
意思決定のリスクが小さく,その結果が分かるまでの時間が長い企業においてよく見られる文化です。銀行や保険会社が該当します。このようなビジネスでは,全体に対して1つひとつの意思決定が与える影響が小さく,また意思決定の良し悪しがすぐにはわからないので,行動の正しさは手続きを遵守していたか否かで評価されます。「何をするのか?」よりも,「どのようにするのか?」が重視される文化と言えるでしょう。
<マッチョな文化>
ちょっと変わった名前の文化ですね。「マッチョ」は「男性的」というニュアンスの言葉ですが,昨今の認識とはあまり合わない言葉かもしれません。これは,意思決定のリスクが高く,結果がすぐに分かる企業においてよく見られる文化です。このような文化では集団よりも個人が重視され,とにかく競争に打ち勝ち高い成果をあげることが求められます。広告業界やテレビ業界など,とにかくバリバリ働くことが推奨される業界に見られる文化と言えるでしょう。
<よく働き,よく遊ぶ文化>
これは何やら楽しそうな文化ですね。これは,意思決定のリスクが低く,すぐに結果が分かる企業においてよく見られる文化です。リスクが小さく結果もすぐ分かるので,従業員はとにかく身軽に動きます。1つひとつの意思決定のリスクが小さいということは,1人ひとりの意思決定が組織的な成果に与える影響が小さいことを意味しているため,従業員同士でチームワークを発揮して,組織として努力していきます。
ディール&ケネディが示したように,その企業が行っているビジネスの特徴によって組織文化は異なると考えられます。『エクセレント・カンパニー』で取り上げられた超優良企業が,必ずしもその後も超優良企業であり続けたわけではないことは既に述べました。これはもしかすると,ビジネスの特徴と組織文化が合わなくなったのかもしれません。組織は成功を収めると,さらなる成長を求めて巨大化していきます。巨大化すると部門が増えたり階層が増えるなど,組織が複雑化します。組織が複雑化すると,意思決定も複雑になります。意思決定が複雑になると,実行が遅れます。超優良企業は成功を重ねてきた企業です。行っているビジネスの性質としては迅速な行動が求められるにも関わらず,成功によって巨大化するにつれて知らず知らずのうちに迅速に行動できる組織文化を失い,手続きを重視しすぎたり,慎重になりすぎてしまって,機会を逃すようになってしまったのかもしれませんね。
強い組織文化論
ここまで説明した内容は,組織文化をその内容から評価するものでした。実は,組織文化の内容ではなく,組織における組織文化の浸透や共有の状況から,組織文化を評価する考えもあります。結論を先取りすると,「(組織文化の内容は問わず)均質な組織文化が広く深く組織に浸透していると,組織の成果は向上する」という考えです。要するに「みんな同じような文化を共有してる組織は強い!」という考えですね。こういった考えを「強い組織文化論」と言います。たしかに,ある価値観があるとして,それを組織メンバーが信奉していたほうがなんとなく良さそうです。そうでなければ,誰もそれに基づいて行動しないので意味がないとも言えます。
では,なぜメンバーが文化を同じように共有している組織はその成果を向上させることができるのでしょうか?それは,メンバー同士を強く結束させ,より良い協働を促すからです。他者と同じような文化や価値観を信奉していると感じられると,人々は「自分は間違っていないんだ」と安心できます。これにより,強い推進力が生み出されます。また,他社も自分と同じ考えだとわかると強い仲間意識が芽生え,お互いに協力するようになります。さらに,お互いの考えもわかるので,無駄なコミュニケーションが不要になり,共同がスムーズになります。以心伝心ですね。
こうして見ると,組織メンバーが均質な組織文化を共有すること,つまり強い組織文化を持つことは良いことづくめですね。みんなで同じ方向を向き,協力していける組織って素晴らしいですね。強い組織文化サイコー!
組織文化は良いことばかり?
ここまで言っておきながらちゃぶ台をひっくり返すようなことを言いますが,果たして強い組織文化を持つということは良いことばかりなのでしょうか?前述したように,強い組織文化論とは「みんな同じような文化を共有してる組織は強い!」というものです。よく考えてみてください。「みんな同じ」ということは,「違う考えを持つメンバーがいない」ということです。違う考えを持つメンバーがいない組織って,どうなりますか?ここでは2つの可能性を指摘します。
1つは,組織からイノベーションが生まれなくなるという可能性です。イノベーションは「技術革新」などと言われることもありますが,本来は技術だけにとどまらない概念です。異なる知識を組み合わせて新しいものを生み出すこと,すなわち「新結合」がイノベーションという概念の本質です。詳細は下記のリンク先を参照してください。
イノベーションを生み出すためには異なる知識を組み合わせたり掛け合わせたりする必要があるわけですが,強い文化を持つ組織では知識に多様性がありません。組織が同じような考えを持つメンバーで溢れてしまうと,新しいこと,すなわちイノベーションを生み出すことができなくなる危険性があります。
もう1つの可能性は,変化に対応できなくなるというものです。強い組織文化を持つ組織では,メンバーが特定の価値観を一様に強く信奉しています。そのため,そういった組織では,別の価値観を受け入れることができなかったり,明らかに自分たちの価値観が状況と合致しなくなったとしても,共有している価値観を捨てることができません。それを捨てたり,その誤りを認めることは,自分たちが否定されることにつながるからです。そのため,何かと理由をつけて自分たちの正しさを主張し続け,新しい価値観や環境の変化を退けます。もちろん,自分たちの価値観を大事にすることは必要です。しかし,過剰にそれにこだわりすぎると,組織が硬直化してしまい,環境に適応できなくなり,いずれ死に至ります。
同じような価値観のメンバーばかりの組織は,居心地が良いとも言えます。自分のことをわかってもらえるし,何を考えているかわからない人もいないわけですから,それを変えたくないというのは理解できます。違う考えを持つ人々を組織に迎え入れるということは,一時的にかもしれませんが組織の安定性を崩します。これは僕の個人的な考えなのですが,人間には混沌を秩序化していく性質があります。混沌は理解不能で,だからこそ不安を掻き立てるからです。要するに人間は混沌を許容できないわけですね。あるいは,許容できないほどの乱雑さを混沌と呼んでいるのかもしれません。だから人間は,その乱雑さを許容できるように自分なりに混沌の中に秩序を見出そうとする。そう考えると,異なる考えを持つ人々を組織から除外することはむしろ自然なことと言えます。
ですが,先ほど確認したとおり,環境変化の激しい現代においては,それでは組織が長期的に存続していくことは困難でしょう。だから,居心地が悪くなるかもしれないけれど,同じ考えのメンバーばかりの組織が与えてくれる精神的な安寧を一時的に犠牲にしてでも,異なる考えを持つ人々を組織に迎え入れる努力をしなければいけないのではないでしょうか。迎え入れるというのは,ただ「これまでにいないタイプの人々を採用する」ということではありません。彼ら/彼女らが組織メンバーであることを踏まえて,改めて組織自体を再編成するという意味です。変化するということは痛みを伴いますが,それでも組織は常に自分自身を更新し続ける必要があるのです。

組織文化はコントロールできる?
この節で今日の講義noteは終わりです。ここまでのお話のそもそもを疑うのがこの節の内容です。僕が大好きな話の展開ですね。
前回と今回の組織文化に関する講義noteでお話ししてきた内容には共通する仮定があります。それは「組織文化はコントロールできる」という仮定です。「好業績につながる良い組織文化とは○○だ!」という主張は,「だから○○な組織文化を持つことができるような施策を実行しよう!」という発想につながります。「みんな同じような文化を共有してる組織は強い!」という強い組織文化論は,「だから組織文化を同じように共有していくような施策を実行しよう!」という発想につながります。これは流れとしてはごく自然なことのように見えます。組織に高い業績をもたらすことのできる文化をつくることができるのであれば,それは悪いことではないでしょう。
ですが,そもそも組織文化はコントロールできるのでしょうか?ここでのコントロールとは,思い通りの組織文化をつくったり,組織メンバーに共通の価値観を半ば強制的に抱かせたりすることを指します。あなたが所属していた組織ではどうでしたか?あなたの組織の文化は,誰かが意図的につくりだしたものだったでしょうか?そして,あなたはその文化を誰かによって共有させられていましたか?
きっとそうではないでしょう。もちろん,あなたの所属していた組織には,意図的にある文化をつくり浸透させようとした人物がいたかもしれません。しかし,それはその人物の思い通りに文化がつくられ広まっていったことを意味しません。なぜなら,あなたを含むその人物以外の組織メンバーは,物事を自由に解釈することが許されているからです。物事は物事としてそこにあります。それは同じ感覚器官を有し,それが同じように機能している人々にとっては共通です。しかし,その物事がどのような意味を持つのかは,人によって異なります。
たとえば,ある体育会系の部活に「部員は全員,頭髪を五厘刈りにする」という習慣があるとします。よくある習慣ですね。このこと自体に意味なんてありません。「意味なんてない」というのは「重要ではない」という意味ではありません。「重要も何もない」という意味です。しかし,この習慣に対して,部員は様々な意味を見出します。ある部員は「この習慣は部員同士の仲間意識を深め,強い結束を生み出すもの」と解釈するかもしれません。別の部員は「この習慣は頭髪にかまけて部活に身が入らなくなることを防ぐためのもの」と解釈するかもしれません。僕のように心の底からひねくれた部員であれば「これは部員が監督の支配下に置かれていることを自覚させるための鎖のようなもの」と解釈するかもしれません。仮に部員全員が五厘刈りにしていても,それは全員が同じように組織文化を共有していることを必ずしも意味しません。一見すると組織文化を共有した結果に見られる行為の裏には多様な異なる解釈がされていて,ただいかなる解釈をしようとも現実的に可能な行為が1つに限定されているだけかもしれません。
このように考えると,組織文化を操って協働を促進することは難しいことのように思えます。あなたはどう考えますか?組織文化のコントロール可能性に対する僕の考えは,ある程度はあります。しかし,それについてはここではお話ししません。次回の講義noteでお話しします。なぜなら,「組織文化はコントロールできるか否か?」という問いは今回の課題だからです。
5.終わりに
前回と今回の2回にわたり,組織文化についてお話ししてきました。文化は僕たちのほとんどが経験していることなので,組織文化は表面的には理解しやすいテーマです。しかし,組織文化のコントロール可能性に関する箇所を読んでいただくと伝わるかと思いますが,深く考え始めるととんでもなく難しいです。この講義ではそのとんでもなく難しいことには極力触れずに,組織文化論の入り口にだけ立ちました。
組織文化という概念はとても扱いが難しいですが,それでも僕たちの行動に多かれ少なかれ影響していることは間違いないように思います。あなたは,この組織文化という概念をどのように捉えますか?今回の講義noteでは『エクセレント・カンパニー』や『シンボリック・マネジャー』など具体的な先行研究も取り上げましたが,僕が重要だと考えているのは実は1番最後に触れた組織文化のコントロール可能性についての議論です。より正確に言うと,コントロール可能性が重要というよりは,組織文化をどのように捉えるか,という点です。組織文化は僕たちから独立して客観的なものとして存在するのか,それとも僕たちの頭や心の中にのみ存在する極めて主観的なものなのか,あるいはこのいずれともまったく異なる在り方なのか。これはすぐには答えが出ませんし,誰もが納得する答えがあるかなんてわかりません。でも,わからないから考えなくていいのではありません。わからないけれど重要だから考えるのです。大学教育において問われる問いは,そのような性質のものであるべきだと考えています。あなたが中核メンバーとして組織を担うようになったとき,きっと組織文化について考える必要性が生じるでしょう。そのときまで,ぜひあなたなりの文化観をつくりあげておいてください。この講義noteがその一助やきっかけとなってくれれば嬉しいです。
ではでは。また次回。
6.課題
組織は,自身の組織文化を意図的に望ましいものへと変えることはできるでしょうか?そして,それを組織メンバーに均一に共有させることはできるでしょうか?前回と今回の講義内容を踏まえて,あなた自身の考えを400字程度で説明してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
