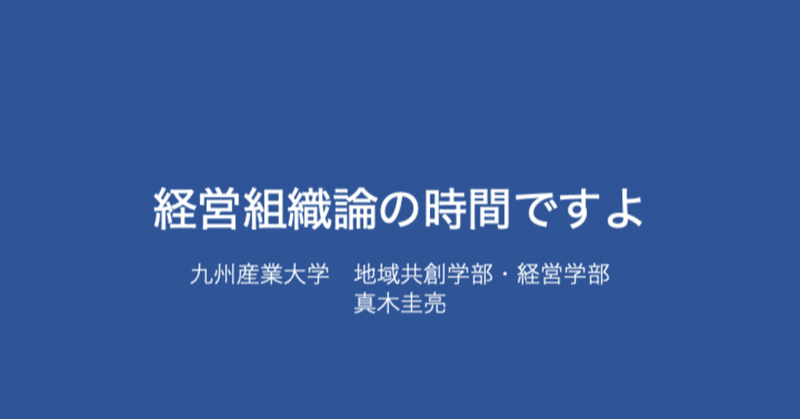
第12回(2020/07/20) 経営組織論 リーダーシップ
1.はじめに
このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第12回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。
こんにちは。この講義も今回で12回目となりました。今日を含めてあと2回ですべての講義が終わります。そろそろ最終レポートについても考えてほしいのですが,7月24日締切の「最終レポートの中間提出」をまだ誰も提出していないのが気がかりです。
毎回,文字数多めの講義noteを書いていますし,その中で割とシビアなことも言っているので僕は厳しい教員と思われているかもしれませんが,そういうわけでもありません(たぶん)。不正をせず,誠実に取り組んでくれればそう悪くない評価をするはずですので,いったん最終レポートを書き上げたら提出してみてください。添削して返します。早めに提出して添削を受けると,それだけ長い時間を修正に充てることができるので,より良いレポートを書くことができます。「良いレポートなんて書けなくていいわい!」という人もいるかもしれませんので,そういった人の心に響く形で言うと,単位を得られる可能性が高まります。中間提出は100点満点中の30点を占めてますから,提出しないと良い成績どころか単位すら相当危うくなるので気をつけてください。相応の努力をしている学生は最大限に評価し,そうではない学生についてはまったく配慮をしないのが,108ある僕の美点の1つです。評価をしてもらうためにはそれ相応のことをしてくださいね。
今日は「3.前回課題のフィードバック」のボリュームが多いので余談はしません。というか,そこで余談をしています。早速,前回講義を振り返っていきましょう。
2.前回の振り返り
前回講義では組織を取り巻く外部環境についてお話ししました。組織の外部環境とは「組織を取り巻くものすべて」のことを指しますが,その中でも組織に影響を与えるものを中心に学びましたね。組織への影響を考えると,環境は以下のように分類することができました。このように環境の多様な側面を考慮しなければならないのですから,経営は大変です。

これだけ多様な環境について考えなければならない上に,これらの環境には不確実性があります。不確実性とは要するに,「これからどうなるかわからない」ということです。不確実性には程度があり,その程度は「環境の複雑性」と,「環境の変化の速度」によって決まります。

これを示したのが上の図です。不確実性の程度が高いということは,将来の環境がどのようになるのかがわからないということです。不確実性の高い環境で事業活動をしている企業は大変ですね。
あなたには,この環境の不確実性について考える課題に取り組んでもらいました。次節では提出された前回課題への回答を用いて,組織と環境の関係についてもう少し補足をします。
3.前回課題のフィードバック
<課題>
環境の不確実性が高い業界と,環境の不確実性が低い業界をそれぞれ1つずつ挙げてください。そして,なぜそう考えたのか,つまりある業界は不確実性が高く,また別の業界は不確実性が低いと考えたのかを,具体的に説明してください(400字程度)。
前回課題のポイントは,講義で学んだ枠組みを用いて不確実性を考えることができているか否かでした。前節の「2.前回の振り返り」でも改めて触れましたが,環境の不確実性は「環境の複雑性」と「環境の変化速度」の2つの要因から決まるとお話ししましたね。この2つの要因から業界の不確実性の高低を考えられているものは高く評価し,以下に取り上げています。逆に,この2つの要因から環境の不確実性を考えられていないものについては,講義内容を踏まえていないため低い評価となっています。必ず講義で学んだ内容を用いて課題には取り組んでくださいね。これは他の講義も同様ですよ。
今回は衣服の業界で考えてみようと思う。環境の不確実性が高い業界はファッション業界、環境の不確実性が低い業界はスーツ業界で考える。
まず、ファッション業界は毎年と言わずシーズンごとに流行・トレンドが変わる。服の生地から変わることも珍しくない。(布から流行はレースに移行等)シーズンによって原材料もデザインも色も何もかもが変わるため、どのファッションブランドも流行を先取りしなくてはならず、複雑性が高く、変化の速度が高いと言える。
反対にスーツ業界は色やデザインは大幅には変わることがとても少ない。スーツは正装として使われることが非常に多く、多くの社会人が少なくとも一着は持っている筈だ。子供でも子供用のスーツを持っている子も少なくない。それだけ需要があるスーツだが、不思議と競争が激しいイメージは私には無い。スーツもカラフルなものはあるが基本は黒や紺、グレーといった落ち着いた色でスタイルも変わると言えば細身だとか袖が洒落てるだとかだと思う。またスーツに使われる材料も大きな変化はない筈だ。
以上の点を踏まえ、私は環境の不確実性が高い業界はファッション業界、環境の不確実性が低い業界はスーツ業界だと設定した。
環境の不確実性が高い業界としてファッション業界を,低い業界としてスーツ業界を挙げてくれました。たしかにファッション業界は先が読めません。毎年,流行が変わるので変化速度は早く,また素材や色など考えるべき要素もたくさんあるため複雑性も高そうです。「ファッション」(fashion)という言葉は,服飾品を指すように思われますが,この単語にはそのものずばり「流行」という意味もあります。
これに対してスーツ業界は需要が安定している印象があります。イギリス風やアメリカ風,イタリア風などスタイルの違いのトレンドはあるのですが,どれか1つのスタイルだけしか需要がなくなるわけではなく,着る人の好みがある程度分かれているので,それほど需要の変動はなさそうです。
ファッション業界とスーツ業界に共通しているのは,どちらも流行や需要をコントロールしようとしているという点です。ファッション業界には「流行色」というものがあります。「その年に流行する色」のことですね。重要なのは,「流行した色」ではなく「流行する色」だということです。実は,流行色は前もって日本流行色協会が決めています。2020年の日本の流行色はヒューマンレッドらしいです(初めて聞いた)。以下の記事が書かれたのは2019年12月13日です。つまり2020年よりも以前に,2020年の流行色を発表しています。
もちろん,流行色の発表だけで実際に流行する色が決まるわけではありません。もっと以前からの流れを無視することはできないでしょうし,流行色の発表後に突発的な要因により別の色が流行することもあるでしょう。しかし,それでも流行色を発表することは,流行をある程度コントロールすることにつながります。これはファッションビジネスでは重要です。衣類は木綿や絹などの繊維を染色し,縫製することでつくられます。繊維の染色は,基本的には縫製する前の段階で行われますが,あらかじめ繊維を染色しておかないと,需要が生じたタイミングで衣類を提供できません。衣類の需要は瞬間的ですから,そのタイミングを逃すと販売機会を逃していしまいます。そのため,あらかじめ繊維を染色しておくことで,迅速な生産・提供が実現されます。
しかし,あらかじめ繊維を染色していると,ある問題が生じます。それは,流行する色の読みが外れてしまうと無駄になる繊維が大量に生じるというものです。ファッション業界は毎年流行が変わりますから,今年使わなかった繊維を来年に回すことできないわけですね。これを避けるには,あらかじめ何が流行するのかを正確に予測すればいいわけですが,成り行きに任せてしまうとその精度はとても低いものになります。そこで,協会が流行色を決めて発信することで,どのような色の繊維を重点的に生産するべきか,ファッション企業は意思決定をすることができるようになります。意図的に流行の方向性を決めることで,不確実性の低減を試みていると言えます。これはファッション業界だけではなく,色が需要に大きく影響する業界であれば同じです。
スーツ業界の需要は確かに安定していますが,それは成り行きに任せた結果として安定しているというよりも,そのようにスーツ業界が働きかけたと考えたほうがよさそうです。就職活動をする際にはいわゆる「リクルートスーツ」と呼ばれるものを着ますよね。このリクルートスーツ,何のことはないただの安いスーツです。たとえば姿勢がよく見える補正機能だとか,どこかから良い香りが出てきてリラックスさせてくれる機能だとか,袖口にボールペンを格納できる機能だとか,何かしらの側面で就職活動に特化しているわけではありません。強いて言えばペラペラで安いから就職活動後に躊躇なく捨てられるくらいです。でも,就職活動を控えた学生は必ずリクルートスーツを買います。このリクルートスーツの売上は,スーツ全体の売上の大きな割合を占めています。
機能的には普通のスーツであるにも関わらず,どうしてリクルートスーツを買うのでしょうか?それは,「リクルートスーツ」という言葉と,それを着る文化・習慣がつくりだされたからです。リクルートスーツという言葉がつくられると,「リクルート(新入社員)用のスーツは,他のスーツとは別物なのか!」という認識が生まれます。そうすると,新入社員になるべく就職活動をする人々はそれを求めるようになります。そして,それが文化・習慣としていったん根付いてしまえば,あとは就職活動をする人々がリクルートスーツを買います。それがもはや当たり前だからです。一般的な人々は,当たり前から外れることを恐れます。人々の習慣に製品・サービスの利用を組み込んでしまうことほど強力な販売戦略はありません。いったん受け入れられ定着した文化・習慣は,変化しづらいものです。したがって,それによって環境からの影響を低減することができます。
しかも,リクルートスーツにはあまり流行がありません。色も形も,だいたい一定の幅に収まります。これは,流行がないというよりは,スーツメーカーが流行をつくろうとしていないのだと思います。流行がないということは,売上の予測を立てやすくなります。売り上げの予測が立てやすいということは,生産の予測も立てやすいということです。リクルートスーツがパッとしないのは,ビジネス的には大きな意味があるのです。
取り上げたのが考えがいのある良い回答だったので,フィードバックが膨らんでしまいました。前回の講義でお伝えできなかったのですが,組織はただ環境に左右される存在ではありません。たしかに環境は組織の行動に大きな影響を及ぼします。しかし,組織はいつだって環境の奴隷なのではなく,環境に働きかけることで自身にとって都合の良い環境をつくりだします。働きかけることのできないものとして環境を捉えるのではなく,変えられるものとして捉えることで,初めて選択肢に入ってくる行動もあるのではないでしょうか。
4.講義内容:リーダーシップ
リーダーシップとは何か?
今日のテーマはリーダーシップです。これまでの講義でお話しした組織の様々な側面をまとめあげ,組織を1つの方向に導いていくことがリーダーの役割ですので,最後に取り上げるのにふさわしいと言えるでしょう。
このリーダーシップという言葉,一般的にも用いる言葉ですよね。当然あなたも耳にしたことがあるでしょう。では,そもそもリーダーシップとは何なのでしょうか?リーダーシップとは何か,あなた自身の言葉で説明することはできますか?いきなりそんなことを言われてもうまく言葉にできないでしょうから,ワークをつうじてリーダーシップについて具体的に考えてみましょう。ワークは以下のものです。あなたの経験を振り返りながら思い浮かべてみてください。

あなたは過去に出会ったどの人物を優れたリーダーであると考えましたか?そして,彼/彼女がどのような人物だから,優れたリーダーであると考えましたか?たとえば「他者に配慮できる」とか「実行力がある」,「ユーモアがある」とか「仕事ができる」など,優れたリーダーの条件として様々な要素を挙げることができるでしょう。よーく思い出し,言葉にして表してみましょう。
人によってワークの答えは様々だと思います。ここでどのようなリーダーシップが優れているということは言いません。ワークの目的は,ひとまずリーダーシップについて考える状態に移行してもらうことです。いかがですか?リーダーシップを考えるモードに切り替わりましたか?切り替わったら,次に読み進めてください。あまり過去に優れたリーダーに出会ったことがなくてイメージがわかないのであれば,スポーツ選手とか歴史上の人物とか,あるいは小説や映画,漫画の登場人物でも構わないので,優れたリーダーについて想像してみてくださいね。
ここまであなたには優れたリーダーについて,あるいは彼/彼女が発揮するリーダーシップについて考えてもらいました。そもそも,リーダーシップとはなんなのでしょうか?リーダーシップを英語表記するとleadershipになります。この単語の接尾語にあたる"ship"は,もちろん「船」という意味ではありません。このshipは「形」というニュアンスを持つ接尾語です。したがって,leader-shipは「リーダーの形」,すなわち「リーダーとしてふさわしいあり方」という意味になります。受験英語もこんなところで役に立つものですね。
しかし,自分で言っておきながらなんですが,「あり方」とはまたずいぶんと曖昧です。具体的にはこの「あり方」とは何を指すのでしょうか?この「あり方」について,ここからはリーダーシップ研究の2つの流れから説明していきましょう。
これまでのリーダーシップ研究は大きく分けて2つの流れがありました。1つは,優れたリーダーの持つ生まれつきの資質・特性に着目したもので,資質論あるいは特性論と呼ばれます。これは,たとえば性格や知能指数(IQ),外見などから優れたリーダーに必要な条件について考えるアプローチです。このアプローチに立つと,「あり方」は「リーダー個人の資質のあり方」となります。背の高いリーダーもいれば低いリーダーもいますし,痩せているリーダーもいればふくよかなリーダーもいるので,外見とリーダーシップに関係があるのかな?と思いますが,性格やIQはリーダーシップに関係しそうですよね。
ただ,この資質論はすでに過去のものとなりつつあります。その理由は,資質だけでは優れたリーダーシップについて説明できなさそうであることがわかってきたからです。上述したように,身長や体重が優れたリーダーシップに貢献するかというと,ほとんど関係なさそうですよね。
この資質論に代わって台頭してきたのが,リーダーの行動に着目する行動論です。優れたリーダーというのがどのような存在であるのかを考えてみれば,行動に着目するのは当たり前です。優れたリーダーを「高い成果を上げている組織を率いている人物」とするならば,それが実現されているのはリーダーが影響力を行使してフォロワー(folower:リーダーについていく人々)の協働を促しているからに他なりません。影響力の行使とは,つまり行動です。このアプローチに立つと,あり方とは「リーダーの行動のあり方」となります。現代のリーダーシップ研究は,優れたリーダーとしての行動を明らかにすることを目的としていると言えるでしょう。
ここでそろそろ大事なお話をしておきましょう。リーダーシップという概念の定義についてです。リーダーシップ研究の歴史は古く,定義も多岐に渡るのですが,ここではリーダーシップを以下のように定義します。この定義を援用する理由は,僕の知っている定義の中でこれがもっとも包括的だからです。
チームの目的を定め,その目的達成に向けてフォロワーに影響力を及ぼすプロセス
Yukl, G. (2002) Leadership in Organizations (5th ed.), Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
この定義では注目すべき点が3つあります。1つめは,リーダーはチームの目的の設定が求められることです。当然ですが,達成すべきチームの目的がなければ,そもそも何のためのリーダーシップかがわかりませんよね。2つめはフォロワーに影響力を及ぼすということです。これは前述したとおりで,フォロワーに働きかけることでその意識や行動に変化を与え協働を促すことが,リーダーシップの機能であると言えます。そして3つめは,プロセスであるということです。リーダーからフォロワーへの働きかけは,単発的なものではなく継続的かつ反復的なものです。
リーダーシップの3つのレベル
<リーダーとは誰なのか?>
ここまで,リーダーシップ研究がどのようなものか,そしてその中でリーダーシップという概念はどのように定義されるのかを見てきました。実は,リーダーシップを考える上でとても重要なことにまだ触れていません。それは,「リーダーとは誰であるのか?」という点です。「何言ってんの?企業だったら社長がリーダーでしょ?このおたんこなす!」と思うかもしれません。たしかに企業において社長はリーダーです。しかし,ことはそう簡単ではありません。「組織におけるリーダーは誰なのか?」という問いには2つの考え方があります。1つは,「リーダーとして影響力を行使できる立場にいる人は誰なのか?」というものです。もう1つは,「リーダーシップを発揮するのは誰なのか?」というものです。同じようなことを言っているように見えるかもしれませんが,前者はリーダーシップは特定の地位・職位と紐づいているという考えであり,後者は必ずしもそうではないという考えです。ここではまず前者について考え,後者については改めてお話しします。理由は,前者の理解があって初めて後者の考えを理解できるからです。

上の図は,組織を簡単に図示したものです。この図においてオレンジ,青色,緑色で示された人々は,すべて組織のリーダーです。もう少しわかりやすくすると,下の図のようになります。赤色の線で囲われた範囲が,そのリーダーが直接影響力を行使できる範囲です。

企業を例に考えると,オレンジ色のリーダーは社長を含むトップ・マネジメント層の人々です。青色のリーダーはいわゆる中間管理職,ミドル・マネジメントの人々です。緑色のリーダーは現場レベルのリーダーであり,たとえば飲食チェーンであれば店長などがこれに該当します。
このような考え方が,前述の「特定の地位・職位とリーダーシップが紐づいている」というものです。組織における特定の地位・職位,特に「社長」や「部長」,「店長」のように「○○長」という地位・職位には,一定の権限が付与されています。権限とは,大まかに言うと「仕事を進めていく上で各組織メンバーに認められた権利」のことなのですが,「○○長」には「部下に指示・命令を発する権限」があります。部下に指示・命令を発するということは,つまり影響力を行使するということです。リーダーシップの定義でも述べたように,リーダーシップは影響力を行使することですから,リーダーシップは特定の地位・職位(=○○長)と紐づいている,と考えられるわけですね。
では,なぜリーダーをこのように分けて考える必要があるのでしょうか?「リーダーならみんな同じとちゃうんかい」と思うかもしれませんね。しかし,そうは問屋が卸しません。その影響力を行使できる範囲によって,リーダーは期待される行動やリーダーシップが異なるのです。ここからは,リーダーの階層ごとに期待される行動について見ていきましょう。
<現場レベルのリーダーシップ>
まずは現場レベルのリーダーシップ です。上述しましたが,店舗や作業現場など,比較的小規模で,リーダーとフォロワーの距離が近い組織をイメージしてください。このような規模の組織では,リーダーとフォロワーは直接関わり合うことになります。つまり,リーダーはフォロワーに直接的に影響力を行使するわけですね。では,このような小規模な組織では,リーダーにはどのような行動が求められるのでしょうか。ここでは小規模な組織の研究から導き出された代表的な2つの理論についてお話しします。
リーダーシップ研究では,伝統的にリーダーの行動の特徴は次の2つの次元に分けて考えられてきました。1つは,フォロワーの仕事に直接的に関わる行動です。当面の目的を決めたり,効果的な分業を考え実施したりすることです。こういった行動への意欲が高いことを「タスク志向が高い」と言います。
もう1つの次元は,フォロワーの感情面を配慮する行動です。フォロワー1人ひとりを気にかけて声をかけてあげたり,時には相談に乗ってあげるなどがこれに該当します。こういったフォロワーの感情への配慮への意欲が高いことを「人間関係志向が高い」と言います。

上図のように,この2つの次元からリーダーシップスタイルは4つに分類できます。このうち,タスク志向も人間関係志向も高い「High-High」のリーダーシップスタイルが場面を問わず有効なものであると,長らく考えられてきました。「High-High」スタイルが,リーダーシップの唯一解とされてきたわけですね。
しかし,これは本当にそうでしょうか?つまり,「High-High」スタイルはいつでも有効なのでしょうか?前回講義で,「状況や条件が変わると適切な組織のあり方や施策が変わるとする理論を,コンティンジェンシー理論(条件適合理論)と呼びます」とお話ししました。リーダーシップの適切さは,状況によって変わるのではないでしょうか?このような疑問に基づいて,リーダーシップ研究はさらに進められました。リーダーシップのコンティンジェンシー理論が模索され始めたわけですね。
リーダーシップのコンティンジェンシー理論の中で有名なものに,「有効なリーダーシップスタイルは,フォロワーの成熟度によって変わる」というものがあります。たしかに,フォロワーが成熟していれば仕事を任せることができますが,未成熟であればそれはできませんよね。下の図は,フォロワーの成熟度と適切なリーダーシップスタイルの関係を図示したものです。タスク志向性は左から右に進むのに対して,フォロワーの成熟度は右から左位進んでいてわかりづらい図なのですがご容赦ください。

まず,フォロワーが最も未熟な第Ⅰステージでは,タスク志向性が高く人間関係志向が低いリーダーシップが求められます。このステージは要するにフォロワーがほとんど仕事について理解していない段階です。したがって,まずはフォロワーには具体的な指示を出し,事細かに監視する必要があります。このようなリーダーとの関わりによって,フォロワーは仕事を覚えて成熟していきます。
少しフォロワーが成熟してきた第Ⅱステージでは,依然としてタスク志向性は高いものの,人間関係志向性も高まってきます。フォロワーはある程度仕事に慣れてきたので,ただリーダーの指示に従うだけではなく,時には仕事に対する自分なりの考えや疑問をリーダーに投げかけます。それに対してリーダーは「いいから従え!」と抑えつけるのではなく,なぜそのような指示を出したのかが理解できるようなコミュニケーションをフォロワーととります。
第Ⅲステージに入ると,フォロワーの成熟度も高まり,だいぶ仕事を任せることができるようになりました。こうなってくると細かいタスク管理はあまり必要ではなくなります。むしろ,どのように進めていくのかをリーダーとフォロワーで話し合って決めていきます。かなりフォロワーがリーダーに信頼されてきたように感じられますよね。
もっとも成熟度が高い第Ⅳステージでは,フォロワーにリーダーの権限が委譲され,仕事を任せることになります。リーダーとフォロワーが同じように考え行動できるようになったからこそできることと言えますね。
もしかすると,あなたは「なんで自分に仕事を任せてくれないんだ!」とか「なんで自分が考えたようにやらせてくれないんだ!」と憤ったことがあるかもしれません。その憤りは正当化だったもしれませんが,他方でリーダーからはまだ未熟であると評価されていたのかもしれません。そう考えると,あなたがすべきことはふてくされることではなく,成熟した姿をリーダーに見せることなのかもしれませんね。
<トップ・マネジメントのリーダーシップ>
次は,ミドル・マネジメントを飛び越してトップ・マネジメントに求められるリーダーシップについてです。たまに,「社長が現場に出向いて一社員として働いた!」みたいなことが話題になることがあります。もちろん現場のことを社長が知るのは大事です。わざわざ社長が現場に出てきたということは,もしかすると現場の様子が社長に伝達されていく過程で,都合の悪い情報が省かれてしまっていることに社長が気づいたのかもしれません。ですので,一概に社長が現場に出向くという行動を否定はできませんが,それでも敢えてはっきり言うと,それは社長の仕事ではありません。現場レベルのリーダーや従業員の仕事です。その違いを無視すると分業の意味がありません。
では,トップ・マネジメントの仕事とはなんなのでしょうか?彼ら/彼女らに求められるリーダーシップや行動とはなんなのでしょうか?それは「自社のあり方を考え,示すこと」に他なりません。
「自社のあり方」には2つのレベルがあります。1つは「ビジョン」であり,「将来のあり方(ありたい姿)」を意味します。これまでの自社のあり方を振り返り,時には問い直しながら,それを踏まえた上で将来どうありたいのかを考えます。顧客にとってどのような価値を提供するのか,従業員とはどのような関係を築くのか,そして社会にどのように貢献するのか。これを考えることがビジョンを考えるということです。
「自社のあり方」のもう1つのレベルは,「事業領域(事業ドメイン)」です。これは「どのような事業を自社で行うのか?」というものです。事業ドメインは,ビジョンの実現に寄与するか否かでその適切性が判断されます。他方で,事業ドメインは単にビジョンと紐づいてさえいれば良いわけではありません。ビジョンの実現に寄与しつつ,事業活動を継続するために十分な利益を上げられるものでなければなりません。
ビジョンや事業ドメインを考えることが求められるトップ・マネジメントの責任は重大です。設定したビジョンが不適切であったり,ビジョンと事業ドメインに整合性がなければ,現在だけではなく将来の経営にも大きな悪影響を与えかねません。ね。ここまでを見てもわかるように,現場に出張って「自分は現場のことをちゃんと見ているんだぞ!」なんてパフォーマンスをしている暇なんて,まともなトップ・マネジメントにはないんですよ。部下を信頼して,自分はトップ・マネジメントとしてリーダーシップを発揮し続けるのが本来の仕事だと思うんですが,どうでしょうかね?
<ミドル・マネジメントのリーダーシップ>
最後に,ミドル・マネジメントに期待されるリーダーシップについてお話しします。前述したとおり,ミドル・マネジメントとは中間管理職のことであり,部長や課長がそれに該当します。「中間管理職」と聞くと,ヨレヨレのスーツを着て疲れた顔で満員電車に揺られている人々を想像するかもしれませんね。たしかに見た目はそうかもしれませんが(失礼),彼ら/彼女らはすごいんです。実は,日本企業の経営は,彼ら/彼女ら中間管理職が担ってきた部分が大きいという考えがあります。それがどういうことかは,これからお話しするミドル・マネジメントに期待される役割を見ればわかります。

上の図は,企業におけるミドル・マネジメントの位置付けを示したものです。トップ・マネジメントがどれほど壮大なビジョンを掲げようとも,それを実現するための具体的業務を行なっているのは現場の人々です。そのため,ビジョンは正確に現場に伝わらなければならないのですが,往々にしてビジョンは抽象的で,現場の業務に落とし込むには解釈が必要です。また,ビジョンが現実離れしたものにならないためには,現場で起きていることをトップ・マネジメントが理解しておく必要があります。トップが掲げた抽象的なビジョンを現場の具体的な業務に落とし込む一方で,現場の状況を理解してそれをトップ・マネジメントに伝える。これを仕事にしているのがミドル・マネジメントです。ビジョンを実践可能な形にしているとも言えますね。これはものすごく大変です。トップと現場の板挟みですからね。彼ら/彼女らの頑張りが,かつての日本企業の隆盛を支えていたということも肯けます。中間管理職になると残業代も出ませんからね。これからは電車やバスで疲れた顔をしたビジネスマンがいたら席でも譲ってあげてください。日本企業を支えているミドル・マネジメントかもしれません。
誰がリーダーシップを発揮するのか?
さて。覚えているでしょうか。「組織におけるリーダーは誰なのか?」という問いは,「リーダーとして影響力を行使できる立場にいる人は誰なのか?」と「リーダーシップを発揮するのは誰なのか?」という2つに分けて考えられるとお話ししたことを。ここまでの内容は立場ごとのリーダーシップのあり方についてお話ししてきましたよね。つまり,1つめの問いに基づいてお話ししてきたわけです。ここからは2つめの問いに基づいて改めてリーダーシップについて考えていきます。
リーダーシップを発揮するのはリーダーだけなのでしょうか?たしかに組織の分業を考えると,権限としては各部署のリーダー(○○長)がリーダーシップを発揮するのは妥当です。
しかし,それは他の組織メンバーがリーダーシップを発揮してはいけないとは言っていません。前述したリーダーシップの定義を思い出してください。リーダーシップを発揮するのが誰なのかは限定されていません。つまり,組織メンバーであれば誰だってリーダーシップを発揮して構わないとも考えられます。むしろ,近年ではそういった考えのほうが主流ではないでしょうか。「組織のリーダー」とは「組織を率いる人」です。目的を達成するために組織の推進力となろうとする意欲があれば,誰だってリーダーシップを発揮することができます。
このような考え方に基づいて,近年ではシェアド・リーダーシップ(Shared Leadership)という概念が生まれています。この概念は以下のように定義されます。
チーム・メンバー間でリーダーシップの影響力が配分されている状態
Carson, J. B., P. E. Tesluk, and J. A. Marrone (2007) “Shared Leadership in Teams: An Investigation of Antecedent Conditions and Performance,” Academy of Management Journal, Vol. 50, No. 5, pp. 1217-1234.
シェアド・リーダーシップが高い組織とは,組織メンバーそれぞれが目的達成のために必要なリーダーシップを発揮している状態を指します。これに対してシェアド・リーダーシップが低い組織とは,組織メンバーに対して1人のリーダーが一方的にリーダーシップを発揮している状態を指します。「リーダーシップが発揮されている組織」として一般的に想定されているのは,シェアド・リーダーシップが低い組織のように思われます。シェアド・リーダーシップと組織の成果の関係性を実証する研究は数多くあります。今後はリーダーシップの考え方自体が変わってくるかもしれませんね。
リーダーだけが重要なのか?
今回の講義ではリーダーシップについてお話ししてきました。その重要性も十分に伝わったかと思います。他方で,組織の成果に影響を与えることができるのはリーダーだけなのでしょうか?つまり,組織の成果について考えるとき,リーダーシップについてだけ考えていれば良いのでしょうか?
こんな問いかけをわざわざするのですから,答えは「No」ですよね。組織にはリーダー以外にフォロワーがいます。当たり前ですが,リーダーはフォロワーがいて初めてリーダーとなります。率いる組織がないリーダーなんていないからです。ついてくる人がいないリーダーなんていないからです。いたとすれば,それはただのお山の大将です。リーダーはフォロワーに認められることでリーダーになることができます。
また,組織に占める人数比で考えても,職位と紐づいたリーダーよりも圧倒的にフォロワーの数のほうが多いですよね。ですから,組織の成果にはリーダーだけではなくフォロワーの行動やフォロワーのあり方も大きく影響すると考えるのが妥当です。
それにも関わらずフォロワーはあまり注目されてこなかったのですが,近年ようやく「フォロワーとしてのあり方」,すなわち「フォロワーシップ」に関する研究が増えつつあります。リーダーの意見にただ従うだけのイエスマンのように,リーダーにとって都合の良いだけのフォロワーは,決して良いフォロワーではありません。フォロワーシップは「組織のゴールをリーダーと共有し,そのゴールに向かうためにリーダーや組織に対して発揮される影響力」と定義されます。フォロワーシップは3つの要素から構成されているとされます。1つめの要素は,リーダーが語っているビジョンの正しさと実現可能性を評価できる能力であり,ついていくべきリーダーを選択する能力です。2つめの要素は,選んだ対象へ意図的に努力する能力,すなわちコミットする能力です。3つめの要素は,意外に思うかもしれませんが,常に批判的にリーダーを評価する能力です。リーダーにコミットしながらも,地震のコミット自体をも疑う冷静さとも言えますね。リーダーシップとフォロワーシップの相互作用によって,組織はより活力あるものとなっていくと考えられます。
5.終わりに
今回の講義ではリーダーシップについて学んできたのですが,実は考えてほしかったのは「誰がリーダーシップを発揮するのか?」と「リーダーだけが重要なのか?」の節で話した内容です。
僕は,シェアド・リーダーシップやフォロワーシップの考え方が好きです。組織への貢献に対する組織メンバーの逃げ道をなくすからです。多くの人々が「自分にはリーダーは無理だから…」とリーダーを引き受けず,組織に対してある意味では気楽な立場に逃げているように思います。もしかすると,あなたもそうかもしれません。リーダーが特定の職位に紐づいていると前提してしまうと,その職位は限られていますから,それ以外の組織メンバーは原理的に組織や他の組織メンバーに対して影響力を行使できません。影響力を行使したい組織メンバーはその状況を好ましく思わないでしょうが,そうではない組織メンバーはこれ幸いとばかりに組織や他の組織メンバーへのコミットメントを放棄します。「自分はリーダーではないから…」と,組織や他の組織メンバーから逃げます。
しかし,シェアド・リーダーシップやフォロワーシップの考え方は,そういった考えを否定し,逃げ道を塞ぎます。シェアド・リーダーシップは,誰でもリーダーシップを発揮し得ることを教えてくれます。フォロワーシップは,たとえリーダーシップを発揮できなくても,組織や他の組織メンバーに貢献できることを教えてくれます。もはや自分はリーダーには向いていないからと,組織に背を向けることはできません。この講義noteを読んでいるあなたもそうです。
1人のリーダーに寄りかかる組織は,そのリーダーでは対応できない状況になったときや,そのリーダーがひどく疲弊し倒れたときに,共に倒れます。特定の個人に依存する組織は,酷く脆弱です。組織として強くあるためには,責任やリーダーシップを分散することで状況の変化に対応できるようにしておく必要があります。特にこれからの時代は,不確実性がさらに高まっていくでしょう。そのような時代を生き抜くためにも,1人ひとりが組織を担う気持ちを持ち,実際にそのように行動していくことが重要なのではないでしょうか。
とうとう次回講義は最終回です。これまでの振り返りとレポートの書き方についてお伝えします。外部公開することに価値のある内容ではないので,次回講義の資料はK's Lifeを通じて配信します,したがって,今回で講義資料をnoteで読んでもらうのは終了です。この講義noteはいつでも誰でも見ることができるものに修正しますので,また気が向いたら見てみてくださいね。きっと,講義を受けている今はあまり理解できなかったり実感がなかったことでも,あなたが大学を卒業し,働き出してから初めてその意味がわかるものもあるだろうと思います。というか,僕は本来,経営学とはそのようなものであると考えています。学部・大学院と経営学を学び,それなりに分かった気でいましたが,僕が本当に実感をもって組織のことを考えられるようになったのは,大学教員として九州産業大学で働き始めてからです。もともと,僕は頭でっかちですからね(物理的にも)。だから,今はそれほどわからなくても問題ないです。ただ,それでも,わからなくても精一杯考えてくれればそれで構いません。最終レポートも,そういった気持ちで,ある意味では気楽に取り組んでくださいね。
6.課題
1人のリーダーが一方通行的にリーダーシップを発揮するのが適切な状況と,組織メンバーそれぞれがリーダーシップを発揮するのが適切な状況とはそれぞれどのような状況でしょうか?400字程度でお答えください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
