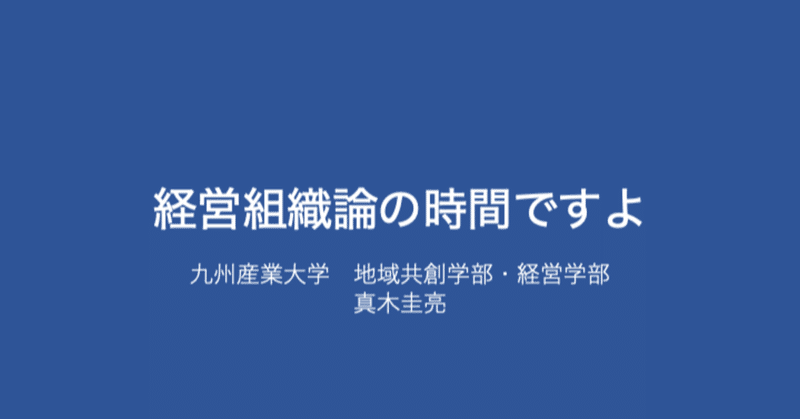
第1回(2020/04/27) 経営組織論 イントロダクション
1.このページの位置づけ
このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第1回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。ゆるめに書いています。動画にしてもよかったのですが,内容的には動画である必要がなく,通信容量を圧迫してしまうのもいかがなものかと考えたため,この形式にしました。また,きっとあなたは遠隔講義期間中のほとんどの講義をスマートフォンで受講するでしょう。ならば,すべてスマートフォンで完結できたほうがいいと考えました。スマホ,便利ですからね。
第1回講義でお話しする内容は,「経営組織論」のイントロダクション(導入)です。この講義がどのように進行されていくのか,あなたはどのように評価されるのかなど,形式や手続きについて説明します。4月27日〜5月13日が履修登録変更期間ですので,このページを熟読した上で,受講するか否かを決定してください。先に言いますが,この講義はいわゆる「楽勝科目」ではありません。「とりあえず言われたことをやれば単位が出る」ということはないので,単位取得には相応の努力が必要です。相応の努力とは「テスト前夜の一夜漬け」ではなく,「半期を通して考え続けること」です。
なお,2020年4月27日時点では,遠隔講義期間は5月6日までです。それ以降に対面型講義(いつもどおりの講義のことです)が可能となるならば,あなたがこの形式で講義資料を閲覧するのは今回限りです。遠隔講義期間が空けた後は,シラバスに記載されているとおりに進めていきます。しかし,遠隔講義期間が延長されるのであれば,当面はこのnoteを通じてあなたに講義内容をお伝えしていきます。このページはその前提で書かれていますが,評価方法などは対面型講義とほとんど同様ですので,今後の状況を問わず,必ず目を通しておいてください。
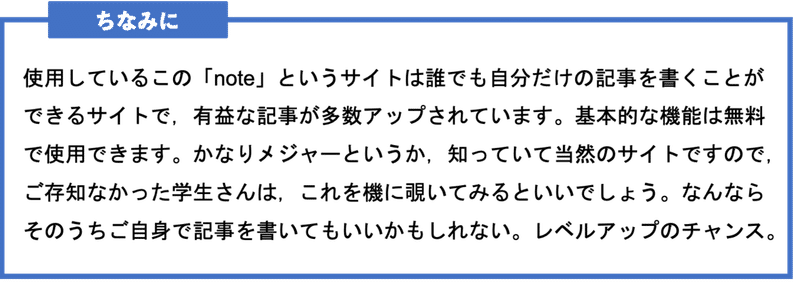
2.自己紹介
真木圭亮です。九州産業大学地域共創学部で教員を務めています。以前は経営学部所属でした。はじめましての人もいれば,また会いましたねの人もいますね。講義科目としては,「経営学入門」(1年次科目),「経営戦略論」(2年次科目),そしてこの「経営組織論」(2年次科目)を担当しています。
専門は企業経営における流行現象で,これはマネジメント・ファッション(management fashion)と呼ばれます。僕たち一般消費者と同様に,企業も流行を追いかけることがあります。「こういうことをしていたほうが,流行りの経営をしているように見えるだろうなあ」と考え,行動することがあります。これは何も悪いことではありません。企業は経営をしていく上で,社会から「良い企業」と認められる必要があります。そうでないと優秀な人々は入社しないし,投資家は投資してくれないからです。むしろ,そういったことを完全に無視する企業のほうが稀と言えるでしょう。
企業が流行を追うということが,企業に何をもたらすのか。それにはきっと良い面もそうでない面もあります。それらを総合的に考えた上で,流行に対する企業の戦略的適応を明らかにしていく。僕はそういった研究をしています。
あとは特に自己紹介としてお伝えすることはありません。所詮,僕はつまらない人間です。しかし,それでもあえて1つだけお伝えするならば,ねこ派です。もはや「ねこ」という字すらかわいい。「ね」ってねこのフォルムっぽいですよね。全世界の人々が1匹ずつねこを飼えば,少しだけ世界は平和になると思います。どれだけ嫌なことがあって心が荒んでも,「家に帰ればねこがいるんだ!」と思えば些細なことです。このような妄想を抱いてしまうことを「ねこ save the world 症候群」といいます。僕の容態は深刻です。
自己紹介はこれくらいにしましょう。もはや紹介する自己がない。
3.講義の進行
「経営組織論」の遠隔講義は,基本的には以下のように進んでいきます。はじめは戸惑うでしょうが,慣れてしまえば習慣化されます。習慣化されるというのは,考えなくても頭と身体が勝手に動く,ということです。それまでは我慢してください。
2-1.授業連絡の通知
講義時間(月曜日09:00)になると,K'sLifeを通じてあなたに経営組織論の「授業連絡」が届きます。その「授業連絡」にURLを貼付しているので,それをクリックしてください。すると,noteの講義ページに移動するので,そのページを読みましょう。この「授業連絡」は,前期中はずっとK's Lifeに掲載しておくので,いつでも閲覧可能です。なお,K's Lifeのサイトにログインしなくても,「授業連絡」はメールで確認できます。しかし,そのメールはあなたが入学時に登録したメールアドレスに届きます。入学後にメールアドレスを変更し,その変更内容を大学に届け出ていない場合は,メールで受信することはできません。K's Lifeにログインして「授業連絡」の内容を確認してください。
2-2.理解度確認
講義終了時刻(月曜日10:40)になると,講義内容の理解度を確認するいくつかの問いが,K's Lifeを通じて配信されます。提出締切はだいたい金曜日の15:00です。この理解度確認が出席代わりとなります。必ず提出してください。なお,提出すればそれだけでいいというわけではありません。あまりに講義内容を踏まえていないものを提出した場合は,講義ページを十分に読まずに提出したという評価になり,未提出扱いとなります。ご注意ください。わからなければ何度でも講義ページを見直しつつ,何が求められているのか,何が問われているのかを考えながら取り組んでください。
2-3.質問の受付
講義終了時刻(月曜日10:40)になると,授業アンケートで質問を受け付けます。授業アンケートも金曜日の15:00までを期限とします。わからないことがあればどんどん質問してください。あなたからの質問は,次回の講義ページでお答えします。質問が皆無だと寂しいので,何かひねり出してください。なお,質問をしたか否かは評価とは無関係です。僕が喜ぶ。37才中年男性が喜ぶ。ただそれだけです。
3.講義ページを読む際のポイント
このような形式の講義を受講するのはきっと初めてでしょうから,いくつかポイントをお伝えしておきます。
3-1.自分のペースで読む
人によって,理解の速さには違いがあります。当たり前ですね。それにも関わらず,限られた時間で多くの学生に必要な内容を伝えなければならない通常の対面型講義では,教員はそういった違いについて必ずしも配慮ができていません。きっと,対面型講義で教員の話を聞き逃してしまったり,説明が早すぎて理解できなくなってしまい,ついつい講義をさぼりがちになってしまったということがあったのではないでしょうか。よくあることです。その場で話されている内容がわからないと疎外感を覚えますよね。そのような場に継続的に参加するのはやや辛い。
ですが,このようなオンデマンド型(好きなときにサービスを受けることができる)の講義は,いつ取り組むのかをあなた自身が決めることができます。もっとも心身が充実したときに,講義に取り組みましょう。そうでないときに無理に取り組む必要はありません。自分の学びを自分でコントロールしていくことで,自分の集中力がどのようなときに高まり,どのようなときに低くなるのかを把握することができます。一石二鳥ですね。
また,講義ページを読み進めていく中で,わからない言葉,わからない漢字,わからない内容があなたの理解を妨げることがあります。そういったときは,いったん講義ページを読むのを止めましょう。きっとあなたはインターネットのブラウジングソフト(SafariとかGoogle ChromeとかFirefoxとかです)で講義ページを読んでいるでしょうから,わからないことはすぐに検索しましょう。漢字の読み方がわからなければ,コピーして検索すればすぐに調べられます。調べようにも漢字の読みがわからず調べられないってよくありますが,コピーして検索は本当に便利です。

何にせよ,効率良くできることは効率良くしていきましょう。スマホもPCもインターネットも,所詮は道具です。道具は使いこなしてなんぼです。確定した答えが既にある問いならば,道具を駆使して答えを調べましょう。調べて,ほぼわかったらまた講義ページを開いて読み進めていきましょう。そして,道具を駆使して調べることで浮いた時間を使って,確定した答えのない問いに取り組んでいきましょう。時間は有限だし,人はいずれ死ぬ。
わからないことを自分で解決できる能力があること,つまり高い学習能力を持つことは,変化の激しい現代において活躍していくために最も求められる要素であると僕は考えています。講義ページはできるかぎりわかりやすく書きますが,それでもわからなければすぐに調べる姿勢を身につけていきましょう。きっと面倒だとは思いますが,それがあなたの学習能力を育み,いずれ強みとなります。強みは自ら育むものです。播いていない種から芽が出ることはありません。そこにワンチャン(One Chance)が介在する余地はありません。
3-2.繰り返し読む
ほとんどの対面型講義では一度しか教員の話を聞くことができません。よくよく考えると,この一度ぽっきりの講義で内容を全部理解しろというのは無理です。一度聞いただけで100分の講義内容をすべて覚えられるわけがない。遠隔講義の方法を検討していく中で,強くそう思うようになりました。
オンデマンド型講義は,講義資料がアップされている間であれば何度でも繰り返し講義を聞いたり読んだりできます。これは素晴らしい。これを活かさない手はありません。講義ページは,何度も読みましょう。他の講義の動画や資料も,何度も視聴したり読み返しましょう。安心してください。何度か読んでも,対面型講義で同じ内容の話を聞くよりは,圧倒的に短い時間で済みます。
あなたは遠隔講義になることで,つまり教員の生の講義を聞けなくなることで講義内容が薄くなるのではないかと危惧しているかもしれません。しかし,僕はそれは逆だと考えています。遠隔講義によって,むしろあなたの学びの密度は上がります。何度でも繰り返し学ぶことで,あなたはより深く着実に学ぶことができるようになります。
3-3.読み方を変える
講義ページを何度か読むとき,次のことを心がけてください。1回目は素直に読むこと。2回目は批判的に読むこと。3回目は「自分だったらこの内容をどう説明するか」を考えながら読むこと。
まず素直に読むことで,講義内容がスムーズに理解でき,頭に入ってきます。1回目はこれを目指しましょう。
でも,それだけだと不十分です。不十分というか,もったいない。僕が講義であなたにお伝えするのは,これまでの経営組織論の歴史の中でおおよそ正しいとされてきた初歩的な理論ばかりです。これらを所与として,つまりそれらは正しいものであるという前提を置いた上で,その後の経営組織論は発展してきています。ですが,経営組織論の新しい研究のすべてが,これまでの研究のすべてを正しいとした上で発展してきたかというと,そうではありません。「こう言われているけど,本当に正しいのかな?」,「いつでもそれは成立するのかな?」,「どのような組織ではそれが生じるのかな?」など,過去の研究に欠けていた点などを指摘しつつ,理論を発展させてきています。こういった「新たな可能性を見つけ,示唆する」ことを「批判」といいます。せっかく学んでいるのですから,これまでのことをただ鵜呑みにするだけではなく,それをさらに発展させることも考えましょう。それがあなたなりのモノの見方をつくります。これが2回目の読み方です。

3回目は,「自分だったらこの内容を他の人にどう説明するかな?」と考えながら読みましょう。自分の言葉で学んだ内容を説明できるようになって初めて,それを自分のものにできたということができます。自分のものにできれば,それだけ使うことができる範囲が増えます。要するに,いろんなことに役立てることができます。学んだことを自由自在に使いこなせること,これを目指して学んでいきましょう。
4.評価方法
4-1.評価方法と評価基準
この講義では以下の方法で評価します。


最終レポートについては次の節で詳しく説明するので,ここではそれ以外について説明します。この講義では,単元ごとに小テストを実施します。2,3回の講義を1単元とし,それが終わるごとに単元ごとの理解度を測る小テストを行います。すべて論述試験です。K's Lifeの「小テスト」機能を用いて行います。
また,毎回の講義内容について理解しているかを確認するために,毎回の講義後に小レポートを提出します。こちらも,K's Lifeの「小テスト」機能を用いて行います。小レポートは小テストのように講義内容の詳細を問うのではなく,講義で学んだ理論や枠組みを使って,与えられたテーマについて自身の考えを記述するものです。
なお,小レポートは出席代わりとなります。最終回以外は毎回行うので,合計で12回の小レポートを提出する機会があります。このうち,未提出回数が半数以上,つまり6回になった時点で最終レポートを提出する資格を失います。要するに単位を修得できなくなる,ということです。
遠隔講義となると,カンニングでもなんでもし放題なので,単元ごとの小テストが意味をなさなくなるのではないかと思うでしょう。成績をつけるという意味では,まさにその通りです。成績をつけるためには,解答にばらつきが生まれるように問題を設定しなければいけないからです。カンニングし放題なら,解答にばらつきはでません。
ですが,「あなたが最終レポートを書くことができるようになるためのアシスト」として小テストを位置付けるのであれば,話は別です。カンニングをしようがなんだろうが,知識を正しく理解し,それを適切に用いて最終レポートを書くことができればそれでかまわないも言えます。後述しますが,最終レポートは出来栄えにかなりばらつきが出ます。細かい評価はそちらを通じて行います。
4-2.最終レポート
4-2-1. 最終レポートのテーマ
この節は暑苦しいです。僕の想いで溢れています。そして,初回講義で最も重要な内容です。心身が充実していないのであれば,いったん深呼吸しましょう。ベストコンディションで読んでもらえると嬉しいです。
準備はできたでしょうか?心臓をやや強めに叩いておいたほうがいいのではないでしょうか?大丈夫ですか?
では始めます。
最終レポートのテーマを初回講義でお伝えする理由は,目標が具体的でなければ,そのときに学んでいることの意味や重要性がわからず,今ひとつ学びに身が入らない可能性があるからです。部活動で「何のためにやっているかわからない練習」ってありませんでしたか?あれ,苦痛ですよね。僕はすごく嫌でした。何のためにやっているのかわかれば自分なりの工夫もできたのに,それができないことがとても嫌でした。効率が悪すぎる。それを避けるために,はじめにあなたのゴールを示します。この講義の最終レポートのテーマは以下のものです。

もう少し詳しく説明します。僕は,あなたには組織をつくる人になってほしいと考えています。誰かがつくった組織にただ参加するのではなく,あなた自身が幸せになることができる組織を,自分でつくることができる人になってほしいと考えています。ここでの「つくる」とは,自分が起業し社長になるとか,組織の代表を務めるとかを必ずしも意味してはいません。自分が組織のあり方に影響を及ぼす可能性があること,つまり自分が組織を変えることができるということを認識した上で,組織をより良い方向にリードしていくことができる主体的な行動の全般を,「つくる」としています。
言いにくいことだから言わないのか,それとも当たり前だからわざわざ誰も言わないのかはわかりませんが,社会にすでにある組織の中で,あなたのために最適化されたものは1つもありません。あなたのためにつくられた組織なんてありません。ですので,就職などであなたがある組織に参加したときに,多かれ少なかれ違和感や息苦しさなどを覚えることがあるでしょう。それは嫌と言えば嫌なのですが,当たり前であるとも言えます。あなたを含めた,しかしあなたそのものではない集合的な誰かのために,組織はあるからです。そういった環境に慣れていくことはとても重要です。
しかし,それは「どんな環境でも我慢しなさい」ということではありません。どうしても耐え切れないほどにその組織で生きていくことが辛いとき,あなたが取り得る2つの選択肢があります。1つめの選択肢は,その組織を離脱すること。会社であれば退職することです。あなたがまず大事にすべきはあなた自身です。たぶん,その組織はあなたがいなくなってもどうにかなります。しかし,あなた自身はあなたがケアしてあげなければどうにもなりません。
組織から離脱すると,あなたは1人になります。もちろん1人で生きていくこともできますが,組織で生きていくことにはいくつかの利点があります。その利点については別の回でお話ししますが,それを享受するためにはあなたは組織に所属する必要があります。新たな組織に所属するとき,あなたはより良い組織を探すこともできますし,自分で組織を立ち上げることもできます。
2つめの選択肢は,その組織を変えるために発言し行動することです。その組織のどのような点に納得がいかないのか,辛いのかを明確に言葉にして声を上げ,それを変えていくために様々な行動をすることです。重要なのは,発言と行動のいずれかだけではダメだと言うことです。不満を漏らすばかりで行動しなければ何も変わりませんし,どうしていきたいのかを言葉にせずに行動すると一貫性が損なわれます。一貫性がない言動はあまり信頼されません。信頼されなければ周囲は納得できず,賛同してくれません。
離脱にせよ発言・行動にせよ,これらの行動の背後には「より良い組織で生きたい」というあなたの希望があります。ならば,考えなければならないのは,「あなたにとって良い組織とはどのようなものなのか?」ということです。これがなければ,新しい組織を選択できません。新しい組織をつくることもできません。そして,組織を変えていくこともできません。新しい組織を選択したとしても,新しい組織をつくったとしても,組織を変えていったとしても,そもそもあなたにとって良い組織が何か,ということが欠落していれば,あなたはその組織でも生きづらさを覚えるでしょう。より良い組織で生きていくために,あなたはあなたが望むものを知る必要があります。そして,それに至る方法,それを実現する方法についても考えていく必要があります。
次いで,なぜレポートで評価するのか,という点について。レポート以外の評価方法としては定期試験がありますが,時間が限られた定期試験でこのテーマに答えてもらおうとするとどうなるでしょうか。高い確率で,あなたは事前に答案を作成し,それを暗記して試験に臨むでしょう。僕はそれに意味があるとは思えません。事前に答案を作成するのであれば,それを提出すればいいだけです。あなたに二度手間を取らせたくありません。
また,このテーマは,時間に追われて取り組むようなものではないと考えています。時間をかけて,ゆっくり大事に考えてほしいと考えています。ですので,はじめにテーマを発表し,さらに時間をかけることができるレポートという形式を採用しました。
4-2-2.最終レポートの評価ポイント
もしかすると,あなたは「ずいぶんと曖昧なテーマだなあ」と感じたかもしれません。きっとそうでしょう。何を隠そう,僕だってそう思っています。この最終レポートは,組織に対するあなたの価値観を表明するものです。他者の価値観を,他の誰かが評価できるのでしょうか?評価してもいいのでしょうか?僕はそれは難しいと考えます。したがって,この最終レポートにおいては,あなたが考える最高の組織がどのようなものであるかは問いません。あなたが本当に理想だと考える組織について,思う存分記述してください。
では,レポートをどう評価するのか?評価ポイントは以下の4つです。

各ポイントについて,順に詳しく説明します。まずは①です。忘れてはいけないのは,この最終レポートはあくまで「経営組織論」という講義の理解度を測るためのものです。最終レポートは思う存分書いていただいて構わないのですが,そこにこの講義で学んだ内容が正しく反映されていないと,どれだけその内容が僕の心を打つものであっても,残念ながらそれは「経営組織論」のレポートとしては無意味です。この講義では,組織を多角的に見るためのさまざまな理論や視点を学んでいきます。その中からいずれかを選択し,その視点でもって最高の組織を論じてください。
次いで②について。どれだけ頑張ってレポートを書いても,それが伝わらなければ意味がありません。具体的には,評価者である僕があなたの考えを理解できなければ意味がありません。僕が理解できるように,あなたは論理的な文章を書くように心がける必要があります。「論理的な文章」というのは,「その言語を理解している人物であれば,誰が読んでも理解や解釈がだいたい1つに収束する文章」を意味します。わかりやすく言うと,「行間を読む力のない人でもわかる文章」です。説明がくどくなっても構いません。とにかく読み手である僕に間違いなく伝わる文章を心がけてください。
次は③ですが,これはそれほど難しいことではありません。たとえば「段落を改めたら,新しい段落の書き出しは1文字下げる」であるとか,「体言止めは用いない」とか,「だ・である」と「です・ます」は混ぜないとか,そんなことです。もし自分の文章に不安があるなら,新書をいくつか読むといいでしょう。
最後に④です。これについては重要なので節を改めて説明します。
4-2-3.最終レポートの作成・提出ルール
最終レポートは以下のルールにしたがって提出してください。

この中で特にあなたが不安に感じるのは文字数でしょう。これまでに,4,000字ものレポートを書いたことがないという人も多いかと思います。しかし,安心してください。どのような項目が必要か,それらの項目ではどのようなことを書くべきかなど,レポートの書き方については後の回で詳しく説明します。提示した項目について1つずつ書いていくと,あら不思議。勝手に4,000字を超えてきます。また,最終レポートの添削期間も設けます。不安な場合は少し早めに書き上げて,僕に見せてください。1人ひとり添削をして返します。僕自身,面倒なレポートテーマであることは自覚しています。それでも僕はこのテーマをあなたに問いたい。考えてほしい。あなたがそれをできるだけのガイドはします。少し大変かもしれませんが,一緒に挑戦してみましょう。
5.今日の理解度確認
ここまでが第1回の講義内容です。僕の講義はどちらかと言えば特殊です。合う人もいれば,合わない人もいます。今回の内容を踏まえて,履修するか否かを決めてください。無理に履修する必要はありません。また,履修に先立ってわからないことはたくさんあると思います。授業アンケートでどんどん質問してください。
今回も理解度確認をしたいのですが,履修登録変更期間が控えていることもあり,具体的な内容についてはお話しできていません。ですので,この講義全体と関わることを考えてもらいます。今回は次のことを考えてもらいます。

最終レポートと同じテーマです。今,あなたが考えている最高の組織を,簡潔に言葉で表してみましょう。きっと,あなたの考えは,この講義を受けていく中で変化していきます。学習には必ず変化が伴います。変化そのものが学習と言ってもいいでしょう。自分がどのように変化していくのかを楽しみながら,この「経営組織論」にお付き合いください。
ではまた次回。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
