
『命懸けの虚構〜聞書・百瀬博教一代』#9
昭和三十五年──。
博教が成人式を迎える、この年、皇太子妃美智子様が浩宮を出産し、浅沼稲次郎社会党委員長が日比谷公会堂で立会い演説中、右翼少年山口二矢に刺殺された。
そして、この年、石原裕次郎と女優・北原三枝が結婚した年であった。
1月19日──。博教の成人式前だった日曜日、裕次郎が初対面の博教に「一度僕の家に遊びにいらっしゃい」との言葉は社交辞令ではなく、現実に実現した。
博教は、親友の後藤のトヨペットの同乗して成城の家を訪ねた。
雑誌のグラビアなんかで知っていた水の江滝子が、丁度あにきの家の前あたりに立っていた。
博教は彼女に挨拶した。
『今日は、石原裕次郎さんの家に来たんです。ここから入るんですか』
とにかく家は立派だった。玄関のベルを押すと女中が出て来て、
『だんな様、百瀬様がいらっしゃいました』
モモセさまなんて言われたの、これが初めてだった。
裕次郎に、部屋やプールのある庭を見せてもらい、しばらくすると食事になった。
裕次郎の妻・北原三枝が料理してくれたステーキと酢のものとオムレツを食べた。
いろいろ話してから帰る時、トヨペット車にやっと入る程の等身大のあにきのバスケット姿の写真を貰った。
裕次郎は、大の酒好きで、けちけち金を使う人ではなかった。
それからは、自宅だけではなく、銀座の『源氏』、乃木坂近くにあった『クラブ・リキ』、赤坂の『花馬車』、新橋の『易俗化』などに連れていってもらったようになった。
裕次郎を、知れば知るほど、博教は魅了されていった。
「ニュー・ラテン・クォーター」は毎夜、一流の芸人を出演させるのと、美しく利発なホステスを置いているので日本中のプレイボーイがやってきた。
長嶋茂雄・王貞治・金田正一といった野球の人気選手も顔を出したが、石原裕次郎が店に現われる時に比べると、まるで横綱と幕内力士ほどの開きがあった。
裕次郎に、太刀打ち出来るプレイボーイは一人も居るわけがなかった。
一夜、あと十分ほどで店が閉店するというところへ裕次郎はお伴の藤村有弘とやってきた。
「博坊、すまないが、ママにあと一時聞くらい俺とバンサ(藤村)を遊ばしてくれるように言ってよ」
「判りました」
ママの山本浅子は数人のバンドマンと十五人ほどの裕次郎係のホステスをホールの中央に特別にこしらえたテーブルに着くよう指示した。
どんなに金が掛かろうと、遊ぶといったらとことん遊ぶんだという心意気は、戦前の財閥三井、三菱の社長かと思うほどの遊びっぷりであった。
それが二十七歳の裕次郎であったことが、博教は、毎夜、万才を叫びたいほど格好良かった。
この年、博教の月給は三万円、裕次郎の出演料は一本五百万である。
三万でも人のうらやむ高給だった時代に、ナイト・クラブヘ二人でやって来て数時間の内に散財するお金が三十万とか三十五万は当時の平均的サラリーマンからすれば狂気の沙汰であろうが、裕次郎はこんな荒っぽい遊びを華やかに、そして嫌味なくやってのけて、ホステス達にチップを切り、引き揚げるのだ。
「おい、パンサ、あれやって見せてくれ」
もうかなり酔が廻った裕次郎が藤村にそう告げると、うれしそうに立ち上がった藤村は、バンドマンのいる舞台のマイクを使って、世界各国の言葉で、いかにこの店のホステス達が美しいかを喋り出した。
英語、フランス語、中国語、スペイン語くらいまではそのニュアンスで理解出来たが、「アッパ、ドン・ドコドン……」と言った時はさっぱり判らなかった。
藤村の口からすらすらと出る外国語を熱心に聞いていた博教に、
「これって全部でたらめなんだぞ、パンサの奴ってうめえだろう」
と裕次郎がバラしてくれた。
どういうわけか裕次郎は藤村有弘が好きで、藤村の住む原宿のセントラルアパートまで、「ニュー・ラテン・クォーター」で飲んだ後の彼を博教がタクシーで送ったのは一再でない。そんな一夜、
「これで後輩達にネクタイでも買ってやれよ」
裕次郎はそう言って一万円くれた。
それは実にダンディで、その格好良さに惚れ惚れした。
裕次郎が背広の上着から厚くふらんだブランドものの財布を取り出し、中を覗き込んでから一枚だけ引き、「ほれ」という感じでくれたとしたらその場で忘れたろう。人生は総て演出だ。
博教はあの夜の裕次郎のさりげなダンディズムをまねびして生涯財布は持つものではないと決めた。
「俺は『人生は演出だ』って言葉も良く使うけど。最初にそれを習ったのは裕次郎ですよ。お金の切り方があんなにカッコイイ人はいなかったね。 財布から恐る恐る札を出すのは野暮だよ。現生(げんなま)って只の金じゃなくて信義を交わすための演出装置なんだからね」
博教が21歳の時だった。
博教は、毎日、洪水のように、世界一流の音楽のステージを目の当たりにしていた。
サラ・ボーン、サミー・ディビスJr、アンディ・ウィリアムス
ジュリー・ロンドン、トニー・ベネット、ブレンダ・リー、アーサー・キット、パット・ブーン、ヘレン・メリル、イベット・ジロー、
次から次へと、世界一流の歌手達が「ニュー・ラテン・クォーター」に出演した。これらの大物タレントが出演する夜の店の華やぎに、ホステスも従業員も異常な盛り上がりを見せた。
そんな人々を夢中にさせる歌手の中でも一番盛り上がったのは、当時まさに「王様」の観のあった、ナット・キング・コールが、フロア・ショーのステージに立った時だった。
この有名過ぎる歌手を来日させたのは若き日の「呼び屋の帝王」永島達司氏であった。
また、トリオ・ロス・パンチョスを紹介してくれた、これまた、呼び屋の卵だった上條恒義は当時、21歳で博教と同じ年、その後も長い付き合いになる。
「呼び屋」といえば、胡散臭く、得体の知れなさだけがただよう。
そういう素顔の知れない人種の中にあって、永島氏は誠実で清い人格の持ち主だった。
「呼び屋」とは海外のタレントを日本に呼んで公演させる仕掛人で、古くは興行師。
博教が成人式を迎えた昭和三十五年頃は、その二年前の昭和三十三年にソ連から「ボリショイ・サーカス」を呼んだ神彰が「呼び屋」として日本中に知られていた。
彼は水商売の興行師をアメリカ式のショービジネス(合理主義)に変えたパイオニアだった。
昭和二十五年六月、朝鮮戦争が勃発すると、戦地慰問の為に、
マリリン・モンロー、フランク・シナトラ、ルイ・アームストロング、パティ・ペイジ等が次々と日本にやって来た。
その頃から日本人がジャズ、ハワイアン、ポピュラー・ミュージックに強く魅かれるようになり、これに目を付けた永島達司は昭和二十八年九月、浅草「国際劇場」で「国際最大のジャズ・ショー」、大阪で「大阪最大のジャズ・ショー」を開催した。
このショーは、国際劇場では十三日のロングランとなり、10万人の客を動員した。
当時、チャールトン・ヘストン、ベティ・ハットン主演の「地上最大のショウ」が封切られて戦後最高の観客動員を記録していた。
永島は、これを見て最大と銘打ったという。この興行が大成功して、彼は「呼び屋の帝王」へ昇って行く。
そして、大物呼び屋となり、ベンチャーズ、ポール・モーリア、ビートルズ、アンディ・ウィリアムズ、カーペンターズ、レッド・ツェッペリン、ローリング・ストーンズ、ホイットニー・ヒューストン、マイケルジャクソンなどを呼んだのが永島氏であった。
永島氏は、平成十一年五月三日に亡くなるまで、興行の世界の大物であり続けた。
昭和三十六年(一九六一)五月八日、ナット・キング・コールが一晩だけ、赤坂のナイト・クラブ「ニュー・ラテン・クォーター」へ出演した。
一晩二千ドルとかいう出演料であった。二千ドルを日本円に換算すると七十二万円だ。二十一歳だった博教の用心棒代は月三万円だから、キング・コールのナイト・クラブ一晩の出演料は博教の二年分の月給と同額だった。
その夜、ステージを終えると、ロビーで博教が喋っていると、永島達司とナット・キング・コールがこちらへ向かって歩いて来た。
永島が、博教だということが判るとにっこり笑った。
こちらも笑顔で応えながら、キング・コールに向かって「グンナイ」と言うと、それに応えて、キング・コールも「グンナイ」と言った。
たったこれだけのことだが博教には天にも昇るほどうれしかった。
そして、ナット・キング・コールのステージを見た、博教は一大決心をした。
「歌手って一度やってみたいんだ。私の『IT’S BEEN A LONG,TIME』(なつかしき思い出)を聴いてくれませんか……」
と永島氏に申し出た。
博教は「竹の家」、「ジ・エンド」で有名なアール・グラントの声と踊りにすっかり魅了されてしまった。
「俺が生涯で本気で弟子入りしたいと心から思ったのは、双葉山の時津風部屋とアール・グラントのふたりだけなんですよ。ま、大好きな殿(たけし)に認められて軍団入りできたら3人目になるけどな。俺、どんな芸名になるんだろうな。下からやるのも嫌だけどな、なべやかんに『兄さん』なんて呼ばなきゃいけないんだろ?やっぱ軍団は無理だなー(笑)」
が、もちろん博教の願いは結実することはなかった。
しかし、その後、30年を超える永島氏との交遊は興行の手はず、呼び屋のマナー、外国人アーティストへの接し方、謝礼の仕方などなど、博教が大いに学習することがあった。
2月、石原裕次郎が志賀高原にスキーに行き、横から女の子に衡突され足の骨を折って、信濃町駅前の慶応病院に入院しているのを見舞った。
暗い病室に、日活俳優課の坂本氏、北原三枝、裕次郎の母堂、石原光子さんの3人がベットを囲んで立っていた。
「痛かったでしょう」と博教が裕次郎に言うと、
「うん、青竹が雑巾絞るようにねじまがっての見たことあるだろう。俺の脚の骨もあんな風に捻じ曲がって折れたんだから」と裕次郎は説明した。
「かあさん。ヒロ坊はね、立教大学に行ってるんだけど、俺が時々行く赤坂のナイト・クラブで用心棒もしているんだ」
「…………」
母堂はこっくりと頭を動かしたが何も言わなかった。
「初めまして、百瀬と申します。いつも御子息にお世話になっております」
挨拶好きな博教は、できる限りの敬意を使って上品で気の強そうな母堂にそう言って深々と頭を下げた。
その後、週に二回は慶応病院に通った。
博教の住んでいた赤坂から信濃町は近かったので、見舞というよりは、裕次郎と話したかったのだ。
裕次郎が慶応病院に入院中、いろんなものをご馳走になった。
夜中に見舞に行くと、奥さんの三枝さんは近くの信濃町駅前のレストランから、カツライスとハヤシライストいった二品を注文してくれるのが決まりのようになっていた。
「博坊、『用心棒』は面白そうだ」
と裕次郎が教えてくれたのは節分の日だった。
昭和三十六年に封切られた黒澤明の「用心棒」は、公開以前のこの年の一月の中旬から、博教の通っていた立教大学の柔道部や相撲部の連中が大いに噂していた。
東京中の運動部に「用心棒」のエキストラのふれが廻っていたからだった。
博教の廻りでも、二枚目で俳優志望だった後藤清忠も、オーディションに出かけたほどだった。
この日、同じ病院に入院している重体の七歳の少女の為に、奥さんの北原三枝の他に病室の人会員で裕次郎のベッドの横で千羽鶴を折っていた。
「貴方も作ってちょうだい」そう北原三枝に言われたが
「鶴なんて折れません」と答えると、
「教えてあげます。下手でもいいのよ」と言われ、三つほど作ったところで作業はやめとなり、「豆まき」が始まった。
「鬼は外、福は内」ベッドに坐ったまま大声を出して裕次郎が豆をまいた。
博教も大豆の入った一升桝を持たして貰い、
「鬼は外、鬼は外、福は内」と大声で叫んだ。
「福は内、鬼は外」の声が止むと、今度は自分の年の数より一粒多く豆を喰べる作業が始まった。
博教は、22個、さらに一年、幸福が続くよう年の数より一粒余計に豆を喰べた。
当時、栓抜きを使わずにサイダーやコーラの瓶の蓋を歯で開けていた博教にとって二十二個の大豆を噛みくだくことは簡単だった。
しかし、一気に飲み込んだ大豆のカスが咽喉にひっかかって気持ちが悪くなった。
博教は、勝手知ったる冷蔵庫を開けてバヤリースジュースを飲んだ。
勿論栓抜きなど使わなかった。
「よしなさい。そんなことしていると、いつか、歯がガタガタになるわよ」
北原三枝が片手で頬を押えながら言った。
「キジ射ち(用便)するから皆さん外へ出て下さぁい」
裕次郎がおどけてそう告げると、北原三枝一人を残して全員が部屋の外に急いで出た。
そろそろ夕食時であった。常識ある大人は用が済むと帰っていったが、博教一人は信濃町駅近くのレストランから、かつライスと魚フライ盛り合せを出前してもらうことにして残った。
博教が出前を食べていると、裕次郎はベッドの横の小机の上から「用心棒」と書かれたシナリオを出して読み始めた。
裕次郎はシナリオを読むのをやめて「用心棒は面白そうだ」と相手をしてくれた。この繊細な気配りが人を魅きつけるのだと思った。
そして博教は「用心棒」を見たいと思った。
「用心棒」の話が終ったので「また来ます」と挨拶して、帰ろうとすると、「ごめん、ごめん、この前持って来てくれた茶巾寿し、美味しかったぞ。また持って来てくれよ」
と言って裕次郎は目をくりくり動かした。
ある日、博教が見舞いに訪れたとき、『月刊平凡』の編集者・木滑良久氏が同席していた。
そのとき、裕次郎の病室に毎週見舞いにやって来る少年がいたが、面会謝絶で毎回会えなかった。
この日、その子供が急に病室の前で「裕ちゃん、裕ちゃん」と大声出して泣き出したが、裕次郎が病室に入れてやったのだった。
少年がズックのカバンの中から自分で彫った『裕ちゃん、マコちゃん倖せに』のメタル色のプレートを裕次郎にプレゼントした後、部屋から出たくないので、貰った菓子を一個一個本当にスローモーションのような動きでバッグにしまっていた。
その子が部屋から出た時、「すげえスローモーだね」と木滑記者は笑った。
子供が名残り惜しそうに帰った後、
「ナメさん。俺の可愛がっているヒロ坊……」
と言って、裕次郎が木滑良久氏を紹介してくれた。
当時30の木滑は、裕次郎番の新米芸能記者であったが、後に『平凡社』改め『マガジンハウス』の社長、そして会長へと出世する。
木滑氏と博教の親密な交際は現在まで50年以上に渡ることになるが、このときが初対面だった。
慶応病院で知り合ってから、その後、羽田空港、ハリー・ベラフォンテの記者会見があったニュー・ラテン・クォーター、日吉の慶応大学で『あいつと私』の撮影中に面会し、いろんなことを話するようになった。
「裕ちゃんの持っている文化は『太陽の季節』なんていう小説のモデルみたいな人とは全く違う、しつかりした家庭で育った子供のたたずまいに溢れていて、当時世間で言われていた不良みたいな人とは全く違うなって感じていた。百瀬君の家は一種独特の世界かも知れないけど、ものすごく愛情とかそういうものに、ビーッと裏打ちされているから、やっぱりちょっと家庭の持っている文化とかさあ、そういうものが感じられるんだよね。Dignityっていう言葉と百瀬博教が合うかどうか別としてね、何か品があるっていうか、とてもね、その辺で馬鹿言っている人格とは違うって感じるんだ。そこが好きなんだよね。裕ちゃんだって他の奴と違うって感じていたから『ヒロ妨、ヒロ坊』って言いながら、百瀬君を可愛がっていたと思う。そうじやなかったら、とてもじゃないけど僕は、おつきあいするのは勘弁してもらいますよ」
と後に木滑良久は語っている。
博教は毎日のように見舞いに訪ねた。
そして裕次郎とたわいもない遊びに興じた。水の江瀧子が持って来たというおもちゃのピストルで輪ゴムを飛ばしたり、ゴム製のトンカチ(鉄槌)で頭を叩いてもらって喜び、大笑いしていた。
この玩具のトンカチは木滑氏が銀座のおもちゃ屋「きんたろう」で見つけたものだった。
木滑氏がこのプレゼントを裕次郎に届けに来た日、やや遅れて博教も見舞いに行った。
そこで木滑と同行していたカメラマン橋本敬之助に裕次郎がトンカチで博教の頭を殴っている写真を五枚撮ってもらった。
セーター姿の博教の頭を「こいつめ、こいつめ」と声を上げながらおもちゃのトンカチで何度も叩いてくれた裕次郎に、仕舞いは抱きついて左頬にキスしているモノクロの写真は一万枚ほどある博教の写真の中で特に気に入った写真になった。
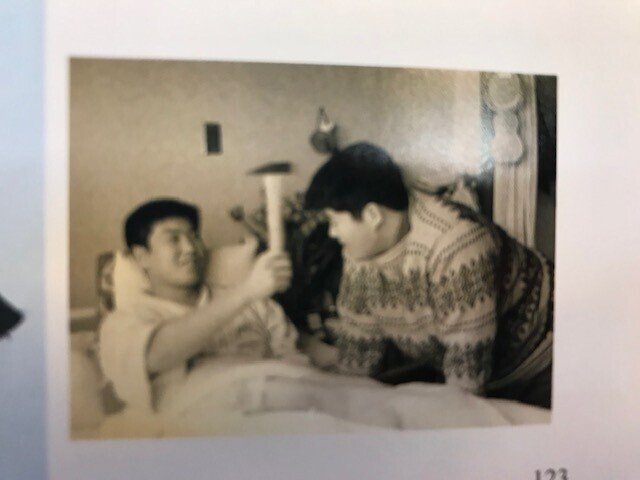
そんなある日、貼り絵で有名な放浪画家・山下清氏が裕次郎と対談するため、編集者に連れられて病室にやって釆た。
博教は高校生の時、山下清氏の作品展を市川の「つるやデパート」で観ていたし、氏のころんとした姿も市川駅で二度見て小たから、病室に入って来た時から興味津々で眺めていた。
山下清氏がべッドに横になっている裕次郎を見るなり、
「ああ、あんた誰」と言ったので、博教はびっくりした。
「い・し・は・ら・ゆ・う・じ・ろ・う・で・す」
裕次郎はゆっくりと自分の名を告げた。
「あんた、何でそこに寝てんの」
「スキーで怪我しちゃったんです。こっちの足が折れちゃったんで、治してるんです」
「足折れたんじゃ、痛かったよな」
そう言うと、ベッドに横になっている裕次郎の右横の窓に目をやり、三枝さんが毎日エサをやるので集まってきている鳩を見た。氏はすたすたと歩いて窓をどんと叩いたので鳩が逃げた。
「駄目、そんなことしちゃ鳩が可哀相でしょ」
自閉症の氏はそのままおし黙ってしまい、対談にならなくなってしまった。
山下清画伯と裕次郎の対談の翌日、裕次郎の病室に入って行くと、石原慎太郎氏が裕次郎を叱っていた。
「『こんな高い部屋に、おまえはずっと入っているつもりか。もっとお金を大事に使え』裕次郎の入っている、一日、数万円もするという病室についての事らしかった。
博教が病室に入ると同時に慎太郎氏はさっと出て行った。
裕次郎は博教の顔を見ると照れくさそうに
「兄貴は、俺を中学生の時みたいに叱りやがる」と言った。
博教が三度目に石原慎太郎に会ったのは、3月9日、有楽町の日活国際会館ホテルだった。
この日、長門裕之、南用洋子御両人の結婚式し結婚披露宴が行なわれた時だった。
スキー場で折った足が治らないままギブス姿で、車椅子に乗って裕次郎は出席する事になった。
裕次郎は結婚式の数日前、病院で博教に「アキオちゃんの結婚式の日、俥椅子を押してくれないか」と言った。
結婚式の日、博教は早目にホテルに行って、昨日から泊っていた裕次郎の着物を着せたり、袴を付ける手伝いをした。仕度が出来ると、
「百瀬さんお行儀よくしてちょうだいね」
と江戸棲を着た三枝さんに言われた。それは、まるでかつて菊江がよそゆきの服を着せながら、くどくどと言ったのと同じ台詞だったので、大いにくさった。こちらはもういい加減大人なのだからと辟易していた。そんな博教にはおかまいなく「お行儀よくしてちょうだいね」と押し被せるように繰り返した。
それを裕次郎は結婚披露宴の会場へ向う車椅子の上でにこにこしながら聞くとみんなに声を掛けた。
「それじゃ出掛けよう」
車椅子にはハンドルなどないのだが、長い廊下を曲る時、裕次郎は手を伸ばして、右に曲る時は右に、左の時は左に、ハンドルを切る真似をした。 廊下を通る客や従業員がそんな裕次郎を面白がって眺めると
「バカ様は御歳、二十六歳」
と、久しぶりに広々とした世界に出た裕次郎は、はしゃいで見せた。
そんな裕次郎の仕草を見ながら、十九歳の博教は大好きな石原裕次郎に、彼の大勢の仲間をさきがけて、車椅子を押す役を頼まれた事に感激していた。
結婚式の終った長門裕之の控室に入って行くと、披露宴直前だというのに新郎長門裕之の顔は髭だらけだった。『人狩り』を撮影中なので、髭を剃ると、前後が繋がらなくなるとかだった。
披露宴が初まり、来賓の祝詞、石原慎太郎氏が挨拶した。
「私の作品『太陽の季節』が奇しくもお二人の出雲の神様となったわけであります。私の小説が世に出た時は『価値紊乱』とかで色々問題がありましたが、本日ここに、おられるこのような美しいカップル誕生に役だった事は思いがけなかっただけに、わたくしは喜びに湛えません。お二人の倖せを心からお祈りします」
長門裕之氏と南田洋子氏は、石原慎太郎の小説『太陽の季節』が映画化された時、主人公の達哉と英子を演じ、それが縁で結婚するまでの仲になった。
慎太郎氏の次は裕次郎が挨拶した、出会ったばかりの二人の仲をちょうちん持ちした頃の話をした。
来賓の挨拶が総て済むと、披露宴にやって来ていた人達が、車椅子に近寄って来て、裕次郎に怪我の見舞を言った。
一番最初にやって来た森繁久弥は、つま先から大腿までギブスをしている裕次郎に向かって、
「奥さんを愛する時にそれじゃ困るだろう、でも、こんな事したり、あんな事したり」とおかしな腰付をしてみせ、生真面目な三枝を赤面させていた。
二番目は、息子がファンだと告げた、古今亭志ん生。
三番目は水原弘だった。水原氏と博教はニュー・ラテン・クォーターで時々会って喋ったりしていた仲だったから、裕次郎さんの車椅子を押している博教とも話をしていった。
水原弘が、白川由美や山本富士子、扇千景等の女優陣の方にいってしまうと、上田吉二郎がやって来た。彼は裕次郎さんのギブスのつま先にまでマジックインクで書かれた、色々な字を目敏とく見付けると、
「なんですかこの字ぃは? どない呪いです」と、質問した。
裕次郎のギブスには、たぶんアメリカ人の真似なのだろうが、早くギブスが取れるようにとの希いを込めて、見舞に来た色々な人達が勝手な文句を、ギブスに書いていった。博教も「治れよ。さらば開けん」とわけのわからぬ句をギブスに記していた。
裕次郎さんからギブスに書かれた字の訳を聞くと、上田吉二郎は万年筆で「裕ちゃんの足、早く良くなれ」と袴をまくってギブスに書き難そうに書いたが、書く前に「おしっこのかからない処へ書こう」と、言って裕次郎を大笑いさせた。
部星に戻ると、ポーカーが始まっていた。
博教が部星の角で裕次郎と喋っていると、慎太郎氏と奥さんがやって来た。
慎太郎氏は、部星に入って来るやいなや、ポーカーに熱が入っている人達の数を算え「俺が入ると、オーシャンズイレブンだな」と言いながら、奥さんを置いてポーカー台の方にいってしまった。
奥さんは裕次郎の処にやって来ると、見舞を言ってギブスで左足が全く曲らない事を知ると
「裕ちゃんそれじゃぁ雲古する時に困るわね」と、心配そうにして言った。
「ええ、そうなんです。病室でキジを撃つ時、毎日マコの世話になってる……」
キジを撃つとは、登山家が野山で用を足す時の隠語である。
竹薮に潜んでいるキジを狩人が鉄砲を構えてしゃがんで狙っている姿からとった言葉らしい。
「三日前、結婚式に出るんだからって言って無理に風呂に入ったんです。入院以来三十六日ぶりだったから、気持がいいったらありゃしない。消しゴムで字を消すように躰の皮がむけた。皮膚が荒れるといけないっていうんで、マコとクニちゃん(水の江滝子の姪)がアルコールで躰を拭いてから、パウダーをはたいてくれた。ずーっと酒飲んでないから、躰中に塗ったアルコールで酔っぱらっちゃった」
裕次郎が笑うと、慎太郎夫人も可笑しそうに笑った。
この結婚式の後、博教は、石原裕次郎の成城の家で長嶋茂雄氏と二人だけで鮨を御馳走になったことがある。
三枝夫人が留守で、一緒に飯でも食べようと誘われて、裕次郎邸に行くと、長嶋茂雄がいた。
二人共に、スーパースターでありながら、まるで兄弟のように親しくつきあっていた。
「若いうちに金を儲けなければ駄目だよ」
と長嶋氏は博教に言ってくれた。
そして、銀座の鮨屋から職人を呼んで、目の前で握らせた裕次郎の歓待の凄さには驚いた。
長嶋氏を招いて寿司を食べるのは2度あった。
ある日、長島氏が「裕ちゃん、実はリキさんのピストル見ちゃいましたよ」と言った。
博教は以前、店で「ユーが(喧嘩)に負けたら撃ってやろうかと思った」って力道山に拳銃を見せられたことがあったのだが、そのことは、長い間、誰にも言わず黙っていた。
博教は、だから、力道山は自分以外のみんなにも見せてんだなと、思った。
拳銃は博教の用心棒という運命を導き、そして博教の最愛のひととの仲を割き、博教を獄へと誘う。
そのことはまだ誰も知らない。
「長島さんと一緒になった時の写真はまだとってるよ。ほら、ご覧。彼とは変なところで会うんだよね。最近も結婚式で会ったね。何時も「先輩!」って行儀よく、俺を立ててくれるよ。
一応、俺、立教の先輩だからね。でも確かに距離感はあるなー。有名人は大好きだけど、俺が彼にグイグイいかないのは格闘技やお相撲さんや芸人さんと違って、もともと野球選手にはあんまり興味がないからかなー」
──この裕次郎の入院の話は博教の本のなかでも長々と事細かに綴られている。
だが、この物語の要約係の私も、どこも切りたくないと思った。
それを伝えると……。
「わかるよ。それはこれが俺の黄金時代を描いているからなんです。
『華麗なるギャッツビー』みたいなもので、この章は『華麗なるユウちゃんモモちゃん』ですよ」(笑)失われてしまった栄光の日々、これはスーパースターの束の間の休日だろ。時間がゆっくりと流れてるんですよ。
誰もこの時代には戻れないし、あにきも逝ってしまって、その後の亀裂も誤解も解けないままだろ。ここは俺だって書いていて涙が出てくるし、読み返しても涙が出てくる。単なる感傷じゃないんだ。好きで好きで、好き過ぎた、あにきとは、こんな蜜月があったんですよ。「覚えていますか?」って天にいるあにきに向けて報告してるようなもんでね、『不良ノート』はこのシーンのために書いたようなもんですよ」
11月に入り、『アラブの嵐』のロケ先カイロに出発する、裕次郎を羽田に見送りに行った時だった。
大スター、裕次郎が海外に出たり、帰ったりする際の羽田のロビーはいつも大混乱だったので控え室は誰にも知らされなかった。
裕次郎は部屋の中の見送りの人達全員に、
「それでは行ってきまーす」
と、小学生が遠足の見送りに駅まで来た母親に言うようにおどけて言ってから、一人一人と握手した。
裕次郎はロビーに出ると早足でゲートに向かった。
水の江滝子と並んで裕次郎の後ろを随いて行った。
水の江が後ろから歩いて来た婦人に頭を下げた。
裕次郎の母堂だった。
二人は立ち止まり二言三言何か喋った。話が終った様子なので、自分も挨拶しなければいけない。母堂に近付いて行くと、
「おお怖い、おお怖い」と言って後ずさりした。
それは不思議な体験だった。
敬愛する裕次郎の母堂に対して、博教が不興を買うような言葉遣いをするわけがない。それでも「怖い」と言われたことは、当時、今夜にも殺されることもある稼業に、夢中で浸かっていた博教の躰に潜在する狂気が、鍾愛の息子を傷つけると察知されていたのであろう。
「アラブの嵐」のロケから、裕次郎が帰国した12月、博教は裕次郎の誕生祝いを兼ねた餅搗き大会に招かれた。
小さなプールのある五十坪ほどの庭に、紅白の幕が張られていた。
臼の前に立った裕次郎は「石原組」と胸に染め抜かれた藍色の半纏を着て、その上に薄い桃色のしごきで襷掛けし、豆しぼりの手拭いで鉢巻きしていた。
「あにき、本日は招いて戴きまして有難うございます」
「ご苦労さま。そっちで着替えて来いよ。ヒロ坊と後藤君に半纏貸してやって」
係りが出してくれた半纏は、裕次郎が着ていた色とは違った。
餅搗き大会に集った裕次郎一家のスタッフが着ている胸に「石原組」と入った黄土色のものだった。
「この色は嫌だ。あにきのと同じのがいい。この半纏だとどこかの商店街の大売り出しに駆り出された、慶応出の若旦那みたいでしょ。半纏が黄土色だからなんだ。藍の半纏着ればああは見えない」
そんなことを話していると、裕次郎と同じ藍色の半纏を着た北原三枝が奥から出て来た。
あにきの鉢巻きは後ろで結んでいたが、三枝は魚河岸の軽子のように、豆しぼりの手拭いをねじり鉢巻き風に前で結んでいた。
襷もしている。半纏の前がはだけないように、そろばん玉の模様の付いた茶色の祭帯を締めていた。その格好が黒のタイト・スカート、黒の靴下にぴったりと似合っていた。
半纏は、裕次郎の着替え用の藍のを貸してもらって決着がついた。
博教が腹に晒を巻くのは、鳥越祭で千貫神輿を担いだ、高校一年生の時以来だった。
餅搗きが始まった。杵を振り下ろすたび「よいしょ」と言っていた掛け声とは違ったおかしな掛け声が飛んだ。
「いやいや!」「だめだめ!」女の声色を使って、杵が臼の中の餅に当る度に自身の腰も妙な格好にねじるので、男衆は大声を上げて笑った。
三枝は真赤な顔をして恥ずかしそうにしている。
が、逃げ出したりしなかったので、エロチックな掛け声はいつまでも止まなかった。
裕次郎は、自らお供えを作っていた。手つきがよかった。
裕次郎は字も上手だが、お供えの形も良い。
お供え作りが終ると、今度は三枝が大福ほどの大きさの丸い形の餅をいくつも作り出した。三枝が丸めた餅を裕次郎は一つ取ると、
「おとうちゃん、カイロで見たの駱駝の雲古このくらいの大きさだったね」
「そうだねえ、もうちょいと大きめだったんじゃない。道にいっぱい転がってて往生したねえ」
三枝さんが餅を丸めている後ろに、割烹着を着た母堂が現われた。
取材に来ていた「週刊平凡」のカメラマンが、お供えを作っている裕次郎の横でそれを見ている母親という図の写真を撮った。
博教は、以前に「おお怖い」と言われたので遠慮して、母堂を遠くから眺めただけで、近付いて挨拶しなかった。
撮影が終ったので、手早く着替え、皆に挨拶して石原家を辞した。
この日、自分も男と生まれたからには、大勢の若い者に「百瀬半纏」を着せて、餅搗大会の一つくらいはやってみたいと思った。
博教が昭和五十三年から毎年主催している「鳥越祭を愉しむ会」の原点は、二十二歳の時に味わった、あの餅搗大会なのであった。
「石原組」の半纏には芥子色のものが混ざっていたが、博教の使っている半纏は藍一色である。
「半纏には俺の拘りがあるさー。親父の兄弟分、深川の大侠客・武部新作に親父が形見に貰った絹半纏は俺の家宝ですよ。若い人はビンテージ・ジーンズとか集めてるけど、俺は半纏、しかも藍色に限るね。あれは祭りの時の一心同体を現す制服なんだよ。濃い藍色で粋に着るのが、俺のありかた、やりかたなんですよ」

昭和37年──。
博教は23歳になった。
4月2日、石原裕次郎が北原三枝を連れて、ニュー・ラテン・クォークーにやって来た。
彼女に会うのは、去年の暮に成城の石原家で行なわれた餅つき会以来だった。
彼女に、餅をもらったお礼の挨拶に行くと、裕次郎が「ひろ坊。映画に出ろよ」と言った。
聞いてみると、石原慎太郎の小説『雲に向って起つ』を、日活で映画化する事に決まった。
が、主演の裕次郎と、間違って喧嘩し、彼を肩にかついで投げ飛ばしてしまう、大きな身体の学生の役をする俳優が見つからないのだそうだ。
そこで、博教の百二十キロの身体が見込まれたらしい。
その二日後、日活撮影所へ呼ばれた。
博教は慶応大学の友人の運転するサンダーバードで撮影所入りした。
食堂で、博教の着くのを待っていてくれた裕次郎は、早速、助監督のところへ連れていってくれた。
助監督は台詞が旨く喋れるかテストすると言い、シナリオが渡され、博教の相手をしてくれる俳優と、同じ台詞を二回やりとりすると「いいんじゃない」と助監督が言った。
この映画には、水谷良重、浅丘ルリ子、田代みどりも出演するらしい。
博教の役は柔道部の猛者で大学七年生の塙団右衛門だ。
国会記者・武馬役の石原裕次郎に恋している亡き政治家の娘浅丘ルリ子の用心棒でもある。
「いい役だぞ」と言われたとおり、台詞が沢山あり、とても面白そうだった。
食堂に戻ると、裕次郎は、小沢昭一氏と喋っていた。
紹介してもらい、小沢氏の話しを聞きながら、ランチの大盛を喰べた。
その間、小沢氏の話があまりにも面白いので、何度も大笑いした。
小沢氏が、全国の「エロ唄」を蒐めている、と言うので、
「『草津節』の変え歌を、知っていますか?」
と横から口を出して小さい声でちょぴり唄うと、小沢氏は「知らない、知らない」と言って、小沢氏は博教が唄う草津節の変え歌を、紙に写すことになった。
「させろ、させろと(台詞)拝むの、頼むの、手を付く、なんぞと
言うからさせりや、ドツコイショ、させてしまえば、コリヤ
(台詞)上付、下付、毛がない、なんぞと言うから、腹が立つよ
チョイナ、チョイナ」
博教は、二度唄って、小沢氏に変え唄『草津節』を伝授した。
食事が終りジュースを飲み終えると、博教は、裕次郎と小沢氏に挨拶して食堂を出た。
タクシーを呼んでもらう為に俳優課に行こうとすると、裕次郎が追って来て、「明日から京王電車で通えよ。調布の駅前に日活の専用バスが待っている。バス代は無料だからな」と言った。
博教は準主役で映画に出演するのだから、格好をつけて行かねばと思いサンターバードに乗って来たのだが、それを注意してくれたのだ。
普通なら食堂で口に出しただろう言葉をわざわざ追ってきて、誰もいないところで言ってくれる繊細さと、人の心を傷つけない鋭い神経に博教は感服させられた。
裕次郎があえて博教に注意するにも理由があった。
シンデレラ・ボーイのように思われる裕次郎にもスターに上り詰める階段はあった。
「慶応大学に行くのが嫌になって家でぶらぶらしている弟を、日活に入社させたのは私だ。日活がどうしても私の作品を映画化したいと言うから、作品を渡すが弟を俳優として使ってほしいと言うと、二つ返事で承知してくれた」
後年、石原慎太郎氏から聞かされた裕次郎の映画入りのいきさつだ。
昭和三十年の七月、石原慎太郎が「文學界」に発表した「太陽の季節」が文學界新人賞、第三十四回芥川賞を受賞し、そのセンセーショナルな内容は“太陽族”の流行語まで生み出した。
その作品を翌年早々日活が映画化した。
日活映画「太陽の季節」は長門裕之と南田洋子の主演で制作されたが、初めは主演を原作者の石原慎太郎自身が希望した。
しかし、彼はその時すでに東宝と三本の出演契約を結んでいたため、五社協定の制約から不可能となり、長門に主演が決ったが、それならば弟を日活に入社させてほしいと願ったのだ。
石原裕次郎は昭和三十一年四月三日、新橋のダンス・ホール「フロリダ」でのクランク・インから、映画俳優としてスタートした。
この時は大学の拳闘部員という端役だったが、そのスマートな長身の躰を画面いっぱいダイナミックに躍動させ、観る者に強い印象を与えた。
日活へ入ったばかりの裕次郎の出演料は一万一千円だったそうだ。
入社してまもなく人気者となって、裕次郎のギャラは、たいへんな金額となった。
それでも、入社当時は、鎌倉の自宅で五時に起き、江の電で藤沢まで出て、横須賀線で東京駅、東京駅から中央線で新宿に行き、更に乗り換えて京王線で撮影所のある調布まで来て、歩いて撮影所に入ったらしい。
そして昭和三十三年の正月映画「嵐を呼ぶ男」は浅草の映画館一館で、六日間に三万八千人の観客を動員し、総配収三億五千六百万円という空前のヒットを飛ばした。この映画で石原裕次郎は時代を支える日本最高のスターの地位を不動のものとした。
日活の堀久作社長は「嵐を呼ぶ男」の大配収で、遅配だった社員の給料もすっきりと払えるようになった。
堀は裕次郎にローレックスの腕時計をプレゼントした。
黄金のローレックス・デイトジャストである。
博教はこの時計を何度か見たことがあったが、そんな経緯のある時計だとも知らずに、
「裕次郎らしくない時計ですね。あにきくらい偉い人はローレックス・デイ・デイトしていますよ」
と、つまらないことを言ってしまった。
裕次郎の指に輝くスターサファイアの指輪を見れば、ローレックス・デイ・デイトを買うくらいはお茶の子さいさいだったのだ。
だが社長のプレゼントである時計をしないで、その時計より何格も上の品をするという不作法を嫌ってのことだとは、まだ博教には知る由もなかった。
自分が日本一の大スターになるのも、こんな道程があったので、裕次郎は、博教にさりげなく注意したのだった。
京王線に乗ると、博教は、早速明日の撮影で喋る台詞を暗記する為にシナリオを開いた。
『雲に向って起つ』は「週刊明星」に連載された、慎太郎氏の小説だとは識っていたが、チラリとも読んだ事がなかった。
翌日、裕次郎に言われた通り、駅前で待っていた日活のバスに乗り、その日から日活撮影所には、連続十入日ほど通った。
しかし、博教が閉口したのは、朝九時に撮影所に入っても一日撮影がなかった事だった。
時には十時間も待たされ、二~三時間の時間待ちは常識らしい。
タバコもトランプ遊びもせず、当時は読書に耽溺していなかったので、博教には自分の出番を待つ間の時間をとても長く感じていた。
そんな或る日、撮影が終った博教を、裕次郎が誘った。
ゴールデン・ウイークに封切られる予定の『雲に向って起つ』を、テレビの「ロッテ・スター・アルバム」が紹介することになり、その録画取りに一緒に行こうと言ってくれたのだ。
その日に限って、博教の中学生の妹、圭子が撮影を見物に来ていたので断ると、妹にも録画取りを見物させればいいと言うので連れていく事にした。
博教と裕次郎とは撮影所からタクシーで有楽町駅前の、そごうデパートの五階にある、読売ホールに行った。
三国一郎氏の司会で、裕次郎は『俺は待ってるぜ』と『五木の子守唄』を唄った。唄の間に、原作者の石原慎太郎、共演者の水谷良重、浅丘ルリ子、山内賢、らとヨットや映画について話をした。
録画の終る一分ほど前、舞台の上の裕次郎と客席の一番前にいた博教の目が合った。その瞬間、
「……それに、立教大学の学生百瀬博教君が僕と大喧嘩して、僕が投げ飛ばされちまうってシーンもあります。とにかく面白い映画ですから、皆さん是非見に来て下さい……」
と無名の博教のことを紹介してくれた。
圭子と二人で控え室に行った。
控室のなかでは、石原兄弟が話をしていた。
博教は、この日、初めて裕次郎から慎太郎氏を紹介してもらった。
石原兄弟と博教と圭子の四人でエレべ-ターに乗った。
五階から一階に降りるまでの間に慎太郎が妹に「兄さんみたいに太っちゃ駄目だよ」と言った。
「慎太郎さんは何時会っても俺の風体をからかうんだよね。彼はハンサムでスマートで頭もイイ。若くして大出世してる、だから他人にジョークで言いたくなるんだろうね。年長者に言われると俺も何も返せないけど、そういうのがユーモアに聞こえない人もいるでしょ。
そういう機微がちゃんとわかるようにならないと政治家としては太成できませんよ。そういうところが裕次郎と大違いでね、俺がもし年上だったら注意したいところなんですよ。今は平気で言っちゃうけどね。
博教は『雲に向かって起つ』の巨漢ぶりが認められて、正月映画の舛田利雄監督『花と竜』にも出ることになった。
出演交渉は「裕ちゃんが喧嘩して負ける巨漢の沖仲仕の役をやってほしいんだけど、承知してくれないかな」の一言。
博教はためらいもなく承知して、約束の日、ロケ地に出発する裕次郎の待つ羽田空港の乗客待合いロビーヘ行った。
「行くぞ、博坊」
裕次郎の後に随いて歩き、日本航空の旅客機に乗った。
いきなり九州まで飛ぶのかと思っていたが、向かう先は大阪らしい。
そこから京都へ行くそうだ。
飛行機の恐さも忘れて喜んでいると、先刻から隣の席で星新一の『ボッコちゃん』を読んでいた裕次部氏が、クックックッと本当におかしそうに笑った。
「何がそんなに面白いんですか」
「何がって、ラストのところが面白かったんだよ。これはショート・ショートって小説だからとても短いんだ。聞いてろ、読んでやるからさ」
そう言うと裕次邸氏は『ボッコちゃん』を朗読してくれた。
そんなことをしている中に、旅客機は大阪空港上空に来てしまった。
目の下に広がる大阪の街はすでに夜で、家々やビルからもれる灯が光って見えて美しかった。
「この飛行機、車輪が出んのと違うか……」
後ろの席から同行の役者が裕次郎の元へやって来た。
「先刻から同じところぐるぐる廻ってて、中々降りまへんのや。きっと車輪が出ないんじゃないかと思います。ほら変な音が聞こえてくるでしょう。こうやって燃料を失くして胴体着陸するんやないかな」
それでなくても臆病な博教は生きたここちがしなくなった。
「胴体着陸、上等じゃないの」裕次郎は顔色一つ変えず平然として言った。
旅客機の車輪が滑走路に接触して少し跳ね上った。
そして、旅客機が完璧に地面を滑って次々と誘導灯を後ろにふっとばして行き無事着いた時、博教は柏手した。
それは巨人軍選手団がベロビーチヘ冬の合宿で飛んだ時、無事着陸の際どこからか拍手が起こりそれが波のように広がったと新聞で読んだのを覚えていたからだった。
しかし、あんなに優しく付き合いのいい裕次郎が、そのときは全く同調してくれなかった。手を叩いた客は博教一人っきりだった。
「花と竜」の撮影で、博教がスタジオに入って行って監督に挨拶しようと、セットの家の汚い廊下に、靴下が汚れちゃうと思って靴のまま上がると、『なんで靴履いてんだ』って誰かが怒鳴った。
博教は反射的に「なんだこの野郎」と怒鳴り返した。
裕次郎は博教に向って、
『お前ね、ここに来たらどんなに汚なくってもこれからは靴脱げよ』
と厳しく言った。
確かに、裕次郎の言うとおり、向うにすれば自分達が夜業して造ったセットの上に、土足で上がって来た野郎は許せねぇって感じだったのだろう。
この年、五月に封切られた『雲に向かって起つ』(石原慎太郎原作、監督滝沢英輔)、十二月に封切られた『花と竜』(火野葦平原作、監督舛田利雄)の中に博教の顔が登場する。
台詞も多い、準主役級の役どころだった。
しかし、二本の映画撮影を体験して、博教は自分はこういう世界は向いてない、俳優には適正がないと痛感した。
朝から撮影所に入って一日中待たされ、その揚句の果てに『本日撮影なし』と言われたらやってられなかった。
初めの頃は、銀座や新宿の通りのセットを見たり、食堂でカレーライスを食べたり、釣りが大好きだった和泉雅子を眺めたりして愉しかったが、あとは退屈過ぎた。
撮影所の、先輩・後輩、徒弟制度のしきたりが色濃く残る体質も、博教には我慢できないことになるだろうと予見した。
「映画に出たのは、この2本だけだな。2本とも喧嘩シーンで裕次郎と絡むんだけど、二つとも喧嘩に勝つ役柄だったんだ。例え映画のなかでも俺は負ける役が許せなかったんだよ。3本目に、初めて裕次郎の口利きでなく「高知喧嘩軍鶏」の出演依頼の声が掛かかたんだけど、これは役柄が宍戸錠に喧嘩に負ける役だったの。なんで俺が宍戸錠にやられるんだよ。やんねぇよ!そんなの!」
撮影所の空気を吸った博教だが、裕次郎のボディガードの仕事は、映画のようなお芝居ではなかった。
ある日「ホテル・ニュージャパン」六七八号室へ日活演技課の坂本正から「裕ちゃんに電話してほしい」との電話があった。
坂本に教わった番号をダイヤルすると半月以上お目に掛っていない石原裕次郎が出た。
「ひろ坊、お前に頼みたいことがある。昨日の日曜日、ニュー・ラテン・クォーターへ行ったんだ。トイレの入口の所で『サインをくれ』っていう二人に会った。ものを頼むような態度じゃないので、そのままトイレに入って出て来ると、『よう、俺達にはサイン出来ないのかよ』、みたいにからんで来た。ボーイに『ひろ坊は』って言ったら、お休みですってことだ。『なんだ、そのひろ坊って』って言うんで、この店の用心棒やってる百瀬のことだと返事すると『おう、上等じゃねえか。そいつを呼んでもらおうじゃねえか』ってことになった。でもお前はいないし、さんざん悪態をつかれた。あんな奴が店に来るんじゃ俺ばかりでなく他の客だって安心して酒が飲めない。銀座で森山敏男って聞けばすぐ判るって意気がってた。お前そいつ等に会って、二度と店に来ないようにしろ。『百瀬上等呼んで来い』じゃみっともないぞ」
裕次郎の言う通りだった。
博教はその場面を見ていないので詳しい事情はよく判らなかったが、裕ちゃんはかなり悔しい思いをしたらしい。
森山敏男の名は一度も聞いたことはなかったが、当時銀座で売り出し中の小林楠扶親分の身内だろうと思った。
しかし、小林事務所に電話して森山について尋ねればことは大きくなる。
後からわかったことだが、森山は住吉一家大幹部のボディー・ガードで、ピストル乱射事件となった浅草妙清寺事件にも関与して、長い務めをしたこともある。
その夜、裕次郎に目茶苦茶悔しい思いをさせた森山を探す為、新橋に住む川村知男(後に生井一家総長)に会いに行った。
川村氏は日本国粋会の会長森田政治の懐刀。森田氏が一番気に入っていた乾分が、気合充分の川村氏だった。
喧嘩三昧の少年時代に受けた斬り傷が顔にいくつもあるが、ヤクザとしては上品な物腰の男である。
森山の居場所は川村氏の事務所を訪ねれば判るはずだが、あいにく川村氏が留守である。
そこで、川村氏がいつも居ると聞いていた「ラバン」を探したが、いくら探しても判らなかった。
目の前の酒場に入って、バーテンに、ラバンを尋ねると、カウンターに坐っていたがっちりとした躰の客が振り返って、その場所を教えてくれた。感じのいい男で、とても判りやすい地図まで書いてくれた。
地下に続く階段を降りてラバンに入った。川村氏はいなかったが、事情を聞いたマスターがすぐ電話して川村氏を呼んでくれた。わけを話すと、
「森山ならよく知ってるよ。今、若いもんに探させる」
十五分と待たずに森山が見つかった。
森山が待っているという鳥森の小さなホテルに川村氏と行った。三階のホテルのドアを開けてびっくりした。先刻親切にラバンを教えてくれた男だったからだ。
「俺に裕次郎の件でなんか話があるそうだが、喧嘩ならいつでも買ってやるぜ」
「おい、森山。話もしねえうちにそう強がったんじゃ、話ができねえよ。博ちゃんはうちの会長の大先輩の実子なんだから、俺がいくらお前といい仲だっていっても、判らないこというんなら相手になってもいいぜ」
「森山さんだったんですか。初めまして。百瀬です。ラバン教えてくれて有難うごぎいました。先日、石原の方にも失礼があったと思いますが、これからは何処で会っても裕次郎には触らないでやって下さい。それを言いに来たんです。つまんない者ですが、私が裕次郎の用心棒をしています。お見知りおき下さい」
「いいなあ、石原裕次郎の用心棒なんて。この前だって、俺の知り合いの女の子にやろうと思ってサイン頼もうとしたんだ。俺が声掛けたらプイと横向いたんで、何でえこの野邸、お高くとまりやがってって怒鳴っちまったんだ。裕次郎からは毎月すごい金が届くんだろうね」
「いいえ、一銭も貰ってません」
「そうなんだ。兄弟、俺このひと気に入っちまったぜ。これからいい付き合いしよう」と森山に言われた。
博教が予想しえない展開だった。
裕次郎から「森山に会ってこい」と命じられた時、天にも昇るほど嬉しかった。
惚れた裕次郎の為に戦うことが出来るのだから男としてこんな倖せはない。
しかし、口の利き方を一つ間違えば大喧嘩となるに決まっていた男から、こんなに早く認められたことも嬉しかった。
川村氏、森山氏、両人に深々と頭を下げてホテルを出た博教は、「俺の黒船で、俺を夢中にさせる石原裕次郎を命懸けで守ろう」
と改めて誓った。
喧嘩にはならなかったが、その後、森山氏には3度擦れ違った。
一度目は新橋で会った二ヵ月ぐらい後、六本木の交差点に立っている時、車の中から「オーイ」と声を掛け、走って行った。
二度目はそれから二十年後だった。
博教が四十三歳の時、六本木のレコード店の中でバッタリ遭遇した。
「久し振りだねえ」と言ってから近くの中華料理店に誘ってくれたが、
人と会う約束があるので断わると、手に持っていた菓子を風呂敷ごとくれた。随分前に組を辞めて今は不動産業をしていると言った。
三度目は「ニュー・ラテン・クォーター」が閉店する一年ほど前、フロントに案内されていつもの席に坐ろうとすると、フロアで森山氏がジルバを踊っているのが見えた。
氏が席に戻ったところへ顔を出し、数年前の菓子の礼を言った。
挨拶が終ってダンスをしていると、森山氏の席が騒がしい。ダンスをやめて係のウェイターに事情を聞くと、先刻森山氏とジルバを上手に踊っていたホステスが指名の客の席に行ってしまい、他のホステスはジルバが全く踊れないので先刻の女を戻せと言っているらしい。
博教は二十年も前、二十四歳の時に、この店の用心棒は卒業していたが、
「森山さん、ちょっと待ってやって下さい。ジルバの上手い女すぐに来るよう言っておきましたから……」
「有難う。おい、お前達、こちらの親分が口を利いてくれたんで許すけど、人見て商売するようなやり方は承知しないぞ」
<親分が口を利いてくれたんで許す>
その言葉を聴いて、博教はなんて甘美な言葉なんだろうと思った。
<不良達はこの甘美さを味わう為に、辛い渡世の修業をするのだ>
と博教は思った。
「この話は『まちがっていない』って漫画にもなっているけど、俺も好きな話でね。人を探して、見たことないから、尋ねた相手にもう一度戻ってくるって、まぁ全部実話なんだよ。稼業にはそれぞれの言葉があると思うけど、『親分』なんて呼ばれまで、この道でどれほどの修行を積むのか、俺なんかは、こういう言葉でぶっ飛ぶんですよ」
裕次郎は「私設用心棒」としての博教の腕っ節を試すような挑発的なことも言った。
お店では、頻繁にお目当てのホステスを巡って揉め事もあった。
西条慶子という名のナット・キングコールに上手いって褒められたことのある美人の歌手がいた。
この娘に福田農林大臣の息子と樽橋運輸大臣の息子が、同時に惚れて恋の鞘当から喧嘩になった。
福田は樽橋に勝てないと思って、住吉連合の阿部重作という大親分のところの村田という不良に応援を頼んだ。
その夜は、たまたま裕次郎と、そのマネージャー的立場にあった日活演技課の坂本正が店に遊びに来ていた。
丁度、福田と樽橋が店でぶつかって喧嘩になった。
福田が殴られたと同時に、福田の用心棒、村田以下、七、八人が樽橋を店の外に連れだそうとした。
「モモちゃん、大変。早く樽橋さんの所に行ってあげて」
ママの山本浅子が博教の所に飛んで来た。
博教は「やめろ!」と一喝して樽橋が店の外へ引っぱり出されようとしている人込みの中に飛び込んだ。
さらに「静かにしてくれ』と言うと、村田は博教を樽橋の味方と勘違いして「何だこの野郎!』と言った。
村田は23歳の博教よりかなり年上だったが、形(なり)が小柄だったので博教も『何だこの小僧』と返した。
村田も子分達の前でナメた口利かれて頭に血が上り、村田とその若い衆が博教にかかって来た。
大乱闘の殴り合いになった。
若い衆の一人は階段の上から走って来て、飛び蹴りで博教の顔を蹴ろうとした。
多勢に無勢で、形勢は不利であった。
そのときに階段から降りて来た客が、博教が旧知の浅草橋の駅前におもちゃ屋の旦那であった。
その人が向こうの親分を知っていたので仲介され、博教は命拾いした。
「待ってくれ。実はこの人は柳橋の百瀬さんの息子で、ウチで流しの用心棒でやってる」って言って喧嘩を止めた。
(客で来ていた四谷の顔役が割って入ってくれて喧嘩は納まった)
一部始終を見ていた坂本の口から、
「祐ちゃんが心配しているから、こっちへ顔を出して……。博坊は喧嘩が弱いって裕ちゃんが言ってるよ」
と言われた時は、博教はさすがにショックを受けた。
裕次郎の席に行くと、
「ヒロ妨、喧嘩はもっと落ち着いてやれ。何かあれば、骨は俺が拾ってやる」と言った。
「いつ短刀に刺されてるかもしれないから俺の顔は、緊張と恐怖でひきつっていたんだろうね。それを目撃した豪胆な裕次郎は普通の人なら、ヤクザとの喧嘩と聞いただけで青くなるのに『弱い俺の姿』に心底がっかりしたのだと思うよ。あにきは俺にもっと強くあって欲しかったんだよ。そのときに嬉しかったのが、それから数日して小林楠扶さんが俺のとこに来たんだよ。それで、『こないだウチの者と喧嘩になったらしいけど、メチャクチャ強かったってねー』って言ってくれたのよ。それから俺は小林さんが大好きになったよ」
そして、博教に決定的な出来事が起こった。
大学相撲部に二年近くいたので、その経験が大いに役に立ち、百キロある少しくらいの腕自慢ともめても、一、二発の突っ張りで二、三メートル先にふっとばしていた。
一夜、店で博教に小柄な奴がからんで来た。
酔ってはいるがその風体は一目で筋の者と判った。
出来るだけ音無しく外に出そうとして、真紅の絨毯を敷いた長い階段が酔った男の背を抱えながら上った。
店を出るや酔漢は博教の横腹に拳銃を押しつけた。
〈拳銃……〉
生まれて初めての経験だったから、恐ろしくて全身の血が凍りつき、体がちぢみ上がった。
運よく撃たれはしなかったが、粋がり放題粋がっていた博教に、この小事件は冷水を浴びせてくれた。
父から預かった拳銃は持っていたが、敵に対抗するには、もっと高性能な拳銃が必要だ、と、この夜から思った──。
拳銃への希求は博教を海外へ、そして暗闇にまで跳ばすことになる。
サポートありがとうございます。 執筆活動の糧にして頑張ります!
