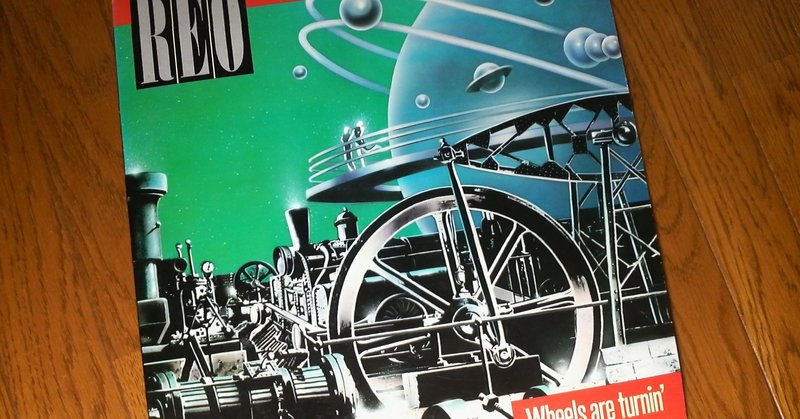
第8回六枚道場(後半)
「THE REAL END OF EVANGELION」小林猫太
作中のKがエヴァンゲリオンなのでカヲル君なのは理解していながらも伊予さんの「Kの脱糞」が頭によぎってしまって、あ、こいつも脱糞するのかと思ってしまいました。
それはさておき、僕がエヴァンゲリオンを見たのは遥か昔、そもそもエヴァンゲリオンそのものがもう四半世紀近く昔の物語なので細かな部分は忘れてしまっていますが、それでもエヴァだよなあと感じさせてくれるので、1.5次創作を言われるだけありますね。
となるとこの物語がどこに着地するのか、そもそもエヴァを題材として納得させることができるのかという部分に焦点があたるわけですが、そこはやられたなあと。エヴァ抜きにしてもよかったんじゃないかと思うくらいの着地のさせ方だと思いました。だってそうじゃないですか、主人公に世界を救うか滅ぼすかの決断をああいった形でさせるなんて。
「ハリー・ライムのテーマ」ケイシア・ナカザワ
お、今回は犯罪小説か。と初っ端からワクワクさせてくれました。もう、文章も語り口も文句なしの安定した流れで、しかも犯罪小説。
なのですが、個人的にはこのまま突き進んでいってほしかったのですが、途中から雲行きがあやしくなってしまいました。これはほんとにもう、好みの問題になってしまうのですが、センテンス・スプリングには登場してもらいたくなかったですね。ちょっとそのあたりが風刺あるいはギャグに走ってしまって、もちろんそういう話が書きたかったということもわかるのですが、ついついケイシアさんには正統派の物語を期待してしまうのです。
「サモンズ☆ドア」夏川大空
いきなりちょっと毛色の変わった、でもWEB小説としては全然変わってもなくむしろ最大派閥できなジャンルを書いてきました。なろう系といえばいいのでしょうか。それとも異世界転生……は転生していないので違いますね。
でもファンタジー系の世界とつなぐ扉が開いてそして元の状態に戻すために異世界の冒険をする。この系統の物語だと平気で10万文字くらいの作品がごろごろとあるなかで、それを六枚道場でやってしまおうという、そしてやってしまったのはすごいですね。でもさすがにエッセンスは残っているけれども、それ以上は難しかったとみえて、夏川さんだったらこの題材でも突き抜けるものを持ってきてくれるんじゃないかと期待はあったものの、正統派で進んでいった部分がちょっと僕とは好みが合いませんでした。
「過去に溺れる」澪標あわい
またしても澪標さんと同じグループになってしまって、しかも今回の僕の作品はあれですから、いや澪標さんに限らず同じグループになってしまった方には申し訳ないという気持ちがあります。
が、そもそも拙作と比較するほうがおかしいわけで、相手がだれであろうとも澪標さんの作品は揺るぐことがありません。
「年齢以上に住む場所が離れている」とか、いいなあという表現を抜き出そうとするとほぼ文章全部になりそうで、Gグループに関していえばこれはもう澪標さんに投票すればいいから楽だなあ。と思ったのですが、ちょっとだけ引っかかりました。
それは主人公が直線が怖いという部分と、それはそれで構わないのですが、それと対比するかたちで登場する蛾の存在。この蛾は作中では一直線に命を燃やす存在として描かれ、でもラストで主人公に命の火を消されます。ここで主人公が蛾を殺す理由が一直線の存在だったから、であれば納得できるのですが、主人公はこの蛾に老いを見出し、見るに見かねて殺してしまいます。
そこがちょっとだけ引っかかりました。
「ブーツを食べた男と冷たい人魚」吉美駿一郎
飢えから靴を食べるというと『チャップリンの黄金狂時代』を思い出します。あの映画を見て僕は昔の靴は食べることができたんだ。と思ったわけですが、残念なことに現代ではそんな知識など役に立つ機会がまったくありません。
吉美さんのこの物語ではブーツを食べた男の物語がどこに向かっていくのかというと、これがさっぱりと要領を得ません。いやどこに連れて行かれるのか予想もつかないといったほうが正しいわけですがそれもそのはず、主人公は漂流してどこともわからぬ場所にたどり着くわけですから。そんな読んでいて不安定な展開が何故か心地よいのは次々と繰り出されるエピソードが強靭だからだと思います。だって読んでいて突然カントの「実践理性批判」なんて言葉が登場したらどう受け止めれば良いのか不安になるでしょう。ブーツを食べた男と人魚が登場する話の中で。でもそこで破綻などせずにズンズンと突き進んでいってそして種族としての滅びとそれとは全く異なる形での愛を描いて終わるのです。
ちょっとだけ気になったのは日本で人魚というと不老不死という部分に結びつくのですがこの物語は日本人はおろか日本も登場せず、いわば西洋の話です。西洋の人魚も不老不死のような要素があるのかな。その部分がちょっとだけ気になったのですが、しかし見方を少し変えると、この物語そのものも洋と和が混在しているような雰囲気もあって、そう考えると、なんですか、この密度の高い話は。
「二週間目の暗黒固茹で卵」Takeman
自作解説です。
前回の六枚道場で印象に残った作品の一つに化野夕陽さんの「ヨコバイの物語」がありました。
この作品は作中で経過する時間が短く、おそらく三十分程度の時間だとおもいます。
そこで僕も作中での経過時間の短い話を書いてみたいなとおもいました。そこから少し発展して、六枚の原稿用紙を読むのにかかる時間と作中の経過時間が一致している、過去において筒井康隆が『虚人たち』でやってみせたようなことをやってみたいなと思ったわけです。もっとも、作中の経過時間と読む時間を一致させたところでなにか得るものが、あるいは面白い読書体験をすることができるのかといえば、原稿用紙六枚程度では無理です。まあ、一致させるかどうかは別として、経過時間の短い話を書きたいなと思ったわけです。
ということで経過時間の短い話ですので物語性は排除して、キャラクターの会話のキャッチボール的な感じになるかなと考えながら、深い意味などまったくない純粋な娯楽作品を目指して作りました。下手に書くと裏読みされる可能性もあるので徹底的に無意味であることを心がけました。
で、最後に性別不明となるように細部を整えてできあがりました。
名前の後ろに(源氏名)とつけてあるのはそのためです。つまり本名ではありません。しかも女性名だからといって当人が女性とも限りません。恋人もそうです。どちらでも成立するように書いてありますので、お好きな組み合わせでイメージしながら読んでみてください。
これはシスターフッドの話として読まれたくないなというのがその理由で、僕の書く世界ではシスターフッドや百合あるいはLGBTQなんて言葉は存在しない、そういったものは僕の世界では当たり前のように存在していてだから特別な言葉など必要ないのです。という決意表明みたいなものです。登場人物たちは僕の世界では何一つ特別ではない普通の人なのです。
で、最後にですが、この物語はこの後が面白くなるだろうと言ってくださる方がいましたが、作者としてはこの後は面白くなりません。登場人物はこの直後に無残に殺されます。虫けらのように。だってノワールなんですからそうでなければいけません。
「カミツキ」ミガキ
これってちょっと完璧じゃないですか。
原稿用紙六枚という分量の中で謎があって魅力的な解明があって、さらに小さなエピソードの中にもひねりがあって、カミツキという言葉に多重の意味を重ね合わせて、もう僕好みの構成です。
まともに描くならばそれだけで紙面をついやしてしまう作中の病気もうまいこと既存の現象とつなげて、説明を分散させて省略させているし、ちょっと技を盗みたくなるんですが、多分僕にはこういう話を書くのは無理なのであきらめます。
愛とは何だろうと始まる冒頭から、そう言いながらもお前、彼女のことを愛してるじゃないか、と思わせる中盤、でも最後になってもう一捻りさせてくる。やっぱり完璧だ。
「桜の咲く頃に」白水縁
原稿用紙六枚をフルに使わず挑んできました。過去にも今村さんがそんな感じで少ない分量の話を書かれているのですが、僕には無理なのでそれだけで敬意をはらいたくなります。
物語の時代背景としてはどのくらいなのでしょうか。僕は昭和あたりをイメージしました。路上生活者という言葉を使っているところなど、言葉使いが優しく、好感が持てるのですが、一方でやはり分量が少ないせいで、主人公の気持ちの変化、生きることを諦めて他の人間に託すという部分に説得力が薄く感じられました。
「王国の母」紙文
紙文さんも今回はtwitter上でいろいろと前哨戦を繰り広げられていて読む前からあれこれ想像をしていたけれども、全く外れました。
王子という名前の少年が登場して、そして彼は天使だという。天使が何かの比喩なのかそれとも実質的な天使なのかというと実質的な天使で彼に王子などという名前がつけられている時点でその設定に説得力をもたらしているあたりがうまいなあ。僕ももう少し登場人物の名前に神経を使いたいと思いました。
主人公は女の子でタイトルが王国の母。だからこの物語は天使である彼ではなく母となる彼女の物語であるはずで、だからその視点でみると、主人公は天使を堕落させる悪魔のように思える。多分、天使である王子君はまだ堕落しておらず、でも彼女の誘いに乗って子供を作った時点で堕落して、じゃあ彼女は何をしようとしているのかというと、そこまでは読み取ることができないのだけれども王国の母である以上、この先に訪れるのは悪魔によって統治された王国=世界なのだろう。
そんなふうに誤読しました。
「小市民」閏現人
異性をどう描くかというのはいつも悩んでいて、こういう表現をしたらハラスメントにならないか、あるいは差別的にならないか、とかそういったことを考えます。もっとも考えたからといってうまくいっているのかといえば定かではないのですが。本作を読んで気になったのは主人公の容姿に触れている部分でした。ここで主人公に名前が与えられていたとしたらまた違って見えたのでしょうが、名前を与えられない主人公の描写においてそういった描写の部分が必要だったのか。その部分が気になります。
とはいえど、主人公に名前が与えられていたら面白くなるのかといえばそうでもなく、実際、後半の展開では面白さが加速して、名もなき彼女であるから面白いのだ、そう思いなおしました。
「無色透明の◯◯」大道寺 轟天
情報というものに対する考察が延々と続きます。もちろん冒頭でその考察をする私という存在いついて語られてしかもその私が少しエキセントリック、まではいきませんがちょっと変わった人物として描かれて、じゃあそんな私が情報についてなにを考え、どんな場所に到達するのか。
その部分は僕にとって興味深く、これってグレッグ・イーガンやテッド・チャンの領域にいくんじゃないか、今度はSFなのかと思ったのですが、そういったところには向かいませんでした。もちろんそれが残念だったというわけではなく。むしろそこから先はお前が考えろと言われた面もあって、ちょっと考えてみたい題材をいただきました。ありがとうございます。
しかしそこからこの物語、いや主人公の考察がどこに向かっていくのかというとちょっと不穏な場所で、それは○○と伏せ字になっているので定かではないのですが、まっさきに思いつくのは遺書で、○○○は主人公が最後に食べた食べ物の名前で、私と誠の間に何が起こったのかははっきりとわかるのに、そこだけが滲んで曖昧になっているのは作者の慈悲なのかもしれません。そんなふうに思いました。
「ナイトビリーバー」深澤うろこ
田中非凡さんが「ささやかな祝祭」で26人の登場人物を登場させて視点をそれぞれ変化させていくということを行っていて、今回は深澤うろこさんが似たようなことをやられました。深澤うろこさんの場合は登場人物をもっと減らして登場人物の存在をわかりやすく、詳しく描写していって、技術的にはこちらのほうが難しそうだなあと思いました。多人数で視点人物を変化させるということは僕もやったことがありますが、でもその場合は章を変えてなので、本作のように流れるように変化させることではありません。少し気を抜くと何がどうなっているのか混乱してしまいそうな気もするのですがそれは僕が書いたとしたらの場合で、本作ではそんなことはありません。でもこういう面白い試みは一度はやってみたくなりますね。
ひとつだけ気になったのは蒲田さんが目を真っ赤に腫らしているのを梶間青年がどうして知っているのかという点でした。
「海外短編文学全集異世界篇より『受動的3秒間』」今村広樹
相変わらず攻めている今村さんですが、まさかの三部作、って勝手に僕が思っていただけですが、その続きがあるとは思ってもいませんでした。まだまだ続くのですね。
今回の肝は作者紹介ということでああ、それもあったか。と膝を打ちました。
今回も秋月国が登場して少しだけ秋月国のディティールが追加されていくのですが、最後にどんな世界を見せてくれるのか気になります。
つたない文章をお読みいただき、ありがとうございます。 スキを付けてもらうと一週間は戦えます。フォローしていただけると一ヶ月は戦えそうです。 コメントしていただくとそれが酷評であっても一年ぐらいはがんばれそうです。
