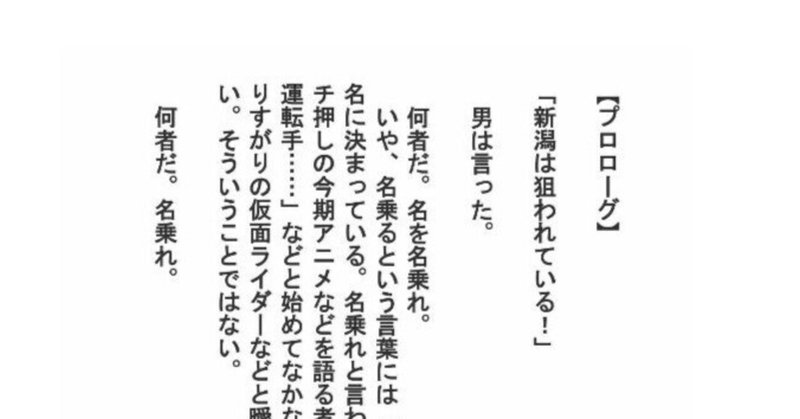
有限会社新潟防衛軍~小林猫太試論~
完成手前稿、電書初版、電書二版、紙版と4種類のバージョンを読んだ。決定稿としては電書版となるだろうが、電書版と紙版の違いは誤植の訂正程度なので大きく違うわけではない……と言いたいところなのだが、じつは大きく違う。僕が読んだ完成手前稿には大きなミスがありそれは作者のミスというよりは、ルビを振った部分が削除されてしまうというMS-WORDの挙動のせいで、ところどころ本来あった単語が消えてしまっているバージョンだった。読んでいてどうしてこんなにたくさんのミスがあるのだろうと疑問に思ったのだが、後で作者のツイートでそれがWORDの挙動のせいだと知り疑問は解決した。電書版ではきれいにルビが振られており、完成手前稿で気が付いた部分や気が付かなかった部分の文章が意味の通る形となっている。一方で紙版はというとルビは一切振られていない。製本上の制約があったのかルビのない理由はわからないのだが、このルビのありなしというのは小林猫太の作品においては重要な役割をもっている。小林猫太はルビを振る男なのだ。どうしてこんな文字にまでルビをふるのだろうとおもうこともある。それはまるで、お前はこの文字を読むこともできないのだろう、だからルビを振っておいてやろう。などという上から目線なのか、そのくらい読めるわとちょっぴり思ってしまい、突っ込みも入れたくなる気持ちもないこともないのだが、小林猫太がルビを振るのは読者へのサービス精神の現れというよりも、自分の文章へのこだわりだ。読み手がその漢字の読み方を知っているかどうかではなく、知らなかった場合にそこで読みのテンポが崩れてしまうことが我慢ならないのだろう。だからテンポが崩れそうな漢字に対してルビを振る。そうでなければ高橋に「たかはし」とルビを振るわけがない。人名にはほぼ必ずルビが振られている。
そういったこだわりはルビ以外にも見受けられる。電書、紙版とでの一頁当たりの文字数が違うのだ。紙版では一頁17行×39文字。電書初版では15行×32文字、そして電書二版ではなんと10行×32文字。電子書籍の場合、特に小説の場合はリフロー型と呼ばれる、文字の大きさを自由に変えられることによって一頁あたりの文字数も変化する形式が主流で、小林猫太の過去二作品もこのリフロー型なのだが本作は文字の一頁あたりの文字数が固定のフィックス型なのだ。一頁あたりの文字数の最適解を追求しようとしているとしか思えない。
そんな小林猫太のゆるぎない力強さはどこからくるのだろうか。
本作でも一頁目からすでに、付いてこれるものだけ俺に付いてこいといわんばかりの文章を全力で叩きつけてくる。
「新潟は狙われている!」という文章から始まる物語で、「イチ押しの今期アニメ」と「「ある時は謎の運転手……」などと始めてなかなか名前にたどり着かない探偵」などという言葉を登場させるのは冷静に考えてどこかおかしいだろうとおもう。「イチ押しの今期アニメ」が平成・令和の言葉ならば「ある時は謎の運転手……」は昭和の時代の言葉だ。振り幅が広すぎる。
そもそも冒頭のプロローグの前半は新潟県知事、猪狩玄太郎が見ている夢の話で、そして猪狩玄太郎自身がその夢に突っ込みを入れているのだ。見ている本人が突っ込みを入れている夢をどうやって読者は真実であると受け入れることができるのであろうか。
しかし、いったい我々は何を読まされているのか、この作者は何を言おうとしているのか、と戸惑いながらもそこで読むのを止めずにすんだ者はすでに小林猫太の魔術的な語りに翻弄されてしまっている。そして小林猫太は自分に付いて来たものに対しては決して裏切らない。
たしかに突っ込みどころはたくさんある。それは作中で登場人物達がひたすらお互いの言動や行動に突っ込んでいるのと同じくらいにだ。
例えば、バッドメンの黒装束の5人が乗っていた白いワンボックスカーは襲撃現場に残されたままであり、白いワンボックスカーは誰の所有者なのか、それともレンタカーなのか。だとしたら借主は誰か。そこからかなりの手掛かりが得られるであろうはずなのだが作中では一切語られることはない。気が付かないのか、作者自身からも忘れ去られてしまっているのか、作中でも語られるように警察は白いワンボックスカーの捜査もふくめて襲撃事件の捜査に一切乗り出そうとはしない。その理由は襲撃者たちの正体が明かされたときに判明する。それは警察に対しても影響力のある人物がいたからで、それを考えると、防衛軍基地である猪狩宅の襲撃も、そんな大人数で襲撃すれば近所から通報される恐れがあるじゃないか、手加減をするといっても暴力行為をするのだ。そんな危険を犯す勇気はどこにあるのだという疑問もある程度は氷解する。もっとも猪狩宅がある場所は国道沿いという設定なので近所に住宅があるのかどうかは定かではないのだが。
木を隠すなら森の中という言葉がある。荒唐無稽な話であるのなら、荒唐無稽なネタの中に隠せばいい。そんなことを体現するかのように、有象無象のギャグをちりばめて、それでも読者に見抜かれそうなときには登場人物の口から「これさえも詭弁なのだ」というセリフを言わせてまでもごまかそうとする。いや、これが小林猫太の魔術的な語りなのだ。読者が疑問を抱こうとする直前、阿吽の呼吸でもって読者の感情を先読みし読者の代弁者として文章をたたきつける。
そうして物語は読者が期待する方向へと突き進んでいく。読者に要らぬ疑問を抱かせないため、そしてなによりも、ここまでついてきてくれた読者のために、これ以上ない読後感を与えるためにだ。とくに本作でも小林猫太はそのリリカルさを発揮させる。イグの創始者とかお笑い担当とかサブカルとか特撮とかオタクネタ(しかもほぼ昭和限定)などとそういった部分に目が行きがちなのだが、そこに騙されてはいけない。たぶん作者本人も自分自身に騙されているのであろう。そろそろ自覚したほうがいいのではないかという気もしないでもないが小林猫太は最初からリリカルな要素を隠そうともせずに描いている。もっとも今回は今まで描かなかった親子という部分に焦点を当てたので初めてエモさを表に出したと勘違いしても仕方ないかもしれない。
猪狩の行動は脳腫瘍が原因だったのだろうか。彼の祖母は見える人だった。そして彼自身も見える人である。早くして亡くなった妻の姿が見えていたことを考えると、脳腫瘍だから見えたというのは考えにくい。確かに脳腫瘍で幻覚、幻聴を引き起こすことはあるが同時に理解力の低下も引き起こす。作中では防衛軍を作るという行為に全くの理由付けがないことを除けば猪狩の言動におかしな部分は見受けられない。エピローグで明らかになる夢のなかの謎の男の正体を考えればエディプスコンプレックスがその根底にあると考えたほうがよいのではないかと思う。無意識に憎み、そこにいない人としてあつかった彼の父親に対するコンプレックスが新潟県防衛軍を作らせたのだ。彼自身が認めようとしていないのだから新潟が狙われているという原因もわかるはずもない。
というわけでそろそろ小林猫太はテーマ的に次の段階へと進んでもいいのではないかと思う。特に有限会社新潟防衛軍はNPO法人新潟防衛軍として生まれ変わったことだし、さらには新メンバーも加入した。次回作ではこの新メンバーを主役としてもう一度、親子の確執というテーマに挑むべきではないだろうか。何しろ、新メンバーの父親は国家権力である警察でさえも黙らせることのできる権力者なのだ。
敵はまだいる。
新潟はまだ危うい。
つたない文章をお読みいただき、ありがとうございます。 スキを付けてもらうと一週間は戦えます。フォローしていただけると一ヶ月は戦えそうです。 コメントしていただくとそれが酷評であっても一年ぐらいはがんばれそうです。
