
裏方という名の主役 ~大場ななと舞台創造科~
カメタ
https://twitter.com/kmt9993
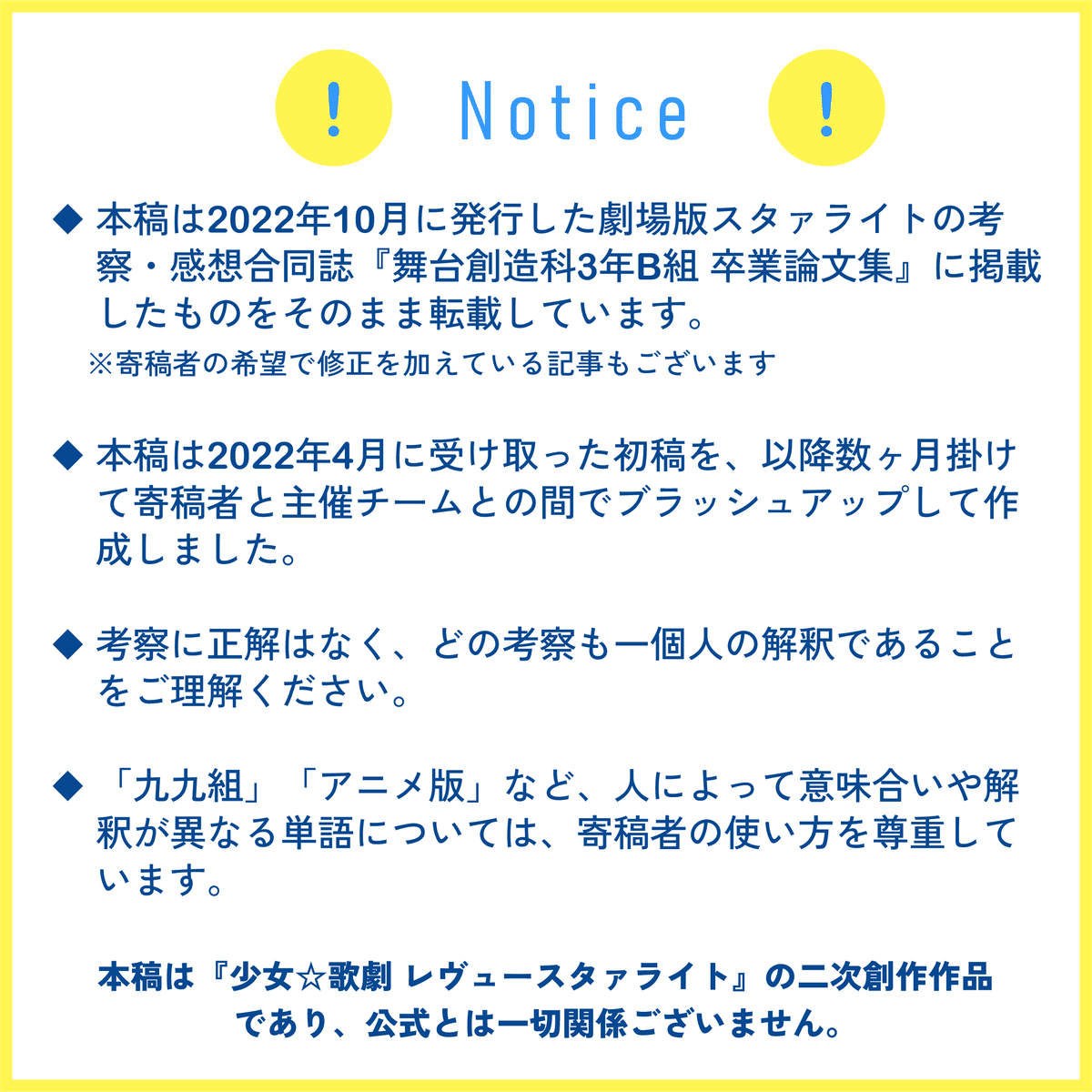
1.はじめに
『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下「スタァライト」)における大場ななという存在が視聴者に与える影響は、語彙を選ばずに言うと「マジでヤバい」のだ。
というわけで、論文とは思えないほどの出だしで1文目を始めてしまった私ことカメタ。「これ論文じゃなくてエッセイじゃね?」という印象で終わってしまうことは想像に難くないので、このページに至るまで数々の素晴らしい論文を読んできた読者様には、目を休めて頂くための小休止のようなお時間を提供させてほしい。まぁつまるところ、何かしら粗があっても見逃してほしいという訳だ。好き勝手に書かせていただくので、何卒ご容赦を。
2.大場ななの特異性
TVアニメシリーズ全12 話のなかで、大場ななに注目が集まったシーンを挙げるとすれば6話Cパートだろう。「スタァライト」において「再演」というタイムリープ概念が生まれるのはこの6話Cパートを皮切りに、7話以降。しかし、実は6話以前にも大場ななから「再演」というワードは発せられている。それが、1話の天堂真矢との談話室でのやり取りだ。
大場「へぇ~、再演するんだ!」
天堂「あのときの敵役が、今度の主役だそうです」
大場「ん~、私は――」
このやり取りはこの後、神楽ひかりを探す愛城華恋によって終わる訳だが、「再演」というワードが1話から出ているのが面白い。また「再演」に関する話題が「神楽ひかりを追いかける愛城華恋」によって遮られてしまう点も、後の展開の示唆ではないかと考えられる。さらに、天堂真矢と大場ななの会話のやり取りに注目すると、再演時の配役変更に関して、大場ななは反対意見を持っていることが予想できる。なんともニクい演出だ。
7話のタイトルが「大場なな」というのも、「スタァライト」における彼女の存在が如何に異質であるかを示している。だって主人公じゃないのに7話でタイトルになっちゃうし、なんならエンディングで歌唱すらしないのだ。当時リアタイ視聴していたカメタはテレビの故障を疑い、リモコンで音量を最大値まで上げ「歌ってくれよ大場! なぁ! 歌ってくれよ!」と狂ったようにテレビを揺さぶったと語る。
7話で最も衝撃を受けた場面は、大場ななが天堂真矢に何度も勝利し、キリンのオーディションにおいてトップスタァであり続けていたというところだ。泣く子も黙るアニメ3 話『誇りと驕り』の天堂真矢が、今まで全くといっていいほど舞台少女としての力量を見せてこなかった大場ななに負けるなど、誰が想像できただろうか。3話という、全12話のなかでも比較的序盤に、愛城華恋は天堂真矢に敗北しており、天堂真矢の舞台少女としての実力は7話より前の段階ではトップであると視聴者に強く印象付けられていた。そんなトップスタァ天堂真矢が文字通り「ずっと何度でも」大場ななに敗北していたというのだから驚きである。その事実が、大場ななの舞台少女としての実力を一気に未知数にした。
キリンが何度目か覚えていられないほどにタイムリープし続け、第99回聖翔祭の『戯曲 スタァライト』を求め続けた大場なな。その姿と執念は、この物語においてかなり異質だろう。大場ななの特異性は「舞台少女としての実力が未知数」であり、数えきれないほどの「タイムリープを行っている」という点にあると考える。
この2点を踏まえて、今度は我々と大場ななの関係性について言及していきたい。
3.大場ななと舞台創造科
そもそも「我々と大場なな」という括り方は表現として違和感があるだろう。アニメは2次元の世界だが、我々は3 次元の世界の住人だ。本当の意味で次元の違う我々と大場ななとの間に関係性など存在しそうもないが、面白いことに「スタァライト」においては、この関係性がカギとなるのである。
「スタァライト」は、舞台とアニメの二層展開式を謳っており、我々ファンのことを「舞台創造科」と呼ぶ面白いコンテンツだ。「スタァライトする」という謎の動詞が主人公の決め台詞として存在し、それを受け身の形にした「スタァライトされる」という表現は「スタァライトのファンになる=舞台創造科になる」という意味を持つ。これはつまり「スタァライトされた者」は「舞台創造科」という役を与えられる、と言い換えることもできるのではないだろうか。「スタァライト」の登場人物にも同じく「舞台創造科」、いわゆるB組の生徒(雨宮詩音や眞井霧子など) が存在している。彼女たちを指す「舞台創造科」と我々を指す「舞台創造科」は、言葉こそ同じだが意味するところは全く違うように思える。
だが、果たして本当に違うと言えるだろうか。
愛城「ここには演者も裏方もいない! 一人で舞台は創れないのに!」
この愛城華恋の台詞は「舞台を創るには演者と裏方(舞台創造科)の両方が必要である」と言い換えることができる。さらに、キリンの台詞に注目する。
キリン「舞台とは、演じる者と観る者が揃って成り立つもの。演者が立ち、観客が望む限り続くのです。そう、あなたが彼女たちを見守り続けてきたように」
ここで何が言いたいのかというと、B組の「舞台創造科」と我々ファンを指す「舞台創造科」は異なる存在でありながら、どちらも「舞台を創造するうえで欠かせない役割を担っている」という点では同じ存在なのである。前者は舞台を創造するために必要な「裏方」で、後者は舞台を成り立たせるために必要な「観客」というわけだ。
愛城「みんなをスタァライト、しちゃいます!」
この決め台詞も「みんなをスタァライト(という舞台の一部に)しちゃいます」という意味なのであれば、主人公の台詞として秀逸でしかないだろう。というか「観客」でありながら「舞台創造科」として舞台を成り立たせるための燃料にもなれちゃうのだ、私たち。キリンかな? にしてもちょっと怖いけどね、都市伝説みたいだね(?)
怖いついでに、もう一つ怖い話をしようと思う。エッセイだから許される所業なのである。
皆様はTVアニメ1話のこのシーンを覚えているだろうか。
大場「でも楽しかったなぁ、1年生のときのスタァライト」
これは、愛城華恋・露崎まひる・大場なな・星見純那の4人が、第100回聖翔祭の準備について話すシーンにおける、大場ななの台詞だ。
このシーンで、大場なな以外は第99回聖翔祭を「去年」と言っているのに対し、大場ななは「1年生のとき」と言っている。確かに、何度も再演しているであろう大場にとっては「去年」という表現を使うにはあまりに年月が経ちすぎているのかもしれない。だが、この台詞に注目してみると、面白いことが起こるのだ。
私がスタァライトされたのはTVアニメが始まった2018年夏。あの夏にスタァライトされ、舞台創造科となったファンも多いはずだ。もちろん、それ以前から追いかけていた舞台創造科の方々や、劇場版から沼に落ちた方々も多いだろう。それは重々承知の上で、ここではTV アニメが始まった2018年夏を始点とさせて話を展開させて頂くことで、私の感じた面白さを共有させてもらうこと、ご容赦願いたい。
あの夏にスタァライトされた舞台創造科として、私も“彼女”と同じくこの台詞を言うことができるのだ。
「楽しかったなあ、1年生のときのスタァライト」と。
どういうことか整理していこう。
いわば、夏の入学生。舞台創造科としての学年があるとすれば以下だ。
1年生: 2018年夏~2019年夏
2年生: 2019年夏~2020年夏
3年生: 2020年夏~2021年夏
これを踏まえて、舞台創造科が追いかけてきたコンテンツの動きに当てはめると以下になる。
1年生:『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』全12話放送
2年生:『劇場版再生産総集編「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」』公開
3年生:『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』公開
大場ななは「1年生のときのスタァライト(第99回聖翔祭)」を楽しかったと言い、舞台創造科は「1年生のときのスタァライト(TVアニメシリーズ全12話)」を楽しかったと評しているこの状況に加え、さらに面白いことが起こる。
大場ななは2年生時点で、第99回聖翔祭までの1年間を繰り返し続ける訳だが、舞台創造科も2年生時点で同じようなことを行っているのである。それを裏付けるのは、『劇場版再生産総集編「少女☆歌劇 レヴュースタァライト ロンド・ロンド・ロンド」』(以下「ロンド・ロンド・ロンド」)の公開だ。舞台創造科として、映画館に何度も足を運んだ方も多くいただろう。ところで、我々が「1年生のときのスタァライト」つまりはTVアニメシリーズ全12話の総集編である「ロンド・ロンド・ロンド」を繰り返し観ているという状況は、大場ななが2年生のときに行っている「1年生のときのスタァライトの再演」と同じ意味を持つのではないだろうか。
これこそが、この二層展開式コンテンツの恐ろしい点なのである。2次元のキャラクターである大場ななと3次元の舞台創造科である我々の行動時制が一致しているのだ。
さらに追い打ちをかけるかの如く「ロンド・ロンド・ロンド」の内容は、我々がTVアニメシリーズ全12話で観たものとは似て非なる内容だった。そこで、舞台創造科である我々はこう思うのだ。
大場「今までの再演じゃない」
つまり、大場ななと舞台創造科は、2次元と3次元という次元の隔たりを越えて、大場ななの過ごした「時間と感情」を、追体験あるいは共有できる関係にあるということだ。
だが、考えてみれば舞台創造科とそういった関係性を築くことは、大場ななというキャラクターにしかできないのだ。大場ななは作品内でも唯一、A組とB組を兼任するキャラクターだ。それはつまり、舞台創造科(B組)に干渉できる唯一の俳優育成科(A組)であることを指している。
我々は彼女を鑑賞しているようでいて、干渉されているのだ。上手いことを言った。
4.大場ななの役割
愛城華恋が結末を書き換えた、第100回聖翔祭の『戯曲 スタァライト』で、大場ななは塔の導き手の役を演じていた。この塔の導き手という部分に注目すると、「ロンド・ロンド・ロンド」においても、大場ななはストーリーテラーという物語の導き手としての役割を担っている。加えて『劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト』(以下「劇場版スタァライト」)においても、結果的に主人公である愛城華恋を塔(東京タワー)へ導いているのだ。
大場ななは、TVアニメ12話エンディングから「劇場版スタァライト」の決起集会後に至るまで、ずっと「導き手」を担っていたということになる。大場ななは、目指す場所を失った「舞台少女」と、キラめく少女たちの舞台を望み続ける「舞台創造科」の両者を導いていたのだ。
話は少し変わるが、みんな大好き「皆殺しのレヴュー」の舞台は電車の上。少女たちを導く舞台として電車が選ばれているのはなんとも興味深い。
というのも、舞台少女と電車は似ているのだ。
電車は行き先があるから電車になる。電車が線路を走るということはつまり、「目的地がある」ということだ。その目的地に向かって走っているかぎり、電車は電車であり続ける。一方、行き先のない電車、つまり線路を走らない電車は電車でなく、ただの「車両」という扱いになる。
これを舞台少女に置き換えると「目指すべき舞台」があるかどうか、が舞台少女を舞台少女たらしめているのではないかと考えられる。
99期生の中で唯一、目指すべき舞台に辿り着いたのは愛城華恋だろう。神楽ひかりとともに『戯曲 スタァライト』を演じることができたのだから。
ここで、目指すべき舞台に辿り着いた愛城華恋を、電車に置き換えて考えてみよう。電車は終点に辿り着くと、行き先を失い、車両になってしまう。では舞台少女が終点、つまりは目指すべき舞台に辿り着くと? 行き先(次の舞台)を失い、ただの「少女」になってしまうのだ。
つまり、舞台少女として死んでしまう。
話を戻すと、進路に迷い舞台少女として死にかけている舞台少女たちにレヴューを仕掛けた大場ななは、舞台少女という名の電車たちに「目指すべき舞台」を与える役割を担っていたのだ。また、舞台少女として既に死んでいる愛城華恋に対しては個別に電車を用意するという優しい導き手である。結局砂漠にて脱線したけれど。
そして決起集会の終わりに、大場ななは「塔の導き手」としての役割をようやく終えるのだ。
大場「おやつの時間はもうおしまい。飢えて、渇き、新しい舞台を求めて。
それが、舞台少女」
大場「私も、自分の役に戻ろう。あの子への執着、彼女へのケリを」
「おやつの時間」という表現は、みんなを導いてあげる時間とも取れるのではないかと考える。皆殺しのレヴュー終わりに花柳香子が「甘い」と台詞を零すが、あのレヴューすら大場ななにとっては今までのバナナマフィン、バナナプリン、バナナンシェ同様、舞台少女に与えてきた「おやつ」の類に含まれるのかもしれない。
ちなみに、「甘い」という台詞は当初天堂真矢に与えられる予定だったらしい◆1。もし天堂真矢がその台詞を言っていたとしたら、かなり言葉の印象が変わってくるが、意味するところはやはり「大場ななのお膳立てともとれる導き(レヴュー)」についての「甘い」という意味になるだろうか。
また「自分の役に戻る」という発言の通り、「導き手の大場なな」から「星見純那に執着している大場なな」に戻っている訳だが、それをわざわざ台詞として言っているあたりもメタ的で面白い。それ以前の自分が自分ではなかったと明言しているのと変わりがないからだ。
おもしれー女、というやつだ。違うかな。
このコンテンツにおいて大場ななが果たしている役割は、ただの2次元の枠に収まらない。2次元と3次元の間の存在「スタァライト」というコンテンツが謳う、まさに2.5 次元の存在といえる。
そんな彼女はまさに、裏方という名の主役なのではないかと、思わずにはいられないのだ。
*1 劇中歌アルバムVol.1 発売記念オンラインスタッフトークショー(2021年08月12日)古川監督の発言より
5.おわりに
という訳でここまで長々と論文ならぬエッセイを書いてきたが、こんなに短くなるとは思わず多少動揺している。いや、書きたいことは書いたけども。こんなに短くていいのだろうか。許してほしい。エッセイだし。
最後に「スタァライト」というコンテンツの二層展開式の魅力を語って終わりにしようと思う。突然だけれど。そうしよう。エッセイだし。
舞台もアニメも、どちらも本人というコンテンツは私にとって初めてだったのだが、その魅力にとんでもなく惹かれた。キャラクター造形に関して、キャストの好みや苦手なものがキャラクターに反映されているのもそうだが、「1人と1人であった存在が、ひとつになっていく」◆2というコンセプトがかなり刺さった。2人が1人になり、18人が9人の存在になっていくその過程を見届けた上で「劇場版スタァライト」を観れば、本編の内容とは違った意味で涙が出てくるシーンに心当たりがある人も少なくはないだろう。
舞台少女が演じる舞台少女を観られるコンテンツなど今後現れてくれるのかは謎だが、少なくともこの出逢いによって追いかけたいと思えるものが増えたのは事実だ。「スタァライト」に出逢ってからというもの、人生楽しいのだ。これでいいのだ。
*2 新作劇場版 初日舞台挨拶①新宿バルト9(2021年06月04日)武次アニメプロデューサーの発言より
著者コメント(2022/10/10)
こんにちは、カメタです。めちゃくちゃ面白い合同誌ですわ~と思いながら楽しく書かせていただきました。そうですね、論文じゃなくてエッセイでしたね。すみませんでした。とはいえ、書きたいことはいろいろと書いたはずなのにあまりにも文章量が少なくて自分でも驚いています。おかしいな。結構喋ったつもりだったのにな。参加者様も多くいらっしゃって、少女☆歌劇レヴュースタァライト、強いな~の気持ちでいっぱいですし、早くいろんな方の熱い想いを読みたくてうずうずしています。ちなみに少女☆歌劇レヴュースタァライトと打ちすぎて、もはや「しょ」と打つだけで予測変換に出てくるようになっちゃいました。PC もスタァライトされちゃう始末。本望ですね。劇場版は終わってしまいましたが、いや、まだ公開している劇場もありますが、スタァライトというコンテンツに出逢えて本当に幸せです。これからも末永く応援していきたいです。参加できて光栄でした、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
