
Taguchi lab2020 for 3回生(13期)
はじめに
皆さんこんにちは。大学のほうも現在キャンパス立入禁止となってしまい、また春学期の対面講義もなしとなってしまいました。皆さんも色々と不安な毎日を送っていることと思います。私もリアルに皆さんとお会いすることができなくなってしまい、とても残念に思っています。
現在の皆さんがやるべき第1はもちろん「自分の身を守ること」ですが、そのことを前提にしつつも、「未来の自分」のために、いま何をすべきか、何を考えておくべきかを踏まえながら、ゼミの残り2年間を過ごしてもらえたらと思います。
13期生の皆さんの今後1年の研究室でのタイムスケジュールは以下のとおりです。
4-5月 基礎体力をつける&AI学会発表準備をすすめる(&そのことを通じ、「未来の働き方」(在宅ワーク、オンラインでの協力の仕方)のコツを掴む)
6-7月 AI学会発表&さらなるステップUPのため基本書を読む(&14期生選抜?)
8-9月 秋の学会に向けて準備
10-11月 行動経済学会・実験社会科学カンファレンス(&新14期生に、田口labのspiritを吹き込む)
12月-2021/1月 14期生とともに合同チームで翌年度の学会投稿準備
今回は「4-5月」の「基礎体力をつける」と「AI学会発表準備をすすめる(&そのことを通じ、「未来の働き方」(在宅ワーク、オンラインでの協力の仕方)のコツを掴む)」について説明します。まずはじめに「基礎体力をつける」について説明します。
4-5月 part 1. 基礎体力をつける
皆さんは、2019年度秋学期に、はじめての学会投稿を体験しましたね。とても大変だったと思いますが、それを無事乗り切り、全チームアクセプトを得たこと、とても嬉しく思います。そしてこの4-5月は、それを前提に「自分たちの(知的な)基礎体力を付ける時間」としてもらえたら幸いです。
具体的には、以下の2つの作業をしてもらえたら幸いです。
作業1:11期生の卒論の中から「自分のベースになりそうな論文」を「1つ」選び、じっくり読む
田口研究室第2章のスタートであった11期の卒業論文は、主に「AI x 社会」に関するものでした。

もうすでにslackにupしたpdfに目を通してみましたか?いずれも非常に独創的で面白い論文です(特に、No.11神先・西論文は商学会卒業論文の最優秀賞を、No. 8西・永田論文は優秀賞を、それぞれ獲得しています)。
ですので、まず皆さんがすべきことは、これら「先輩の卒論をじっくり読む」(=良いところはどこか、また今後の「伸びしろ」(未解決の課題)はどこか、自分たちの研究に使えそうな素材はないかを吟味する)ことです。
(これまでも皆さんには折に触れて述べてきた通り)我々のラボは、「組織戦」「チーム戦」で戦う研究室です。11期の先輩が残してくれた財産(=卒論)を、無駄にせず、これらを有効活用しましょう。つまり、「点を線にする(先輩たちの卒論を、自分たちの問題意識とリンクさせ、自分たちの研究に応用する)」作業をしてみましょう。そうすると、今後の研究へのハードルが少し低くなるかもしれませんし、また、4回生になってから執筆する卒論も抵抗なく取り組めるかもしれません。
※具体的には、13期生の皆さんには、ゴールデンウィーク明けに「googleフォーム」(もしくは「Microsoft teams」(大学メールで利用しているofficeに入っているwebクラウド上の作業場)・・・後日どちらを使うかを提示予定)で、①どの卒論を選んだか、②その卒論の良さ・伸びしろはどこか、③自分たちの研究にどうリンクできそうかを課題として提出してもらう予定です(【個人タスク】です)。また5月のオンラインゼミでも、少しディスカッションしたいと思います。
作業2 課題図書「シン・ニホン」を手に取り、読み、考える
また第2は、(先にslackで提示した課題図書の1つである)安宅2020『シン・ニホン』を手に取り、読み、考える時間をとってもらえたらと思います。
安宅和人2020『シン・ニホン-AI×データ時代における日本の再生と人材育成』-NewsPicksパブリッシング
https://www.amazon.co.jp/dp/4910063048
安宅先生のyoutube動画も参照
https://www.youtube.com/watch?v=G6ypXVO_Fm0
https://www.youtube.com/watch?v=o2Bc7ClLRjg
皆さんは、これまでのゼミ活動を通じて、未来社会がどの様になるか、またなったらよいか、色々と考えてきたのではないでしょうか(現在のような不安定な状況なら、なおさらでしょう)。本書には、まさにそのことが、多くのデータとともに記されています。
私も本書を読みましたが(分厚いが、面白いので一気に読めると思います)、AI社会における日本の今後の「先行きの不透明さ」(安宅氏はあえてポジティブに「伸びしろ」という表現を用いています)を、多くのエビデンスとともに突きつけられ、「何とかしなくては・・・」「自分にできることはなんだろう?」と考えさせられました。
皆さんもこれまで、田口研究室で未来社会について色々と考えてきました。ここで、皆さんがこれまでやってきた研究と本書とをリンクすることができたら、とても大きな力になるのではないでしょうか。
※それとともに、本書から皆さんが学んで欲しいのは、「エビデンスの付け方」や「脚注の効果的な使い方」です。事実を裏付ける圧倒的なデータは、とても説得的ですし、また本文の裏側にある「熱い想い」をうまく脚注で表現するこの技術を見習っていけたら、テクニカルな意味でも本書は皆さんの今後の研究に有益といえるでしょう。
※こちらについても、13期生の皆さんには、ゴールデンウィーク明けに「googleフォーム」(もしくは「Microsoft teams」・・・後日どちらを使うかを提示予定)で、本書の感想を課題として提出してもらう予定です(こちらも【個人タスク】です)。また5月のオンラインゼミでも少しディスカッションしたいと思います。
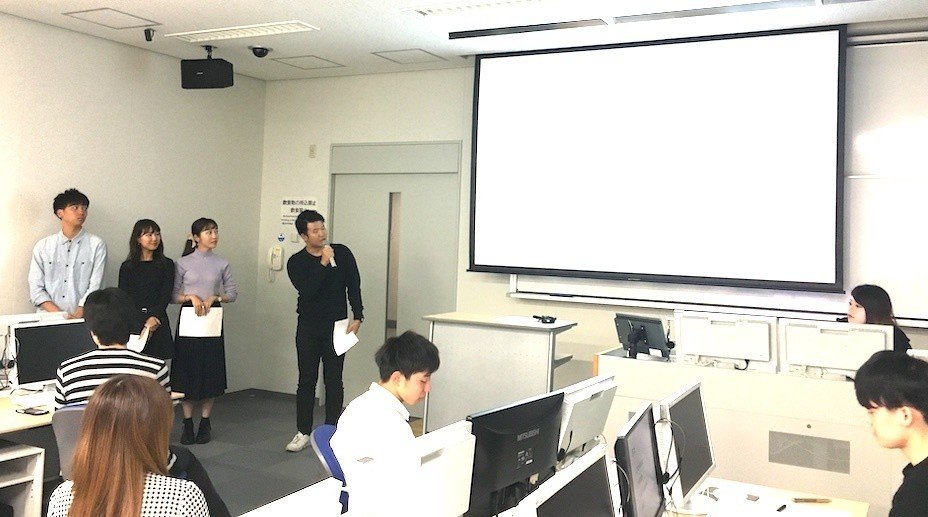
4-5月 part 2. AI学会発表準備をすすめる
また次に、4-5月の「AI学会発表準備をすすめる(&そのことを通じ、「未来の働き方」(在宅ワーク、オンラインでの協力の仕方)のコツを掴む)」についても簡単に説明します。
本格的な資料作成は5月からでも良いと思いますが、今のうちからグループで、どのようにオンラインでの作業を進めていくか、そのツールや情報共有手段を確認しておきましょう。google driveでファイル共有するだけでなく、slackで独自のチャンネルを作り(すでに自分たちのチャンネルを作って、うまく活用している班もあるようですね)進捗管理をしつつ、またzoomなどを使ってミーティングしていけたら良いと思います。
そして、そのことを通じ、皆さんには、以下のことを考えてほしいと思います。
①近い将来、社会人になって「働き方改革」で在宅ワークをするとしたら、自分はどのように効果的な働き方ができるだろうか?【自分単体での効率的・効果的なオンラインでの仕事の仕方を考える】
②将来の在宅ワークにおいても、チームで協力しながら仕事をすることはきっと変わらない。であれば、在宅ワークで皆とうまく協力するには(他のメンバーの協力を引き出すには)どんな工夫をすればよいだろうか?(どのようなスケジュール管理、どんな業務分担、どんな役割分担、どんな情報共有、どんな声掛けができればよい?)【他者との関係性の中でのオンラインでの仕事の仕方を考える】
現在、実際に多くの大手企業が在宅ワークを(試行錯誤しつつも)実践しつつあります。きっと皆さんが社会人になるときには、(現在の状況が収まったとしても「働き方改革」が一層進み)「在宅ワークが基本」となっているかもしれません。そんな中でも、やはりチームでの協力は必要です。では、どうすれば、それができるでしょうか・・・?
そんなことを考えながらいまの時間を過ごすことが出来たら、きっと皆さんの今の作業は、「いまだけのこと」(点)に終わらず、将来にまで続く「線」となり、将来の皆さん自身を助けることになるでしょう。是非そのようなマインドを持って取り組んでください。
※ちなみに学会自体も、オンライン開催になりました!
※なお、発表スライドですが、これまでの先輩たちのスライドを参考にしつつも、①「IMRAD」を大切に、②うまい業務分担を考えつつ、かつ(オンラインでの作業となりますので)③できるだけシンプルなかたちで作ることをおすすめします。その点は、また5月のオンラインゼミでも確認しましょう。
***まとめ***
以上、皆さんは、4-5月は「基礎体力をつける」と「AI学会発表準備をすすめる」をテーマにタスクを進めてください。
具体的には、まず「基礎体力をつける」については、以下の2つのタスクをこなしてもらえたらと思います(個人タスクとしての課題提出あり)。
作業1:11期生の卒論の中から「自分のベースになりそうな論文」を「1つ」選び、じっくり読む
作業2:課題図書「シン・ニホン」を手に取り、読み、考える
また「AI学会発表準備をすすめる」については、今のうちからグループで、どのようにオンラインでの作業を進めていくか、そのツールや情報共有手段を確認しておきましょう(かつ、未来の「働き方改革」での在宅ワークを想像するマインドセットを持ちましょう)。
このようなご時世ですが、健康にはくれぐれも留意し、また、これまでと異なる生活サイクルですので、ストレスも溜まりがちかと思いますが、心のなかで「笑顔と拍手」を忘れず、日々過ごしてください。
またもし何か不明点や、作業の進め方などでの相談事とかあれば、遠慮なくおっしゃってください。私は皆さんの味方です。
【今後のスケジュール】
4/15 online ゼミ第1回 →(課題1・2提出)→ 5/20 onlineゼミ第2回
→5/27 onlineゼミ第3回
田口聡志(同志社大学)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
