第54回(2022年)社会保険労務士試験 択一式(厚生年金保険法問1から10)
発信スケジュール(マガジンに載せています)
2023/9/3⇒ 労働基準法 問1から7 ⇒『4点』確保
2023/9/3 ⇒ 労働安全衛生法 問8から10 ⇒『1点』確保
2023/9/9 ⇒ 労働災害補償法 問1から7 ⇒『6点』確保
2023/9/13 ⇒ 雇用保険法 問1から7 ⇒『5点』確保
2023/9/24 ⇒ 徴収法 災:問8から10 雇:問8から10 ⇒『6点』確保
2023/10/1 ⇒ 健康保険法 問1から10 ⇒『4点』確保
2023/10/7 ⇒ 国民年金法 問1から10 ⇒『8点』確保
2023/10/15 ⇒ 厚生年金保険法 問1から10←本日はここです。
2023/10/22 ⇒ 社一 問6から10
2023/10/29 ⇒ 労一 問1から5
第54回(2022年)社会保険労務士試験の合格基準

択一式問題をとくときのマイルール
設問文の『正しい』『誤っている』『誤っている or 正しいもの の数』『組み合わせ』なのか、間違えないように、〇で囲む。
A の選択肢は最初に絶対に読まない。正解の確率が低いから。
選択肢の『文章量が少ない』選択肢から〇×を判断する。判断できないときは、△にする。
文節ごとに、スラッシュをして文節ごとに正誤を判断する。
実況中継(厚生年金保険法 問1から10)
〔問 1〕 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第38 条第1 項及び同法附則第17 条の規定によってどちらか一方の年金の支給が停止されるものの組合せとして正しいものはいくつあるか。ただし、いずれも、受給権者は65 歳に達しているものとする。
ア 老齢基礎年金と老齢厚生年金
イ 老齢基礎年金と障害厚生年金
ウ 障害基礎年金と老齢厚生年金
エ 障害基礎年金と遺族厚生年金
オ 遺族基礎年金と障害厚生年金
A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ

問1は、『難問』。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。「一方の年金の支給が『停止』されるもの」に〇、小職は併給できると、読み違えまちがえたので、難問。
ル2 ル3 ル4 で「ア」から「オ」は基本テキストに記載しているので、「ア」は併給されるので「◯」。「イ」は併給されないので「×」。「ウ」は「◯」「エ」は「◯」「オ」は「×」で「×」の数である正解は、「Bの 二つ」。
〔問 2〕 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(以下本問において「当該被保険者」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 当該被保険者を使用する適用事業所の事業主が、当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をしたときを除き、当該被保険者は保険料の全額を負担するが、保険料の納付義務は当該被保険者が保険料の全額を負担する場合であっても事業主が負う。
B 当該被保険者に係る保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負うことにつき同意をした適用事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を得て、将来に向かって当該同意を撤回することができる。
C 当該被保険者が保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、厚生労働大臣が指定した期限までにその保険料を納付しないときは、厚生年金保険法第83 条第1 項に規定する当該保険料の納期限の属する月の末日に、その被保険者の資格を喪失する。なお、当該被保険者の事業主は、保険料の半額を負担し、かつ、当該被保険者及び自己の負担する保険料を納
付する義務を負うことについて同意していないものとする。
D 当該被保険者の被保険者資格の取得は、厚生労働大臣の確認によってその効力を生ずる。
E 当該被保険者が、実施機関に対して当該被保険者資格の喪失の申出をしたときは、当該申出が受理された日の翌日(当該申出が受理された日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に被保険者の資格を喪失する。


問2は、『正解』。したいところ。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 で「D」。細かい論点なので、「△」保留。基本テキストには記載内容。
③ ル3 ル4 で「E」。基本テキストに記載しているので「〇」。これが正解。残りの選択肢を軽く見る。
④ 「B」は「×」⇒「A」は「×」⇒「C」は「×」やはり、正解は、「E」。
〔問 3〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 甲は、昭和62 年5 月1 日に第3 種被保険者の資格を取得し、平成元年11 月30 日に当該被保険者資格を喪失した。甲についての、この期間の厚生年金保険の被保険者期間は、36 月である。
B 老齢厚生年金の加給年金額の加算の対象となっていた子(障害等級に該当する障害の状態にないものとする。)が、18 歳に達した日以後の最初の3 月31 日よりも前に婚姻したときは、その子が婚姻した月の翌月から加給年金額の加算がされなくなる。
C 適用事業所に使用されている第1 号厚生年金被保険者である者は、いつでも、当該被保険者の資格の取得に係る厚生労働大臣の確認を請求することができるが、当該被保険者であった者が適用事業所に使用されなくなった後も同様に確認を請求することができる。
D 障害手当金の受給要件に該当する被保険者が、障害手当金の障害の程度を定めるべき日において遺族厚生年金の受給権者である場合は、その者には障害手当金は支給されない。
E 同時に2 以上の適用事業所で報酬を受ける厚生年金保険の被保険者について標準報酬月額を算定する場合においては、事業所ごとに報酬月額を算定し、その算定した額の平均額をその者の報酬月額とする。


問3は、「正解」したい。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。
③ ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。これが正解。残りの選択肢を軽く読む。
④ 「A」は「〇」、「B」は「〇」、「C」は「〇」やはり、正解は、「E」。
〔問 4〕 次のアからオの記述のうち、厚生年金保険法第85 条の規定により、保険料を保険料の納期前であっても、すべて徴収することができる場合として正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 法人たる納付義務者が法人税の重加算税を課されたとき。
イ 納付義務者が強制執行を受けるとき。
ウ 納付義務者について破産手続開始の申立てがなされたとき。
エ 法人たる納付義務者の代表者が死亡したとき。
オ 被保険者の使用される事業所が廃止されたとき。
A (アとウ) B (アとエ) C (イとウ)D (イとオ) E (ウとオ)

問4は、『難問』。捨て問。かなり難しいと思う。
① 「オ」は「〇」、それ以外は「△」保留。
② 「D」と「E」に絞ることができる。「イ」と「ウ」で比較する。
③ 破産手続き中に保険料を回収できる余地があるのではないか、と考え、「ウ」を「×」とできれば、正解の『D(イとオ)』が選べるが、試験会場で正解するのは至難。小職は、『E』を選び間違えました。捨て問。差がつかないと思われる。
〔問 5〕 老齢厚生年金の支給繰上げ、支給繰下げに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 老齢厚生年金の支給繰上げの請求は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行うことができる者にあっては、その請求を同時に行わなければならない。
B 昭和38 年4 月1 日生まれの男性が老齢厚生年金の支給繰上げの請求を行い、60 歳0 か月から老齢厚生年金の受給を開始する場合、その者に支給する老齢厚生年金の額の計算に用いる減額率は24 パーセントとなる。
C 68 歳0 か月で老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った者に対する老齢厚生年金の支給は、当該申出を行った月の翌月から開始される。
D 老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行った場合でも、経過的加算として老齢厚生年金に加算された部分は、当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出に応じた増額の対象とはならない。
E 令和4 年4 月以降、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行うことができる年齢の上限が70 歳から75 歳に引き上げられた。ただし、その対象は、同年3 月31 日時点で、70 歳未満の者あるいは老齢厚生年金の受給権発生日が平成29 年4 月1 日以降の者に限られる。


問5は、「正解」したいところ。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 で「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。
③ ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。これが、正解。残りの選択肢を軽くみる。
④ 「A」は「〇」、「B」は「〇」、「E」は「〇」法改正。やはり、正解は、「D」。
〔問 6〕 加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害等級1 級又は2 級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65 歳未満の配偶者又は子(18 歳に達する日以後最初の3 月31 日までの間にある子及び20 歳未満で障害等級1 級又は2 級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。
B 昭和9 年4 月2 日以後に生まれた障害等級1 級又は2 級に該当する障害厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、受給権者の生年月日に応じた特別加算が行われる。
C 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240 以上であるものに限る。)の受給権者が、受給権を取得した以後に初めて婚姻し、新たに65 歳未満の配偶者の生計を維持するようになった場合には、当該配偶者に係る加給年金額が加算される。
D 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の年金額には、加給年金額は加算されない。また、本来支給の老齢厚生年金の支給を繰り上げた場合でも、受給権者が65 歳に達するまで加給年金額は加算されない。
E 老齢厚生年金の加給年金額の対象となっている配偶者が、収入を増加させて、受給権者による生計維持の状態がやんだ場合であっても、当該老齢厚生年金の加給年金額は減額されない。

問6は、「正解」したい。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。
③ ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。これが正解。残りの選択肢を軽く見る。
④ 「A」は「×」「B」も「×」「C」も「×」。やはり、正解は「D」。
〔問 7〕 厚生年金保険法の適用事業所や被保険者に関する次の記述のうち、正しい
ものはどれか。
なお、文中のX、Y、Zは、厚生年金保険法第12 条第1 号から第4 号までに規定する適用除外者には該当しないものとする。
A 常時40 人の従業員を使用する地方公共団体において、1 週間の所定労働時間が25 時間、月の基本給が15 万円で働き、継続して1 年以上使用されることが見込まれる短時間労働者で、生徒又は学生ではないX(30 歳)は、厚生年金保険の被保険者とはならない。
B 代表者の他に従業員がいない法人事業所において、当該法人の経営への参画を内容とする経常的な労務を提供し、その対価として、社会通念上労務の内容にふさわしい報酬が経常的に支払われている代表者Y(50 歳)は、厚生年金保険の被保険者となる。
C 常時90 人の従業員を使用する法人事業所において、1 週間の所定労働時間が30 時間、1 か月間の所定労働日数が18 日で雇用される学生Z(18歳)は、厚生年金保険の被保険者とならない。なお、Zと同一の事業所に使用される通常の労働者で同様の業務に従事する者の1 週間の所定労働時間は40 時間、1 か月間の所定労働日数は24 日である。
D 厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5 人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。
E 宿泊業を営み、常時10 人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。

問7は、できれば「正解」したい。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載されているので「×」。
③ ル3 ル4 から「D」を解く。基本テキストに記載されているので「×」。
④ ル3 ル4 から「B」を解く。基本テキストに記載されているので、「〇」。これが正解。残りの選択肢を軽く読む。
⑤ 「A」は「×」、「C」は「×」。やはり、正解は「B」。
〔問 8〕 厚生年金保険法の在職老齢年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 在職老齢年金の支給停止額を計算する際に用いる総報酬月額相当額は、在職中に標準報酬月額や標準賞与額が変更されることがあっても、変更されない。
B 在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、適用事業所に使用される70 歳以上の者に対しては、この在職老齢年金の仕組みが適用されない。
C 在職中の被保険者が65 歳になり老齢基礎年金の受給権が発生した場合において、老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止額を計算する際に支給停止の対象とはならないが、経過的加算額については在職老齢年金の支給停止の対象となる。
D 60 歳以降も在職している被保険者が、60 歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって被保険者である場合で、雇用保険法に基づく高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その間、60 歳台前半の老齢厚生年金は全額支給停止となる。
E 在職老齢年金について、支給停止額を計算する際に使用される支給停止調整額は、一定額ではなく、年度ごとに改定される場合がある。


問8は、できれば『正解』。したいところ。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。これが、いきなり正解。残りの選択肢を軽く読む。
③ 「A」は「×」「B」も「×」「C」も「×」「D」も「×」。やはり、正解は「E」。
〔問 9〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 1 つの種別の厚生年金保険の被保険者期間のみを有する者の総報酬制導入後の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算では、総報酬制導入後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を当該被保険者期間の月数で除して得た平均標準報酬額を用いる。
B 65 歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である7 月1 日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定する在職定時改定が導入された。
C 保険給付を受ける権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利については、「支払期月の翌月の初日」がいわゆる時効の起算点とされ、各起算点となる日から5 年を経過したときに時効によって消滅する。
D 2 つの種別の厚生年金保険の被保険者期間を有する者が、老齢厚生年金の支給繰下げの申出を行う場合、両種別の被保険者期間に基づく老齢厚生年金の繰下げについて、申出は同時に行わなければならない。
E 加給年金額が加算されている老齢厚生年金の受給者である夫について、その加算の対象となっている妻である配偶者が、老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が240 月以上となり、退職し再就職はせずに、老齢厚生年金の支給を受けることができるようになった場合、老齢厚生年金の受給者である夫に加算されていた加給年金額は支給停止となる。

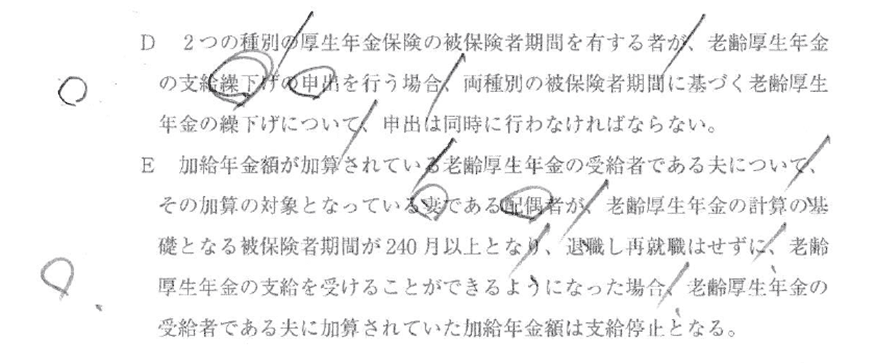
問9は、できれば、『正解』したい。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 から「D」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。
③ ル3 ル4 から「C」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。
④ ル3 ル4 から「B」を解く。法改正で「×」。これが正解。他の選択肢を軽く見る。
⑤ 「A」は「〇」「E」も「〇」やはり、正解は「B」。
〔問 10〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 常時5 人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。
B 適用事業所に使用される70 歳未満の者であって、2 か月以内の期間を定めて臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、厚生年金保険法第12 条第1 号に規定する適用除外に該当せず、使用される当初から厚生年金保険の被保険者となる。
C 被保険者であった45 歳の夫が死亡した当時、当該夫により生計を維持していた子のいない38 歳の妻は遺族厚生年金を受けることができる遺族となり中高齢寡婦加算も支給されるが、一方で、被保険者であった45 歳の妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた子のいない38 歳の夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族とはならない。
D 障害等級2 級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300 に満たないときは、これを300 とする。
E 保険給付の受給権者が死亡し、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときにおいて、未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2 人以上あるときは、その1 人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1 人に対しての支給は、全員に対してしたものとみなされる。


問10は、『正解』したい。
① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。
② ル2 ル3 ル4 から「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。
③ ル3 ル4 から「A」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。
④ ル3 ル4 から「B」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。
⑤ ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載されているので、「〇」。これが、正解。最後に「C」は「×」やはり、正解は「E」。
まとめると、
問1 ⇒ 難問
問2 ⇒ 〇
問3 ⇒ 〇
問4 ⇒ 難問
問5 ⇒ 〇
問6 ⇒ 〇
問7 ⇒ 〇
問8 ⇒ 〇
問9 ⇒ 〇
問10 ⇒ 〇
厚生年金保険法は、『8点』ないしは『9点』以上、確保できるのではないでしょうか。健康保険法で足切り回避して、年金科目で稼げば十分合格点達するでしょう。ここまでで合計『42点ないし44点』。最後の『一般常識』を4点確保すれば合格点を超えることになる。
ただし、試験の後半になるので、時間配分や基本テキストに記載の内容の定着度合いで、他の受験生と差がつきやすい出題になっているのは言うまでもない。基本テキストと過去問を繰り返し、基礎力を養うことが大切だと個人的には感じずにはいられない。問1のような引っかけには気をつけること。落とすと差がつく問題の典型。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
