
ピックアップのマグネットについて書けるだけ書いてみる ③
エレクトリックギターのピックアップの内蔵マグネットについて色々と書いてきたが、今回は実際にピックアップを選ぶときの基準や目安、最低限必要とされる知識をお伝えして3回にわたる記事の締めくくりとしたい。
☆
マグネット(以下mag)によるピックアップ(以下PU)のトーンキャラクターの違いについて、最も分かりやすいサンプルはセイモアダンカン(SEYMOUR DUNCAN)のSH-5 Duncan Customとその派生モデルである。
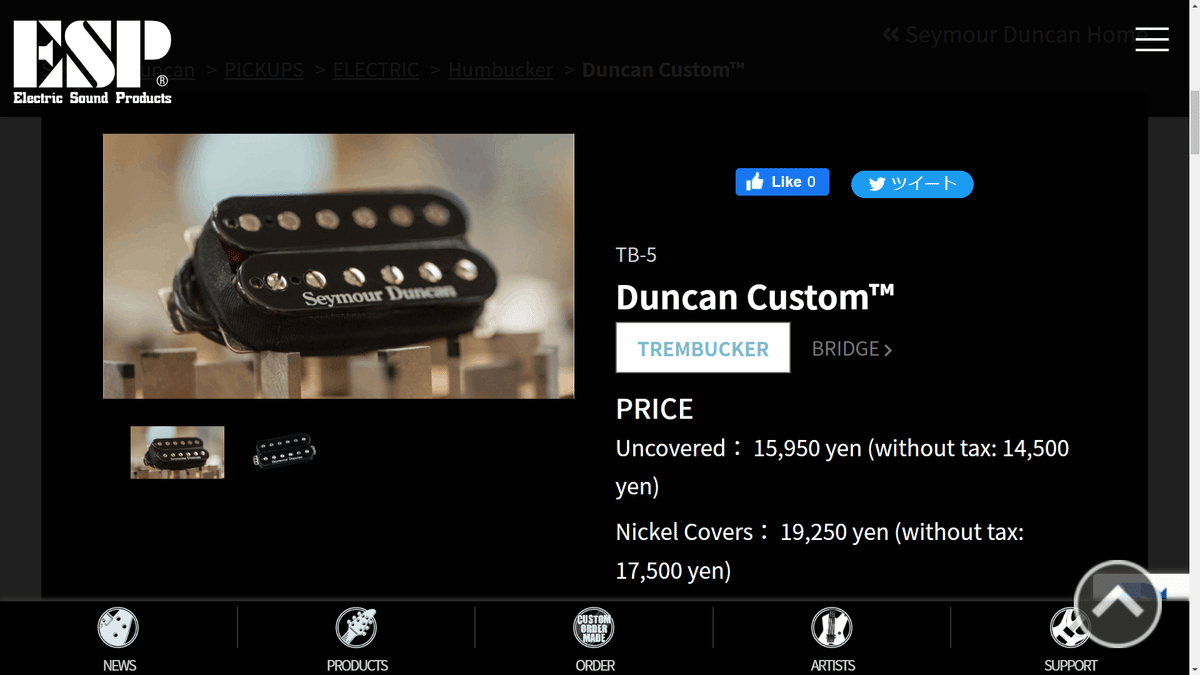
同社の看板モデルのひとつにしてPAFレプリカのスタンダードである’59(SH-1)をベースに、コイルのターン数を増やして出力を上げたこのモデルにはセラミックmagが採用された。
しばらくして、このモデルを使ったギタリストから、出力は同程度を保ちながら「スィートでウォームな」トーンを持ったPUを造ってほしいという声があがる。
それに応えるべくSダンカンはDuncan Customの基本設計はそのまま、magをアルニコⅡに替えたモデルをSH-11 Custom Customの名で発売する。
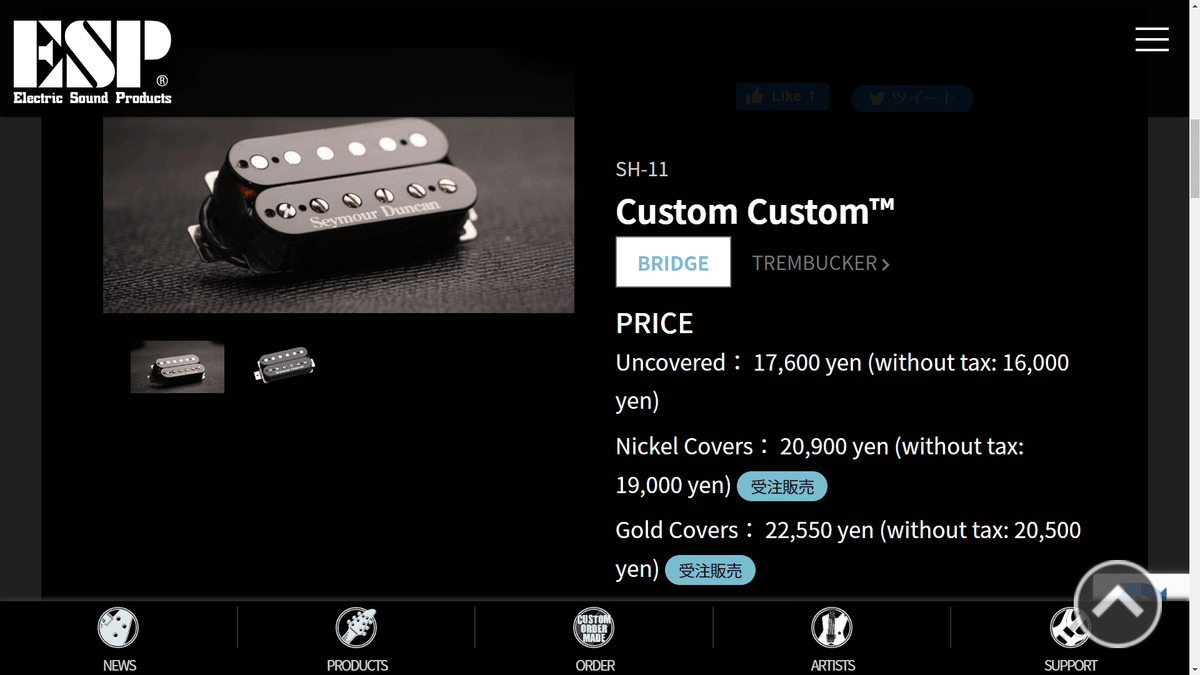
すると今度は、もっと低~中音域に厚みをもたせたモデルを造ってほしいという声が寄せられたようだ。
Sダンカンも慣れたもので、この要望に対してアルニコⅤをmagに採用したモデルを開発、SH-14 Custom 5と名付ける。
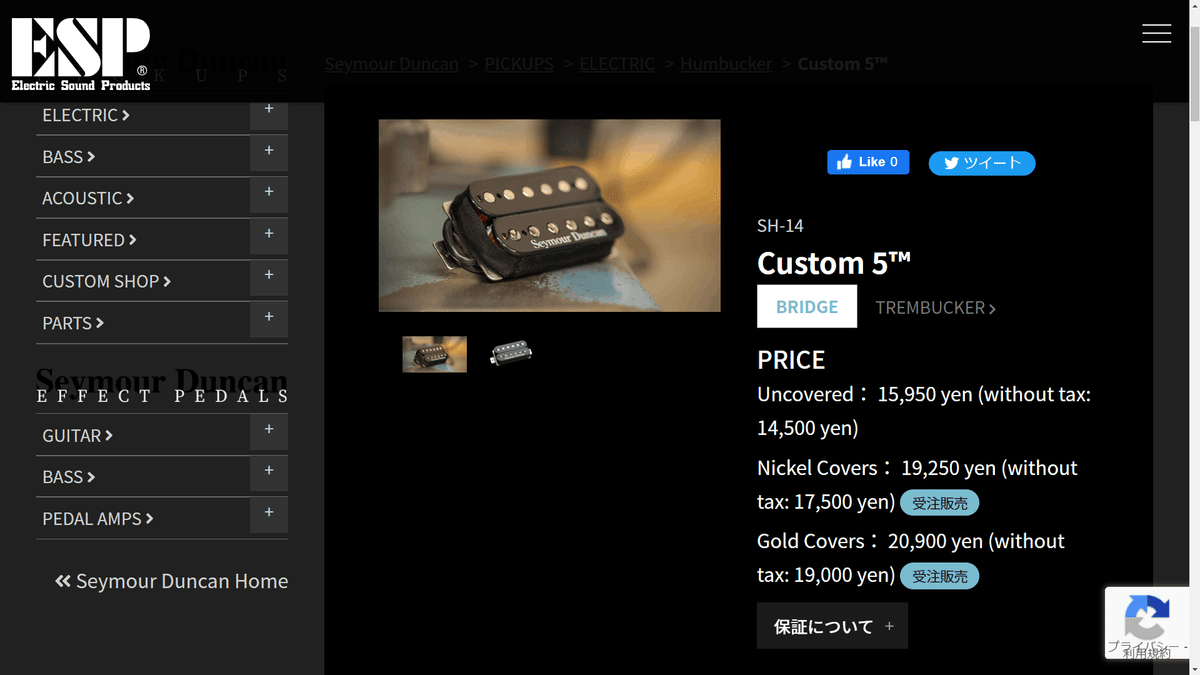
このSダンカンのCustom系3モデルをみれば、PUのトーンキャラクターにmagが与える影響はだいたい判るのではないだろうか。
☆
もうひとつ、ハムバッカー系PUでのサンプルを挙げるとすればディマジオにおけるスティーヴ・ヴァイのモデルである。
1993年に”Evolution”の名でリリースされたヴァイの専用PUはアイバニーズのシグニチュアモデルのJEM7Vに純正搭載された。

私は楽器屋時代にこのEvolutionの、ブリッジ用だからDP159になるが、JEM7Vとは異なるタイプのギターに搭載されたものを鳴らしたことがあるのでよく憶えている。
大音量でさらされれば膝が笑うような凄まじいディストーションが、溶岩の流れ出るがごとくアンプからドロドロと床を這うように迫ってくるのは異様としか言いようがなく、これほどの重くラウドなサウンドをヴァイはどうやってコントロールしているのか不思議で仕方なかったものだ。
考えてみれば90年代初期のヴァイのギターサウンドは低音から高音まで十分に、十分すぎるほど歪んだうえで金切り声に近い鋭さを響かせるものだったわけで、そのヴァイが求めるサウンドを生み出すにはEvolutionの強烈なキャラクターが求められていたのである。
そのヴァイも嗜好の変化があったのだろうか、2006年発売のアイバニーズJEM77Bに搭載のディマジオPUはEvolutionよりも出力を約10%おさえており、さらにmagがセラミックからアルニコⅤに変更されたという”The Breed”に代わっていたのである。
これによりヴァイの求めた「クラシカルなハムバッカーのニュアンス」が得られるようになったというが、その変化は音源を聴けばすぐに分かるだろう。
歪みの深さは十分に確保されながら艶やかで伸びのある中音域、暴れすぎず割れすぎない低音域は非常に魅力的だと思う。
☆
先に例を挙げたハムバッカー系モデルだが、カタログデータの直流抵抗からコイルの巻き数と大まかな出力を、magがアルニコかセラミックかでだいたいのトーンキャラクターを推測することができる。
難しいのはフェンダー系シングルコイル(SC)である。磁界の広がり方や密度がそのままPUのトーンキャラクターに直結するからだ。
前回の記事の画像をもう一度使わせてもらうが、

伝統的なSCではこの、ボビンの支柱であるポールピースが磁化されることでmagとなる。
一方で

このようにPU底面に大きめのセラミックmagを配したSCも多くみられる。
この場合のポールピースは必ずしもアルニコである必要は無く、磁性体でありさえすればいいので使う金属の、耐久性や加工のしやすさ、そして何より価格の制約が減ることもあってこの方式は安価な製品で多用される。
それが逆にこの方式のSCに対する「音が良くない」という偏見をよんでしまっているように思える。

シェクター(SCHECTER)製品の純正PUにしてクオーターパウンド系SCの代表作モンスタートーンは、ポールピースに鉄を用いており、

マグネットはセラミックの大ぶりなものを底面に配している。
「特性」=トーンキャラクターに対する好みの差はあるにせよ、モンスタートーンのPUとしての、弦振動のセンサーとしての「性能」を疑うギタリストのほうが少数派であろう。
PU、特にSCはコイルの巻き数や巻き付けの際のテンション、ワイアの選択等の要素が重なり合ってトーンキャラクターが決まるのであり、magの配置だけで判断するのは浅慮というものだ。
SCリプレイスメントPUを選ぶうえで、50~60年代の仕様の忠実な再現がセールスポイントのヴィンテージレプリカ系モデルを求めるのであればmagはアルニコ一択であり、迷う必要はない。なにせお手本となる当時のPUにはアルニコしか用いられていなかったのだから…
一方で、ヴィンテージサウンドをうたうモデルを使ってみたものの、
○歪ませたときの音像が重たくぼやけてしまう
○高音域の反応の鈍さが気に入らない
という場合は出力が高めの、セラミックmagのモデルを検討すべきだろう。
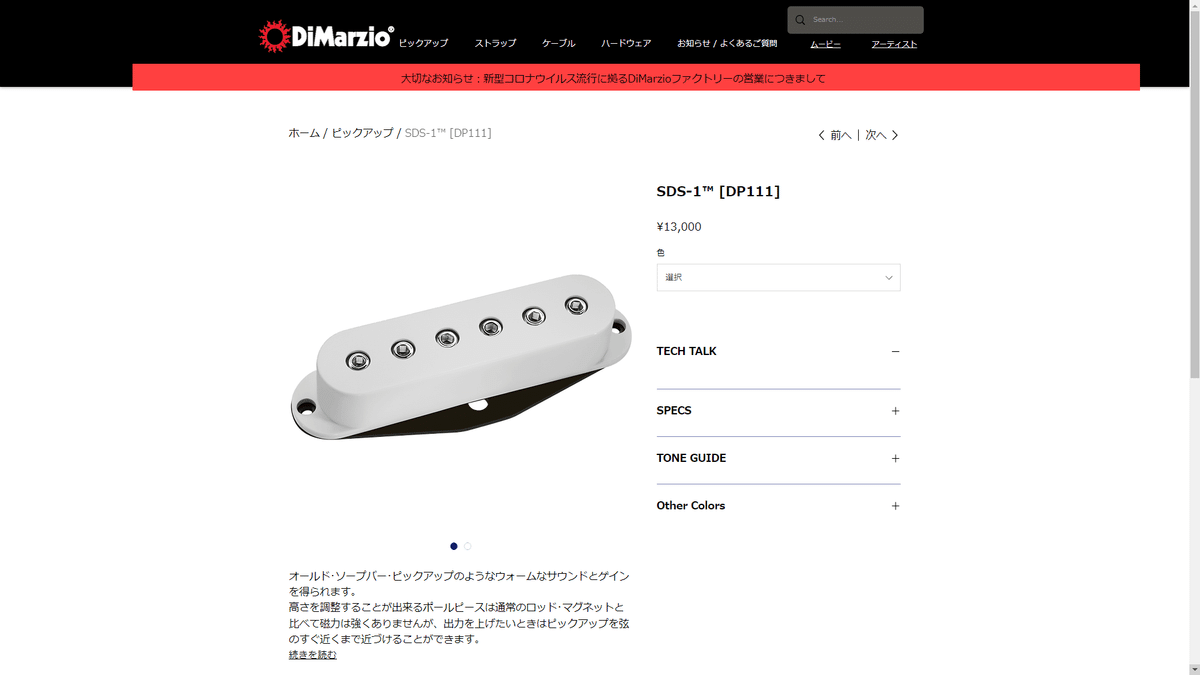
ディマジオDP111 SDS-1はSuper Distortion Stratを名の由来にもつだけあってかなりのハイパワーであり、ヴィンテージレプリカとは真逆の方向に振り切ったモデルである。
発売は1978年というから目新しさは全く無いが、見方を変えればこのモデルでないと得られないサウンドを今もギタリストが求めているということである。

もうひとつ、G&Lの純正PUの中のS-500用MFD SCも挙げておきたい。
金属製ヨークによる積極的な磁界のコントロールによりmagの保磁力やコイルの巻き数に頼ることなく十分な出力を確保するマグネティック・フィールド・デザイン(MFD)を用いたこのモデルはストラトキャスター用SCとほぼ同寸で互換性がある。
レオ・フェンダーもまたG&L期にはPUのmagをセラミックに切り替えており、そこにMFDによる硬質でクリアな音像が組み合わさることでトラディショナルなSCとは一線を画すトーンキャラクターを獲得している。
残念ながらG&Lの輸入代理店である山野楽器はPUの単体販売を行っていないようなので本国USのHPを掲載しておいたが、中古を含めたリプレイスメントパーツの個人売買が普及した現在であれば入手は比較的容易ではないだろうか。
☆
かつてのエレクトリックギターの業界を染め上げたヴィンテージギター礼賛の風潮も2020年代の現在では随分と薄れてきているものと思う。
オールドのギターとはキャラが違うから、という理由でヘヴィディストーションやシャープなクリーントーンを鳴らすことにギタリストが躊躇する必要は無い。
明確な個性を持った、それゆえ上手く使えるギタリストには強力な武器となりえるPUは視野を広げればまだ見つかるはずだ。
PUにおける主要スペックである内蔵マグネットについて知り、興味を持つことで最良のPUが最短距離で見つかることを願っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
