
自粛要請の中でのK-1開催、実は経営でも「あるある」?目指そう!全体最適!
新型コロナの影響で、大規模イベントの自粛「要請」がなされています。そんな中、2020年3月22日に通常であれば1万人規模のイベント、「K-1」が開催されました。
自粛要請もK-1開催 主催者「最大限の対応策とり決定」
主催者の発表によると6500人程の来場者数があったそうです。国が大規模イベントの自粛を要請し、会場であるさいたまスーパーアリーナのある埼玉県の知事も自粛を要請した中での開催。どう思われたでしょうか?
多少落ち着いてきたとはいえ、まだ日本全国的に感染が拡大している現在、感染拡大を防ぐという日本「全体」のことを考えたら、これほどの人数が集まるイベントは開催しない方が良かったのでしょう。ですが、「K-1」の主催者という「部分」を見てみると、実は開催した方が合理的と言うことになります。日本「全体」で判断したら「開催しない」という判断になるでしょうが、主催者という「部分」で判断したら「開催する」という判断になる。これを部分最適と言います。
そしてこの部分最適、実は企業経営にとって「あるある」なのです。なぜ部分最適に陥るのか、それを防ぐ方法はないのか、この記事ではそこを考えていきたいと思います。
「K-1」は主催者にとって開催した方が合理的
これを読んでいる方の中には、「なぜこんな状況で開催したんだ!」「日本全国のことを考えられないのか!」という批判的なことを感じている方もおられるかもしれません。感染拡大を防ぐという意味では、開催しない方が妥当でしょう。ですが、「K-1」主催者にとってみれば開催した方が合理的と考えられます。私は主催者というわけではないですが、そう考えられる理由が沢山あるのです。以下、考えられる理由を挙げると、
理由①:多額の損失
このような1万人規模が集まる会場は利用料もバカにになりません。実際、今回のさいたまスーパーアリーナの会場費は以下のHPから確認できます。
さいたまスーパーアリーナ利用料
設営・撤去・リハーサルを含めると、料金は1125万円にもなります。おそらく直前キャンセルは100%に近い金額のキャンセル料となるでしょう。その他、集客のための広告宣伝費も相当使っているでしょう。今回のイベントはS席で1万5千円、一番下のB席が7千円です。平均すると1万円を超えるぐらいでしょうか(もっといい席もありますが、数は少ないでしょう)。平均1万円のチケットを1万席(通常開催時はこのくらいの規模)売るのに20%程度広告に使っていてもおかしくありません。そうすると、広告宣伝費でも2千万円(1万円×1万席×20%)掛けていることになります。他にも様々な費用が発生し、すでに支出されているでしょう。開催されないとなったらそのすべてが損。数千万円の損になります。

理由②:資金繰り
①で書いたような費用は基本全て前払いになります。数千万円前払いしなければいけないということです。大きいイベントとはいえ、主催者は超大企業というわけではありません(主催企業の資本金は1億66百万円。従業員は15名。中堅程度というところでしょうか)。開催のための資金は融資を受けている可能性が高いです。開催して、回収したチケット代で返済する契約で。こういう短期的な資金の融資は、中小企業では「あるある」です。そして、これが返せないと倒産するリスクまであります。
理由③:参加は自己判断
開催するからと言って、参加者を強制的に集めるわけではありません。チケットを買って参加するかどうかは参加者の自己判断です。良い悪いは別にして、今回の感染拡大を防止するという最終判断は主催者ではなく参加者にあるとも言えるのです(クドイようですが、良い悪いは別にして)。
まだ他にも理由はありますが、開催する方が合理的という状況に主催者側はある、ということは分かって頂けたのではないかと思います。そして、開催したとしても、「感染者がでなければ」長期的に責められるようなことはありません。
開催しない:多額の損が出て下手すれば倒産
開催する :感染者がでないかもしれない。
出ても最終意思決定者は参加者
という状況。そりゃ、「開催する」という判断をしてしまうでしょう。開催しなければ、下手すれば主催者側が倒れてしまうのですから。
主催者側からすると、どうしても「開催する」と判断した方が合理的になってしまうのです。
世間に非難されたくはないでしょうが、苦渋の決断をせざるを得ないのでしょう。
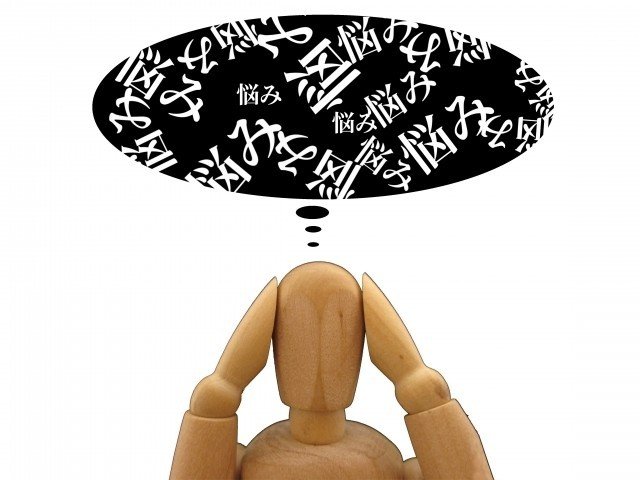
部分最適と全体最適
部分最適・全体最適という言葉があります。聞いたことがあるでしょう。普通は「部分の集合」が「全体」になります。毎回食べ物の話題で恐縮ですが、例えばラーメンは、スープ、麺、チャーシュー、その他の具材、といった部分部分が合わさってラーメンという「全体」を作っています。

ラーメンの美味しさは何で決まりますか?麺ですか?スープですか?スープが美味しければ、仮にのびのびの麺でも美味しいラーメンですか??おそらく違うでしょう。「全体の調和」これが大事なのではないでしょうか?
このラーメンの中で、今までアッサリ味だったチャーシューをコッテリとした味に変えたとしましょう。チャーシューはそれで美味しいかもしれません。ですが、これまでのスープと味を変えなかったらラーメンの調和が崩れてしまいます。チャーシュー「だけ」味を変える。これが部分最適なのです。
これに対して、チャーシューだけじゃなくて、スープも麺も「全体の調和」を考えて調整する。チャーシューだけをとってみたら、コッテリ味に変化しきれていない状態になるかもしれません。でも大事なことは「ラーメン全体の味」。「全体を重視する」これが全体最適です。
今回の「K-1」の問題はこの、部分最適と全体最適の問題と言えそうです。日本「全体」のことを考えたら、新型コロナが拡大している中、「開催しない」という判断になりそうです。ですが、先ほど述べたように、主催者という「部分」で考えると、「開催する」が合理的な判断になるのです。部分的には最適な判断が必ずしも全体として最適になるとは限らない。放っておくと部分最適に陥ってしまう。これが部分最適と全体最適の問題です。
そしてこの部分最適と全体最適の話、ラーメンの話で例えましたが、実はそのくらい身近な話なのです。決して今回の「K-1」のような状況で起こるものではなく、皆さんの会社でも日常的に起こっている問題です。
あるあるな「部分最適 vs 全体最適」
日常的に起こっている?と疑問に感じられるかもしれません。ですので例を挙げてみましょう。「部分最適 vs 全体最適」の例です。
例①:営業 vs 経理
例えば在庫の保有量でこのような状態になっていませんでしょうか?営業の立場としては売り逃しをしたくありません。ですので、注文が入ったらすぐ持っていけるように在庫を多く持ちたいと考えます。他方経理では資金繰りの観点から在庫を多く持ちたがりません。「在庫を多く持つ」のが営業の立場では最適、「在庫を少なく持つ」のが経理の立場では最適。「そこそこの在庫で売り逃しがほぼない」というのが全体最適でしょうが、放っておくと声の大きい部署の意見に寄ってしまいます(大概は営業が強いです)。
例②:上司 vs 部下
これも「あるある」だと思いますが、頑張れば3日で終わりそうな仕事を「1週間でやっておいて」と上司に言われたら部下はどう動くでしょうか?「3日で終わらせる」こう行動するでしょうか?恐らくしないでしょう。あまりに早く終わらせると次から「3日でできる」と思われて、今回結構頑張ったのに次から当たり前に「3日で」と仕事の依頼が来るかもしれません。そうすると部下は1週間かけて終わらせようとするでしょう。上司としては生産性が高まった方が嬉しいですし、会社全体のためになるでしょう(全体最適)。ですが、部下としては1週間かける方が合理的なのです(部分最適)。なので、放っておくと必ず1週間かけて仕事を終わらせるということになります。
例③:経営者 vs 社員
残業のことを考えてください。会社の目的は「お金を稼ぐこと」。全体のことを考えたら残業は少なく仕事が終わった方が残業代も必要なく、会社全体のためです(全体最適)。ですが、社員としてみると、生活のために残業した方が良い、残業代で稼ぎたい、そう考えることもあるでしょう(部分最適)。放っておくと残業代が欲しい社員はずっと残業をし続けることになるでしょう。
いかがでしょうか?いくつか例を挙げてみましたが、アナタの会社でもありそうではないですか?こういった部分最適と全体最適の対立は「K-1」に限らず身近で起こっている、「あるある」な問題なのです。そして放っておくと部分最適に陥るというのも「あるある」な話です。

目指すは全体最適!
では、部分最適と全体最適、どちらを目指すべきなのでしょうか?
言うまでもありませんよね。目指すべきは全体最適です。例えば先ほどの例で「営業 vs 経理」の場合、売り逃しを無くそうと営業が頑張って頑張って在庫の積み増しを要求し、実際その通りにドンドン在庫が増えてしまったら、最後は在庫を調達する資金がかかり過ぎて会社「全体」が倒産してしまいます。「営業で売り逃しを無くす」この部分最適だけを追っても、所属している会社が倒産してしまっては意味がないでしょう。
同じように、「上司 vs 部下」も、生産性が低い会社は他社に負けて淘汰されてしまいます。「経営者 vs 社員」も残業代が負担になって倒産なんてことになったら働き口がなくなってしまいます。
「K-1」の問題もそうです。仮にここから感染が拡大して感染者・死者が爆発的に増加することになってしまったら、次回のイベント開催どころの話ではなくなるかもしれません。
ですので、目指すべきは「全体」。全体最適こそ目指すべき姿なのです。

全体最適を成し遂げるためには
ではどうしたら「全体最適」を目指せるのでしょうか?実はそのために、大事な言葉があるのでお伝えします。
どのような尺度で私を評価するのか教えてくれれば、どのように私が行動するか教えてあげましょう。もし不合理な尺度で私を評価するなら、私が不合理な行動をとったとしても、文句を言わないでください。
私もコンサルティングで使っている「TOC理論」で格言のように言われている言葉です。簡単にまとめると、全体最適を目指したいなら、「全体最適のための評価をしなければならない」ということになります。
先程の例の「営業 vs 経理」だったら、「売る」ことだけを評価にしていては、営業は「在庫を増やす」という会社全体にとって不合理な行動をとってしまいます。「在庫を増やさず(あるいは減らしながら)売る」これができた人を評価することにすれば、自ずとそうなるでしょう。
「上司 vs 部下」なら、3日で終わらせて、次に「3日で」と頼んだとして、それができなかったとしても大丈夫な仕組み、余裕を持つ。個人を怒らない。という感じです。
「経営者 vs 社員」なら、生産性を高めて儲かった分は必ず社員に賞与として還元するなどの「全体を見た評価」にすると、社員の行動が変わるでしょう。
「K-1」も評価という考え方は難しいですが、「評価される」ということは「イベントが存在し続けられる」ことに繋がります。そうであるならば、「開催しない」という意思決定をした時に「今後もイベントが続けられる状況」これを用意するのが全体のための「評価」と言えそうです。ネットでもよく言われていましたが、「損失を政府が補填する」というやり方も一つです。決して「K-1」という部分のために「損失を補填」するのではなく、日本全体を考えた補填ということになります。

まとめ
今回、「K-1」という大規模なイベントで起こった部分最適と全体最適の問題。遠く離れた場所で起こった問題のように思えますが、実際は普通の会社でも起こっているとても身近な問題なのです。
1人1人の部分では最適な行動なはずが、全体としては最適な行動にならない。いくつか例を挙げましたが、とても「あるある」な問題でしょう。放っておくと必ず部分最適に陥ります。
目指すべきは全体最適。例え部分が良かったとしても、全体がダメになってしまうと、結局その部分もダメになります。「K-1」も感染拡大で日本がダメになれば、これからの興行できなくなる可能性があるのですから。
そのためには結局重要なことは「評価」なのです。部分部分に「評価」させていると、全体を考えない不合理な「評価」になってしまいます。「全体」を考え、そこから導き出される「評価」を行う。これが全体最適を目指すためには必要不可欠です。
「K-1」という遠い世界のこと、とは思わずに、自分事として、自社の全体最適を目指していきましょう!
【PR】
現在、執筆に関する下記勉強会に参加しています。今回の記事はその課題の一貫として書きました。執筆を学ぶ勉強会・オンラインサロンです。対象は士業や専門家や会社員など働き方に関わらず、執筆について学びたい方が集まっています。今後正式スタート後には執筆に関するインプットとアウトプットを提供する場となっていくようです。現在準備室の段階で参加者を募集しています。参加は無料となっています。よろしければ覗いてみて下さい。
参加無料♪ ビジネスライティング勉強会・準備室https://www.facebook.com/groups/1106721649667633
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
