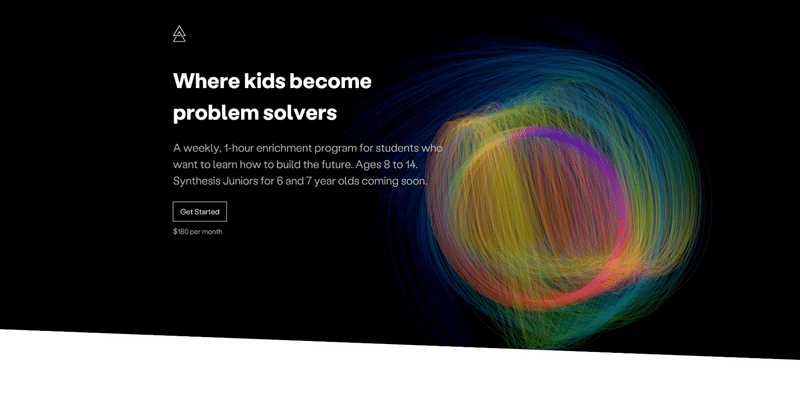
イーロン・マスクが作ったプライベートスクールをオンライン教育プログラムとして提供するSynthesis
先日たまたまTwitterで、Synthesis というオンライン教育プログラムを知りました。これはイーロン・マスクの思想が関わっているプログラムで、彼が始めたプライベートスクール Ad Astra が元になっています。
Ad Astra の概要とその特徴
2014年、イーロン・マスクは自分の子供たち向けのプライベートスクールとして、SpaceXキャンパス内に Ad Astra を作りました(そんな場所にある学校って単純にすごい)。このスクールについては日本ではほとんど記事や話題になっていないので、TeslaやSpaceX好きの中でも詳細を知っている人は少ないかもしれません。ちなみに Ad Astra はラテン語で to the stars(星に向かって)という意味。
元々ロサンゼルスの Mirman School という(ギフテッド向けの学校と言われているらしい)スクールに通わせていたイーロンの5人の子供(双子と三子)を含め、最初の年の Ad Astra の生徒数は8人のみ。イーロンの子供以外は全員SpaceX社員の子供で、教師はその Mirman School の元教員のJoshua Dahn氏。イーロンが彼を引き抜いて、Ad Astra を彼に任せたことからはじまったと言われています。なので彼は Ad Astra の共同創業者となります。
現在 Ad Astra の規模は30〜40人くらいになっているようですが、それでも非常に少人数制と言えます。そして入学条件などもあまり公にはなっておらず、SpaceXの社員の子供であっても全員が入れるというわけではないらしく、招待制との噂も。最近では限定的にSpaceX外にもオープンになる場合もあるようですが、入るのは至難の業と思われます。
Ad Astra の対象年齢、というか生徒の年齢は7〜14歳。ただし、一般的な学校のような学年には別れておらず、年齢でクラスやグループを分けることはないそうです。これはみんながみんな同じ年齢やタイミングで同じ分野に興味や関心がでるわけではない、というイーロンの考えから。
最近ではプライベートスクールだとこういった年齢や学年で分けることをしないスクールは増えてきているように思います。特に欧米では。
Ad Astra のカリキュラムの根幹は problem solving(問題解決)、ethical thinking(倫理的思考)、collaboration across both age and ability levels(年齢や能力を超えたコラボレーション)です。
一般的な学校とはかなり異なり、 サイエンス、数学、エンジニアリング、ロボット、AIなどに重点をおいた critical thinking を養い、問題解決能力を育むプログラムとなっているのが特徴。スポーツや音楽、外国語のクラスは一切なし。Astra という独自通貨まで使っているそうです。
ツールから教えるのではなく、実際に課題を与えてそこからツールやソリューションを見つけ出す、というのがイーロン流で、例えばエンジンを解体するという課題を与え、それに必要な道具ややり方を考えさせる、といった感じです。
このアプローチはイーロン以外でも提唱している教育者は増えているように思います。それは同時に、今の教育システムが全くの逆アプローチで、今後社会でより必要となるであろう問題解決能力を鍛えるのに適していないという捉え方もできます。
読んだ記事に載っていた Ad Astra のカリキュラムの一例は、AIがもし悪に寝返ったらどうすべきか、や、工場からの排水で汚染された湖について責任が一番大きいのは誰か、といった倫理感を伴った思考問題から、プログラミング、観測気球やバトルボットなどの製作など、「考える」こと、そして「エンジニアリング」に重点が置かれていて、まさにイーロンの思想が入っているなーという印象。そして生徒たちは一人ではなく、チームで課題に取り組むことが求められます。ここらへんもTeslaやSpaceXでチームを大切にするイーロンに通じる部分があります。
Astra Nova School
Ad Astra のカリキュラムをベースに、Ad Astra よりもオープンに開かれたスクールが Astra Nova です。Astra Nova はラテン語で New Star(新星)。このスクールは2016年スタートの非営利企業で、今は完全オンラインとなっています。
このスクールも創業者はJoshua Dahn氏で、以下の動画で彼が Astra Nova の特徴や方針について少し語っています。
まず、Astra Nova の特徴の一つは、生徒主体であるということ。Astra Nova では ClassDojo と共同で Conundrums(なぞなぞ)を作って、それを元に思考や議論のプログラムを行っていますが、その作成にも生徒が参加しており、いわば学校のカリキュラム作成に生徒が参加しているイメージ。
そしてWebサイトにも書かれていますが、行ったカリキュラムと生徒からのフィードバックをもとに毎年改良を加えるため、カリキュラムが毎年アップデートされます。従来の教育システムではなかなか考えられないフレキシブルさです。
Astra Nova でも Ad Astra 同様、problem solving や critical thinking に重点が置かれたカリキュラムとなっていて、ここは教育のコアの部分で統一されています。上の Conundrums からもわかる通り、与えられる課題はとても思考や議論を掻き立てるものばかりです。
現在 Astra Nova は完全オンラインということで、以下の3つのコースが提供されています。
1. フルタイムの完全コース
2. 毎週金曜日のみのコース
3. 毎月1回(土曜日)のスペシャルコース
Synthesis
Synthesis は Ad Astra や Astra Nova で取り入れられているゲーミフィケーションを取り入れたコラボレーション型課題解決プログラムをオンラインで提供する新しい取り組みで、2020年11月にスタート。
Synthesis はこのプログラム自体の名称でもあり、このオンラインサービスの名前でもあります。
現在の対象年齢は8〜14歳。(今後6 & 7歳向けのSynthesis Juniorsも追加予定。)
創業者はJosh Dahn氏と、ClassDojoのエンジニアだったChrisman Frank氏。Chrisman Frank氏が何度もJosh Dahn氏を説得して、ローンチに至ったようです。(イーロンはこの事業 / スタートアップには直接は関係していない模様。)
尚、Josh Dahn氏の現在のメインの仕事は依然として Astra Nova だとインタビューで語っていました。
Synthesisの教育哲学は Ad Astra、Astra Nova 同様、problem solving であることには変わりありません。それに加え、ゲーム感覚、オンライン、そして他人と協力 / コラボレートするという複数の特徴が加わっています。
そして Synthesis はできる生徒の能力をより伸ばすことにフォーカスしており、中間層やボトムの底上げなどに重きを置く従来の教育とはここが異なります。
要は、STEMに長けた生徒の能力をさらに伸ばし、将来イノベーションを起こす人数や可能性をあげよう、というミッションです。
現在のところは週一で、通常の学校教育やホームスクーリングの補完プログラムという位置付けですが、将来的には世界中から優秀な子供を見つけ出すトーナメント的な役割も見据えているとChrisman Frank氏はインタビューで語っています。上位1%の生徒にはさまざまな機会やリソースを与え、世界を変えるイノベーションを加速させる、という狙い。
月$180という価格ながら開始からたった数ヶ月ですでに1,000人以上の子供がSynthesisを使っており、ARRも〜$2Mと、エドテックスタートアップとしても普通にすごいトラクションと言えます。今後さらにスケールさせる予定ということで、注目です。
---
オンラインでの教育の限界や、その難しさが叫ばれる中、課題解決型の教育プログラムをオンラインで提供しているということはもちろん、チームコラボレーションを実現できていることも非常に魅力的だと感じました。オンラインでもやればできることを証明してくれているように思います。
最後に、Synthesis の共同創業者のChrisman Frank氏が、彼とJosh Dahn氏が実際に自分たちの子供に行っている教育内容をツイートしたものが以下です。課題解決とSTEMを合わせたこれからの教育の一つの形として、とても参考になると思いました。
Here's what Josh and I are doing for our own kids...
— Chrisman (@chrismanfrank) March 30, 2021
1/ Forest school 3-4 hrs/day
Wander in the woods or beach. 10-15 kids w/ a teacher or two. Socialize and observe ecosystems. Foster joie de vivre. Avoid spirit-crushing modern school environment.
