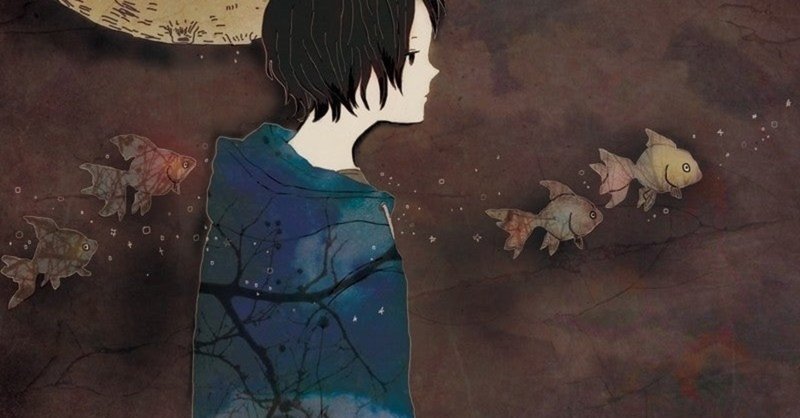
Photo by
tecteckpoo
115|「具体と抽象」読みました

具体と抽象の繰り返しで
世の中の変化は起こっていく
常にセットで考察
連携させた上で
計画と実行のバランスを使い分ける
不連続な変革期においては
→抽象度の高いレベルの議論
連続的な安定期には
→具体性の高い議論
永遠の議論の大部分は
「どのレベルで話をしているか」
という視点
変えること 変えざるべきこと を
抽象度に応じて切り分けることで
論点が明確になる
枝葉を切り捨てて幹を見る
最終的に何を実現したいか
抽象化は一度手にしたら手放せない
・抽象化の目的は「一を聞いて十を知る」
アナロジー(類推)
・「要するに何なのか」をまとめて話せる
要点をかいつまんで情報処理
・一度知ると戻れない「解釈」
例:方程式
抽象化だけでは生きにくい
・抽象化の概念は固定化されやすい性質があり
偏見や思い込みを生み出し判断が狂い
自然をありのままに眺めるのが困難
・抽象度という座標軸におけるスタンスが
人によって異なるために
人間同士のコミュニケーションに弊害が出る
・考えると行動できなくなる
結論
具体と抽象の繰り返しで
世の中の変化は起こっていく
常にセットで考察
連携させた上で
計画と実行のバランスを使い分ける
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
