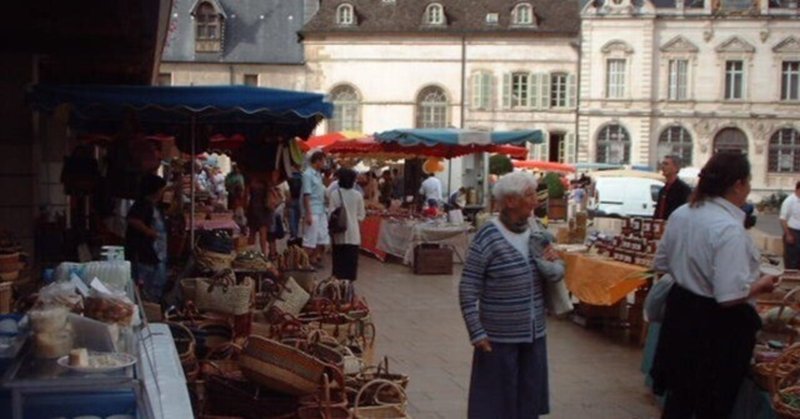
就活に不安を感じている皆さんへ④
③では就職試験が入学試験と異なること、そして面接が重要なポイントとなることをお話ししました。
今回は就活の下準備から会社選びのポイントについてお話しします。
「しようがないから会社員になる」???
大学生の中で3年生になるまでに、どのような企業を目指すか決めている人はあまり多くはありません。専門職を目指す人、例えば公務員、教員、医師、看護師、法曹関係、会計士、税理士、建築士などは、大学に入るときに方向性を定めて学部を選ぶ必要がありますので、目指す方向をきっちり定めているでしょう。
しかし大半の大学生は「しようがないから会社員にでもなるか」といって就活を始めます。つまり、ビジネスの世界に入るのは「つまらない人生を歩むこと」という風にとらえている学生が多いように思います。
それには原因があると思います。高校から大学に至るまで、経済社会のことを学び、見聞きする機会があまりないまま、就活時期を迎えてしまったからです。高校や大学の教員は会社員を経験してこなかった人が多いですから、おのずと生徒・学生に語り掛ける内容は、自分の生きてきた世界の中での関心事ということになってしまうのです。その話題には、業界や企業そして企業の中のいろいろな仕事のことは入ってきません。
学生がそれまでの人生で接してきた大人といえば、教師くらいしかいないわけですから、学生の視野がその方向に向いて来なかったのは仕方がないことなのかもしれません。
親が会社員である家庭は非常に多いわけですから、両親から会社での出来事を楽しいこととして聞いてきた子供は、会社員になることをポジティブに考えるようになると思います。しかし、家庭で嫌な上司の悪口や、仕事のつまらなさばかり聞かされると、子供は会社員というものを「いやな職業」という印象を持ってしまうのです。
私の父は高校教師でしたが、商業科の教師であり、戦後間もないころ、教師になる前にいろいろな会社に勤めた経験も持っていたので、「ビジネスは面白いもの」という印象を私に与えてくれました。私はそのおかげで、高校生になるとすぐに、国際ビジネスに従事することに憧れを抱くようになりました。
私は、断じてあなたに言います! 会社員は「つまらない職業」ではありません。
会社では、新入社員として入ると、先輩社員が教育係となって仕事のイロハを教えてくれます。1年もすると、結構一丁前の顧客対応ができてきて、自分でも自信が付いてきます。3年目くらいから後輩社員が入社してきて、教育係になるという場合も出てきます。6,7年目の社員は新入社員にとっては「大変良く仕事を知っていて、顧客の信頼もあり、人生の先輩として尊敬の目で見られる存在」となるのです。若手社員にとっては、公私ともに影響を受けやすい先輩なのです。
10年目くらいからは班長、係長や課長代理として、課を統括するような仕事が増えてきます。つまり、管理職としての修業を積む段階となるので、リーダーシップが問われるようになるのです。取引先の信頼はどんどん高まって、15年から20年めに課長というタイトルをもらう準備が進みます。
課長になったら「一国一城の主」です。課に課された職務を全うするために、部下に最大限実力発揮してもらって、会社に大きく貢献することが使命です。その分野では、「自分が会社をしょって立っている」などと自負心を持つようになるかもしれません。
「貢献度が高い」と経営陣が認めるようになると、部長あるいはさらに執行役員へと昇進していく道も拓けます。
現代では家庭や地域の中の役割も重要ですので、このような人生を送る際に、ワークライフバランスをうまく図りながら暮らす必要があります。このことは男女共通に言えることです。
意義深い人生をおくるために
どうしたら、会社員になることを「つまらない職業に就く」ことと思わないようになるでしょう。それには、就活に当たって自分の人生をプランしてみることです。
まず目標を設定します。50歳になった自分をイメージしてください。お金持ちになる。高い地位に就く。国際人になる。楽しい家庭を持つ。みんなから尊敬される。やりがいのある特定の職を持つ。大都会の中心で仕事をする。田舎で仕事をする。等々。
どれも魅力的な人生ですが、「これは外せない」というものを見極めながら優先順位を付けてみるのです。
次に、その優先順位に基づいた目標を達成するために、30歳および40歳で何をしているかをイメージしてみます。例えば、30歳で一人前の営業担当者になって800万円の収入を得ているとか、40歳で独立して事業を始めているとかです。
外国では(欧米・アジアに共通)、若者はそのような考えた方をしているように思います。日本のように「会社に就職する」という考え方ではなく、「何の専門家になるか」というのが就職ですから、文系の学生でも営業、経理、財務、人事、広報、物流など、明確な職業選択をします。従って大学に入るときにどの職業で生きていくかを決めて、それに合った学部・学科・研究室を選ぶのです。
日本の大学に通うあなたは、そのような考え方をすることなく、就活時期を迎えてしまったのかもしれません。しかし、今からでも遅くはありません。上に述べたような考え方をしてみて、まず人生をプランし、「会社」ではなく、自分がする「仕事」をイメージしてみてください。
営業に向いているか、内部の仕事である総務や経理か、人にかかわる人事か、会社を売り込む広報か、お金のマネージをする財務か、等々です。
大学で学んできた中で、興味が湧いたことを参考にするのもいいでしょう。自分の性格と相談するのもいいでしょう。
このように考えてくると、「就職試験に受かるかなあ」とびくびくして時を過ごすのではなく、「いつ自分に合った職業が見つかるかなあ」と楽しみに就活をするようになるでしょう。
会社選びはどうする
前述のように、会社を選ぶ前に自分がどのような仕事をしたいか、あるいはどのような職務に向いているかを考えるべきと強調しました。
それが明確になってきたら、次は業種を選ぶ番です。会社を狙い撃ちしても、入れるとは限りません。第一志望がだめなら同じ業種内の第二希望を狙うべきです。なぜなら、業種が異なると、志望動機や面接での応対が違ってくるからです。
実は業種を選ぶというのは結構難しいことです。昔は繊維産業、鉄鋼業、自動車産業、流通業、運輸業、ホテル業などと、企業はある業態を一途に追及するという形態でしたが、最近では、繊維会社が炭素繊維を使って自動車部品や産業用素材を作り、鉄鋼会社が環境ソリューション事業をし、自動車会社がまちづくりをしたりと、業種横断的になってきています。
ですから、自分の将来の仕事をプランする際に、多くの業種や企業をインターネットなどで調べて、自分が打ち込めるような仕事が、その中で見つけられるかどうか研究をする必要があります。
そして、「この会社が自分に向いている」と思ったら、更に深く調べて、自分がそこで活躍している姿をシミュレーションしてみるといいでしょう。
もちろん1社だけでなく、いくつかの会社に自分を当てはめてみて、選択肢を広くしておくべきです。
では今回はこのあたりで終わります。
次回はもっと具体的に、面接の受け方についてお話しします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
