
2020年ベストアルバム10選

・Jyoti/Mama, You Can Bet!
2020年を振り返ると世の殆どの人にとって良い報せより悪い報せ、悲しい報せの方が多かったのではないだろうか。それは音楽界においても例外ではなく、様々な訃報なども聞かれたが、個人的にはハル・ウィルナー逝去のニュースには驚かされた。
数多くの名盤をプロデュースしてきたウィルナーであるが、ウィリアム・S・バロウズやアレン・ギンズバーグといったビート作家による音楽的なリーディングアルバムの制作、あるいはルー・リードがエドガー・アラン・ポーにインスピレーションを受けて制作した「The Raven」における仕事等を鑑みると、音楽と文学の橋渡しとなる活躍をした人物であったと評価することもできるだろう。
そしてウィルナーと言えばやはりトリビュート・アルバムで、ニーノ・ロータ、クルト・ワイル、ディズニーの楽曲といった、メジャーな存在でありながら自分のような者からしてみればもう一つ真価を測り損ねていた音楽たちに、親しみやすくも新鮮な解釈が付与され、音楽的視野の拡張に大きく貢献してくれたものだった。
中でも白眉は、チャールズ・ミンガスへのトリビュートとなる1992年にリリースされた「Weird Nightmare: Meditations on Mingus」であったと認識している。
人種差別への激しい怒り、コンセプチュアルなアルバム形態、デューク・エリントン直系のスウィング感、映像喚起カあるアレンジ、そして太い音色のウッドベースといったミンガスの特徴を、意外性と幅広さのあるウィルナーならではの人脈を活かした上で、ミンガスのオリジナル楽曲を換骨奪胎しながらも深い愛情が溢れる、まさにトリビュートという名に相応しいアルバムだ。
そして2020年に最もミンガスへのトリビュートを感じさせられたのが本アルバム「Mama, You Can Bet!」だった。
Jyotiことジョージア・アン・マルドロウは1983年生まれでLAを中心に活動をしており、2006年にデビューして以来、平均すると毎年2枚以上のアルバムを出しているという多作っぷりの上、自ら作詞作曲をするのを始め、プロデュース、複数の楽器演奏までこなすマルチな才能を持つのだから恐れ入る。
とは言え、自分がこの人のことを知ったのは、2018年にBrainfeederからリリースされた「Overload」から。よく比較されるニーナ・シモンというよりはローラ・マヴーラ(もっともこの人も現代のニーナ・シモンなどと言われているが)に近い資質を感じさせるとともに、Brainfeederに所属する他のアーティストと同様に、黒人音楽の伝統に敬意を表した上でのハイブリッド感と現代性といった辺りに遅ればせながら感心させられた。
Jyoti名義としては7年ぶり3枚目となる本アルバムについて、ミンガスの直接的なカバー(リミックス)は⑥「Bemoanable Lady」と⑭「Fabus Foo(=Fables Of Faubus)」の2曲に留まるが、太いウッドベースに導かれる楽曲の数々=ジャズをベースに、ファンク、ヒップホップ、アフリカ音楽、ポスト・ロックなどをミックスする感覚、そしてアルバム・タイトルどおり母と女性に対するエンパワーメントなども含めての現代におけるミンガスへのトリビュートと解釈できるし、また、1979年にその名も「Mingus」というアルバムを出したジョニ・ミッチェルが今も現役だったらこのような音楽的アプローチを取っていたのではないか、などという想像も膨らむ。
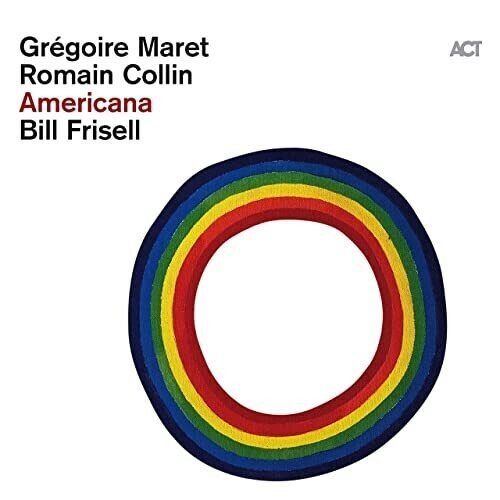
・Gregoire Maret, Romain Collin & Bill Frisell/Americana
先に挙げた「Weird Nightmare: Meditations on Mingus」の音楽面での支柱となったのが、ここ数年来、私的年間ベスト・アルバムの常連的存在であるとともに、繰り返し「道標的アーティスト」と位置付けてきたビル・フリゼールである。
2019年にOkehからBlue Noteへと移籍し、ペトラ・ヘイデンのボーカルをフィーチャーして制作された「Harmony」は、フリゼールがそれまで追求してきた歌心溢れるインタープレイとサウンドスケープの集大成的な傑作であり、当然年間ベスト・アルバム10枚にも選定した。
そして2020年にはBlue Note移籍後第2作目となる「Valentine」をリリース。ライブではずっと共演していたトーマス・モーガンとルディ・ロイストンによるトリオとしては初のスタジオ・アルバムとなる本作も勿論素晴らしかったが、ここではグレゴア・マレ、ロメイン・コリン、クラレンス・ペンとの共演による、その名もズバリ「Americana」を選定させてもらった。
数あるフリゼール関連のアルバムの中での最愛聴盤は1999年にリリースされた「Good Dog, Happy Man」なのだが、深い音色のアコースティック・ギター、独特なボリューム・コントロールを駆使するエレキ・ギターの真価はやはりアメリカーナというジャンルでこそ発揮されると認識しており、アルバム冒頭を飾る名曲「Rain,Rain」、ライ・クーダーと共演したスタンダード「Shenandoah」など、目を閉じると行ったこともないアメリカの雄大で豊穣な大地が目に浮かぶような楽曲が並ぶまさに名盤である。
一方、本アルバムのリーダー的存在となるハーモニカ奏者のグレゴア・マコは、ジミー・スコットとの共演などを経て、スティーヴ・コールマン、カサンドラ・ウィルソン、ミシェル・ンデゲオチェロといった所謂M-BASE系のアーティストとの共演も多いことから、インプロヴァイザーとしての確かな腕を持っていることが分かるし、郷愁誘うその音色はフリゼールのギターとの相性も抜群だ。
そして本アルバムであるが、そのタイトルや「Rain,Rain」のセルフ・カバーが収録されていることからもコンセプトは明確であろう。カバーの選曲に関してもダイアー・ストレイツ、グレン・キャンベル(ジミー・ウェッブ)など意外性がありながら、しっかりとこのバンドが目指すアメリカーナ・サウンドに昇華されていて感動的。
これまでアメリカーナというジャンルに興味がなかった方の入門盤としても最適だと思う。

・Ron Miles/Rainbow Sign
ベテランのコルネット・トランペット奏者であるロン・マイルスのことを知ったのは2003年にリリースされたジョー・ヘンリー「Tiny Voices」だった。
ジョーのアルバムの中でも屈指のヘビーさを持つ本作において、ロン・マイルスのトランペットはドン・バイロンのクラリネット・サックスとともに絶妙なアクセントを加え、名盤の誉れ高い「Scar」におけるオーネット・コールマンとはまた異なったアプローチでジャズ的な魅力を付与していた。
そのロン・マイルスにとって大きな契機となったと思われるのが2017年にMuzak/Yellowbirdからリリースされた「I Am a Man」だろう。
盟友フリゼールに加え、ブライアン・ブレイド、ジェイソン・モラン、トーマス・モーガンという超凄腕を揃え、最高の環境でレコーディングされたのはロン・マイルス流のブルーズをベースとした味わい深いインタープレイの数々。派手さはなくとも楽器間の会話という形容が相応しい、聴くほどに「このプレイとこのプレイも呼応しているのか」といった発見に溢れるアルバムで繰り返し聴いた。
その出来に手応えを感じたのだろう、同一メンバーによりレコーディングされたのが本アルバム「Rainbow Sign」。
曲作りに際して、父の介護と合わせてジェイムズ・ボールドウィンのエッセイ「The Fire Next Time(次は火だ)」の影響を強く受けているとのことで、これを機会に読もうとしたところ、翻訳本は既に廃刊され、中古市場でも相当な価格になっていたので残念ながら未読。
ともあれ、確実に前作「I Am a Man」の延長にありながらトーンはより内省的でメロディック。特に②「Queen Of The South」、③「Average」、⑤「The Rumor」辺りの楽曲及びインタープレイの美しさ、加えて、ブルーズ/バップの枠からスリリングに飛躍するジェイソン・モランのピアノは印象的であり、また、ブライアン・ブレイドのThe Fellowship Band名義の近作にも通ずる幽玄さをも併せ持つ。
そして、レコーディングに満足したフリゼールがBlue Noteの社長であるドン・ウォズに本作を聴かせることを進言し、まさしく同レーベルに相応しいアルバムとしてリリースされることとなった。

・The Nels Cline Singers/Share The Wealth
ネルス・クラインのBlue Note移籍第1作目の「Lovers」は、本人曰く構想25年以上、ジム・ホール、ギル・エヴァンス、ヘンリー・マンシーニなどの影響を受けた"ムード・ミュージック"集、移籍第2作目のジュリアン・ラージとの双頭ユニットとなる「Currents Constellations」は、⑤「Amenette」というタイトルも象徴的に、オーネット・コールマンのコンセプトを大胆に取り入れるなど、趣向を変えつつ絶好調ぶりを発揮してきたが、移籍第3作目となるネルス・クライン・シンガーズ名義での本アルバム「Share the Wealth」も例に漏れない。
その名義とは裏腹にヴォーカリストは不在ながら、ネルスのギターは歌い囁き咆哮し、ヴァーサタイルな面が最も際立つと言えるこのユニットには、スカーク(サックス)、ブライアン・マルセラ(キーボード)、トレヴァー・ダン(ベース)、スコット・アメンドラ(ドラム)、シロ・バプティスト(パーカッション)が名を連ねる。
興味深いのは、もともとはレコーディングしたジャム・セッションを素材をとして利用し、様々な加工をした上でリリースするプランであったのが、その素材自体があまりに出来がよかったので、そのままの状態でリリースしたという話。
まずはガル・コスタ(作曲はカエターノ・ヴェローゾ)の①「Segunda」から強烈。延々と続くGのコード上でソロを爆発させるコンセプトは、さしづめネルス流ブラジリアン・モードといったところだが、クイーカやブラジリアン・パーカッションが使用される楽曲も目立つことから、ブラジル音楽(MPB)が本アルバムの重要な要素となっていることは間違いないだろう。
加えて⑥「Princess Phone」、⑦「The Pleather Patrol」といった曲は、1960年代末から1970年代にかけてのマイルス・デイヴィスを意識したと思われるものが多分にあり、ネルスの激しいギターにもピート・コージーを彷彿とさせるものがある。
本アルバムで聴かせてくれた強烈な演奏とチャレンジングな姿勢が今後のWilcoにおいてどう反映されるのか、今年リリースされたジェフ・トゥイーディーのソロアルバムとは全く方向性が異なるだけにこちらも楽しみだ。

・Logan Ledger/Logan Ledger
ビル・フリゼール、ネルス・クラインとくれば、2019年に日本でも公開されたドキュメンタリー映画「カーマイン・ストリート・ギター」のことを思い出してしまうのだが、19世紀のNYに建築されたビルの廃材で特別なギターを制作する小さな工房と訪れる様々なギタリストとの会話からは音楽の持つ豊かさそのものが感じられ、また、フリゼールの弾く「Surfer Girl」、ジェフ・トゥイーディーへの贈り物となるギターをどれにしようかと迷うネルスのコメントなどは映画に絶妙なアクセントを与えてくれた。
そして同じく映画の中で印象的だったギタリストがマーク・リボーで、相変わらず上手いんだか下手なんだか分からないけど、とにかく味わい深いギターソロを堪能させてくれた。
比較的寡作だった2020年のリボーであるが、特に良かったのはカリフォルニア出身、現在はナッシュビルを拠点に活動しているSSWローガン・レジャーのデビュー・アルバムだった。
その制作体制は、リボーのほか、プロデューサー(そしてギターも弾いている)にT・ボーン・バーネット、ドラムにジェイ・ベルローズ、ベースにデニス・クロウチ、ペダル・スティール・ギターにラス・パールという鉄壁の布陣で、レコーディングはナッシュビルのHouse Of Blues Studiosで行われた。
肝心のローガン・レジャーの資質に関して言えば、エルヴィス・プレスリーの深みある声と節回し、ロイ・オービソンの白昼夢的な甘美さを合わせ持つボーカル・スタイルと、50年代ロックンロール、サーフ・ミュージックから初期The Whoを彷彿とさせる熱量、そしてオービソン或いはクリス・アイザックに対しデヴィッド・リンチが見出した不穏な妖しさが感じられるなどなかなかに一筋縄ではいかない。
リボーの演奏はトゥワンギー、フェイザーを駆使したブルージーなものが多く、また、長年組んでるベルローズの腰の据わったドラムとのアンサンブルも申し分ない。
因みにベルローズに関しては、T・ボーン・バーネット、ジョー・ヘンリーがプロデュースする作品にかなりの頻度で参加しているほか、2020年はジェフ・パーカー「Suite for Max Brown」に参加するなどジャンルを超えた活躍も目覚ましく、今後もこの人がクレジットされた作品を抑えるだけで名盤に巡り合う確率もかなり高くなるに違いない。

・The Haden Triplets/Family Songbook
2019年のベスト・アルバムに選定したフリゼールの「Harmony」とthat dog.の「Old LP」については奇妙な偶然があって、残念ながら2014年に亡くなってしまった名ベーシスト、チャーリー・ヘイデンの忘れ形見となる三つ子の姉妹のうち、ペトラが前者に、レイチェルとターニャが後者に参加し、両アルバムとも同日となる10月4日にリリースされた。
その三姉妹によるボーカル・ユニットが、その名もずばりヘイデン・トリプレッツで、もともとが音楽一家だったため、三人とも若いころから様々な形で音楽活動を続けていたらしいが、大きな転機となったのは、チャーリー・ヘイデンがアメリカーナに真正面から挑んだ2008年のアルバム「Family & Friends: Rambling Boy」だろう。
エルヴィス・コステロ、ロザンヌ・キャッシュ、ユニークなところでは(2006年にターニャと結婚している)ジャック・ブラックらが参加した本アルバムの中でも三姉妹のハーモニーの美しさは抜きんでており、それこそボズウェル・シスターズに匹敵すると言いたいほど。
そんな三姉妹のライブを見て感激し、プロデュースを申し込んだのがライ・クーダーで、2014年にアルバム「The Haden Triplets」でデビュー。幼少期から親しんでいたカントリーやブルー・グラスのスタンダード曲に加えてニック・ロウの「Raining Raining」のカバーなども含まれるが、ライ・クーダーのアメリカン・ルーツ・ミュージックに対する深い造詣溢れるプロダクションに彼女たちのハーモニーが加わると全てが独自の世界に染まっていくようであった。
そしてウディ・ジャクソンをプロデューサーに迎え、ビル・フリゼール、ジェイ・ベルローズ、そしてドン・ウォズまで参加するこのセカンド・アルバム「The Family Songbook」においてもそのハーモニーの美しさ、味わい深いアメリカーナ・サウンドは健在で、例えばカニエ・ウエストの「Say You Will」のカバー曲ですら完全に彼女たちの世界に仕立てあげられているのだから驚かされる。
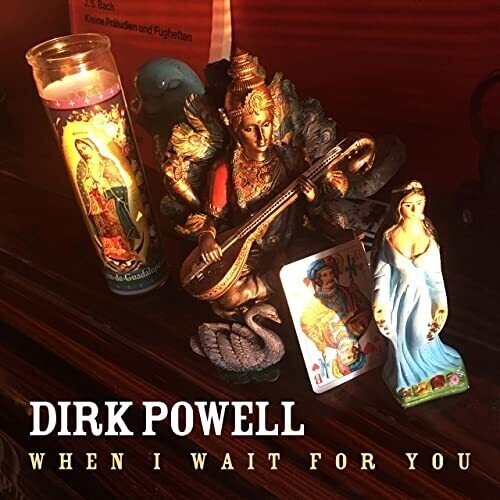
・Dirk Powell/When I Wait For You
ここ数年来最も注目しているボーカリストがリアノン・ギデンズなのだが、2015年にリリースされたソロ・アルバム第1作目「Tomorrow Is My Turn」のプロデューサーがT・ボーン・バーネット、第3作目「There Is No Other」のプロデューサーがジョー・ヘンリー、そして第2作目「Freedom Highway」のプロデューサーがダーク・パウエルである。
もともとブルー・グラスやケイジャン畑で活躍をしていたらしいパウエルであるが、初めて知ったのはエリック・クラプトンの2016年の秀作「I Still Do」においてアコーディオンとマンドリンでクレジットされていたことから。クラプトンが指向するブルーズにアーシーかつ軽やかさを与えるその演奏が即気に入ってしまい、調べるとそのマルチな才能を活かし、2000年代からロレッタ・リン、リンダ・ロンシュタット、アーマ・トーマスなど数々の大御所とも共演済みであったということで驚かされた。
パウエルとリアノンとはかなり縁深く、リアノン、レイラ・マッカラ、アリソン・ラッセル、アミシスト・キアによるユニットOur Native Daughtersでもプロデュースのほか、アコーディオン、バンジョー、ギター、ベースなど様々な楽器でサポートしているほか、本アルバム「When I Wait for You」の⑤「Say Old Playmate」では、二人が息の合ったデュエットを聴かせてくれている。
そしてリアノンが「There Is No Other」でアメリカーナのルーツとなるケルト・ミュージックを求めるかのようにアイルランドでレコーディングしたのに対し、本作はスコットランドでレコーディングされており、やはりケルト・ミュージック色の強い共時性を感じさせるものとなっている。
パウエルによる演奏の達者さは言うまでもなく、そのソングライティングのセンスも素晴らしく、モロにザ・バンドな④「The Bright Light of Day」などはご愛敬として、⑥「Let the Night Seize Me」、⑨「Jack of Hearts」はヒットしてもおかしくないようなポップなポテンシャルが感じられるし、ケイジャンのルーツとなるフランス語で歌われる⑧「Les Yeux de Rosalie」辺りも実に楽しく、ルーツ・ミュージックの熱心なファン以外にも十分アピールできる内容に仕上がっていると思う。

・Lera Lynn/On My Own
1984年生まれ、ナッシュビルを活動拠点とするSSWレラ・リンの名前が世に知られたのはT・ボーン・バーネットが音楽面でのプロデュースを担当したHBOのTVドラマ「True Detective」に参加したことが大きいだろう。
バーネットらしいアメリカン・ゴシック感溢れるプロダクションに憂いと透明感のあるレラ・リンのボーカル、自ら弾く(トレード・マーク的な)トゥワンギー・ギターとの相性は素晴らしく、その美しき不穏さに新世代のカウボーイ・ジャンキーズ(マーゴ・ティミンズ)と評されたのも宜なるかなと感心させられた。
「True Detective」以前のアルバムも遡って聴くと、安易にカントリー・ロックとカテゴライズするのも躊躇われる独特な曲が横溢するアルバムをコンスタントにリリースしてきたことが理解できたのだが、自分の中でその実力が決定的となったのが2018年の「Plays Well With Others」だ。
伝統的にカントリーはデュエットのフォームを取ることが多く、本アルバムに収められた全9曲でも大御所のロドニー・クロウェルほか、ジョン・ポール・ホワイト、同世代のアンドリュー・クームスやディラン・ルブランとのデュエットを聴かせてくれるが、相手が誰であれ全ての曲においてレラ・リンの歌唱力は圧倒的で、中でもJD・マクファーソンとの⑦「Nothing To Do With Your Love」におけるシャウトのかっこよさはその年に聴いたロックンロールにおけるハイライトと言えるほどであった。
そして本アルバム「On My Own」であるが、前作がデュエット・アルバムであったのことの反動か、作詞・作曲・歌唱はもちろんのこと、プロデュース、そして全ての楽器を自らこなす、まさにタイトルどおりのアルバムとなっている。
カントリー、ブルーズ、フォークを基調とするレラ・リン流ロックンロールは、よりパーソナル色強く内省的なトーンを帯び、特に③「So Far」、④「It Doesn't Matter」、⑧「Make You OK」、そして⑨「Isolation」といったスローな曲ではバッキングがシンプルな分、歌の上手さが際立ち、この時代ならではの向き合わなければならない孤独さが剥き出しの感情とともに伝わってくるようだ。
なお、クリスマスの時期に合わせて4曲入りEP集「Love One Another」もリリースされており、ジョニ・ミッチェルのカバー④「River」も素晴らしい出来なのでぜひ合わせて聴いていただきたい。

・Laura Veirs/My Echo
1973年生まれのポートランドを拠点にして活動をするSSWローラ・ヴェイアーズであるが、ソロ活動のほか、ニーコ・ケースとKD・ラングとのユニットである"ケース/ラング/ヴェアーズ"の一員と言った方が日本では通りがいいのだろうか?
ともあれ、ローラの結婚相手であったタッカー・マルティーヌがプロデュースほか、ドラム、ミックス、カバーデザイン等で全面協力した2018年の前作「The Lookout」はスフィアン・スティーヴンスとの共演といった話題性もあり、また、フォーク、カントリーをベースにしたソングライティングのセンス、幻想的なアレンジも冴えた見事な出来で、年間ベスト・アルバム10枚にも選定した。
そして本アルバム「My Echo」であるが、前作同様にタッカー・マルティーヌがプロデューサーを務めてはいるものの、制作過程で離婚し、それが作品内容にも大きく反映されているとインタビューでも語っている。必然的に全体的なトーンはメランコリックなものとなっているが、ローラの独特なビブラートのかかったボーカルの軽やかさもあって、音楽として必要以上に沈鬱なものとはなってはいない。
楽曲的にも従前どおりにシンプルなメロディと幻想的なアレンジで聴かせるものが多い中でのローラ流ボサノヴァ②「Another Space and Time」、多重コーラスの切れとプログラムのユニークさが際立つ③「Turquoise Walls」、マイナー・コードが切迫感を醸しロックンロール的カタルシスも溢れる⑥「Burn Too Bright」、ヴィヴラフォンも印象的でニール・ヤングを思い出さずにいられない⑩「Vapor Trails」などアルバムの構成としてもバラエティに富んでて飽きさせない作りになっている。
なお、本アルバムにもフリゼールがギターで参加している。

・Tessy Lou Williams/Tessy Lou Williams
最後はオースティンを拠点として活動するカントリー系SSWテッシー・ルー・ウィリアムズのデビュー・アルバムを。
もともとはモンタナの音楽一家で育ち、幼いころからカントリーに親しみ、約10年間はショットガン・スターズというバンドに在籍しながらソングライティングとライブ活動を地道に続けたいたとのこと。
デビュー・アルバムながら、プロデューサー/エンジニアについては、アリソン・クラウス、グレン・キャンベル、ボブ・シーガーなども手掛けてきたルーク・ウーテンが務め、ギターにブライアン・サットン、ペダル・スティールにマイク・ジョンソンら腕利きを揃えていることから、その業界内での期待の高さが窺えるというものだが、確かにどの曲取っても新人らしからぬ貫禄と完成度が漲っている。その上で、クリシェには陥らず、テッシー・ルーの伸びやかで透明感のある声もあって瑞々しさすら漂わせる辺りのバランスも絶妙だ。
小さな町のバーで酒を飲みながら愛おしい人に思いを馳せるといったロマンティックな歌詞、男女のコーラス含む伝統的なカントリーのフォーマットというのは自分の日常とは縁遠いところで鳴っているものかもしれないが、先に書いた「Americana」同様に、ここではない異風景を感じさせ、憧憬を掻き立ててくれる音楽であることに変わらない。
曲単位で言えば、マンドリンも軽快な③「Mountain Time in Memphis」、⑤「One More Night」、スライドギターの乾いた音色とメランコリックなメロディが印象的な⑥「Someone Lonely」、ワルツ風の⑩「Pathway of Teardrops」などは特に気に入っている。
これほどの歌唱力とソングライティング力があるのなら、例えばケイシー・マスグレイヴスのように路線を変えればメジャーな存在にもなり得るのではないかと思ったりもするのだが、伝統的なカントリーに対する深い愛情はこれからも不変であろうし、その中でのチャレンジなども楽しみに待っていたい。
