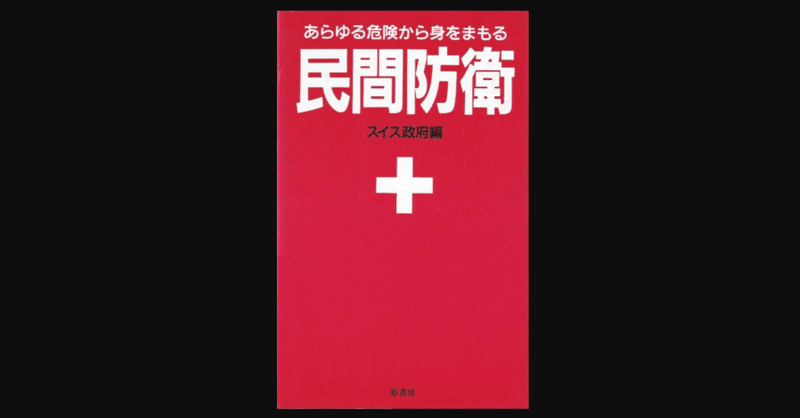
平和とは勝ち取るものであるとスイス政府は教えてくれる 『民間防衛』【読書ログ#133】
先日、デジタルリマスター『男はつらいよ』1作目を見て酒を飲む会というものに参加してきたのだけど、これがとても充実して良かった。
『男はつらいよ』がこんなに面白いなんて、全然知らなかった。
しかも、日本映画にすこぶる詳しい方々とご一緒ということで、酒を浴びながら、皆さまの映画への深い愛情も浴び、とても良い経験をした。
おかげさまで、ますます倍賞千恵子が好きになりました。
いやぁ、倍賞千恵子の破壊力たるや。あんな可憐な女性が日本に居たなんて、この作品をリアルタイムで楽しんだ方々がうらやましい。
実はわたくし、『男はつらいよ』シリーズは通しで見た事が無い非国民ででした。以前から、大の寅次郎ファンであるインド出身の友人に、「あなたは本当に日本人なのか」と言われるほど見ていない。
ただ単に見る機会が無かったという事なのだけど。
でも、もう大丈夫。1作目を4Kで堪能するなんて、これはもう立派なファンってことで大丈夫でしょう。大丈夫だ。残りの作品は、残りの人生の、残りの時間でコツコツとみていこう。楽しみが増えた。
あとどれくらいあるのかなとWikipediaなんかで調べてみたら『男はつらいよ』の映画シリーズは1969年の第一作目から始まり、主演の渥美清が亡くなり遺作となった四九作目まで続いた。
制作が絶えてから二七年が経過しているのだけど、その人気は衰える事が無く、とうとう公開から50年ということで、今年には五〇作目が公開されることになった。
いやぁすごい。歴史を感じる。
そう、そこで民間防衛な話になる。1969年に見覚えがあって、なにかなぁ、とおもっていたのだけど、ふとしたきっかけで思い出した、そう『民間防衛』がスイスで刊行され、全スイス国民に配られたのが1969年だった。
民間防衛とは、スイス政府が作成した、「ありとあらゆる脅威」から身を守るための心得本だ。
その内容の充実度、網羅性は目次を見れば一目瞭然だ。いや、一目には収まらない分量だ。
【内容目次】
平和
われわれは危険な状態にあるのだろうか
深く考えてみると
祖国
国の自由と国民それぞれの自由
国家がうまく機能するために
良心の自由
理想と現実
受諾できない解決方法
自由に決定すること
将来のことはわからない
全面戦争には全面防衛を
国土の防衛と女性
予備品の保存
民間防災の組織
避難所
民間防災体制における連絡
警報部隊
核兵器
生物兵器
化学兵器
堰堤の破壊
緊急持ち出し品
被災者の救援
消化活動
救助活動
救護班と応急手当
心理的な国土防衛
戦争の危険
燃料の統制、配給
民間防災合同演習
心理的な国土防衛
食料の割当、配給
地域防衛隊と軍事経済
軍隊の部分的動員
全面動員
連邦内閣に与えられた大権
徴発
沈黙すべきことを知る
民間自警団の配備
妨害工作とスパイ
死刑
配給
頑張ること
原爆による隣国の脅迫
放射能に対する防護
被監禁者と亡命者
危険が差し迫っている
警戒を倍加せよ
防衛
戦争
奇襲
国防軍と民間防災組織の活動開始
戦時国際法
最後まで頑張る
用心
戦いか、死か
戦争のもう一つの様相
敵は同調者を求めている
外国の宣伝の力
経済的戦争
革命闘争の道具
革命闘争の目標
破壊活動
政治生活の混乱
テロ・クーデター・外国の介入
レジスタンス(抵抗活動)
抵抗の権利
占領
抵抗活動の組織化
消極的抵抗
人々の権利
無益な怒り
宣伝と精神的抵抗
解放のための秘密の戦い
解放のための公然たる闘い
解放
知識のしおり
避難所の装備
医療衛生用品
救急用カバン
2週間分の必要物資
2ヶ月分の必要物資
だれが協力するか? どこで?
なんという充実っぷり。これが全国民に配られた。
都民であれば、東京都が全都民に配った『東京防災』がこれに近いのだろうけど、良しあしは別として、この迫力たるや。東京防災は足元にも及ばない情報量だ。良しあしは別としてね。
スイスという国の立ち位置や歴史を考えれば、これくらいの覚悟が必要なのかなとは思うのだけど、それにしてもすさまじい。近代史において、スイスという国の物理的な位置、政治的な位置を鑑みるに、平和を手に入れるというのは、すさまじい執念と努力の結果なのであろう。
さすがに50年前の本なので、内容は古い。現代のものに置き換えるべき項目もあるし、今の時代にあわせて読み替える必要がある箇所も多い。だが、細かいことはいいのだ、そういう事を求めて買う本ではないのだ。本書で何を得るのか、それは普段からの覚悟の持ち方だ。
本書をぱらぱらとめくってみて思うのは、普段からの心構えがいかに大事かということだ。何かあったとき、何を優先してまもるのか、保険を選ぶとき、住む場所を選ぶとき、車を選ぶとき、ニュースを見る時、隣人と付き合う時、判断基準をどこに置くか。
もちろん自分の命が大事だが、子どもが居るのであれば、自分よりも子供が生き残ってほしいと思う親も多いだろう。では、普段からどのような会話を親子でしておくのか、準備をしておくのか、常に意識し続ける必要がある。また、生き残ったうえで、保善したいものはあるか、土地も仕事もすてて流浪となった場合(東日本大震災では多くのかたがそうならざるを得ない状況となった)の生きる手段はあるのか。
本書は、紛争や戦争、テロ、パンデミック、災害からの身の守り方、放射線からの身の守り方、といったわかりやすい脅威への対応策などもありつつ、プロパガンダや扇動など、直接的ではない脅威にも対応する為のすべを知らせてくれる。
寅さんは、フーテンで身一つで旅をする。究極のミニマリストだ。口八丁で売りをやるから、必要なのは売り物だけ、これだってその辺の古本屋などから仕入れりゃいい。寅さんの生き方は、後先をかんがえていないようで、実はもっとも防衛力の高い生き方なのかもしれない。真似できないけど。
書店で見かけたら手に取ってみてください。
「それって有意義だねぇ」と言われるような事につかいます。
