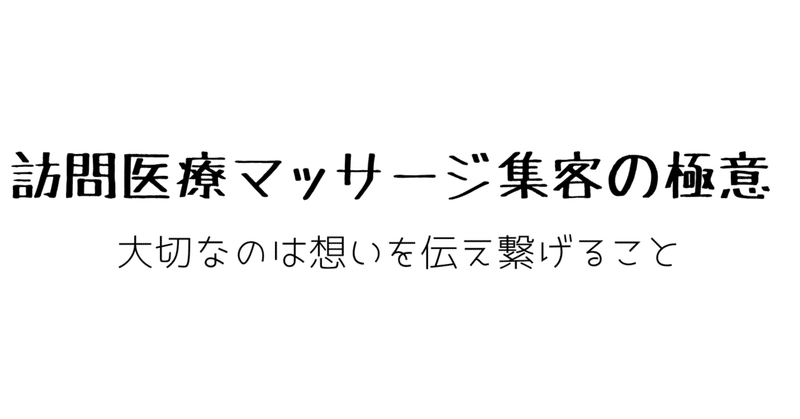
訪問医療マッサージ集客の極意ー営業資料は手作りで!
営業資料の作成
皆さんの訪問医療マッサージ事業所は、営業資料についてどれだけ工夫をされているでしょうか。世の中にはさまざまなキャッチコピー、わかりやすいパンフレット、昨今では紙で資料を作成せずにiPadを持参する営業担当者もいると聞きます。事業所によっては集客のためにさまざまな工夫をされていると思いますが、実はこの医療・介護・福祉の業界は部分的にはIT化が進められていますが、まだまだ「昭和の域」を脱していないアナログが幅を利かせているのが現状です。私が前職でコンサルティングに介入していた都市部の急性期病院ですら、地域の介護事業所とのやりとりにFAXを使用していました。病院がFAXを使用しているのですから、地域包括ケアシステムを構築するための必要な介護事業所や施設との連携においては、当然FAXになってしまいます。
こういう状況を見ていると、もしかしてFAXとはすごく画期的なのではないかなとも思ってしまいますが、20代や30代においてはFAXよりもメールが使いやすく、中にはメールもつかわずSNSの方が便利だと思っている人が多いでしょう。つまりこの医療・介護・福祉業界では、働く世代大きく使うツールが変化するということです。
医療・介護・福祉業界がFAXや手紙という紙を多く使用しているのには、この新しい時代を嫌う世代が多く残っているからです。これまでのやり方を変えられない多くの50代以上の人たちが、学ぼうという気持ちもなく、若い人たちに権限を与えずその場所に君臨し続けています。もちろん私の知っている50代の中には、この業界にいながらも変化を追及し考えることをやめない尊敬できる方が多くいます。
つまり地域の居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、そして医療機関にはこういった、まだまだ紙に慣れている世代が現役で働いているのです。それは訪問マッサージ事業所を運営する経営者やその営業担当者にとっては「集客のターゲット」になります。
この業界で事業展開をするのであれば、FAXや手紙は、強力なツールとして大いに活躍することを覚えておいてください。営業資料の使いどころは、営業担当者が居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、医療機関に持参する場合をメインとしてあり、足りない営業活動や知名度向上のためにFAXや手紙を使用します。ここでお伝えしたいのは営業資料の作成方法です。営業資料とは相手に届いたとき「見る」→「関心を持つ」→「よいと思う」→「記憶に留める」→「問い合わせる」ことを目的として作成しなければなりません。多くの事業所では、営業資料について安易に考えすぎています。そして自分の好みで作成しています。営業資料は業界を知り、届ける相手を知り、最終的にどうしてほしいのかということを考えながら作成しなければなりません。
ここからは私の経験から、この業界で相手の心に響く資料作成の五つのポイントをお伝えしたいと思います。
①手作り感を出す
資料というのは、その業界にあったものを作成しなければなりませんが「手作り感」というのは文字通り、完璧できれいな資料ではなく、自分たちで頑張って作成した努力が滲みでるような暖かみを感じられる資料のことです。皆さんの多くは業者に依頼し、会社のパンフレットのような資料を作成されていることでしょう。しかしそれでは人の心を掴むことができないのです。
訪問医療マッサージにおける最終的な顧客は、地域住民です。そこにたどり着くための中間地点に、居宅介護支援事業所のケアマネジャーや地域包括支援センターの相談員がいます。まずは彼らに知ってもらい、そしてここなら患者さんを紹介しても安心であると思ってもらう必要性があるのです。それには資料を読み込む前のファーストインプレッション(第一印象)が重要です。人は出会って2秒の見た目で判断されますが、まさにそれと同じ事がいえます。例えば、A4の用紙1枚の資料の制作を業者に依頼すると、勝手に郵便受けにポスティングされる「チラシ」っぽいイメージになります。このようなチラシというのは、相手に読む気力を失わせます。ファーストインプレッションで興味と関心を惹きつけるためには、「手作り感」が欠かせないのです。
ランチやディナーでお店に入ったとき、グランドメニューはもちろんですがスタッフが手書きしたお勧めメニューをついつい選んでしまったことはありませんか。また店頭にあるブラックボードに、スタッフが手書きしたイラストやお勧めメニューに関心を抱いたことはありませんか。「手作り感」には人の心を惹きつける人間味があるのです。完璧よりも少し欠点が見えると、人の気持ちを惹きつけることができます。
私たち訪問医療マッサージ事業所が営業に利用する資料も、基本的にはそれと同じ原理です。したがって営業資料や会社資料の制作を業者に任せにすることは、あまりお勧めできません。業者に制作を依頼するということは、大きな費用がかかりますす。また前回作った資料の「数字を1カ所だけ変更」したい場合でも、再度依頼する必要があります。また、一度の印刷部数も多いため変更前のものが大量に在庫として残ってしまうことにもなります。ですから基本的にはPowerPointやイラストレーターなど自作できるツールを活用し、時代や顧客のニーズに対応できるようにするとよいでしょう。最初は下手でも制作していればそれなりに上達します。
②顔写真を載せる
営業資料に顔写真を掲載することに抵抗のある人は多いです。個人情報の取り扱いが難しい時代ですから、自社の営業マンに強制することも難しいでしょう。しかし例えば自分が患者側だったとして、自分や両親の施術をお願いする場合に担当者の顔や名前などの情報があれば、一つの安心材料になると思いませんか。これもファーストインプレッションであると理解してください。
すべての情報発信は、相手がいることが前提なのです。いかにして主観的な要素を取り除き客観的な視点を持てるかなのです。私のクライアントでも、やはりその地域に長く住んでいるから顔写真を掲載することに抵抗があるといわれることもあります。その気持ちは十分理解できます。しかし、顔写真を掲載するだけで患者さんが安心してあなたの事業所に新規問い合わせするとしたらどうでしょうか。患者さんが増えれば売り上げも増える。売り上げがアップすれば事業が大きくなり、社員へ還元することができます。
どうしても抵抗があるという場合には、集合写真で個人が特定できないようにする、またはイラストで似顔絵を作成するという方法もあります。事業所全員のイラストを作成してみるのも「手作り感」からいうと、よいアイデアかもしれません。
なお開業がこれからの事業所で、営業資料に顔写真の掲載をしたい場合は、社員証などの顔写真が利用できるようにするのも一つです。社員証などを作る際に行う個人情報の利用目的を通知するときに、営業資料も記載しておくとよいかもしれません。昨今の詐欺など犯罪が多い中で、今後、競合が増えることも予想されます。各訪問医療マッサージ事業所が、どれだけ訪問する人間の事前情報を患者さんに届けられるかが勝負となると思います。しかしだからといって、従業員から顔写真と名前を掲載するのを拒否されている場合は、無理強いしてはいけません。同意してくれた人だけで進めていくようにしましょう。どんな場合でも法令順守を忘れてはなりません。
パレートの法則というのがあります。何を考えるにしてもほとんどの事象はこの法則に近い数字に当てはまるのです。組織というのは、常に2:6:2の比率で構成されています。最初の2割はとてもやる気のある人たちです。最後の2割はやる気のない人たちです。そして真ん中の6割の人たちはやる気がある方にも流れるし、やる気が無い方にも流れてしまうどっちつかずの人たちです。組織というのはほぼ確実にこのように構成されており、やる気のない人たちだけを辞めさせても6割の中からやる気のない人が生まれるのです。
むしろ、やる気のない人たちがいるからこそやる気のある2割がいるのだと思います。ですから、顔写真や個人情報を掲載することに対して非協力的な人がいる場合は、やる気のある2割とどっちでもない6割の人たちで進めていく外堀から埋める作戦しかありません。大多数が協力しているのに、自分たちだけ非協力的である愚かさを感じてもらい、そのうち協力してくれるように仕向けていくのです。それでも嫌だという人は労働組合的な考え方しかできない残念な人だと諦めるしかありません。
③実績を載せる
居宅介護支援事業所のケアマネジャーや地域包括の相談員、そこから紹介のあった患者さんから信用を得るにはやはり実績を掲載することです。人の信用とは悲しいもので、肩書やブランド、世の中で多く広まっているもの、自分がよく目にするものを真実であると思い込んでしまうものなのです。よく知らないけどなんとなくテレビで見たことがある人だから大丈夫だろうとか、駅でよく広告を見る企業だから安心だろうとか、とにかく私たちは知らないうちに情報に洗脳されているのです。
実際、中身はどうあれ大手企業の安全性や信用性が高いのはいうまでもありません。私が「木下の介護」で入居相談員として成績を上げられたのも半分以上は会社のブランドがあったからです。会社がCMを流して宣伝しホームページを作るなどして、広告費用をかけていたのです。それだけの武器がありながら、むしろ契約がとれない、問い合わせをもらえない営業担当者がいたとすれば、それは本人の問題かもしれません。
肩書、資格、ブランドこれらは日本で働く上ではとても有効です。日本はまだまだ資格社会ですから、個人や法人の知名度がなければ福祉や医療に関する国家資格を前面に押し出すことは戦略としては間違っていません。開業して間もない訪問医療マッサージ事業所であれば、持っている資格や自身の経験を前面に出して営業するしかありませんが、すでに開業されていればこれまでの施術件数、年齢層、月間問い合わせ件数、さらには患者さんの実際の施術風景、改善された事例など(これらを実績と呼びます)を、出し惜しみすることなく営業資料に掲載してください。
実績というものは、初対面の人でも安心してもらえる強い武器になります。私も会社を設立した当初、小さく始めたコンサルティング事業の実績を積み重ねるごとにパワーポイントで作成した会社概要に記載してきました。大きな実績がなくともよいのです。すでにある小さな実績を、どれだけ詳細に記載できるかというのがポイントになります。
課題を抱えた患者さんに対して、どのように施術計画を立て、どのように居宅介護支援事業所や地域包括支援センターと連携しているか。また、例えば患者さん本人の抱える課題を家族とも話し合い、施術を進めた結果「ありがとう」という言葉をもらったなどの事例をストーリーにして記載することも相手の心に響く方法です。数字でわかりやすく表記する方法もあれば、長々と患者さんの事例を作文のようにびっしり書くことも、実はマーケティングの手法の一つなのです。どれが相手に響くかという正解はないので、可能性のあるすべての方法を試してください。考えすぎて行動が止まってしまうよりも、とにかく実践し修正を繰り返していけば予想以上に短い期間で効果が得られるかもしれません。
④ターゲットを決める
営業資料とは、私たち営業担当者の分身です。営業担当者が居宅介護支援事業所や地域包括支援センターを訪問したとき、例えば担当者が不在で電話対応中の場合は、会って話をすることができません。そんなときに営業資料は大いに役に立つのです。
担当者に会うことができなくても、営業資料をポストに投函する、または事務の方に手渡ししておくことで私たちの代わりに営業をしてくれます。直接営業をしても中々会うことができないケアマネジャーの場合、むしろ営業資料が120%の役目を果たしてくれることは間違いありません。訪問営業とはただ訪問すればいいというものではなく、また1日20件訪問したからといって満足するものでもありません。営業活動の目的は成果を上げることです。その成果のプロセスとして欠かせないのは「問い合わせをもらう」という目標です。
営業資料を作成する上で重要な点は、誰に向けた資料なのかをはっきりさせるターゲティングです。今手もとにある資料を見てください。その資料は誰に向けた資料か、はっきりとわかるでしょうか。居宅介護支援事業所のケアマネジャーに向けたものですか。地域包括支援センターの相談員ですか。それとも診療所の医師や整形外科の医師でしょうか。地域に住む高齢者ご本人、高齢者と同居しているご家族の場合もありそうです。さて誰に向けた資料として制作したのでしょうか。もし今、皆さんの手もとにある資料が万人向けに制作している資料であれば、その資料は一度見直しをする必要があります。
前述した「トレードオフ」という概念は、何かを得るためには何かを捨てなければならないという考え方を指します。私はこの概念をケビン・メイニーの著書『トレードオフ―上質をとるか、手軽をとるか』(プレジデント社)で学ぶことができました。消費者というは、常に手軽なものを購入するか上質なものを購入するか選択しているといいます。企業が商品開発をするときにもこの考え方は重要となります。また、手軽なものか上質なものかというのは人の価値観に左右されるところが大きいというのは、前提条件としてあります。
例えば、音楽について考えてみてください。音楽を配信サイトからダウンロードすれば、手軽でかつ安価となりますが、コンサートに足を運ぶとなれば、それは上質ではないでしょうか。握り寿司なら、回転寿司は手軽にあたり、厳選されたネタを取り扱っている高級寿司店はもちろん上質となります。
私が最近ズレていると感じるのは100円ショップです。手軽で安くなんでも購入できる100円ショップにおいて、最近は500円以上の商品を取り扱っています。実際は500円で取り扱っている商品もそれ以外の店で買えばもしかすると1000円の商品かもしれません。しかしここに落とし穴が存在しています。
私たちにとって100円ショップはとにかく安いので例え購入した商品が壊れても100円だから仕方ないかという気持ちがあり、安価かつ手軽であるというイメージが強く根付いています。その中で500円以上の商品を取り扱うことは「手軽」というコンセプトに「上質」を加えてしまうことで、中途半端なイメージを消費者に植え付けてしまうのです。「100円という通常価格の5倍もする商品なのに壊れたらどうしよう」と感じるということです。同じメーカーが製造した商品でも、お洒落な雑貨店で販売するのと100円ショップで販売するのだと、おそらく雑貨店で購入する人のほうが多いでしょう。それは、人がブランドの持つイメージも一緒に購入しているからです。
理屈では同じ商品で価格も同じなら、どこで購入しても一緒です。しかし感情面で自分が満足できるかどうかは、別なのです。営業資料についても、まったく同じことがいえます。万人に受ける資料をつくろうとすると、ときとして中途半端になり間違った戦略を生み出してしまいます。
もう一度聞きます。皆さんの手もとにある資料は、誰に向けた資料ですか。いい方を変えるのであれば「誰に見てもらう」必要がありますか。マーケティングの概念は、営業資料に深く反映されているのです。
⑤生の声を載せる
人は感情の生き物であるというのは、皆さんもよくご存じのことだと思います。理屈で考えられる人は少なく、多くの人は感情で判断してしまいます。私たち事業を営む者として、人は感情で動くものであるということを常に心に留めておく必要があります。理屈で検討し選択をしなければならない場面でも、感情が邪魔するときがあります。営業資料を作成する場合、どこかで相手の心に訴えかける要素を盛り込む必要がありますので、ここでは、嫌でも感情面について触れないわけにはいきません。
そこで私がお勧めするのは「職員の生の声」という手法です。「生の声」というのは、資料用に作成したコメントではなく、書いた本人の本音が伺えるコメントである必要があります。私たちは生の声を活用したさまざまなチラシなどの販促物を目にしますが、見る側の多くは、ありきたりなコメントに飽きています。ですから、その人独自の生の声が必要となるのです。
コメントの内容は、なぜ訪問医療マッサージが必要なのか、どういった施術効果があるのか、医療業界や介護業界への想いについてなどで、書いてもらいたいことはたくさんあります。
もちろん、この生の声以外も前述の通りターゲットに合わせて掲載するのです。例えば、ターゲットがケアマネジャーであれば、訪問医療マッサージについてあまり知らない場合も多いので、訪問医療マッサージの歴史から現在に至るまでを掲載します。訪問医療マッサージの中で機能訓練を取り入れている事業所もあることから、介護保険の限度額を超えても医療保険である程度の機能訓練が対応できることを示すのも有効です。実は、まだまだ「訪問医療マッサージ」が医療保険なのか介護保険なのかというのも認知されてはいないのです。
人間は、言葉によってコミュニケーションを図るため、言葉で他者を感動させることや、傷つけることができます。言葉は武器であるといいますが、なるほどと納得せずにはいられません。本来は営業担当者が直接訪問したときに、すべてを伝えることができればいいのですが「伝える」ということは、実のところ一方的な行動です。本当は「伝わる」ことが重要なのです。伝わるためには相手に、聞く体制が整っていなければなりません。直接訪問しても、相手に話を聞く体制が整っていなければ半分も伝わることないでしょう。その点、営業資料に書かれているコメントが本心からのものであれば、それは心のこもった相手への手紙となります。相手に対するプレゼントであるといい換えることもできます。忙しいときにでも、心のこもったメッセージであれば、手を休め、足を止めて読んでくれるはずだと思うのです。
生の声をヒアリングするには、社内だけで実施するには少し難しいでしょう。そこには恥ずかしいという感情がつきまとい、本音を語ると会社や上司からの今後の自分への対応について、悪い方向へ行く可能性が懸念されます。誰もいない場所で自分自身で言葉を考えるか、もしくは第三者からのインタビューをしてもらうことが適切であると考えます。記載するコメントにはバリエーションがあったほうがいいでしょう。毎月一つの営業資料を作成するのであれば、年間で十二のコメントがあればいいのです。カテゴリーを決め、予めコメントをとっておけば、通常業務に支障をきたすことはありません。世の中に魔法の資料など存在しないのですが、その理由は時代と人の進歩であると考えます。トレンドといい換えてもいいかもしれません。人が時代をつくり、そしてトレンドが常に変化してく激しい時代の中で、どんなにプロフェッショナルなマーケターでも、長年同じ思考では流れに乗り遅れてしまいます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
