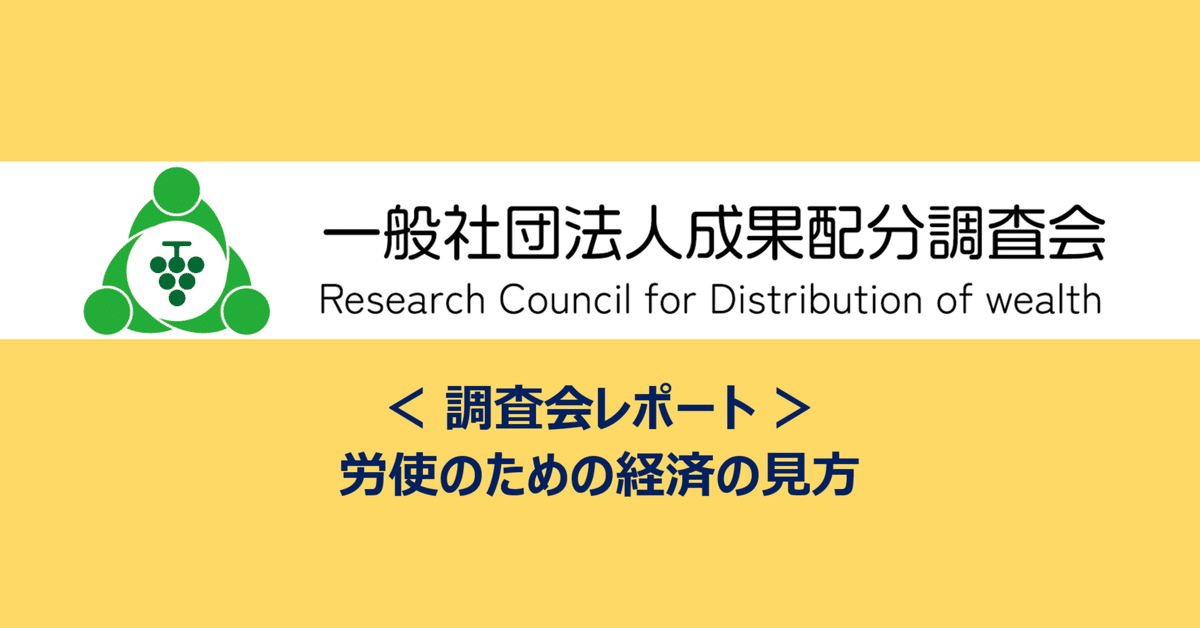
(2)オーソドックスな経済学とは①
2023年4月17日
一般社団法人成果配分調査会代表理事 浅井茂利
<情報のご利用に際してのご注意>
本稿の内容および執筆者の肩書は、原稿執筆当時のものです。
当会(一般社団法人成果配分調査会)は、提供する情報の内容に関し万全を期しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。この情報を利用したことにより利用者が被ったいかなる損害についても、当会および執筆者は一切責任を負いかねます。
なお、本稿の掲載内容を引用する際は、一般社団法人成果配分調査会によるものであることを明記してください。
このレポート「労使のための経済の見方」については、長期にわたって継続的にご利用いただけるよう、お知らせなしで随時、内容の補強・更新をして参ります。(訂正については、お知らせいたします)
*前号「(1)マスコミ報道と経済の見方」では、
・建設的な交渉・協議を行っていくためには、「経済の見方」について、労使が共通の基盤に立っている必要があること。
・マスコミ報道の情報は重要だが、鵜呑みにすべきではないこと。
・とくに、大新聞に書いてあるから、事実、真実に違いない、と思い込んでしまうことは、絶対に避けなくてはならないこと。
・1776年にアダム・スミスが『国富論』を発表して以来、革命や世界大戦、ハイパーインフレや金融危機、大恐慌など、人類がさまざまな経験を重ねる中で、オーソドックスな経済学が形成されていること。
・統制経済に親和的だったり、一部の読者を惹きつけるために、オーソドックスな見方とは異なる見方を提供する経済学者やエコノミストも存在するが、
・オーソドックスな経済学が100%正しいというつもりはないが、労働組合として、また経営者として経済情勢の判断や経済政策の是非を検討する場合には、まずは「オーソドックスな経済学の観点から見て、どうか」ということを出発点とすべきであること。
を指摘しています。わが国のマスコミなどでは、オーソドックスな経済学の見方が必ずしも優勢とは言えないので、世間の風潮に流されずに判断していくことがとくに重要です。
*本号では、オーソドックスな経済学とはどのようなものか、まずは、マンキューの「経済学の十大原理」について、ご紹介したいと思います。
代表的な経済学の教科書によってオーソドックスな経済学を学ぶことができる
*経済学の世界では、その時代ごとに代表的な教科書が存在します。
戦前:アルフレッド・マーシャル『経済学原理』
戦後:ポール・サムエルソン『経済学』
80年代:ルディガー・ドーンブッシュ、スタンレイ・フィッシャー『マクロ経済学』
現在:グレゴリー・マンキューの教科書
などです。
*マンキューの教科書は、邦訳版では、
・『マンキューマクロ経済学Ⅰ入門篇』、『マンキューマクロ経済学Ⅱ応用篇』
・『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』、『マンキュー経済学Ⅱマクロ編』
そして、『マンキュー経済学』を再構成した
・『マンキュー入門経済学』
という5冊が出版されています。
*このような代表的な教科書によって、オーソドックスな経済学を学ぶことができます。翻訳ではなく日本人が執筆したものとしては、伊藤元重『入門経済学』がオーソドックスな経済学を学ぶために適しているのではないかとと思います。
ミクロ経済学とマクロ経済学
*『マンキュー経済学』は「ミクロ編」、「マクロ編」となっていますが、
ミクロ経済学:家計や企業行動、労働者の行動などに関する経済学
マクロ経済学:国全体の供給と需要、物価、雇用、貿易、財政、金融などに関する経済学
です。マクロ経済学のほうがなじみやすく、サムエルソンの教科書では「マクロ → ミクロ」の順番でしたが、マンキューの教科書では「ミクロの意思決定を考慮せずにマクロ経済の発展を理解することは不可能」ということから、「ミクロ → マクロ」の順番となっています。ちなみに「労働経済学」は、ミクロ、マクロの両方の分野を含んでいます。
*なお、ミクロ経済学では企業行動に関する分析を行っているわけですが、だからといって、企業はミクロ経済学に則った行動をとればよいかというと、それはまた別問題です。ミクロ経済学では、「企業の目的は利潤を最大化することである。利潤は総収入から総費用を差し引いたものである」とされていますが、多くの企業がめざしているのは、意識されているかどうかはともかく、「企業の永続的な発展」だと思います。企業の永続的な発展のためには、利潤を生みだしていかなくてはなりませんが、利潤を最大化すれば、企業の永続的な発展が図れるわけではありません。現実の企業経営においてその知見を参考にすべきは、ミクロ経済学ではなく経営学です。
*もちろん、ミクロ経済学が役に立たないわけではなく、企業行動のルールや企業に特定の行動を促す仕組み、たとえば独占禁止法であるとか、温室効果ガス削減に向けた企業へのインセンティブのあり方であるとか、そうしたものを形成していくためには、ミクロ経済学の知見は欠かせません。
マンキューの「経済学の十大原理」
*マンキューは、次のような10項目を「経済学の十大原理」として掲げています。
1.人々はどのように意思決定するか
第1原理:人々はトレードオフ(相反する関係)に直面している
第2原理:あるものの費用は、それを得るために放棄したものの価値である
第3原理:合理的な人々は限界原理に基づいて考える
第4原理:人々はさまざまなインセンティブ(誘因)に反応する
2.人々はどのように影響しあうのか
第5原理:交易(取引)はすべての人々をより豊かにする
第6原理:通常、市場は経済活動を組織する良策である
第7原理:政府が市場のもたらす成果を改善できることもある
3.経済は全体としてどのように動いているか
第8原理:一国の生活水準は、財・サービスの生産能力に依存している
第9原理:政府が紙幣を印刷しすぎると、物価が上昇する
第10原理:社会は、インフレと失業の短期的なトレードオフに直面している
*「経済学の十大原理」について、詳細は『マンキュー経済学Ⅰミクロ編』、または『マンキュー入門経済学』を読んでいただきたいと思いますが、筆者なりに解説すると、以下のようになります。
第1原理:人々はトレードオフ(相反する関係)に直面している
第2原理:あるものの費用は、それを得るために放棄したものの価値である
*米国には、”There ain't no such thing as a free lunch.(無料のランチなんて在るわけない)”という言葉があります。酒を飲めば昼食はただ、という酒場に由来しているとのことで、昼食代は飲み代に含まれているぞ、という意味です。
*何かを得るためには、別の何かをあきらめなければならない、というのがトレードオフです。ある問題に対して夢のような解決策が提案されていたとしても、費用や弊害が必ず隠されているはずで、その解決策による効果と費用・弊害とを比較考量して、実行するかどうかを判断していかなくてはなりません。
*費用というのは、単に購入価格を意味するわけではありません。マンキューが例としてあげているのが、大学進学の費用です。大学に支払う入学金や授業料、教科書代などだけが大学進学の費用ではなく、大学に進学しなければ稼ぐことができたはずの所得も、大学進学の費用ということになります。衣食住の生計費は、大学進学をしたために多く必要となった分のみ、大学進学の費用となります。
第3原理:合理的な人々は限界原理に基づいて考える
*限界原理とは、追加の行動で得られる効果と費用の関係、と言えると思います。喫茶店においしいコーヒーを飲みにいったとします。価格が500円であれば、500円出して1杯飲むわけですが、飲み終わって、「もう1杯飲みたいかな」と思うかもしれません。しかしながら、すでにある程度は満足しているので、もう500円出す気にはならない、ということがあると思います。その時、メニューに「おかわり200円」とあれば、「200円なら飲もうか」ということになるかもしれません。
*客のほうからすると、2杯目には500円分の満足はないけれど、200円を上回る満足は得られると判断しているわけです。一方、店のほうは、おかわりによって追加的に発生する費用が200円を下回っていれば、利益を得ることができます。「おかわり200円」は客にも店にも得になる、こうした考え方が限界原理です。もし、空席待ちの人がたくさんいて、1杯飲んだ客が早く出て行ってくれれば、次の客が500円で1杯目を飲んでくれるという場合には、「おかわり200円」という価格設定は、店にとって合理的ではありません。
第4原理:人々はさまざまなインセンティブ(誘因)に反応する
*インセンティブについては、説明の必要はないかもしれませんが、注意すべきなのは、インセンティブによって、意図した結果が生まれるとは限らない、ということです。たとえば、企業で若年層のモチベーションを高めるために、いわゆる年功的な賃金カーブをフラット化する、ということが行われたとします。新卒入社後、まもなく基本賃金が50万円くらいになり、あとは実力次第、というような賃金体系であれば、モチベーションは高まるかもしれません。しかしながら、若年層の賃金水準が世間相場よりもちょっと高い程度であれば、賃金カーブのフラット化は、若年層の将来不安を招き、モチベーションを下げることになるかもしれません。中高年層になった時に必要な生計費を確保できるという前提がなければ、賃金のフラット化はモチベーション向上につながりません。
第5原理:交易(取引)はすべての人々をより豊かにする
*この原理については、「分業」と「比較優位」というふたつの考え方が関わっています。
*少し前のことですが、必要なものすべての自給をめざして努力していた男が、結局はあきらめて、自給できたのは電力だけだった、というハウスメーカーのCMがありました。すべてを自給しようとすると費用は莫大になりますし、そもそも能力的、時間的に作れるものは限定されてしまいます。各人がそれぞれ特定の職業に就いて分業を行い、生産した商品・サービスを取引し合うことによって、みんなが豊かな生活を送れるようになるわけです。これが分業という考え方です。国と国との交易も同様で、無理に自国で生産しなくても、安く生産できる国から輸入するほうが、生活は豊かになります。
*また、A国とB国というふたつの国で、それぞれ働いている人が100人いて、自動車とコメだけを作っているとします。1年間の生産量が、
A国:自動車が60人で100台、コメが40人で100トン
B国:自動車が60人で50台、コメが40人で80トン
したがって、
両国合計:自動車が120人で150台、コメが80人で180トン
であるとします。
*自動車もコメも生産量を左右するのは労働力だけ、と仮定した上で、もしA国でコメの生産をやめて全員が自動車を生産し、B国で自動車の生産をやめてコメの生産に特化したとすると、
A国:自動車が100人で167台、コメが0人で0トン
B国:自動車が0人で0台、コメが100人で200トン
両国合計:自動車が100人で167台、コメが100人で200トン
となります。自動車もコメもA国のほうが生産性が高いのですが、A国は自動車、B国はコメに特化したほうが、両国をあわせた生産量が多くなりますので、A国とB国で交易を行えば、両国とも生活水準が向上するわけです。
*なぜこうなるのかというと、A国では、最初の状態から自動車生産を1台増やすために、1.5トンのコメが生産できなくなるだけですが、B国では、2.
4トンのコメが生産できなくなってしまいます。一方、コメの生産を1トン増やすために、A国では、0.7台の自動車が生産できなくなりますが、B国では、0.4台にすぎません。A国では自動車、B国ではコメの生産に特化したほうが、「それを得るために放棄したもの」が少ないわけです。これが比較優位という考え方です。
*付加価値の高い分野で比較優位を持っていたほうが国民生活は豊かになるので、そうした分野に対する支援策は、国際ルールの範囲内であれば、ありうるかもしれません。しかしながら、そうした支援策は、途上国では往々にして、産業の高度化や国民生活の向上に結びつかず、単に国内で独占的に事業を行っている地元財閥に一層の利益をもたらすだけ、ということになりかねないので、注意が必要です。途上国の産業を育成し、国民生活を豊かにするのは、(一般的なイメージとは異なるかもしれませんが)やはり多国籍企業の進出であり、そのためには、交易のしやすい環境である必要があります。
*食料やエネルギーについては、食料安全保障、エネルギー安全保障の面から国内自給を促進するため、輸入に高関税が課されたり、輸入制限が行われたり、国内産業に補助金が与えられたりしている場合があります。これについては、
・関税や輸入制限によって外国産の安いものを購入できない場合には、国内自給のための費用を消費者が負担していることになる。
・自国で市場を開放していない場合には、当然、相手国の市場も閉ざされてしまうので、国内の輸出産業に負担を強いている。
・補助金の場合には、費用は納税者が負担している。
・食料については、国内が不作となる可能性もあり、入手先を多様化していることが、結局、安全保障につながるという面もある。
ということを意識している必要があります。
第6原理:通常、市場は経済活動を組織する良策である
第7原理:政府が市場のもたらす成果を改善できることもある
*統制経済の下では、何を生産するか、それをどう配分するかは政府が決定に強く関与します。一方、市場経済において、何を生産するか、どう配分するかをコントロールするのは「価格」です。
*活用できる資源が限られている中で、生産者が得られる満足と消費者が得られる満足を最大にするために、市場経済では、無数の生産者や消費者によって形成される価格を通じて、マッチングが行われます。統制経済の下で同じ状態を実現しようとすれば、政府がすべての商品・サービスの生産費用と、すべての個人個人のニーズを掌握する必要がありますが、そんなことが不可能なのは明らかです。
*ただし、前号で触れたとおり、市場経済が有効に機能するためには、市場経済に参加する者の対等性を確保する必要があります。そのためのルールや保障が不可欠であり、それは政府の仕事です。
*市場において、需要不足・供給力過剰が生じている場合、政府が投資を行うことによって、そのギャップを解消することができます。しかしながら、そうした政府による景気刺激は常態化しがちで、その結果、政府頼みの経済体質となって、民間経済の活力を削いだり、民間投資を圧迫したりする可能性があることに留意する必要があります。
第8原理:一国の生活水準は、財・サービスの生産能力に依存している
*これについては、とくに説明の必要はないと思いますが、日本においてバブル崩壊以降、問題となっているのは、財・サービスの生産能力に対し、需要が追いついておらず、そのために生産能力の増強も行われにくい、ということだと思います。
第9原理:政府が紙幣を印刷しすぎると、物価が上昇する
第10原理:社会は、インフレと失業の短期的なトレードオフに直面している*「政府が紙幣を印刷する」というのは象徴的な表現であって、具体的には、政府が発行し民間が保有している国債を、中央銀行(日銀)が買い取ることによって、市中に資金を供給する、ということになります。
*経済の成長力に見合った資金よりも多くの資金が供給されれば、物価は上昇します。逆に、成長力に見合った資金が供給されなければ、物価は下落します。
*物価変動の要因については、日本では、オーソドックスではない経済学が優勢のように見えます。白川日銀の時代は、わが国の成長力に見合った資金が日銀から供給されなかったので、デフレが続きましたが、この間、「人口が減少しているから、少子社会だからデフレになる」といった「呪術的(ブードゥー)経済学」のような説を唱える人もいました。
*黒田日銀の量的・質的金融緩和により、少なくともデフレの状態が解消されたことは間違いありません。「2%」という物価目標に関しては、確かに「2.0%」には届きませんでしたが、2013年末から2014年の前半には、消費税率引き上げ分を除いても1%台後半の上昇率となっていましたので、四捨五入すれば「2%」の目標に達していた、と判断してもよいと思います。
*その後、日銀が金融緩和の縮小に転じたため、物価上昇率は鈍化してしまいましたが、白川日銀時代は年度ベースで5年間のうち4年間で物価上昇率がマイナスとなったのに対し、黒田日銀時代は10年間のうち2年間(2016年度のマイナス0.1%と2020年度のマイナス0.2%)ですから、まったく様変わりであったといえます。
*資源価格の高騰により、世界各国で物価が大幅に上昇しています。こうした「コストプッシュインフレ」の場合には、物価の上昇は本来、一時的なものになるはずですが、今回はコストプッシュ要因が複合的に続いているため、物価の上昇も長引いています。
*コストプッシュインフレに対して、金融引き締め、すなわち需要の削減で対抗するのは、本来、悪手です。ただ、ウクライナ情勢が膠着し、産油国などに対する増産要請も成功していませんので、物価上昇率を鈍化させるためには、金融引き締めによって需要を削減せざるを得ません。需要を削減するので、当然、雇用にも影響が出てくることになります。
*日本では、金融緩和はすでに終了していると思われますが、まだ「金融引き締め」には至っていないので、景気後退、失業増という状況にはなっていません。米国が金融引き締めを行い、日本が行っていなければ、日本に比べ米国の金利が相対的に高くなり、ドルで運用したほうが儲かるので、円売・ドル買が進み、為替は円安方向に向かいます。円安は輸入品価格が上昇するので、物価上昇要因のひとつではありますが、逆に、わが国の物価上昇率が低いために円安になっていると言えます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
