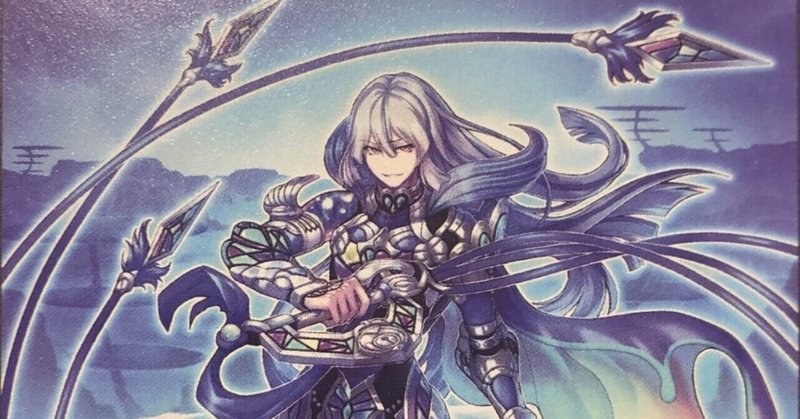
ティアラメンツ 雑感
日本選手権エリア代表決定戦で使用したティアラメンツです。

ネクストプレイ杯で使用したリストの解説記事です。
よろしければ、こちらもご参照ください。
目指す盤面
基本的には《ティアラメンツ・キトカロス》+《壱世壊に軋む爪音》+手札誘発、《烙印融合》が絡む場合は加えて《氷剣竜ミラジェイド》です。
トーナメントシーンの大半を占める【スプライト】に対しては、フィールドに送り込まれるモンスターを徹底的に妨害、後続とアドバンテージを確保し早期決着を目指します。
《デスピアの道化アルベル》
《烙印融合》のパワーは健在で、発動に成功すれば大きなアドバンテージの確保に繋がります。
《深淵竜アルバ・レナトゥス》の存在から《氷剣竜ミラジェイド》の効果を発動することで《烙印融合》以外にも《融合派兵》をサーチできます。
そのため、《烙印融合》の発動=返しのターン以降でのティアラメンツの動きも狙えます。
また、このカードを採用するメリットとして、メインギミック内で《沼地のドロゴン》を融合召喚できることから、サイド後に一定数採用が見られる《月女神の鏃》のケアも無理なくできます。
1.《デスピアの道化アルベル》召喚、《烙印融合》サーチ。
2.《烙印融合》発動、《アルバスの落胤》と闇属性ティアラメンツモンスターAを墓地へ送り、《神炎竜ルベリオン》を融合召喚。
3.《神炎竜ルベリオン》と《アルバスの落胤》で《氷剣竜ミラジェイド》、ティアラメンツモンスターAと《デスピアの道化アルベル》で《沼地のドロゴン》をそれぞれ融合召喚。
4.相手スタンバイフェイズに《沼地のドロゴン》効果。自身を闇属性に変更。
ネクストプレイ杯で使用したリストでは、代わりに《絶海のマーレ》を採用していたためこの動きを目指すことはほぼできませんでしたが、《氷剣竜ミラジェイド》の成立+ティアラメンツの動きだけでなく、メタカードへの対応も柔軟に狙えることから召喚権はこのカードに使いたいところです。
一方、安定性の向上を図るために《烙印開幕》まで採用すると手札誘発との噛み合いが悪いだけでなく、《神炎竜ルベリオン》の効果による手札コストと合わせてアドバンテージの損失が大きいため採用には至りませんでした。
※《氷剣竜ミラジェイド》の成立を目的とするならば、これらに繋がるカードへのアクセス札を1枚でも多く採用するべきだったので、手札コストの事を考慮しても採用するべきだったなと思います。
《融合派兵》
召喚権を《デスピアの道化アルベル》に使用するのであれば、ティアラメンツへのアクセスは別の方法に頼る必要があります。
先述で軽く触れた《烙印開幕》と違い、手札コストを必要しない、《烙印融合》と制約がほぼ被っていることを考慮すると最大値投入しても問題ないと判断しました。
また、後攻時において《アルバスの落胤》を特殊召喚することで、《烙印融合》が絡まなくても《氷剣竜ミラジェイド》を融合召喚することも可能です。
※その他にも《サイバー・ドラゴン》《キメラテック・フォートレス・ドラゴン》《キメラテック・メガフリート・ドラゴン》を採用すると、仮想敵とは離れますが、【@イグニスター】からリンク召喚される《ジ・アライバル・サイバース@イグニスター》の処理がしやすくなります。
《月の書》
《ティアラメンツ・レイノハート》や《デスピアの道化アルベル》といったモンスターへの《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》をケアできます。
他にも【スプライト】対面において、フィールドに送り込まれたモンスターへの妨害として機能します。
そのため、先攻用カードとしての質は非常に高いのが利点ですが、【スプライト】側のサイドデッキで採用率の高い《ハーピィの羽根帚》《ライトニング・ストーム》に弱いことから、妨害として考えた場合にメイン戦でしか機能しないことが多いため今後の採用は要検討です。
闇属性ティアラメンツモンスター
最低限の動きを目的とするならば1種類の採用で事足ります。
しかし、ティアラメンツモンスターの墓地効果を《D.D.クロウ》や《墓穴の指名者》、《屋敷わらし》といったメタカードで妨害された場合、《烙印融合》を使用しない限り《壱世壊に軋む爪音》だけでなく2枚目以降の《ティアラメンツ・レイノハート》等も役割を失います。
そのため、妨害のケアを考慮すると最低2種類は必要です。
3種類目を採用するメリットとしては、上記の妨害をより重く考えた場合やそれぞれのティアラメンツモンスターの効果による期待値を上げられる点です。
また、1種類素引きしている時に限りますが、《ティアラメンツ・キトカロス》+《壱世壊に軋む爪音》の動きが成立している場合の選択肢が広がります。
1.《壱世壊に軋む爪音》発動、《ティアラメンツ・レイノハート》を墓地へ送る。
2.《ティアラメンツ・レイノハート》効果、自身を蘇生し手札のティアラメンツモンスターAを墓地へ送る。
3.《ティアラメンツ・レイノハート》と墓地へ送ったティアラメンツモンスターAの効果をそれぞれ発動、《ティアラメンツ・キトカロス》Bの融合召喚とティアラメンツモンスターBを墓地へ送る。
この時点で、フィールドの《ティアラメンツ・キトカロス》B、墓地のティアラメンツモンスターBの効果が待機している状態です。
《ティアラメンツ・キトカロス》Bの効果で後続の《ティアラメンツ・レイノハート》をサーチしつつ、ティアラメンツモンスターBの効果で《捕食植物ドラゴスタペリア》の融合召喚ができます。
また、《ティアラメンツ・キトカロス》Bの効果でティアラメンツモンスターCを墓地へ送ることで《捕食植物ドラゴスタペリア》の2体目の成立も狙えます。
これは主に《幽鬼うさぎ》に対するケアとして有効です。
ただ、この動き自体が《増殖するG》を重く受けてしまう点を考慮すると現実的とは言いにくく、2種類あれば上記の動きは成立するため過剰な選択でした。
《赫灼竜マスカレイド》
《デスピアの道化アルベル》初動で《烙印融合》を発動した場合の選択肢で、対【エルドリッチ】を想定しています。
この対面において《捕食植物ドラゴスタペリア》が強くないことから、先手後手問わずシステムモンスターとして重宝します。
特に《沼地のドロゴン》とフィールドに存在することで《黄金卿エルドリッチ》による除去ができないため除去手段が限られます。
罠による突破を試みようならその後のライフレースで優位に立てる見込みがあります。
《クロノダイバー・リダン》《天霆號アーゼウス》
前者は妨害の貫通、後者は高性能の盤面除去です。
《ティアラメンツ・シェイレーン》が絡まない限り、この2枚を使用することはほとんどありませんが、一度フィールドに出てしまえばほぼ毎ターン自身を除外できることから除去が困難になります。
《クロノダイバー・リダン》は効果で素材を取り除くため、素材として使用した《ティアラメンツ・シェイレーン》や《ティアラメンツ・レイノハート》の効果を使用することができます。
また、除外効果を使用してターンが返ってきた時にドローフェイズに素材を埋めてバトルフェイズに入ることで、相手に何かしらのアクションを強要できます。
特にサイド後に採用率の高い《次元障壁》に対して融合以外の選択肢を作れるのも利点です。
《PSYフレームギア・γ》
《エフェクト・ヴェーラー》や《無限泡影》と違って無効にしたモンスターを破壊してくれるので、スプライトモンスターの特殊召喚条件をケアできます。
特に《鬼ガエル》や《深海のディーヴァ》をほぼ確実に1:1交換で処理できる利点は他のカードにはないと思います。
制限カードであり、デッキ内に《PSYフレーム・ドライバー》を採用しなければいけない点が懸念されますが、手札誘発の複数枚持ちが前提となる【スプライト】対面において1枚で解決できる期待値が高いため、リスクよりリターンを求めました。
【スプライト】対面
レベル2モンスターがフィールドに送り込まれたらに《壱世壊に軋む爪音》を発動し、スプライトモンスターの特殊召喚条件をケアします。
その際に《捕食植物ドラゴスタペリア》を融合召喚することで、モンスター効果無効だけでなくレベル変動も持ち合わせていることから、後続のスプライトモンスターの連続特殊召喚を牽制できます。
しかし、《捕食植物ドラゴスタペリア》の効果が通った場合でも《鬼ガエル》による自爆特攻→墓地の《粋カエル》効果で蘇生されてレベル2を供給されてしまうことがあります。
そのため、場合によってはモンスターは守備表示を徹底し、自爆特攻を防ぐことも意識しています。
【ティアラメンツ】対面
ミラーにおいて《壱世壊-ペルレイノ》の存在が重要で、お互いが発動に成功しているとターンプレイヤーが不利になります。
例えば相手が《ティアラメンツ・キトカロス》+《壱世壊に軋む爪音》の盤面、自分が《ティアラメンツ・レイノハート》を召喚した場合に相手が《壱世壊に軋む爪音》を発動したとします。
お互いにティアラメンツモンスターを墓地に送り、それぞれ効果発動を宣言。この場合ターンプレイヤーがチェーン1となります。
融合モンスターが特殊召喚されたタイミングでそれぞれの《壱世壊-ペルレイノ》の起動タイミングが訪れますが、ターンプレイヤーがチェーン1となるため、非ターンプレイヤー側は相手の《壱世壊-ペルレイノ》の発動タイミングを確認できます。
この時に非ターンプレイヤーは《壱世壊-ペルレイノ》を上からチェーンを組むことで、逆順処理で相手の《壱世壊-ペルレイノ》を一方的に処理できます。
雑感なので簡易的な内容になります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
