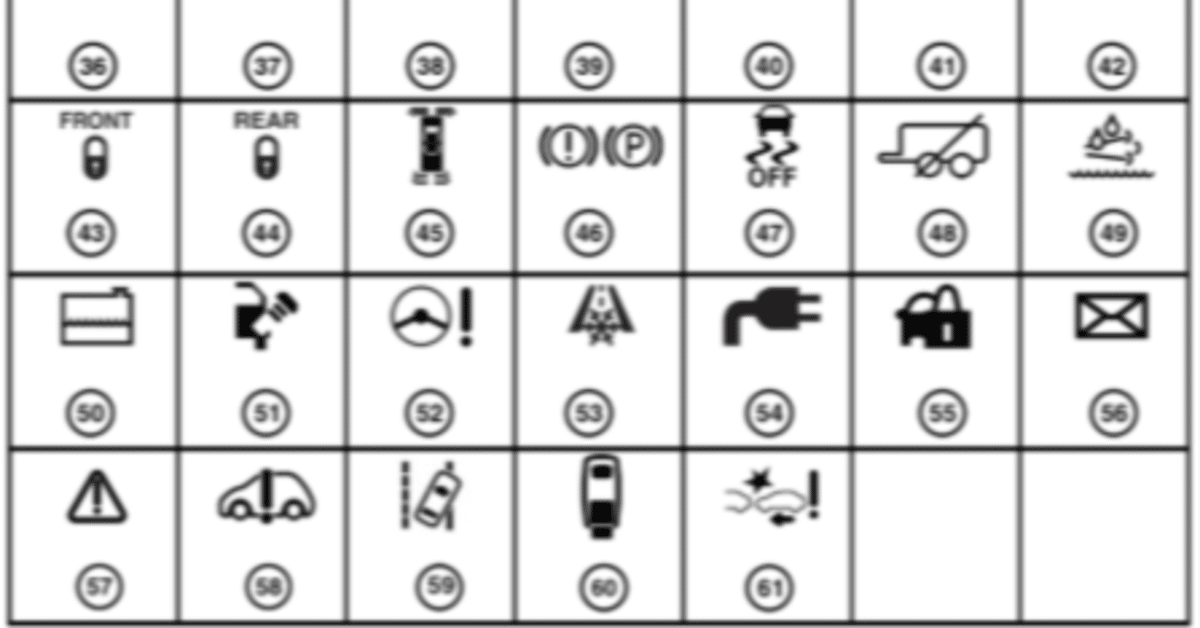
6ステップで行うトラブルシューティングの心得
① 問題点を確認する
故障診断手順の第一段階は顧客の持つ不満や不安、苦情内容を正確に確認する事、顧客からなるべくたくさんの不具合に関する情報を収集する事です。
必要に応じて、顧客と一緒にテスト走行を行い、不具合状況を確認しましょう。
又は、顧客が経験した問題発生の状況と同じ環境下で車両を操作してみましょう。
顧客は、自動車のプロではありません。
顧客にインタビューする場合も、質問方法を工夫しましょう。
例えば「どの様な時に、不具合は発生しますか?」のような質問では、顧客は、発生時の状況をうまく表現できないかも知れません。
その様な時には、質問を選択式又は、はい/いいえで答えられる方法に変えて見ましょう。
《例》
「エンジンが冷えている時と温まっている時ではどちらが発生しやすいですか?」
「不具合が発生した時に雨は降っていましたか?」
「渋滞路走行時(高速走行時)に発生しましたか?」
特に、発生頻度が低い不具合の場合、顧客からたくさんの情報を得ることが、診断/修理の時間短縮につながります。
また、モジュールにDTCがセットされている場合は、作業前に記録を残しましょう。
・ 全DTCのリスト
・ DTCがセットされているモジュール
・ DTCの状態(アクティブなのかストアなのか)
不用意にDTCを消去しないようにしましょう。
DTCを消去すると、環境データやフリーズフレームなどの、症状分析を行う場合の重要なヒントも消去されてしまいます。
また、モジュールによっては、バッテリターミナルを外したり、モジュールのコネクタを外したりして常時電源が失われると、DTC情報を消去してしまう場合があります。
② 関連する症状を究明する
このステップでは、いまだ情報を収集している段階であり、交換作業や修理を実行していない状況で、①の継承段階であると位置づけています。
顧客苦情の原因となっている実質的不具合は、時として他のシステムに影響を及ぼす恐れがあります。
実際の問題点に関連する全ての車両システムをチェックすることが必要です。
問題点がどのように関わっているかを判断するために、『サービスマニュアル』や『配線図』を参照してください。
複数の問題点を特定できた場合、それらがどのように関わりあっているかの解読を試みます。
問題が発生しているシステムが共通回路を共有している場合には、1ヶ所の修理で複数の不具合を解決できる場合があります。
③ 症状を分析する
①②で得た情報をもとに、症状を分析します。
不具合が発生したシステムを作動させるために、必要なコンポーネント(センサ、スイッチ、モータ、ソレノイド、必要な信号を送ってくる他のモジュールなど)を特定(リストアップ)します。
診断機器やテスターなどを用いて、システムをモニターします。
・ システムをサポートしているすべてのモジュールが作動しているか
・ システムに関連するスイッチやセンサからの信号、他のモジュールからバスを通して送られてくる情報などが正しく入力されているか
・ 診断機のアクチュエータテストなどを実施して、出力回路が正しく機能しているか、DTCがセットされていれば、『サービスマニュアル』に記載されている「考えられる原因」の項目も参考にします。
症状の分析ができたならば、これから行う作業のプランを作ります。
・ 点検/確認/調整を行う箇所や内容のリストアップ
・ 作業の順番(どの様にしたら、効率よく作業が行えるかを考える事と、「■■を外す前に、●●を確認/測定をしておけば良かった!」が無いようにしましょう。)
DTCがセットされている場合
モジュールにDTCがセットされていれば、環境データ(EVデータ)も確認しましょう。
環境データには、DTCをセットした不具合がどれ位の時間継続していたか、DTCがセットされてからイグニッションスイッチを何回操作したかなどの追加情報が含まれている場合があります。
フリーズフレームがセットされている場合
セットされているDTCにフリーズフレームが残されていれば、忘れずに確認しましょう。
④ 問題となる故障を特定する
このステップでは、問題点によっては、たくさんの作業工程が必要になります。
単一コンポーネントの特定から、車両の一部の分解を要する作業に至るまで、広い作業範囲があります。
①~③までの間で正しくプラン通りに遂行することが、明確な結果を導く手段につながります。
問題点の原因が、コンポーネントやモジュールである時があります。
場合によっては、良好であることが分かっているコンポーネントを一時的な代用品として使用し、問題を特定することもできます。
この手法は、ランプ類やモータなどの部品には有効ですが、コントロール・モジュールを代用品と交換することはリスクがあります。
多くのモジュールは、2台以上の車両に使用することを前提に設計されていません。
従って、車両に搭載された個々のモジュールを入れ替えると、正しく機能しなかったり、「車両製造時コンフィギュレーション」データを失ったり、また、装備が異なる車両間で、モジュールを入れ替えると新たな装備を学習して、もとに戻すことができなくなったりします。
自動車メーカーによっては、車両間で、モジュールを付け変えることを推奨していません。
また、新品のモジュールやセキュリティ関連の部品などは、車両に取り付けるとVINやIDを学習してしまう物もあります。
一度学習したVINやIDは、多くの場合、変更することができません。
⑤ 故障を修理する
④までで実行した結果から、正しい手順、正しい工具などを使用して不具合箇所の修理を実施します。
配線やコネクタの修理を実施する場合は、不具合の原因を考慮する必要があります。
配線の断線やショート、接触不良などのトラブル原因が配線の取り回しや水の侵入によるものかもしれません。
この場合、配線の取り回しを正しく修正する作業や水の浸入を防ぐ作業を追加する必要があります。
モジュールなどの特定の部品を交換する場合、必要に応じて正しく設定を行います。(VIN、ピニオンファクタ、モジュールの初期化/再学習など)この作業を正しく行わなかった場合、更なるトラブルに発展する可能性があります。
また、作業中に分解した部分も正しく組み付けを行います。
作業後、DTCの状態を確認します。(例:作業前にアクティブだったDTCがストアになっていること)
確認後、DTCを消去します。
⑥ 正しく作動していることを確認する
顧客の不満だった部分が解消されていること、修理部分を含めて、車両システムが正しく機能していることを確認します。
作業を実行するために、一時的に取り外した部品が正しく取り付けられて、正常に機能しているかも確認します。
DTCが発生していない事の最終確認をおこない、顧客の不満だった不具合が解消されていることを確認した後、車両を顧客に返却します。
この①~⑥は、故障診断の基礎です。
実践して、漏らさず聞き取りをしましょう。
あなたのサポートがネタ集めの励みになります。
