
ごちうさオタクが解説する米国コーヒーとスターバックスの歴史
「ご注文はうさぎですか?」に関する記事を普段投稿していますが、今回は少し視点を変えて、ごちうさの題材である「コーヒー」そのものについて語ってみたいと思います。きっかけは、この記事を書いている時点でのごちうさ最新話(まんがタイムきららMAX 2021年8月号)が、神沙映月ちゃんとブライトバニーにスポットを当てた話だったことです。
※この記事ではごちうさ連載最新話(2021年8月号分:単行本第10巻範囲)までのネタバレが含まれますので、アニメ派や単行本派の方はご注意ください。
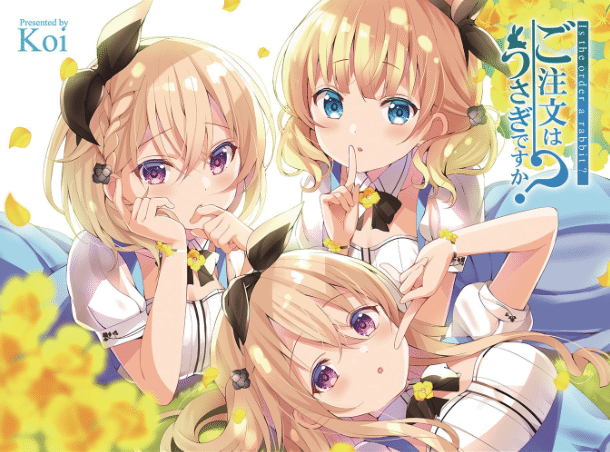

お姉ちゃんなのに頼りなさそうな様子だった前半から一変、堂々とブラバ社員と対峙するエルちゃんのかっこよさには震えました。が、そもそもブライトバニーというのはどんな会社なのでしょう? 社長である神沙姉妹の父親は未だ作中には直接登場せず、まだ謎に包まれている部分も多いです。しかしブラバのロゴや、呪文を唱えるように注文するスタイルなどは明らかに現実のスターバックス社に似せており、スターバックスをモデルとしているのは明らかです。そこで、現実のスターバックス社を研究することで、ナツメ・エル姉妹のルーツに迫れるのではないか…? そう思い少し調べてみたところ、結構面白いことが分かりました。私はオタクなのでスターバックスのようなお洒落な店は普段あまり使わないですし、スターバックス社に対しても「コーヒーの味とか一ミリも分からない意識高い系の人が飲んでそう」「お洒落な雰囲気だけで売ってそう」「ふざけた味に決まってます…!」等の偏見を抱いていた訳ですが、実は創業期のスターバックス、中々にガチなコーヒーオタクな人の集まりで、時には社員同士のコーヒー観の違いから分裂や離反が起こっていたりして、オタク的目線から見ても面白いのです(オタクは他のジャンルのオタクが解釈違いで殴り合うのを見るのが好き)。
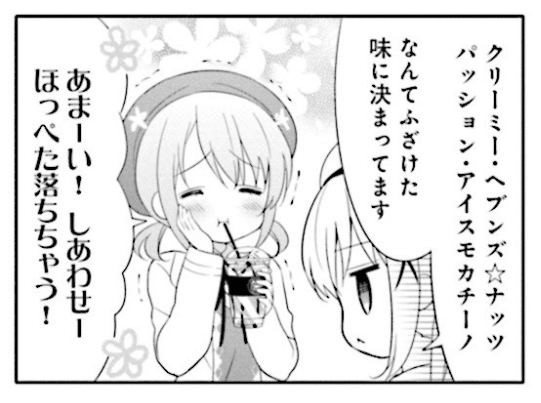
↑一般的なオタクがスターバックスに抱きがちな偏見の図
ということで本記事では意外と奥の深いアメリカのコーヒーとスターバックスの歴史を紹介していきます。しばしお付き合いいただければ幸いです。
【注意・免責事項】
※筆者は別にバリスタやコーヒーに関する専門家ではないので、インターネットで調べたりいくつかの本を読んだりしてこの記事を書いています。もしかしたら内容には間違いがあるかもしれません。筆者の知識を信じるな、ごちうさだけを信じろ。
スタバ前夜 ~アメリカのコーヒーはまずい?~
スタバ創業の話をする前に、背景として当時のアメリカとアメリカにおけるコーヒーはどういう状況であったのか? の話をしないといけません。ぶっちゃけて言うと当時のアメリカのコーヒーというのはクソ不味かったので、「これは何とかせんといかん」ということで品質の高いコーヒーを消費者に提供しようとする運動、「スペシャルティコーヒー運動」というものが興りました。この運動とスターバックスを切って語ることは出来ません。ではなぜそもそも、アメリカのコーヒーは不味かったのでしょうか? アメリカ人の味覚センスが無いから? いいえ、違います。それにはとある歴史的な背景がありました。

当時は東西冷戦の世の中。そんな中、コーヒーの主要な産出国である南米諸国(特にブラジル)は、国の外貨獲得のほとんどをコーヒーの輸出に頼るという、コーヒー一本足打法のような経済構造を持っていました。いわゆるモノカルチャー経済というやつです。そこでアメリカが懸念していたのは、コーヒーの輸出が上手く行かず、南米諸国が経済的に破綻してしまった時、それらの国々はソ連に接近=赤化してしまうのではないか? ということです。しかし、アメリカにとって裏庭と言われるほど地理的に近い中南米諸国がソ連側についてしまうのは、アメリカとしてはとてもまずい。実際にそれでまずいことになったのがキューバ危機だったりする訳です。
アメリカは一計を案じました。「国際コーヒー協定」というものを結び、南米で生産されたコーヒーをアメリカが必ず買い取るようにしたのです。ただでさえコーヒーというのは天候に非常に左右されやすい作物。冬に霜が下りれば生産量は少なくなり値段が上がりますが、一方で豊作すぎると一気に値段が崩壊してしまうのです。ある時にはあまりにコーヒーが取れすぎて捨てるしかないので、蒸気機関車の動力に炭化したコーヒー豆が使われたとか。そこで需要にかかわらずアメリカが必ず買い取ることで価格を安定させ、南米諸国の経済をも安定させようとしました。ここまでを図解すると以下のようになります。

おわかりいただけただろうか。
しかし、この策にはある副作用がありました。南米から買い取るコーヒー豆の味・質が年々低下していったのです。アメリカが必ず買い取ってくれるということは、つまり商品に競争原理が働かなくなるということ。南米のコーヒー生産者は「どうせ同じ価格で買い取ってくれるんだったら、苦労して美味しいコーヒー豆を作る必要なくね?」となってしまったのです。南米のコーヒー生産者はリゼちゃんのように常に規律正しくとは行かなかったようですね…。この時代、アメリカに正規ルートで出回るコーヒー豆の質があまりに低い一方で、コーヒー協定に加盟しておらず拘束を受けない東側諸国には質の高い豆が横流しされていたので、上質なコーヒーを求めるアメリカの消費者は一度東側に流れたコーヒー豆を闇ルートで輸入してくるといった現象まで起こっていたそうです(tourist coffee=渡りコーヒー)。それにしても、資本主義国のはずのアメリカが競争原理が働かない故の商品の質の低下に苦しみ、社会主義国の方が逆に上質なコーヒーを堪能していたというのは、何とも皮肉な歴史と言えるのではないでしょうか。
伝説のコーヒー店に集う3人の創業者
「世界一裕福なはずのこの国の住民は、こんなお粗末なコーヒーを飲んでいるのか…」。1966年、カリフォルニア州バークレー。成熟したコーヒー文化を持つオランダ出身のアルフレッド・ピートは、アメリカのコーヒーの味に悪い意味で衝撃を受けていました。
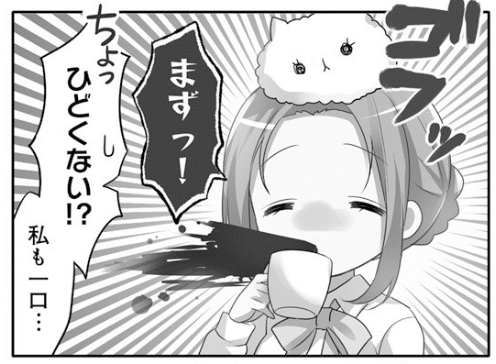
↑アメリカのコーヒーの味に衝撃を受けるピート氏の図
この現状を深く憂いたピートは「ピーツ・コーヒー&ティー」という自分のコーヒー豆店を立ち上げることにしたのです。アメリカのコーヒー史を語る際にこの店抜きには語れない程の伝説の名店です。コーヒー豆の焙煎の仕方には浅煎りと深煎りとがあって、前者は飲みやすくあっさりした味、後者は苦くコクのある味になるのだそうですが、ピートはゴリゴリの深煎り至上主義者。「俺が本物のコーヒーとは何か教えてやる」と言わんばかりの、上質なアラビカ種の豆だけを使った深煎りコーヒーの店は、徐々に評判になり、カリスマ的人気を集めるようになるとともに、彼のコーヒー哲学に共鳴する若者たちの学びの場としても育って行きました。スターバックスを世界的企業に育てた立役者であるハワード・シュルツ(後ほどまた紹介します)は、後年彼のことを指してこう述べています。「スターバックスを精神的に支えて来た祖父のような存在は、深煎りコーヒーをアメリカに紹介したオランダ人、アルフレッド・ピートである。ピートは既に70歳を過ぎているが、独立心あふれる白髪の頑固で率直な人物だ。お世辞は大嫌いだが、最高級のコーヒーや紅茶について本当に学びたいと思っている者には何時間でも付き合ってくれる。」……何だか、チノのおじいちゃんをイメージさせるような紹介だとは思いませんか?
そして、1971年のこと。ピートの店の常連客であるゴードン・バウカー、同じく常連客のジェラルド・ジェリー・ボールドウィン、ゴードンの隣人で紅茶好きのゼブ・シーグル。「自分たちの住むシアトルの人たちにもピートの店の味を味わってもらいたい」――そう考えたこの三人によって、スターバックスは創業されました。ちなみにピートの店のあるバークレーとシアトルとは直線距離で1000km以上は離れています。東京~稚内くらいの距離です。三人は、ピートの店で接客やコーヒーの焙煎について学びながら自分たちの店を経営しました。最初はコーヒー豆もピートの店に発注していましたが、一年もしないうちに中古のロースターを輸入して自家焙煎を始めたそうです。店の評判はとても良かったようですが、しかし、この三人は良質のコーヒーを提供することだけに興味が向いていて、ビジネス的に店を大きくすることにはさほど関心がありませんでした。スターバックスが世界的大企業に成長する第一歩を踏み出すためには、「この男」が入社する1982年まで待たなければなりませんでした。
神沙父のモデル? ~ハワード・シュルツ~
ハワード・シュルツ。

世界的によく知られている喫茶店としてのスターバックスのスタイルを確立したのはこの人です。本物の創業者たちよりも遥かに有名人となっており、「スターバックスの事実上の創業者」として紹介されることも多いので、神沙姉妹のお父さんにもし実在のモデルがいるとすればこの人なのかなぁ、と思ったりします。ただ、この人は決して裕福な生まれではなく、貧しい地域の生まれの人です。特待生として大学に進学し、その後ゼロックス社の営業職、雑貨会社の副社長を経てスターバックスに入社、スターバックスをグローバル企業に育て上げる……という、アメリカンドリームの体現のような経歴を持つ人ですね。雑貨会社の副社長時代、コーヒーメーカーを大量に注文したスターバックスという小さな会社に興味を持ったシュルツは、出張という名目でスターバックス社を訪れます。そこで振舞われたコーヒーの味に惚れこんだシュルツは、経営陣を熱心に説得してスターバックスに入社することになります。(コーヒーとの)出会いが人生を変える……まさにそんな一シーンだったのではないでしょうか。ちなみにこの時のシュルツのスターバックスへの入れ込みようは物凄く、シアトルの高級レストランで行われた創業者を含む経営陣との最終面接で、スターバックスに入社したら何をやりたいか、シュルツはあまりに熱く語り過ぎてドン引きされて一度は「お祈り」されたのだそうです。しかし結果に納得いかなかったシュルツは創業者の一人ジェリーに再度電話して無事合格となったのだとか。
しかし、シュルツとスターバックスの命運をより大きく変えることになる出会いは、シアトルではなくイタリアにありました。スターバックスに入社後、出張で訪れたミラノで、シュルツは人生で初めてエスプレッソ・バーを訪れることになります。当時はアメリカではまだメジャーではなかったエスプレッソの、濃厚で風味の強い味わい。バリスタがカプチーノに真っ白な泡を載せる際の、それ自体が一つの芸術かのような鮮やかな手つき。そして何と言っても、顔馴染みの常連客たちと腕の良いバリスタの醸し出す連帯感と居心地の良さ。エスプレッソ・バーの魅力にすっかり憑りつかれたシュルツが、こう考えるようになるのは自然な成り行きでした。「今のスターバックスに足りないものはこれだ……スターバックスは、喫茶店になるべきなんだ!」
そう、実はこの時点では、スターバックスは「喫茶店」ではなかったのです。あくまでも焙煎したコーヒー豆を売るだけの「コーヒー豆店」でした。モデルとしたピートの店がそのようなスタイルだったので、それを踏襲していたのです(店内で試飲は出来たようですが)。エスプレッソ、カプチーノ、カフェラテ。そういったイタリア流の、アメリカではまだ知られていないコーヒーの飲み方を啓蒙すること。そして、スターバックスをただの小売業者ではなく人々の憩いの場所である「喫茶店」にすること。シュルツはそれが自らの使命だと考えるようになりました。
「ミラノのピアッツァ・デル・ドゥオモがある中心街に入ると、文字どおり街路の両側にエスプレッソ・バーが軒を連ねていた。歩いていると、コーヒーの香りや焼き栗のにおいがただよい、政治を論じ合う大人たちの会話や制服姿の小学生たちのお喋りが聞こえてくる。ちょっとしゃれたスタイルのコーヒー・スタンドもあれば、大衆向きの大きなコーヒー・スタンドもある。朝はどのコーヒー・スタンドも混んでいて、エスプレッソを出す。本物のコーヒーのエキスだ。椅子のない店が多く、あってもわずかだ。お客は西部の酒場のように立ち飲みし、男たちはみな煙草を吸う。店内は活気づいている。イタリア・オペラの調べに交じって、初対面の人たちや店で毎日顔を合わせる友人同士の挨拶が聞こえてくる。こうしたコーヒー・スタンドは、人々に、家庭の延長とも言えるくつろぎと交流の場を提供しているのだ。しかし、顧客同士はコーヒー・スタンドにいるときだけの付き合いなのかもしれない。」……シュルツはこの時の経験についてこう書き残しています。ごちうさの卒業旅行編でも、チノと千夜が都会の個性的なカフェの数々にカルチャーショックを受けながらも堪能する様子が描かれていましたが、まさにそれと同じような経験をシュルツもミラノでしたのかもしれませんね。

シュルツ退社 ~コーヒーに関する「解釈違い」~
イタリアから帰ったシュルツは早速、イタリア式のエスプレッソ・バーを立ち上げるという自分のアイデアを実行に移そうとしますが、しかしことはそう上手く行きませんでした。スターバックスに元々いた社員たちはシュルツのプランには反対でした。「今のスタイルでも毎年利益が出ているのに、なぜ敢えて危険を冒す必要があるのか」。この時点でスターバックスは創業から既に10年以上経過しており、小さいながらも十分成功した企業なのでした。それでもシュルツは経営陣の説得を粘り強く続け、1年以上経ってようやく試験的に、店の片隅のわずかなスペースではありましたが、エスプレッソ・バーを出店することが出来たのです。シュルツはこの計画は大成功するだろうと確信しており、そして実際その通りになりました。スターバックスの最も繁盛している既存店舗の一日の来店者数が250人なのに対し、エスプレッソ・バー店舗への来店者数は初日から400人。その2か月後には800人を超えました。実験の成り行きをチェックするためにシュルツが店に立ち寄るといつも行列が出来ており、必ずお客が寄って来て「エスプレッソは素晴らしい」と感想を述べてくれたそうです。シュルツは当然ながらエスプレッソ・バー店舗をもっと拡大していくことを要求します。しかしこのような圧倒的な実績を見てもなお、経営陣は首を縦に振ることはありませんでした。この時、シュルツと、シュルツを採用した張本人でもある創業者の一人ジェリーとのコーヒー観の違いはいよいよ深刻なものとなっていたのです。
「スターバックスをコーヒーを飲むために立ち寄る店などと思われたくはない」。ピートの店を理想とするジェリーはこのように考えていました。
「我々はコーヒー焙煎業者なんだ。レストラン業をするつもりはないよ」
「ハワード、いいかね。単にやりたくないと言っているんじゃない。コーヒーを飲ませることが主体になれば、ほかのレストランやカフェテリアと同じ になってしまう。一つ一つの段階は合理的に見えても、最後はコーヒーのルーツまで見失うことになるんだ」。
コーヒーのルーツとは、コーヒーの楽しみ方をバリスタから直接教えてもらい、人々との暖かい交流があったあのミラノの街角のカフェにこそある。そう考えているシュルツとの議論はどこまで行っても並行線でした。そして、自分のアイデアを諦めきれなかったシュルツは、スターバックスを退社することになりました。入社から3年後の1985年の末のことでした。
確実にニーズのあるアイデアにゴーサインを出さないジェリーは経営者としてどうなんだという感がありますが、一方で面接落ち後に頼み込んでまで採用してもらった会社をわずか3年で辞めてしまうシュルツの方もなかなかになかなかな感がありますね……。まあ、二人ともコーヒーガチオタクなのでお互い譲れないものがあったのでしょう。オタクが解釈違いで喧嘩するのはいつものことだからね。仕方ないね。
スターバックスを去ったシュルツは「イル・ジョナーレ」という自分のブランドの店を立ち上げることになります。
伝説の店を買収、そして身売りへ
ここで時計の針を少し巻き戻して、シュルツが退社する直前のスターバックスで何が起こっていたのかを見てみましょう。この頃のスターバックスでは、創業以来の大波乱が起こっていたのです。1984年、スターバックスは何と「ピートの店」ことピーツ・コーヒー&ティー社を買収しました。この頃、ピートの店のオーナーはピート本人ではなくなっており、新しいオーナーが店を売りに出すことを決め、そのチャンスにスターバックスは飛びついたのでした。スタバの創業者たちはピートの店で修行を積んでいた訳ですから、言ってしまえばこれは息子が父親を飲み込むような買収でした。規模的にもピートの店は5店舗で、スターバックスの店舗数も同程度で、スターバックスの方が大きい会社だったという訳ではありません。この買収は財務的にかなり無理があり、スターバックスは多額の借金を抱えることになりました。そしてこの買収を決定したのこそ、ピートの店至上主義者であり、コーヒー観でシュルツと対立していたジェリーだったのでした。自分が信奉する伝説の店が売りに出されたら、全財産はたいて銀行から借金してでも買う――コーヒーオタクの鑑のような行為ですが、この決断は経営者としては完全にアウトでした。スターバックス側からすればずっと憧れていた相手と一緒になれた嬉しい買収だったのでしょうが、ピーツ・コーヒー&ティー社の社員からしてみれば、伝統と格式ある我が社が田舎の成り上がり者に突然買収されたとしか思えなかったのです。ピーツ社はスターバックスの企業文化を中々受け入れず、経営統合は遅々として進みませんでした。テコ入れのためにスターバックスの経営陣は毎週のようにピートの店に飛ぶことになりますが、上で述べた通りスターバックスのあるシアトルとピートの店のあるバークレーの間の距離は東京~稚内程もあります。ピートの店の立て直しに時間とお金と労力を割かれた結果、今度はスターバックスの末端社員の側の不満が大きくなっていきました。スターバックスでは労働組合が結成され、組合運動が興り、ジェリーの髪は白くなりました。そして、シュルツが出て行った後の1987年のこと。いよいよスターバックスとピートの店の経営は苦しくなり、スターバックスかピートの店か、どちらかを売るしかないという状況に追い込まれます。
ここまで読んで来たみなさんならお察しでしょうが、ピートの店至上主義者であるジェリーの決断は一つしかあり得ませんでした。ジェリーは自分が10年以上かけて育て上げたスターバックスを売却し、ピートの店の経営に専念するという決断を下します。ピートの店の味に惚れこんだコーヒーオタク、ここに極まれりという感じですね。そしてスターバックスの買収者として名乗りを上げたのが、イル・ジョナーレを立ち上げていたシュルツでした。イル・ジョナーレはこの時わずか3店舗、スターバックスが6店舗と企業規模ではスターバックスの方が遥かに大きく「サケがクジラを飲み込むような」無理のある買収でしたが、シュルツは何とか関係者を納得させます。シュルツはスターバックスを辞めはしましたが、その製品であるコーヒー豆と企業理念には深いリスペクトを抱き続けていたのでした。「この買収は運命だ」。シュルツはそうまで言っています。さらにはシュルツは買収後、自分の創業した「イル・ジョナーレ」の名前を捨て、社名を「スターバックス」に変更してしまいます。君ら、もうちょっと自分の創業したブランドに愛着持って……。まあシュルツも自分の店の名前に愛着が無かった訳ではなく、イル・ジョナーレという名前は覚えづらいとかスターバックスの方がブランドとして既に浸透しているとかの理由もあったみたいですが、シュルツのスターバックス大好きぶりが再びここでも発動されてしまった形ですね。喫茶店としての業態のスターバックス社はここに誕生し、みなさんの良く知る世界的大企業スターバックスの第一歩はこうして始まったのでした。
ブラバとスタバ、二社の経営戦略を比較する
スタバの社史を時系列で追うのはここまでにして、ここからはトピック的に「ブラバ」と「スタバ」の二社を比較していくという試みをしてみたいと思います。とはいえ、あくまでごちうさは少女たちを主役とする日常系漫画であり、ブラバがどんな企業なのか詳細に描写されている訳ではありません。その総帥である神沙父がどんな人なのかも未だ分かりません。限られた情報から想像力を最大限に膨らませながら見て行きましょう。
・ブラバはフランチャイズを採用しているのか?
まずは重箱の隅のような細かい点から。単行本9巻99ページ。

フユの住み込み先がブラバという物語上重要な情報が開示されたシーンですが、ここで注目して欲しいのはその後さらっと言っている台詞です。「オーナーの老夫婦」と言っています。この台詞からすると、フユの住み込む店はフランチャイズオーナーが経営しているのではないかと推測できます(ブラバ本社の直営店だったら店長って言いますよね?)。しかし実は現実のスタバはフランチャイズを採用しないというこだわりのある企業として有名です。フランチャイズを採用すればフランチャイジーが経費をいくらか負担してくれる分、会社としての初期投資は少なくて済みますが、スタバは「顧客との直のつながりを大事にする」という大方針の下、フランチャイジーが会社と顧客との間に介在することを良しとしないのだとか。それに比べるとブラバはいくらか普通の企業だということになりますが、まだ顔も出てこない「オーナーの老夫婦」がどんな人物なのかは気になります。もしかすると、ブラバの店舗を経営してはいるけどブラバの社員ではない、神沙父の影響下からは一歩引いたところにいるという独自の立ち位置から、神沙姉妹の物語にかかわってくることもあるのかもしれません。
・出店場所選定へのこだわり
2021年8月号ではブラバ社員が立地条件の良い用地を買収するためにフルール・ド・ラパンを訪れており、会社として出店場所にはこだわりを持っていそうに見えます。

この点は現実のスタバも一緒で、最初の5年間で100店以上という急速な拡張戦略を取るスタバにとっては出店場所の選択を誤る余裕はなく、この間はシュルツ自身が全ての出店場所に許可を与えていたと言います。しかし、さらに出店ペースが加速するにつれて新規出店はいよいよシュルツ自身の手に余る仕事だという結論に達しました。そこでシュルツは旧友で不動産仲介会社を経営するアーサー・ルビンフェルドという人物を新規出店部門のトップにスカウトしたそうです。アーサーは出店場所の選択、店舗設計、建設工事の全てを担当する強力な組織を作り上げ、新規店舗の企画もオープンも1日1店のペースで行えるという体制が出来上がりました。この結果、スターバックスは「最初の1000店のうち、用地の選択を間違ったために閉店に追い込まれたのは、わずか2店に過ぎなかった」とまでの記録を打ち立てることになるのです。
ところでブラバに話を戻すと、木組みの街1号店(フユの住み込む店)がフランチャイズだったのに対し、2号店の用地の買収のために社員が動いているということは多分2号店は直営店で出店しようとしてますよね。それが物語上何か意味があるのかは分かりませんが……
・We are Family★
スターバックスは「社員を家族のように扱う」を経営戦略の中核に据えている、とシュルツは述べています。社員は家族……と聞くと何だか怪しげなブラック企業でも掲げられていそうなスローガンに聞こえますが、スタバが凄かったのは実際にそれを実現するための様々な制度を、関係者の反対や困難を乗り越えてまで導入したことです。たとえば、正社員だけでなくパートタイマーにも健康保険を導入する。人件費削減の風潮が広まっていた当時のアメリカでは考えられないような施策でしたが、シュルツは懐疑的な取締役会を説得しこれを導入します。これは国民皆保険制度ではないアメリカでは社員にとって非常にありがたい施策だったのは間違いないでしょう。他には、「ビーンストック」と名付けた特殊なストックオプション制度を導入しました。ストックオプションというと経営者や一部の特殊技能を持つ優秀な社員に与えられる報酬というイメージで、実際にそれはアメリカでもそうだったのですが、スタバはそれを全社員にまで導入したのです。当時まだ株式公開前だったスタバが700人以上もいる全社員に株式購入権を与えるというのは全く前例のないことであり、証券取引委員会から特例措置を取り付ける必要があったのだとか。

さて、ごちうさ作中に目を向けると「家族」はラビットハウスに集まる「Petit Rabbit's with beans」の7人の関係性を表すものというイメージが強いのではないでしょうか。では、ブラバの方はどうでしょうか? この点については、繰り返しになりますが神沙父の人となりもまだ分からない現状では不明というほかありません。ブラバ社員で実際に作中に登場しているのも、住み込みアルバイトのフユを除けば2021年8月号で登場したモブ社員くらいです。しかし、一つ気になることもあります。

ナツメ・エル姉妹は、マヤやメグ達と出会う前までは「私達の世界は二人きり」とまで言い切るような、共依存にも近いような閉鎖的な姉妹関係を築いていたと思われます。「二人きり」と言うからには、そこには両親すらも入りこむ余地はなかったでしょう。ナツメ・エルと両親との関係はどのようなものなのでしょうか? オタク特有の悪い方向への深読みも多少はあるかもしれませんが、転校の原因を作ったのは普通に考えれば両親なのでしょうし、自分たちを普通の子供ではいさせてくれない「家柄」というものへの反発もあって、両親に対しては複雑な感情を抱いていたのではないでしょうか。また、きららMAX2021年6月号の描写からすると、ナツメとエルはスパルタな音楽の先生に師事していたようで、「子供」として愛情持って育てられるというよりは「将来の会社の跡継ぎ候補」として厳しく教育されていたのではないかという推測も成り立ちます。2021年8月号でも、フルール・ド・ラパンの用地買収をやめるよう父に提案したエルは「怒られた」と言っています。娘の言う事だからといって何でも聞いてくれるような甘い人では決してない訳ですね(だからこそ、そんな父を恐れず真正面から対決したエルの勇気ある行動の尊さが際立ちます)。

神沙父が自分の会社の社員を家族として扱っているかどうかは分かりませんが、それ以前のこととして、自分の娘たちのことをちゃんと(外面だけでなく、心の奥底から)家族として扱っているのだろうか? 仕事を優先するあまり、家族の気持ちを疎かにしてはいなかっただろうか、というのが気になります。血が繋がっていなくても、学校も学年もバイト先もバラバラでも「家族」の絆で結ばれることはある一方で、本物の家族であっても気持ちがすれ違ってしまうこともある。本物の家族である人たちが、どうやってお互いの気持ちにもう一度気付き絆を取り戻して行くか――そんな物語が、神沙家を巡る物語のテーマになってくるのかもしれません。
ということで、いつもの記事っぽい適当な展開予想に話が脱線してきたところで、今回の記事はそろそろ〆とさせていただきます。

お読みいただきありがとうございました!
参考・引用文献
スターバックス関係者の発言部分は「ハワード・シュルツ、ドリー・ジョーンズ・ヤング(1998)スターバックス成功物語、日経BP社」から引用しております。またアメリカコーヒー史に関する部分は「旦部幸博(2017)珈琲の世界史、講談社現代新書」を参考としています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
