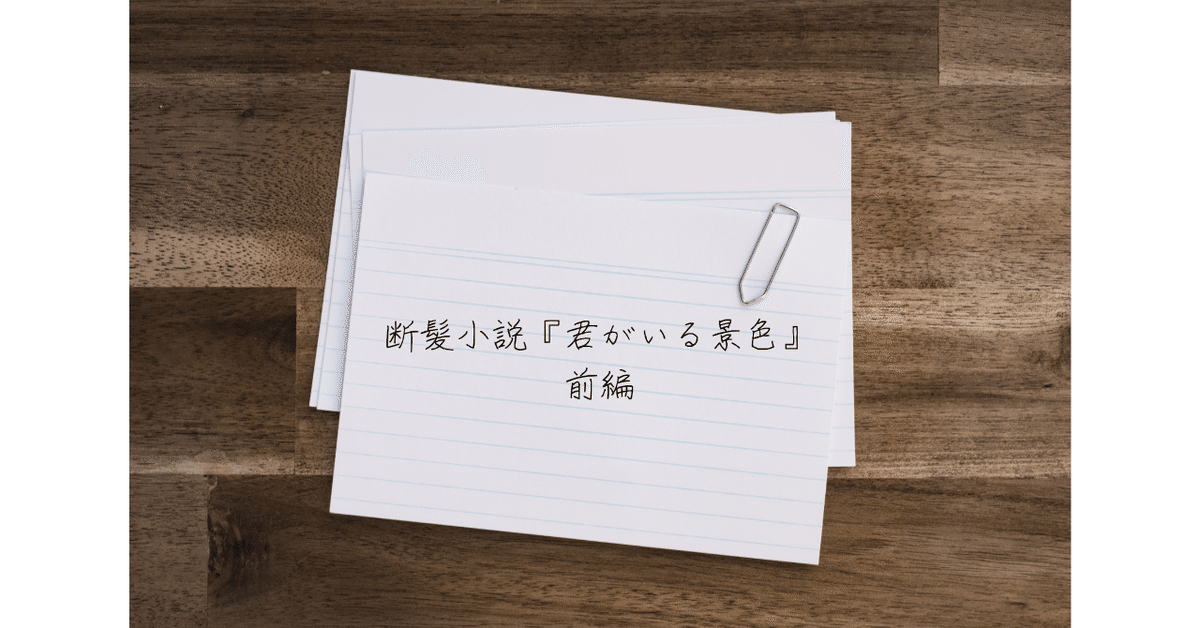
断髪小説『君がいる景色 前編』
あらすじ
一つ前の席に座る一際目立つ存在のクラスメイトは美容師志望の高校生。ひょんなことから彼のカット練習に付き合うことになり・・・
小説情報
文字数 :5,900文字程度
断髪レベル:★☆☆☆☆
キーワード:高校生、美容師志望、少女漫画風
項目の詳細はこちらをご覧下さい。
本文
0.プロローグ
「ここ。今開けるから」
目の前のガラス扉には“CLOSE”のプレートを吊り下がっている。それを気にかけることもなく、真新しい紺色のブレザーを着た男子高校生が慣れた手つきで鍵を回し、音を立てて開け放つ。
先へ進んでいく男の子に付いて足を踏み入れた瞬間、ツンと鼻をつくような美容室特有の香りが漂ってきた。
「ここ、母さんの店。ま、適当に座って」
そう言いながら、彼は鞄をカウンターテーブルの上に置き、脱いだブレザーも無造作に放り投げていた。
「お邪魔……します。……えっと國府田くんのお母さんは?」
きょろきょろと辺りを見回しながら質問を投げかけた。挨拶なしに居座るのは気が引けるからだ。
「休みだからどうせ出かけてるよ。あ、そっちじゃなくてこっちね」
入り口の左側に見つけた待合イスに座ろうとしたところを制止された。壁に掛けられた鏡と一対になるように置かれたイスの一つをくるりと回して、座面をこちらに向け手招きされた。
ゴクリと一つ喉を鳴らして、そのイスへと向かった。
私、古坂菜摘が國府田くんに誘われるまま初めてこの美容室へやって来たのは、高校に入学してからちょうどひと月経った――新緑の季節だった。
1.春の訪れは
高校生になったら、自分でも少しは大人っぽく見えると思っていた。
(うわ、おでこ広すぎっ)
出来上がったばかりの高校の制服を着て、鏡の前で前髪をセンターパートにしてみたけど、なぜか似合わない。
(じゃあ、斜めに流して)
今度は前髪の流れを変えてみたけど……、子供が背伸びして大人の真似しているみたいになって余計に痛々しく映る。
ポンパドール、編み込み、ハーフアップ、お団子……、手先が不器用すぎてどれもきれいに纏まらない。
ガックリと肩を落とし、仕方なく今まで通り目にかかるくらいの前髪をまっすぐ下ろして、眼鏡を掛けた。これで童顔に見せている丸目も少しは隠れるだろう。
黒目がちの大きな丸目に低めの小さな鼻、典型的な童顔のおかげで中学生なのに小学生に間違われたのは数知れず。低めの身長がより拍車をかけてくれる。
高校の制服を着れば大人っぽくなるかもしれないという淡い期待を抱いていたものの……、結果はご覧の通り。中学生のころと変わらない童顔眼鏡っ子姿に落胆しただけだった。紺色のブレザーとストライプのネクタイ、赤いチェックのスカートの制服が可愛いのはせめてもの救いだと力なく笑みを浮かべた。
◇◇◆◆◇◇
高校に入学して一週間も過ぎれば、教室の中はなんとなく数人ずつのグループができてくる。そんななか、入学式初日に場違いかもしれないと感じ未だクラスに馴染めていなかった。そのくらいクラスメイトたちがキラキラとして眩しい。
さすがは制服の可愛さで評判の学校、同じ一年生でも垢抜けている子が多い。特に女の子は軽くメイクして目はパッチリ、口唇はぷるぷるして、髪もサラ艶だったり、コテで巻いてアレンジしたり、とにかく可愛い子が多くて圧倒される。
「昊! この後カラオケいこうぜ」
「今日はムリ」
「えー! なんだよ、付き合い悪いな」
「昊が来ないなら、私も行くの辞めよっかなー」
「エリカまで、そんなこと言うなよ」
賑やかな声が一つ前の席から聞こえてくる。宿題をチェックしているフリでぼんやり眺めていたノートから目を外して、ちらりと前を見た。五、六人の集団で学校終わった後に何をしようか、ああでもないこうでもないと話をしているみたいだ。
國府田昊――その中で一際目立つ存在で、教室の一番後ろを座る私の一つ前の席のクラスメイト。彼を中心に男女関係なく人が集まっている、今の私とは正反対の男子だ。整った顔立ちとワックスで仕上げるのかふんわり動きのあるカジュアルな髪型が雑誌のモデルみたいに洗練されていて派手じゃなくても目を引くみたいだ。
「なぁ昊、いつなら空いてんの?」
「うーん、月曜とか」
「いつも何してるの? バイト?」
「まぁ、そんな感じ。もうすぐ授業始まりそうだから席に戻れよ。ねぇ古坂さん、次の授業は何だっけ?」
不意に國府田くんがこちらへ振り返り、バチっと目が合った。
「ふぇっ! え、えと次は数A」
突然のことに声が裏返った。
「あぁ、そうそう。たしか宿題あったよな?」
「う、うん。問題集の……」
「え、うそ、やっば!」
「うわ、俺当たるかも! 誰か答え見せて!」
國府田くんの周りにいたクラスメイトが急にバタバタと慌ただしくなって、自分たちの席へと戻っていく。
「ほんと賑やかな奴らだな」
失笑している國府田くんに釣られてつい笑ってしまった。大人びて見えていたクラスメイトも年相応なことに今更気付いたのが、妙に可笑しかった。
◇◇◆◆◇◇
「なぁ、古坂さんって自分で髪切ってる?」
國府田くんからそんなことを聞かれたのはゴールデンウィークが明けてすぐのこと、しかもこちらをじっと見つめてだ。
「あ……、まぁ」
気まずさを覚えて、彼の視線から逃れようとこちらから目を逸らした。今日はやたら目が合う気がしたけど、自意識過剰ではなかったらしい。
前髪を長めに下ろしているから月一で切らないとすぐに伸びてくる。連休中にセルフカットで揃えたばかりだ。クラスに気付く人がいるとは思いもしなかった。
「高校生にもなって美容室に行かないって、変なのは分かってるから」
「え? いや、そういう意味じゃ……」
「ほら不器用だし、童顔だし……。國府田くんからしたら野暮ったいよね。だからあまり見ないで」
手の甲で額を隠して、あははと自虐してみせた。いつにも増して口早に言葉が出るのは先にこの話題を封じ込めたいからだ。
「あー……今日さ、学校終わってから用事ある?」
「とくにないけど」
「じゃあちょっと付き合って」
「はい?」
返答する間もなく予鈴が鳴り、教室に先生が入って来た。
(え、ええっ、どういうこと!?)
その後の授業の内容は全く頭に入ってこなかった。
2.最初の一歩は
「そっちじゃなくてこっちね」
誘われるままイスで手招きする彼のもとへ向かう。もう頭の中は真っ白だ。
あの後、断るタイミングはまるで掴めなかった。学校を出てから「髪を揃えるだけだから、ちょっと付き合って」と言われ、その後もいくつか言葉を交わしたけど、結局は押し切られてしまった。
「鞄とブレザー、貸して」
「う、うん」
荷物を預けると無造作に扱っていた彼の荷物とは違って、きちんと客用のクロークに私の鞄を置いて、ブレザーは丁寧にハンガーに掛けていた。そして一台のワゴンを伴ってこちらへ戻ってきた。
「ここに座って」
こちらに向けられた座面に腰をかけた。くるりとイスが回転すると鏡には童顔眼鏡っ子が映る。
(我ながら冴えないな)
一緒に映っている國府田くんとは同じ高校生とは思えない。
(國府田くんも私を相手にするより可愛い女の子の方が楽しいだろうに)
「髪、触るね」
卑屈な考えをよそに着々と準備が進む。腰近くまで伸びる髪を持ち上げ、白いカットクロスが体を覆う。本当にここで髪を切るのかと実感し出して心臓の音も早くなる。
「眼鏡はここに置いて」
「あ……、うん」
少し躊躇う。童顔が目立つからできるだけ外したくないのだ。けれどここで付けっぱなしは不自然すぎて、外した眼鏡を目の前のテーブルにあったトレイへ置いた。
「……ほんとに國府田くんが切るの?」
今更その質問に意味はない。
繰り返し髪にくしが通る。びっくりするほど優しい手つきで。骨ばった大きな男の子の手なのに力強さはまるでない。それが逆にくすぐったくて体が強張る。
「長さもスタイルも変えないようにするからって言っても、不安だよな」
「……」
ここまできてやっぱ止めたはお互いに言えるはずもなく、スプレイヤーで髪を湿らせ前髪が持ち上がる。
「ちょっと目閉じてて」
瞼を閉じ視界が暗くなると、軽快なハサミの音が数度鳴る。
(あ……)
くしが通って、またハサミの音がした。今度は少しゆっくりと。
鳴り止んだところで恐る恐る目を開けた。
(わっ……)
鏡に映る姿に大きな変化はなかった。カットクロスには細かく髪が落ちているのと、前髪の切り口が目を閉じる前と違う。
「前髪、ちょい斜めに見えて気になってさ」
「あ……」
刷毛で髪が払われてから改めて鏡で見返すと、きれいに前髪が揃っていた。私のセルフカットではこうはならない。
「すごい」
「だろ?」
得意げな顔をして笑った彼はキラキラとして眩しかった。
◇◇◆◆◇◇
「後ろも揃えていい?」
コクリと一つ頷くと髪をクリップで留め、毛先を軽快に切り出した。
「美容師を目指してるの?」
あまり詳しくないけどただ手先が器用な人の手捌きではないのは分かる。
「うん。学校の奴らには言うなよ」
「どうして?」
「アイツら絶対面白がってここに押しかけてくるだろう?」
確かに無遠慮にグループで押しかけて、店を埋め尽くしそうだ。しかも彼らに悪気はない。想像したら少し面白かった。
「そうかも。だけど私はいいの?」
友人と呼べるほど話したことはない。どう考えても席の近いだけのクラスメイトだし、秘密を共有するほどの接点もない。
「まぁ口固そうだし。無理言って練習に付き合ってもらったし」
「あまりにも変で見るに見かねてだと思ってた」
ふは、と笑い出していた。
「古坂って面白いな。これ、後ろも自分で切ってるだろう?」
「え、なんで分かるの?」
素人が切ったのは分かるかもしれないが、なんで私と分かるのか不思議だ。
「間近で見ればな。意外と器用だな」
「そんなことは……。こんな高校生、変だよね」
美容師の親を持って、本人も目指している人にはさぞ奇妙に映るんじゃないだろうか。
「それ学校でも言ってたけど、なんで?」
「なんでって、みんなはちゃんとお店に行くでしょう」
「好きでしてるなら、それで良くね」
「……」
意外な返答に二の句を告げなかった。
「あーあれだ、“みんな”とか気にせずやりたいようにすればいいって言いたいだけ。自分の髪だし。ここに連れてきた俺が言えたことじゃないけど」
私がよっぽど怪訝そうな顔でもしたのだろうか。國府田くんは気まずいのか困ったように頭を掻いていた。彼なりに言葉を尽くそうとしているのが伝わるようで――
「ふ、ふふ、あはは」
不意に笑いが込み上げてきた。
「なんだよ、急に」
「いや、確かにわざわざ切り揃えてくれる人が好きにすればいいって、可笑しいなって」
「あ? おまえなぁ、人が気にして」
「ごめん、笑って」
「ったく」
ぶつぶつ言いながらも手際よくハサミを動かし始める。
「ありがとう、國府田くん」
「あれだけ笑ったあとに言われても嬉しくねーよ」
「本心だって」
「どーだか」
ひとしきり笑ったあとに言った言葉はなかなか信じてもらえそうにない。さすがにひどい態度だった気がしてくる。
「ホントだよ。美容室に行くと小学生扱いされて困ってたの。大体切りっぱなしのぱっつんになってさらに子供っぽくなるし。だからやりたいようにすればいいって言われてほっとしたのは本当。笑ってごめんなさい。ありがとう」
「……もういいよ、別に」
ぶっきらぼうな言い方だったけど、一先ず許してもらえたらしい。髪を少し切り揃えただけなのに、憑き物が落ちたように気分も軽くなった気がした。
◇◇◆◆◇◇
「全く美容室とか行かないのか?」
ドライヤーの風が髪を通り抜けていく。乾かすというよりは切った髪を吹き飛ばそうとしているみたいで風向きが一定じゃない。
「うーん、たまに千円カットみたいなところに行くくらいかなぁ」
ドライヤーの音に負けないように声を張り上げた。セルフカットを続けると、だんだん髪は傷んで広がってくる。自分ではどうしようもなくなったら事務的に応対してくれる店を探して行っていた。
「ふぅん。なぁ俺の練習台にならないか?」
「はい?」
「月に一回、今日みたいにカットの練習に付き合ってくれないか?」
ドライヤーの音が混ざって聞き間違えたと思ったが、どうやらそうではなかったらしい。
「いやいやいやいや、私なんかより他の可愛い子の方が練習捗らないかな!?」
ブンブンと勢いよく首を振った。國府田くんがよりによって私を相手にする理由がさっぱり分からない。
「ここ知ってるの古坂くらいだし、俺も他の人にあんま知られたくないし」
「そうかもしれないけど、私の髪を切っても面白くないって」
國府田くんはふぅと一つため息を吐いていた。
「急には無理な相談だよな。考えておいて」
「……」
國府田くんの残念そうな顔にちくりと心が痛むけど、さすがに練習にならなかったら申し訳ないのだ。そんなやり取りをしても彼は手を抜くことなくヘアオイルを揉み込んで髪を整えてくれる。
「すごい」
思わず目を見開いて鏡を覗き込んでしまうくらい、私の髪でもいい香りはするし、しっかり艶が出ていた。
「あぁ、やっぱりそうか」
「え?」
「それ伊達眼鏡だろ。それかほとんど度が入ってないやつ」
目の前の机に置いてあった眼鏡を顎でくいっと指し示しながら言った。
(うそ、バレてる……)
一瞬で背筋が固まって顔が熱くなった。童顔を隠すためのもので度は入ってない。
「あ、当たりなんだ。てっきり近視だと思ってたけど意外だな」
「な、なんで分かったの」
「俺、コンタクトだからなんとなく。眼鏡を外してから全く目を細めたりしないから、裸眼でほぼ見えてるんじゃないかって」
「……そうなんだ」
恥ずかしくて穴に入りたいとはこのことだ。オシャレ眼鏡ならまだしも単なる普通の眼鏡だ。それを私がわざわざ掛けているなんて、たぶん知らない他人から見たら意味のわからない痛い人な気がする。
「あぁ、知られたくなかったのか。なんで掛けているのかは聞かないでおくよ」
「アリガトウ」
今更そんな配慮いりませんが本音だった。
「ま、眼鏡のこと黙っておく代わりにカットの練習は付き合ってくれるよな?」
「……國府田くん、案外いい性格してるね」
「褒め言葉として受け取っておくよ」
悪びれず、にっこりと満面の笑みを浮かべているのが癪に触る。
「眼鏡のことバラしたら、ここのことバラすからね」
せめてもの意趣返しだった。
「はいはい、二人だけの秘密だな」
「〜〜っ!」
ニヤリと笑って口に人差し指を当てている。思わせぶりなその言動は絶対自分がカッコいいことを自覚しているやつだと思う。
「あ、そうだ。一つ訂正するけど、古坂は可愛いから練習捗ると思うわ」
「それ、揶揄ってるでしょっ!!」
店の中に私の声が盛大に響いた。「まじ面白れぇ」とか言いながら國府田くんはお腹を抱えて笑っていた。
時すでに遅く、これからも彼にこうやって振り回される気がしてならなかった。
後書き
なかなか更新もない中でも、ご覧いただきありがとうございます。
❤️もいただいたりと執筆の励みになっております。
後半に続きます。
長い割に断髪描写少なめヌルめですが、ハッピーエンド目指しておりますので、よかったら読んでやってください。
よろしくお願いします。
All rights reserved.
Please do not reprint without my permission.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
