
【対談#1】 原瑠璃彦×matohu 堀畑裕之 「スハマーとは何か?――現代に生きる海辺の思想を探る」
『洲浜論』の刊行を記念して、2023年8月9日に代官山 蔦屋書店でトークイベントが開催されました。
著者の原瑠璃彦さんと、カバーのビジュアルをご担当いただいた服飾ブランドmatohuの堀畑裕之さん、「スハマー」(洲浜を愛する人)のお二方をお招きし、装丁の制作秘話をはじめ、洲浜という視点から見えてくる「まったく新しい日本文化」の見方についてお話しいただきました。その模様を2回に分けてお伝えしていきます。

■洲浜を愛する人、スハマーになったきっかけ
原 最初に僕からご説明しないといけないことがたくさんあるんですけれども、6月1日に『洲浜論』という本を出させていただきまして、その表紙のイメージをmatohuの堀畑さんにお願いしました。なぜお願いしたのかと言うと、もともと僕はmatohuさんの大ファンでして、もう長いもので2012年にハマってから11年くらいになります。この洲浜についての研究も、ちょうど同じ頃からはじめたものでして、これは大学の卒業論文から取りかかり、修士論文、博士論文と10年ぐらいやってきたもので、その博士論文をもとにしたのがこの『洲浜論』です。

堀畑 筋金入りのスハマーですね!
原 (笑)。そういう研究の裏で、節目の度にmatohuさんの服をなんとかゲットすることで、パワー、インスピレーションをたくさんいただいてましたので、書いているときから、「これが本になるときにはmatohu先生に表紙をお願いできたらいいなあ」というふうに思っていました。それで、去年の年末のお忙しい時期にお願いして、ご担当いただくことになりました。実は、堀畑さんご自身、洲浜のことをとてもよくご存知で、今日は「スハマー」というタイトルになってますけど……。
堀畑 これは僕が勝手につくった言葉です(笑)。
原 ちょっとドイツ語っぽい言葉でもありますよね。堀畑さんはもともとドイツ哲学を修めておられて、哲学者を目指してらっしゃったんですよね。ドイツに留学されるくらい、そちらの方面に行かれてたんですけども、服飾の方に転向されて今日に至られるわけです。最初のお打ち合わせの後に、堀畑さんがメールで「スハマー」という言葉を書いて下さったんですよね。ブックデザイン担当の保田卓也さんと編集者の倉畑雄太さんと僕と堀畑さんで、とりあえずスハマー4人は確保だと(笑)。これはこれからどんどん増えていくんじゃないかと。
堀畑 今日来た皆さんは、きっと帰りにはスハマーになってますね(笑)。
原 皆さん「洲浜」という言葉は普段あまりお聞きになることはないと思うのですが、以前、僕が堀畑さんに「洲浜」についての研究をしているとお話ししたときに、「ああ洲浜ですか」と、すごくお詳しくてですね。おそらくは僕よりも先にスハマーだったんじゃないかなと思います(笑)。僕がスハマーになったのは2011年くらいからですから。
堀畑 ああ確かに、もうちょっと前からスハマーですね(笑)。
原 ですから、実は堀畑さんは僕もよりも先輩スハマーなんですね(笑)。そういうこともあって、今回、表紙をお願いしたんです。おかげさまで本当に目を惹くものができたと思っています。
まずは堀畑さんに、どういうきっかけがあって洲浜をお知りになられたか、ご興味持たれたかいうことをお伺いしたいと思うんですけれど、そもそもmatohuさんのロゴは千鳥ですよね。
堀畑 そうなんです。matohuと書いて「まとう」と読むんですが、ロゴの横に古典的な千鳥の形をモダンにデザインしたものがあります。小さな点の集まりで、これも群れ千鳥みたいになりますけど、ブランドのロゴをつくるときに家紋みたいにしたいと思ってつくったのがきっかけです。日本の美術のなかで千鳥を見ていくと、必ずと言って良いほど、砂浜とセットです。そういう絵をたくさん見てるうちに、これは何か深い意味があるんじゃないかと思うようになりました。たとえば、これは狩野山雪が描いた雪の浜辺の絵です。

目を惹くのはなんといっても群れ千鳥です。さらにその下に逆巻いている波とか、手前の松とか、左にある藁屋みたいなものとか、一番奥の彼方にある濃紺の夜空に光る銀色の月。それらが金屏風に描かれている見事な絵です。ここで皆さん、どこに洲浜が描かれているかおわかりになりますか?
洲浜というのは、つまり砂浜ですよね。海や川の水が運んできた砂がたまって、それがいろんな形に変化している砂浜。海なので満ち潮もあれば引き潮もある。生まれては形を変えて消えていくという、ある意味不定形に移ろっていくものなんです。そこに千鳥がそっと降り立つ。そういうイメージがほぼ共通していることにある日、気が付いて「これはなんだろう?」と思ったわけです。そういうふうに考えているなかで、洲浜というものが実は、鳥が降り立つ清浄で聖なる土地、清らかな場であったということに、さまざまなものを調べて気が付いたんですね。
そういうのが一つと、あと家紋の洲浜って皆さん、見たことありますか? これ、可愛いでしょう?
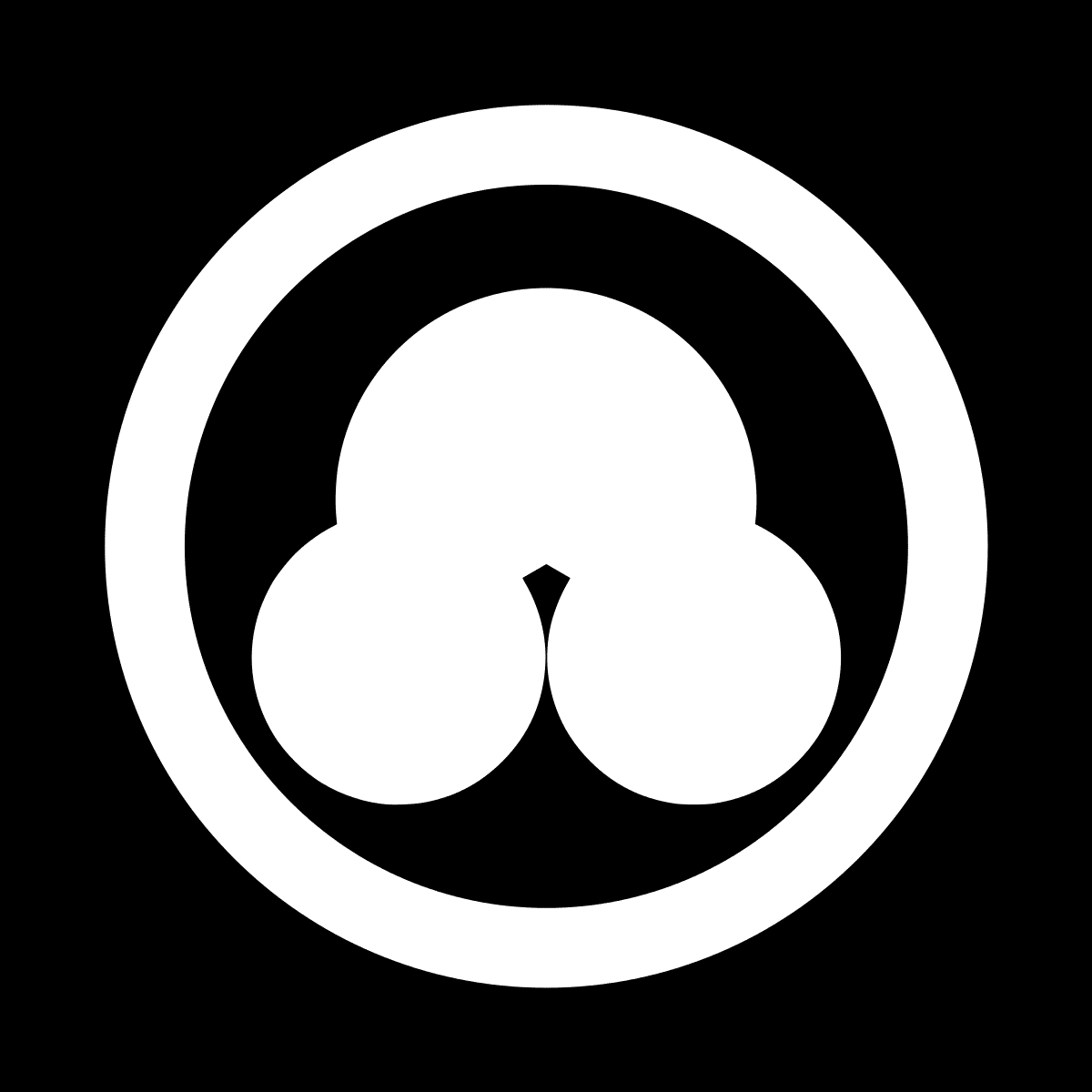
なんともいえない愛くるしさがあって、これに目と口とヒゲ3本をつけたら、藤子不二雄の漫画に登場しそうなキャラクターになる感じです(笑)。日本の家紋にはいろいろ紋様がありますけど、洲浜の紋様ってどこか惹かれる不思議さがありますよね。それでこれバッグにしてもたらどうかな思いまして、「洲浜バッグ」というものまでつくってしまいました(笑)。オリジナルテキスタイル製で、千鳥の金具までついてます。

こういう具合に、相当、洲浜に入れ込んでいましたが、詳しくはよくわかっていなかった。でもこの原さんの『洲浜論』では洲浜の本当の価値を解き明かされていて、僕にとって目から鱗なことばかり。日本の美術も工芸も伝統的な芸能も庭園も、あらゆるものが洲浜で満ちているということを深く気づかされた本です。今日はそれを皆さんに是非知っていただけたらなと思っております。
原 ありがとうございます。本当にこの洲浜紋って独特ですよね。和菓子でも「洲浜」と言ってこんな形をした豆菓子がありますが、一番皆さんが聞いたことあるかもしれない「洲浜」と言うと、かろうじて和菓子の洲浜くらいかなと思います。それが実は海辺のイメージだということは、こうしたかなり造形化された家紋や和菓子からするとちょっと飛躍があると思います。

堀畑 そうですね。これはだいぶ簡略化されてますよね。僕たちはブランドのロゴなので、こういうピンやピアスなど、やたら千鳥のアイテムをつくっていますが、実際に洲浜と千鳥以外にもなにかあるんでしょうか。

原 千鳥と洲浜のセットは、僕の本のなかでは若干出てくるものの、多いのは鶴と洲浜なんですよね。古くはやはり鶴亀蓬莱と言って、鶴も亀も長寿の象徴ということで、洲浜の海辺に鶴が立ってたり、亀がいる絵がよく見られます。たとえば、これはものすごく古い、春日大社にある《銀鶴及磯形》と言われるものですけれども、こういう曲線からなるの洲浜の島に松が生えてて鶴が飛んでるという図像はたくさんあります。
堀畑 このグニャグニャしている不思議な感じ、これはまさに洲浜の典型ですよね。
原 ほんとに曲線が独特なんですよね。堀畑さんも、そこに反応されたんですね?
堀畑 そうですね。このうごめくアメーバのような(笑)。
原 これは僕がよく使う図で、『洲浜論』の冒頭の方にも出てきますけれど、これは『うつほ物語』という平安時代の最初の長編物語の一場面を描いたものです。この絵自体は江戸時代の絵ですが、洲浜台のなかに浜千鳥がちょんちょんいる風景を詠んだ和歌なんですね。この男性が女性に求婚の和歌を贈るときの洲浜台です。

堀畑 この洲浜台ごとラブレターにしてるってことですか?
原 ラブレターをここに付けて贈ってるんです。洲浜台は、和歌を贈るときの道具の一つだったので、昔は和歌だけを贈るんじゃなくて、その舞台をつくってそのまま贈るということをやっていたわけです。
堀畑 ええ、すごくないですか。ラブレターにジオラマみたいな物までつけて、それごと渡すっていう(笑)。
原 これはノーとは言えないみたいな(笑)。和歌は「浦せばみ跡かはしまの浜千鳥ふみやかえすと尋ねてぞかく」というものです。古代中国には、浜辺の千鳥の足跡を見て文字をつくったという伝説がありますよね。それと少し関わるのですが、洲浜台のなかに浜千鳥の足跡があって、それが手紙の文字でもあるということになっています。「ふみやかへす」というのは、千鳥が浜辺を歩いて踏み返すという意味と、お手紙(=文)を返すということを洒落ているわけです。おそらく海辺に千鳥がいるミニチュアをつくって贈っていたイメージだと思います。ここにもそういう絵が描かれていますね。
堀畑 このグニャグニャの形の台が……?
原 これが洲浜台ですね。この曲線は本当に特徴的ですね。木を切ってこういう造形をつくるのは大変ですよね。脚もヴァーティカルなものじゃなくて、華足(けそく)と言う曲線的な脚になっている。そこまでしてこういう曲線にこだわっていたということがよくわかると思います。
では、堀畑さんは、そういう千鳥とのご縁で洲浜に興味を持たれたわけですね?
堀畑 僕はそうですね。逆になぜ原さんはスハマーになったんですか?
原 もともと洲浜は、僕が所属していた松岡心平先生の大学院のゼミの秘蔵のネタだったらしいんです。時々ゼミで絵画とかに洲浜が出て来ると、「あれ、これ洲浜じゃない!?」とか言って急に熱くなる、というような感じで(笑)。
堀畑 ということは、初代スハマーは松岡先生?
原 そうかもしれませんね(笑)。長らく松岡先生は、洲浜について誰かがちゃんと研究するべきだと思ってられたそうです。そういうなかで、僕も研究テーマとして勧められました。最初はよくわからなくてスルーしてしまっていたんですけど、卒業論文のとき、枯山水庭園を研究したいと思っていたところ、ああいうふうに白い砂を敷くことには洲浜と関係あるんじゃないかということで、洲浜の研究をすることになりました。でも振り返ってみれば、自分のなかで海というものがいろんな場面で印象に残っていたことに気づいていって、調べていくとともに、それがなぜなのかが徐々にわかってきました。だから、すごく良いテーマを教えてくださったと思っています。
堀畑 じゃあ最初は庭から入ったってことですね。
原 そうです。たとえば、龍安寺の石庭だと、たくさんの人が縁側に座って、何を見るともなく、ぼんやり庭をながめている様子が見られますが、それが、海辺で人がぼんやり海をながめている様子とどこか似ているなと、高校生くらいのときから直感的に思っていました。それが、そもそも庭自体が海を表象した場所なんだということが勉強してわかるようになって、やっぱりつながっていたんだと。そういうふうに認識していきながら、研究を進めていくことになりましたね。
堀畑 原さんは庭から入って、僕は千鳥から入ってるんですけど、洲浜には色々な入口があるみたいですね。この本のなかでも庭園だけじゃなくて和歌だったり、屏風の絵だったり、能などの芸能だったり、いろんな分野に洲浜の表象は散らばっているわけですよね。今日は、そういうものを原さんと解き明かしていきたいなと思います。
■表紙イメージの制作プロセス
原 では、そろそろ、この表紙がどういうプロセスで出来たかという話をしましょうか。
堀畑 原さんに会うたびに「お願したいことがある」って、ずっと言われてたんですよ。
原 なかなかちゃんと申し上げなかったですよね。「なにをやねん!?」って感じですよね(笑)。
堀畑 「でも、それはまだ秘密です」っておっしゃられながら、何年か経った。そしてようやく依頼されたのが、この記念すべき最初の著作の表紙のデザイン。原さんはこれからたくさん本を出されていくと思いますけど、最初の著作の表紙としてぜひmatohuをまとわせたいという話をくださいました。最初絵を描こうと思ったんですが……。
原 そうです。堀畑さんの名著『言葉の服』(トランスビュー)が刊行されたのが2019年ですよね。2019年は、僕がこの博士論文に一番取り組んでいた時期で、勝負の年でした。その頃、これを読んで非常に大きな元気をいただいたんですけど、そのときに、このようなサインをいただいて、千鳥に洲浜の形を描いて下さった思い出があります。これが僕のなかではイメージとしてありました。


堀畑 そうなんですか、これなんか出来そこないの生姜みたいですけど(笑)。
原 生姜!?(笑)先程、洲浜紋の話もありましたが、時代が下るに従って、洲浜ってどんどん造形化していくんですよね。現実から離れていく。だけど、もともとは美しい海辺の風景、リアルな海辺の風景の体験をもとに出来たはずなわけです。そういう原初の洲浜を探るようなドローイングをお願いできないかと考えていました。もちろん僕のなかでは、matohuのテキスタイルを使って下さったらうれしいなと思っていましたけど、「最初からそれは言えんな」と思い、ドローイングならお願いできるかなと思ってご相談させていただきました。
堀畑 僕は画家じゃないので、絵よりもなにかイメージの世界をつくったほうがいいなと思うようになりました。そしてテキスタイルを使ったイメージをつくろうと。この表紙に使っているのは、matohuのオリジナル・テキスタイルです。濃淡4色の藍染糸を切り替えてつくった、特殊なテキスタイルです。相棒の関口真希子がデザインしたんですけど、藍の色をさざ波のように描いたようなテキスタイルです。これを下地に使いながら、砂で絵を描いたらいいんじゃないかと思いつきました。それで白砂を手に入れて、砂絵を直接一回限りで描くというのをやってみました。実際の洲浜も波に洗われて消えていく一回性のものなので、そういうものをテキスタイルの上で表現したのです。

原 このテキスタイルのディテールは皆さんお持ちの『洲浜論』を見ていただくのが一番わかりやすいと思うんですけど、すごい仕組みで4色の糸を結び合わせてるんですよね?
堀畑 はい。淡色から濃色まで4色の藍染の糸を、アレンジワインダーという機械で1m間に9000回結び合わせているんです。人間の手では絶対できない特別なテキスタイルですね。それがグラデーションになっているので、だんだん海が手前から遠ざかっていくような感じになりました。
原 全体のグラデーションもありますよね。ここに砂で絵を描いていただいて写真を撮ったわけですね。
堀畑 そうですね。だから一回限り。
原 砂の絵なので、ちょっとテキスタイルを動かしただけでズレてしまうし、しかも再現できない。撮影のときは、matohuさんのお店にテキスタイルを敷かせていただいて、絵を描いていただきました。「堀畑さん、気合いが違うな!」と思ったのは、最初部屋に入ったとき、すでにこれ専門の職人さんのように、こういう道具が揃えて並べられていたことです(笑)。

堀畑 形から入るタイプです(笑)。事前に何回も練習したんですよ。それでベストな道具がこれに。
原 そうなんですか(笑)。この瓶が結構重要だったんですよね。
堀畑 どれくらい砂が出ているのか、見ながらやらないといけないんですけど、細口の硝子瓶じゃないとうまく描けない。ドバっと出ちゃうので。これは僕が秘蔵している18世紀のフランスのアンティークの瓶です。
原 めっちゃ由緒正しい道具(笑)!
堀畑 そう。それを使っちゃいました。砂で傷つくのを覚悟で。
原 これはお花用に持ってらっしゃったんですか?
堀畑 お花とか、あとはお酒を入れたりとか。
原 貴重なお道具を!
堀畑 いろんなのを試したんですけど、これが最高にいい感じで。
原 すごく印象深いのは、一番最初にカメラを通してPCの画面に出してもらってたんですけど、この藍染のテキスタイルをカメラ越しに見たときに、ハッと異様な気配を感じたことです。そこにある現実だけど、それをカメラを通すことで、違うものに見えてくる。

堀畑 一種の見立てですよね。
原 ぼんやり何か想像上の海が見えてくるような、神秘的な感じがしました。
堀畑 狙い通り(笑)。
原 それで砂絵を描いていただいたんですよね。このとき2回描いていただきましたね。しかも文字がどこに来るかも予め把握して、直にPCを見ながら描いていただきました。

堀畑 周りに5、6人いてめっちゃ緊張しました。「人を連れて来ないで」って言ったのに、いっぱい来てましたね。
原 これはもう完全にパフォーマンスでしたね。さっき枯山水庭園の話をしましたけど、枯山水は砂を敷いて、水なしで水辺の風景を表現するわけですけど、これまさに新しい枯山水の手法ですよね。テキスタイルと白砂による。
堀畑 何がいいかと言うと、砂は自分でコントロールが出来ないことですね。つまり絵を描いちゃうと自分の手跡が出るんですけど、砂だと半分ぐらいは砂の行きたいように動く。最後にちょっと筆で撫でて形を整えて、いらない砂を横にやるというようなことはしましたけど、ほぼ自然な無作為と自分の作為が入り混じるような感じでできました。
原 自分でコントロール、支配し過ぎない。いかに予測不可能なものを取り込みつつ、つくっていくかということですね。
堀畑 実際、僕たちがテキスタイルをつくるときも、そういうふうにあんまりバチッと自分たちの個性を出すというよりも、織りとか染めとか自然に生まれてくる揺らぎみたいなものを大事にしていますね。
原 このテキスタイルのちょうど真ん中あたりが白くなっているのが、水平線みたいに見えますよね。
堀畑 ありがとうございます。
原 広げるとこんな感じになってるんですね。皆さんどうでしょう、この本でご覧になっているのと、少しスケールに違いがあったかもしれませんね。

堀畑 本には帯が巻かれていますから、下部分が見えないですよね。手前がこちら側の地続きの砂浜で、奥にあるのが生まれては消える儚い島のような洲浜になってます。
原 これは本当に、思いも寄らぬやり方で僕の要望を実現して下さったなと思っています。洲浜は時代とともにどんどん造形化されていくと言いましたけど、そもそも、それは砂でできているわけですよね。本当は砂浜があんな丸い曲線をしているわけはなく、あくまで微粒子の集合体で出来ていて、しかも常に波が寄せているから非常に動的なものであるわけですよね。このイメージは、そういうことも気づかせてくれるようなものにもなっているし、また、こっちが此岸であっちが彼岸という構造にもなっている。
堀畑 「原初的な洲浜な風景ですね」と言っていただきましたが、この本を読むまで僕はそこまでよくわかっていなかった。
■此岸の洲浜と彼岸の洲浜
原 たとえば、この本のなかに《地獄極楽図屏風》というすごく重要な絵が出てきます。この絵では、上のほうに極楽浄土が描かれていて、白くて、海岸線がくねくねした洲浜で囲まれた島の上に極楽浄土がある。左下が地獄で、右下が現世になっていて、その間は全部海なんですね。手前側は地獄や現世だけれども、海の向こうに理想の世界がある。皆さんもお気づきの通り、この図像は平等院と非常によく似た構造になっています。
堀畑 10円玉の裏面の鳳凰堂ですね。

原 平等院も、一見、背後が地続きになってそうに見えますけれども、実は後ろには水が通っていて、池のなかに独立した中島に極楽浄土に見立てた鳳凰堂がある構造になっています。
堀畑 だから橋がないと渡っていけないわけですね。島のなかに浮いてたんですね、平等院鳳凰堂って!
原 それがこれをつくった藤原頼通のこだわったところでした。
堀畑 鳳凰堂の周りに白い石みたいなものがありますが……。
原 これは最近手入れしたものですけど、発掘すると、平安時代にはすごくこだわった、宇治川から集めてきた大きさの揃った白い石を敷きつめた洲浜があったことがわかりました。洲浜に囲われた浄土にしていたということなんですね。
堀畑 洲浜の島の上に極楽浄土があるという考え方、言われて気がついてびっくりしました。
原 これ、しかも東を向いてますから、池のこちらから西を向くと極楽浄土が見えるようになっています。いわゆる「西方浄土」と言われるように、極楽浄土は西の世界、西の彼方にあるものですから……。
堀畑 建物のあちらに向って夕日が沈むんですね。
原 そういうことですね。それを池のこっち側から拝むようになっていますが、その拝む側にも洲浜をつくっていたと言われています。
堀畑 いまは砂利道みたいになってますけど。
原 いまは舗装されてますが、昔は拝むための洲浜もあったそうです。ですから、その辺が、この表紙と同じような構造をしてるんですよね。手前に私たちの現世の洲浜があって、海の向こうには理想的な洲浜に囲まれた島があるという……。
堀畑 つまり向う側の洲浜はあの世ってことですか? あの世か、あるいは常世か。
原 そうですね。
堀畑 僕もあんまり考えないで描いたんです。無意識に。
原 こういうのって、何となくやっているのに、後からいろいろわかってくるということが出てきちゃうんですよね。
堀畑 平等院って、あの美しい鳳凰堂があって、池の反対側から建物を見てるイメージがあるじゃないですか? 昔はその足元にも洲浜の白石が敷きつめてあったことを考えると、鳳凰堂は建物に入るものじゃなくて、池のこちら側から礼拝するものだったということですね。
原 もちろんなかも重要ですが、こういう構成が非常に大事にされているということですね。
堀畑 浄土が海の彼方にあって、それをこちらから見ているっていう構図がすごく大事だと。
原 昔は宇治川の方からも見えたと思うんですよね。いまは川の方からは見えないと思うんですけど、昔はお寺に近付けない人でも、あそこに極楽浄土が見えるというふうになっていたと思います。「極楽を見たいんだったら平等院を見たらいい」という歌を子どもたちが歌ってたという記録があったりするので、それぐらいインパクトがあったんだと思います。
堀畑 しかも夕日が真西に沈んでいったときに、手前の洲浜から見れば平等院鳳凰堂が夕陽で黄金色に光輝くっていうことですね……。
原 そうです、そうです。
堀畑 それで思い出すのが、先日島根県の松江にいった時のことです。宍道湖という大きな湖があって、その湖に嫁ヶ島という島が浮かんでいて、ちょうど夕日がそこに沈んでいくんですね。圧倒的に美しい光景ですけど、これもある意味、日本の原風景ですね。

原 まさに理想的な島ですね。
堀畑 古代の出雲人が毎日見ていたこの風景。その前には縄文人も住んでいたので、縄文人もきっとこの夕日を見ていたんだろうと思います。
原 この嫁ヶ島にも神社があるんですか? 拝まれる聖なる島ですか?
堀畑 そうですね。いま水神様が祀ってあると思うんですけど、松だけが生えてるんですよね。人は行けないんですよ。もちろん船を出せば行けるんですけど、鳥しか降り立たない。人間が触れられないような清浄なる地ですね。
原 では禁足地ですか?
堀畑 基本的には人がずかずか入らないところですね。
原 もう一つ堀畑さんが以前教えてくださったのは、羽田空港に行くモノレールに乗ると洲浜が見えるというお話ですね。
堀畑 あれは僕の思い込みかもしれないんですけど(笑)。皆さんモノレールに乗って羽田に向かうときに左手側の席に座ってください。昭和島から天空橋へ向かう途中で海がわーッと広がるんですけど、そこに三日月型の洲浜があります。そこにいるのは千鳥だけですね。スハマーとしては、「いつかあそこに行きたいなあ」という気持ちにさせられる。満ち潮になると消えるので、行きたくても行けないのです。
原 僕、実は今日チェックしに行ったんですよ。前からお伺いしてて行けてなかったので。でも今日は潮が満ちてたような気がします。杭かなんかがありますかね。
堀畑 杭もありましたかね?
原 そこにちょっと鳥が留まっていました。
堀畑 グーグルマップの写真で見るとちゃんと見えますよ、三日月形の影が。
原 ちょっと今日は日が悪かったみたいですね。この宍道湖は出来過ぎなくらいですけれども、こういう風景、聖なる島というのは、いろんなところにありますよね。
堀畑 日が沈むあたりに浄土があるというのは、仏教的な考え方ですよね。
原 とくに大阪の天王寺とかは、昔は西側に海が接していたわけですから、あそこから入日を拝むという、日想観が行われていましたね。お日様が西に沈むのを仏さまとして拝むわけです。これも日本でやたら受けるんですよね。もともと仏典にあるいろいろな仏様の拝み方の一つとして日想観があるに過ぎないんだけども、日本でやたらこれが受けたのは、やはり海が関係してるからだと思います。
堀畑 海の向こうに日が沈んでいくと、赤い夕日が沈むあたりには何かあるんじゃないかと思いますよね。見てみたいけど決して行けない。
原 何か遠い彼方に誘われるような気持が、安心を呼び起こすんでしょうね。
堀畑 僕たちはこっちの方向へ行くとフィリピンがあるなとか、こっち行ったらハワイがあるなとかわかってますけど、古代の人は海の向こうに何があるか全然わかんないわけなので、僕たちが無限の宇宙を見ているのと同じような感覚かもしれないですよね。
*【対談#2】に続く
【プロフィール】
原 瑠璃彦 (はら・るりひこ)
1988年生。静岡大学人文社会科学部・地域創造学環専任講師。一般社団法人 hO 理事。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は日本の庭園、能・狂言。著書に『洲浜論』(作品社、2023)、『日本庭園をめぐる』(ハヤカワ新書、2023)、共著に『中世に架ける橋』(森話社、2020)、共著『翁の本』シリーズ(凸版印刷株式会社、2020-22)などがある。日本庭園の新しいアーカイヴを開発する庭園アーカイヴ・プロジェクトの代表をつとめ、ウェブサイト「Incomplete Niwa Archives 終らない庭のアーカイヴ」(2021)を公開。また、坂本龍一+野村萬斎+高谷史郎による能楽コラボレーション「LIFE-WELL」(2013)、演能企画「翁プロジェクト」(2020-)等でドラマトゥルクを担当。
堀畑 裕之 (ほりはた・ひろゆき)
服飾ブランド matohuデザイナー。同志社大学院 文学研究科哲学専攻博士過程前期修了。文化服装学院を卒業後、コム・デ・ギャルソンを経て、渡英。’05年matohuを関口真希子と設立。以後、東京コレクションや美術館での展覧会などで作品を発表。著書『言葉の服 おしゃれと気づきの哲学』 (トランスビュー)では、人と服の関係性や、おしゃれの意味について、平易に深く問いかけている。
ブランドホームページ:https://www.matohu.com/
