
【新刊】訳者・工藤順さんによる寄稿/『ウクライナの小さな町』
現在の西ウクライナにまたがるガリツィア地方の小さな町クラコーヴィエツがたどった歴史を語る歴史書にして、この町と深い縁のある著者じしんのユダヤ人の家族がたどった苦難の歴史を追いかけてゆく年代記でもある『ウクライナの小さな町』(バーナード・ワッサースタイン、工藤順訳)。ウクライナ辺境の町の歴史と、あるユダヤ人一家の歴史の交錯する軌跡を描いた本書は、東欧の複雑な歴史を複雑なまま理解するためにまさに今求められる注目書です。
近日中に刊行予定の本書の訳者による、「訳者あとがき」に代わるテキストを公開します!
『ウクライナの小さな町』に寄せて
翻訳書を訳者あとがきから読むタイプの方には申し訳ないことだが、『ウクライナの小さな町』に訳者あとがきはない。著者の意向もあるが、それがなくとも、あとがきを書こうとしたときに、「とにかく読んでください」という言葉しか出てこなかったというのが理由として大きい。じっさい、ここに書いてあることを解釈したり要約したりするような試みは、著者の意思にそぐわないと思った。歴史を人間の目線に戻そうとする試みなのだから、私たちとしては、前置きなく、一人の人間としてその歴史に立ち会うのがよい。遠い文脈に住む私たちがそこに立ち会うことを可能にするために、必要最小限の註という形で足がかりは用意してあるつもりだ。それでも、訳しながら思ったことをいくつか。
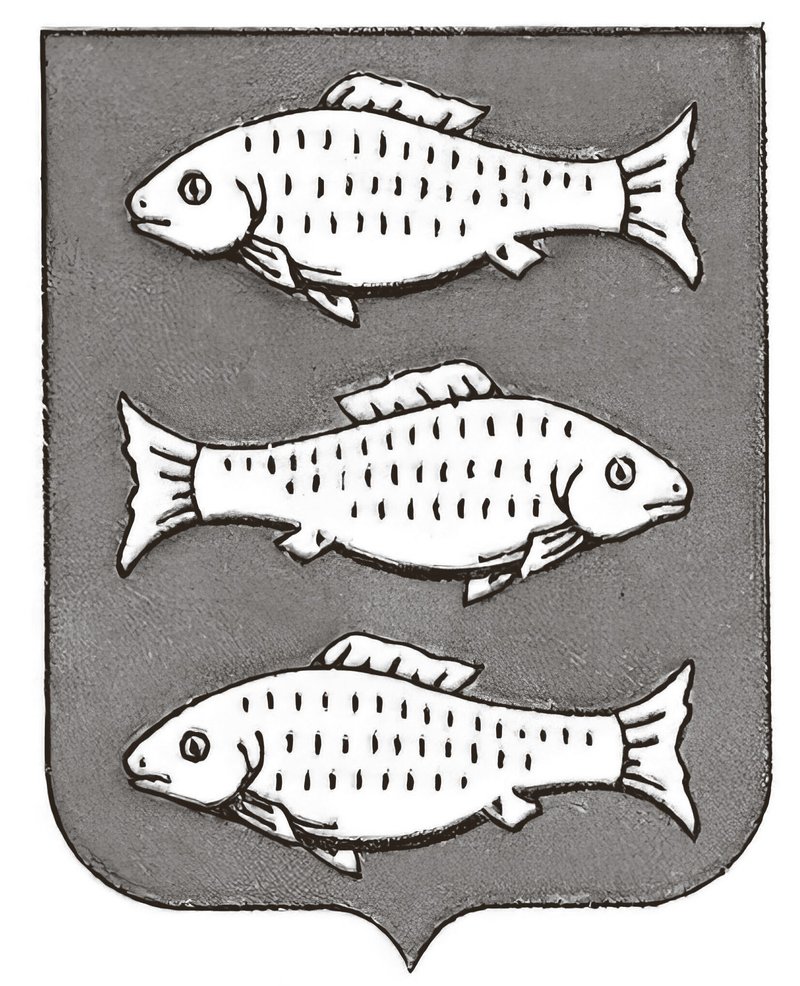
人は神ではないから、個に個として目を注ぎながら、同時に、全体をあまねく一度に見わたすことはできない。それをあえてしようとすれば心が壊れるだろう。人が歴史や戦争を語るときに国家や宗教や民族という物語枠を設定するのは、そのほうが口当たりがよいということのほかに、一人の人間が扱えることには限界があるから、枠によって情報量を制限せざるをえないということもあるだろう。そのためのいくつかの枠組みを学問は提供し、それは必要でも有益でもあるが、その枠からはみ出るものについては黙して語らない、語りえないということになる。
物語や枠組みを置くとき、あるものとあるものでないものを区別する線ができる。ごく抽象的に言えば、本書の影の主人公はそのような「線」である。本書中の地図を眺めるだけでも、いくつもの線が引かれては消え、こちらからあちらに移動しつつ、近代に近づくにつれて精緻さと複雑さと不安定さを増すことがわかる(もちろん地図で表わされない線も無数にある)。このように言ってしまえば無味乾燥で大した意味もないが、大切なことは、地図上で事もなげに線が現れたり消えたり移動したりするとき、そこではほとんど必ず暴力が生まれてきたし、悲しいことに今もそれは変わらないということだ。
暴力、例えば戦争の暴力はある物語枠で語りえない存在に対してもっとも苛烈に襲いかかる。戦場における物理的な暴力という意味でもそうだし、第三者の語りによる暴力という意味でもそうだ。本書が設定する語りの枠は、あえて単純化して言えば「ガリツィア地方のユダヤ人の歴史」ということになるが、ユダヤ人はそれ自体として一つの枠でありつつ、ヨーロッパにおいてはさまざまな枠の外にいることを強いられてきたマージナルな(margo=縁・境の)存在であって、つねに枠と枠の狭間で状況に巻き込まれてきた人たちでもある。現代の語彙でインターセクショナルな(そうあることを強いられてきた)人たちと言えるかもしれない。そしてある程度同じことは、歴史的にさまざまな国家に属し翻弄されてきたガリツィア(現在の西ウクライナにまたがる地方で、ウクライナ語ではハルィチナー)という土地についても言える。
戦争や歴史を理解しようとするとき、私たちはしばしば枠と枠(例えば民族、宗教、国家……)とのぶつかりあいとして語る。しかし素朴な言い方をすれば、戦争とはかけがえのない一人ずつが取り返しようもなく殺されることの繰り返しに外ならない。本書におけるワッサースタインの視点は歴史家としての客観と、歴史を生活として実際に生きた――そう生きるほかに選択肢などなかった者たちの主観とを見事に組み合わせたもので、歴史には人の血が流れているということを最良の形で思い出させてくれる。そしてその記述にあたって、「国家」の枠の狭間に置かれたユダヤ人とかガリツィア地方という視点が採られていることは必然であっていささかも戦略的なものではないが、そのおかげで私たちは距離をおいてその「枠」の有り様を眺めることができ、私たちが所与の御大層なものとして捉える「枠」とは所詮人間の考えごとであること、そしてその考えごとによって人は苦しみ、今も殺されつづけているということを、あらためて考える機会をもらえる。人――ある具体的な人間個人とはそもそも、何か枠組みに所属する前に、枠を超え、矛盾を抱え、つねに変わりつづける複雑怪奇な何かではないか。そのことを語ることに長けたジャンルとして「文学」があり、そしてその意味で本書は歴史書でありながら、文学と境を接してもいる。
ちなみに、冒頭で「著者の意向」について触れたが、訳者あとがきを執筆することについて著者の許可を求めたとき、まさに「枠に嵌められたくないから」という理由で難色を示されたのだった。ここまでの文章をわたしは著者の許可を待ちながら書いていたのだが、「枠」というキーワードの偶然の一致に驚いた。結局あとがきという形にはできなかったが、ここまで述べてきたことを踏まえれば、著者の懸念はなるほどよく理解できる気もする。

本書が記述対象とする時代、主題分野、言語、文化圏はとてつもなく広く、訳者の力不足はもとより明らかなことだ。言語だけでも、英語はもちろん、ポーランド語、ウクライナ語、イディッシュ語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、ハンガリー語などなどの知識を要した。すべてに通暁することはできないから、とにかくたくさんの参考文献に当たることで、何とか足りない知識の埋め合わせをしようと努力した(翻訳に当たって参考にした文献の一部を訳者のホームページで紹介している)。イディッシュ語やユダヤ文化については赤尾光春さんのご助言をいただいた。それでも行き届いていない点はいろいろと見つかると思う。専門家の皆さまからのご指摘を謙虚にお待ちしたい。
本書を翻訳しはじめたのは二〇二二年のことで、自分としては、戦争(侵略については言うまでもない)とは人殺しであるから絶対に悪であるということは前提として、戦火を交えるロシアとウクライナについて、どっちが善とか悪とかそういう話(だけ)ではないだろう、複雑な歴史を複雑なままにまず理解しようと努めなければ自分ごときが何かを言う資格はないと思った。そんなときに本書を訳すことができたことは幸いなことだった。貴重な機会を与えてくれた編集者の倉畑さんに感謝する。
この本が出るまでにはウクライナでの戦争が終わっていることを祈りながら翻訳を進めていたのだが、校正作業に入った二〇二三年十月にはイスラエルによるパレスティナ全面攻撃が始まってしまった。なぜなのか。ユダヤ人のこれほどの歴史を踏まえたうえで、しかし、いやだからこそ、なぜなのか…… 本書が扱う歴史じたい非常に苦しいものだが、翻訳の作業には歴史とリアルタイムの現実とがシンクロしてしまう苦しさもあった。ウクライナとガザは繫がっているのだ――まさにこのようにして。残念ながら、これほどアクチュアルな本もないと思う。
どうすれば人間は暴力と手を切ることができるのだろうか。誰も答えてくれないが、過去に学ぶこと、学ぼうとすることをやめないことは、自分なりに答えを出すために欠かせない条件であるはずだ。考えることをやめないために、過去から未来へ宛てられた重い宿題をお届けする。
二〇二四年三月 工藤順
■
【プロフィール】
工藤 順(くどう・なお)
1992年生まれ。翻訳労働者。訳書に、アンドレイ・プラトーノフ『チェヴェングール』(石井優貴との共訳、作品社、2022、第9回日本翻訳大賞受賞)等がある。
