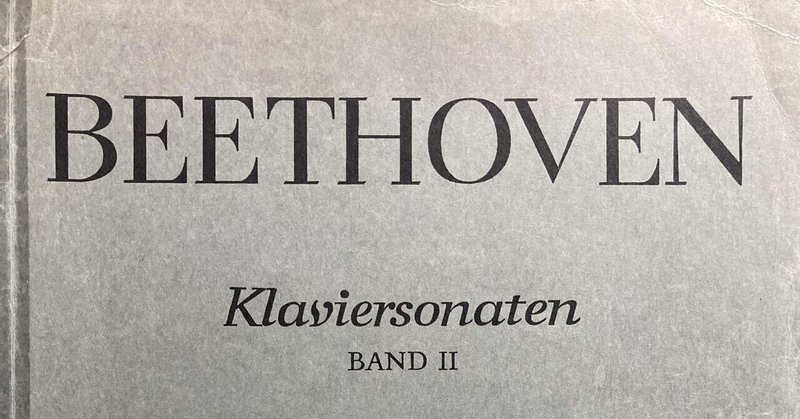
ピアノソナタのレッスンで思ったこと
この間、大人の生徒さん(Sさん)がレッスンの時、
「こちらに伺うようになってから、ワクワクして本当に楽しいんです!」
と言ってくださった。
勉強が足りていない私めなどに
もったいない言葉です。
Sさんは昨年の3月頃から習いに来はじめました。
音大を卒業し、諸事情で会社の社長をやっているが、
改めてピアノを習いたいと。
さすがに音大を卒業されているので
1を言えば10わかってくださいます。
これまでに数曲弾いて頂きましたが、
「実は、今までちゃんとベートーヴェンを弾いたことがなくて、これをやろうと思って…」
と持っていらしたのが
ベートーヴェンピアノソナタ第17番『テンペスト』op.31-2
です。
ソナタの第一楽章は、どの作曲家のソナタでもそうですが、特にベートーヴェンは
テンポの作り方が難しいと思います。
序奏、提示部、展開部、再現部、コーダ
これら、微妙にテンポが変わっていくのです。
やりすぎるとイヤらしいし、
メトロノームに合わせたみたいに弾くと
退屈してしまいます。
指の都合や調性などで弾きにくいところがたくさんあるので、
弾くことに一生懸命になりすぎて、
テンポのことは後回ししてしまいがちにもなります。
長年弾いてきて思うのは、
テンポが良いと難しい所も弾けてしまう
ということです。
なかなかできることではありませんが^^;
私は壁にぶつかった時、
ピアノの譜面を
オーケストラだったらどうなるか
と、
簡単にですが、オーケストレーションしてみます。
できない時は歌います。
すると、ピアノだけで弾いてる時とは違うテンポ感が生まれてきます。
Sさんは、オーケストラだったら…というレッスンがとても気に入ってくださったみたいです♡
学生時代、
指揮の勉強をしていた先輩(夫になりました)の伴奏(指揮伴と言います)を友人と2人でやっていました。
ピアノ2台でやるわけですが、
4hands有ればだいたいですが、
オーケストラのパートは網羅できます。
指揮のレッスンに着いて行くと
面白いことを体験できるのでした。
先生方が振ると、
まるでオーケストラみたいな音になり、難しくて弾けないところがサラッと弾けちゃうんです。
震えるほど感動したのを今も忘れません。
そして
生徒が振ると、ピアニストも途端にポンコツになってしまいます。
その後今に至るまで、いつも悩みどころはテンポ。
レッスンしていても自分が弾いていても、
これだ!というテンポが自分のものになるまで苦しいですが、
今までにない自分に出会えるようでワクワクもするんです。
私には指揮者の夫が後ろ盾にいるので、勉強にもなり、怖くもあり。
彼は彼で、ベートーヴェンの交響曲のテンポの難しさに魅力を感じていて、
いつもそのテンポの魅力について
嬉しそうに話してくれます。
話し出すと止まりません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
