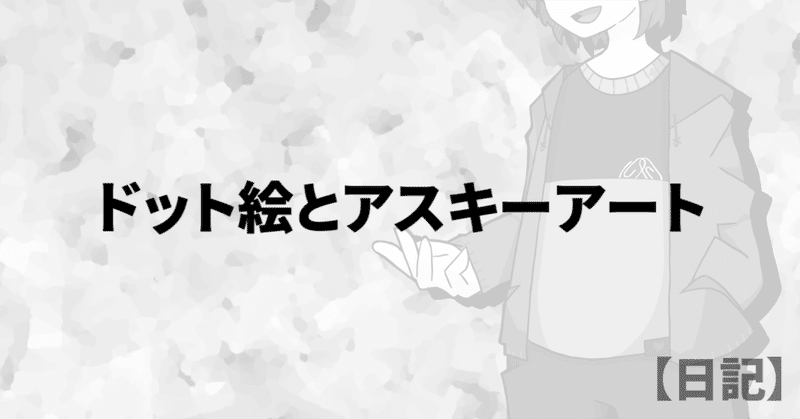
【日記】ドット絵とアスキーアート
■アスキーアート
アスキーアートという言葉も、もう死語になってしまった。いや、死語にはなっていないかもしれないが、アスキーアートと聞いて、たとえばモナーやギコが冒険するような作品を思い浮かべる人はかなり少ないと思う。
文字のやりとりが中心だった「掲示板」の時代、画像を貼るよりも手軽で、意思疎通ができて、ミーム性もあるアスキーアートという便利な文化は、インターネットという大海で小舟を漕ぐために必要な仕草だった。
たぶん。
今はツイタターで画像リプした方が早いので、アスキーアートは必要なくなってしまった。むしろ、現代のアスキーアートには「わざわざ文字で書いている」という面白さが加わっており、昔とは文脈が変わってしまった。
(ちなみに、アスキーアート昔ばなしに熱がこもってしまうのは、ずばり自分の出自が(かつての)2ちゃんねるであり、しかもAA長編板(=アスキーアートで長編漫画を描こう)というイカれた文化で育ったからだ)
きっと、現代の若者にとってアスキーアートとは、わざわざやってる人が存在しない意味不明の文化であり、半角スペースを気にしながら自分で書くものではなくて、どこからか拾ってくるものなのだろう。いや昔からか。
■ドット絵
次にドット絵の話。ドット絵は廃れることなく、未だに支持されていると思う。特にマインクラフトとアンダーテイルの影響は少なからずあるんじゃないだろうか。子供達にも、まだまだドット絵が身近な存在だと思う。
個人製作のゲームでも、ドット絵は活躍している。ドット絵を描くのは楽で簡単な作業だ、と言うつもりはないが、画質やマシンスペックにこだわる必要がなくなったり、動かすのが簡単だったり、導入する恩恵は多い。
ちなみに、ドット絵の最強ツールはやっぱりこれですか?
このソフト、ドット絵のツールで調べると秒でヒットするド定番ぽくて、買い切りだけどそんなに高くない+セールで安くなることもある、という点も良いし、肝心の機能面も痒いところに手が届いてる感じがして良さそう。
雑だけどツイタターで「Aseprite 便利」とかで調べると、どのあたりが便利なのか感想が出てくるので読んでるとフムフムとなる。いや「便利」って呟く人にとってはそりゃ便利なのでは?←ウルサイナー!シズカニシロ!
ちなみに、自分が最も好きなドッターはRド氏。カードコマンダー(カラーサモナーズ)やソウルサモナーでお世話になったのも大きいが、この人のドット絵はケレン味とデフォルメのまとめ方が上手で安心感がある。

こんなに高画質が生み出せる時代になっても、未だドット絵には表現方法の一つとして格式があり、なんならオクトパストラベラーみたいな「ドット絵なのに高画質」みたいな概念も生まれていて、確かな存在感がある。
■共通点
ドット絵とアスキーアートには共通点がある。それは「線が真っ直ぐ引けなくても絵が描ける」ということだ。さらに付け加えるなら「正解がわからなくても不正解がわかれば絵を描ける」とも言える表現方法だと思う。
自分は美術部出身だし、それなりに絵を描く機会もあるが、やはり本職のイラストレーターには遠く及ばない。最もそれを痛感するのは「自分の引いている線は正解ではない気がする」という不安、劣等感と言ってもいい。
つまり、白いキャンバスには無限の選択肢があり、そこに一本の線を引くだけでもストレスがある。正解があるはずなのに手掛かりがない。当てずっぽうに引いた線を消しては書き直し、それを繰り返すのは余りに無策だ。
そこで、解像度を極端に下げて、たとえば、32x32のキャンバスに絵を描くならどうか。驚くことに、自由度が下がっているはずなのに、線を引くことに対する精神的な負担が減っていることに気付く。それはどうしてか?
自由度が下がっているということは、選択肢も少ないということだ。選択肢が少ないのだから、「正解」に辿り着くまでの総当たりが少なくて済む。最初から当てずっぽうで引いた線を修正する前提なら、ではあるが。
もちろん、ドット絵にはドット絵の難しさがあり、少ない要素でどう表現するか、という探求には、解像度の高いキャンバスと比較しても(難しさの種類に違いははあれど)同じレベルの苦難があるのは承知している。
ドット絵は要素が少なくて自分の描きたいものが描けない!という感想を抱くイラストレーターもいるだろう。それは当たり前のことだ。だが、その要素の少なさが、いわゆる「とっつきやすさ」を生んでいるのは確かだ。
アスキーアートも同じだ。アスキーアートを描いたことがない人が「絵を描けばそれで済むのに、わざわざ文字で描かなければいけない」という「縛りプレイ」のように感じているのであれば、それは大きな誤解だ。
実は、アスキーアートには多くのセオリーがある。たとえば、右斜めの直線は/で表現できて、もっと角度をつけたいのなら半角にして/を使えばいい。左斜めなら\になるが、/の反対は存在しないのでヽで代替された。
要素を分解することもできて、たとえば「`i、」のように点を並べることで、目の錯覚で左斜め半角を表現したこともあった。しかし、これでは見た目があまり美しくないので「∧」の右側だけを使ったり、工夫があった。
もっちりとした腕を描く時には、「つ」が好んで使われた。これは記号の「⊃」を使うよりも自然な丸みがあり、キャラクターを生き生きとさせる効果があった。「つ」の反対は存在しないので、「と」が使われたりした。
アスキーアートの素晴らしい点は、たとえば(・∀・)という顔があったなら、誰が描いても(・∀・)という顔になり、いつ描いても(・∀・)という顔になるところ、いわゆる「絵柄のブレ」が存在しないところだ。
手書きの漫画だと、こうはいかない。Aさんが描いた(・∀・)とBさんが描いた(・∀・)は微妙に変わるだろう。また、同じ作者であっても、初期に描いた(・∀・)と後期の(・∀・)は顔が変わってしまうだろう。
だが、アスキーアートは違う。誰が、いつ、どんなコンディションで描いても(・∀・)は同じ顔になる。自分の世代では、この顔はモララーと呼ばれることが多かったが、モララーは誰が描いてもモララーになるのだ。
これらのキャラクターのアスキーアートは、ハンコのようなものだ。設計図でもあり、ある種のパブリックドメインだった。ブーン系小説も同じ仕組みで、キャラクターを役者として起用できるのが画期的だった。
そう、アスキーアートは、絵を文字に起こす面倒な作業をしているのではなく、「絵を描く」という本来であれば感覚的なものを、規則に従うだけで仕上げることができる、いわばプログラミングのような概念だったのだ。
ドット絵と共通していたのは、ある程度の自由が奪われることによって、制作者にとっては「正解」を追求するハードルが下がり、いわゆる「絵心」や「絵柄」に自信がなくとも、理詰めで絵を描ける、という点だった。
だから夢中になれた。「自分も参加していいんだ」と思えたから。
■蛇足
とは言っても、もうAA長編(繰り返しになるが、アスキーアートで漫画のように物語を描こうという文化、そして、もう滅びつつあり、ゼロに等しい文化)を読める気力のある人は、かなり少ないんじゃないかと思っている。
本当は、醜いHEROとか読んで欲しいよ。(規定の文字コードの関係で文字化けしてしまう可能性が高いので、そこでまず躓いてしまうかも)
でも、これ系のアスキーアートには、言葉を選ばずに言えば「読む技術」みたいなものも必要で、初見の人にはどの線が何を意味しているのかイメージするのが辛いかもしれない。そういうのも含めて「文化」だった。


だから、もう「あの頃のAA長編を読んでくれ」とは言わない。なんなら、自分ですらこのレベルのAA長編を読む体力はないと思う。でも、たしかに青春がそこにあったんだ。純度の高い創作意欲に溺れるような日々が…
というか、最近の子に「ブーン系小説って知ってる…?」って聞いたら、やっぱり知らなかった。そりゃそうだ。しかも、たぶんブーン系小説も読めないんじゃないか。やはり「文化ごと読む」というのは難しいことだ。
ちなみにブーン系小説なら、ド定番だがアルファベットが好きだ。アルファベットを読んだ人は全員、「〇〇が〇〇するところまで読んで」と言いたいだろう。でもそれは無理だ。だってアガサクリスティなんだもん…。
ちょっと違う話になるかもしれないが、数年前、スープカレー屋さんの本棚に「NANA」があった。少女漫画が大好きだった幼少期を思い出しながら「お、懐かしいな」と手に取った。が、一冊も読めずに閉じてしまった。
なんか、「ついていけなくなっている」のだ。そう、少女漫画も「文化」が強烈なのだ。そうなると「文化ごと読む」必要があるのだが、これには物凄く体力を使う。結局、ナナとナナが出会う前に読むのを諦めてしまった。
今の自分は、いわゆる「なろう系」のようなジャンルも、さほど体力を使わずに読めるが、そのうちきっと、胸焼けのような感覚が生じて、読めなくなってしまうと思う。その頃には別ジャンルが隆盛しているのだろうか。
断言するが、アスキーアートの世界がまた盛り上がることは決してないだろう。インターネット上でもプロの漫画がたくさん読めるようになった。動画も、配信も、サブスクも、ソシャゲも、SNSも、なんでもある時代だ。
だからこそ、たまに思い出さなきゃなと思う。MSPゴシック標準12ポイントで彩られたあの美しい文化が、頭の中から消えてしまわないように。
■追記
ふと、自分都合でノスタルジックに浸って、未だ文化の存続に尽力している人を無碍に扱い、腐すのはよくないと思ったので、ちゃんとアスキーアートを、それも長編を書いている人をきちんと調べて追記することにした。
バリバリ更新されてました。しかも単なるポートフォリオでなく、ビギナーがゼロからアスキーアートを描けるようになる講座や、AA長編板のまとめ等も、わかりやすく、そして詳細に記載されていました。素晴らしい。
発作のように昔話をして、知りもしない現状を嘆く大人にはなりたくないと思っていたけど、人間どうして、Nの轍を踏み抜いてしまうものですね。適当なこと書いてすみませんでした。皆様、これからも頑張ってください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
