
美術史と思想
はじめに
こんにちは!皆さまお久しぶりです。オカヤマでございます。段々と暖かくなり、春が近づいていることを感じます。早くも今年の6分の1が終わったと思うと時の流れに驚きます。
今回の話題
さて、今回は私が美術史を学ぶ中で印象に残った「思想」についてお話します。
美術史を学ぶなかで、作品には製作者や依頼者など、関係する人々の思想が強く反映されることを知りました。作品を分析していくと、教訓や戒めがメッセージとして込められていたり、理想とする生き方、美学を表していたりすることが分かります。
ここからは私が学んだ代表的な思想についてお話します。
鑑戒
「鑑戒」とは簡単に言うと「戒めとすべき手本」という意味です。美術史でもこの思想を示す例が多くありました。作品では主に、主君としてあるべき姿、家臣としてあるべき姿、そして人間としてあるべき姿、といったものが投影されるようです。
その一例として挙がるのが「帝鑑図」です。これは、中国の伝説上の皇帝である堯から始まる中国歴代皇帝の治世のうち、善い政治と悪い政治それぞれの事績を図示したものになります。
この「帝鑑図」の典拠は、西暦1573年わずか10歳で明の皇帝に即位した万暦帝の教育のために、明代の政治家張居正(1525~1582)などが著わした『帝鑑図説』になります。劉備玄徳が諸葛孔明を三顧の礼をもって迎えた話「君臣魚水」や「酒池肉林」など、私たちにも馴染みがあるお話も描かれています。

「帝鑑図」はその内容ゆえ、屏風絵や城の障壁画の画題となりました。有名なものは、江戸狩野派初代・狩野探幽が名古屋城本丸御殿上洛殿に、3代将軍家光の訪問に際して制作した作品があります。
今まで、お寺や博物館で障壁画をたくさん目にしてきましたが、描かれる内容にはそんなに深い意味があったとは思いもせず、またひとつ美術の奥深さを感じました。
「鑑戒」の画題としては、人々が農耕に勤しむ様子を描く「農耕図」なども、皇帝が民の労苦を知り自らを戒めて善政を敷くための絵として描かれました。このような鑑戒画は、権力者に何が求められていたのかを知ることができるので、とても興味深いなと思います。
暢神
続いては「暢神」です。これは「神」(精神)を「暢べる」(のびのびとさせる)という意味です。社会の競争や人間関係に身を投じていると、しばしばその苦しみにとらわれてしまいます。そこで昔の人は自然に心を向けることで精神の安寧を求めたようです。
「暢神」の思想を示す画題として、自然の風物が様々描かれてきました。私が好きな画題は「武陵桃源」です。これは世間から離れた別天地や理想郷を表す画題で、宋時代の詩人である陶潜(陶淵明・365~427)が記した「桃花源記」に出てくる秘境になります。内容は晋の太元年間に、湖南武陵の人が桃林の奥の洞穴の向こうに出てみると、秦末の戦乱を避けた人々の子孫が住む別天地があって、世の移り変わりも知らず、自然の中で平和に暮らしていたというものです。
私は授業でこれについて調べる機会があったので、その内容を調べるとともに「武陵桃源」を描いた作品を何点か見たのですが、どれもできることなら私も訪れてみたいと思わせるもので、昔の人々の「武陵桃源」への憧憬がよく伝わってきました。私もいつか自然の中で自由に暮らしてみたいものです・・・。
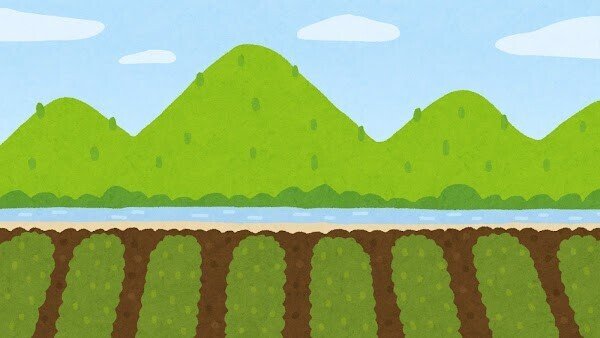
さいごに
今回は美術史における「思想」について、私が印象に残っているものをいくつか取り上げました。作品と「思想」の関わりを知ることで、目に見える作品を通して、その奥にある人々の心を読み解く美術史の面白さを感じました。
季節の変わり目です。皆さまどうかお元気で!それでは次回もよろしくお願いいたします。
【参考】
Twitter:noteの更新をお知らせしています!
YouTube:講義を期間限定で配信中!杉本の特別企画もあり、美術史についてより深く学ぶことができます。そして何より、ここで取り上げた講義を実際に聞くことができ、気軽に体験授業を受けることができます!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
