
僕の町にはコンビニがない
1.全然コンビニエンスじゃない!!
岡山県の倉敷市出身の私ですが、高校生の時、クラスメイトに「僕の地元の町にはコンビニがない」と言っている人が何人かいました。
今どきそんなところあるの?
結論、ありました(笑)
詳しく話を聞いてみるとその町にはスーパーもなく、新しくコンビニが出来てたこともあったけどその地域に住んでいる人が少ない上に利用率も低いため、僅か3ヶ月ほどで潰れてしまい、以降、商業施設が何もない、田んぼと畑ばかりの町になったと聞きました。
都市部と地方の格差、過疎化、といった言葉をよく耳にしますが、社会科の教科書に載っていることくらいに認識していた当時、高校生の私は友達の住んでいるところという身近な場所で教科書に載っていたり、ニュースで取り上げられていたりするような地域になっているのを知って、実際に起こっていることなんだと当事者意識を持つきっかけになったのを覚えています。
では実際問題、地方でどんなことが起こっているのかというと少子高齢化による人口減少が起こっています。そして人口が減少することでその地域に住んでいる人に直接的に発生している問題とは...
①生活関連サービス(小売・飲食・娯楽・医療機関等)の縮小
②税収減による行政サービス水準の低下
③地域公共交通の撤退・縮小
④空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地等の増加
の大きく分けて4つあります。これらは全て人口減少することにより、経済のマーケットの規模が小さくなってしまうことが原因であると考えられます。
ではこれらの問題に対してどのように地方創生をしていけばいいのか。
2.地域活性化の成功例
島根県大田市の中村ブレイス株式会社では義肢装具、医療器具として形状も色合いも本物そっくりな人工の手や耳、乳房などを提供している企業で、世界的に注目されているほどの技術を持っています。この企業は社会貢献活動の一環で40年間の間に50軒以上の古民家を再生、再建していて、街の景観維持に貢献しています。具体的には旧郵便局舎を活用した日本一小さなオペラハウスなども作り、こういった取り組みがメディアに取り上げられ、地域のPRになり、さらに改築した古民家には平成26年度の時点で63名もの若者が移住しているという実績を残しています。
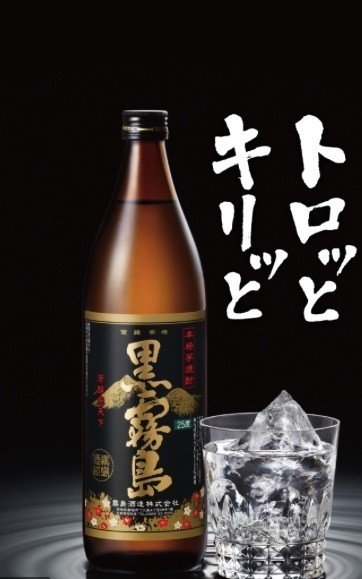
私の大好きな芋焼酎の黒霧島を製造している霧島酒造株式会社の例も挙げると、企業理念の「地域に根差し、地域とともに発展する」をモットーに本社を構える南九州産の原材料を使用して業界シェアNo.1を獲得しているだけでなく、自治体と連携して、ふるさと納税を利用したPRも実施し、肉用牛、豚、ブロイラーの産出額が日本でも首位級である都城市と連携し、「日本一の肉と焼酎」として、同社の製品をふるさと納税の謝礼品にしています。その結果、平成27年度には市のふるさと納税寄付金額は、全国1位になり地域に大きく貢献しています。
このように地方では地方での努力をしているのに加えて、地方に補助金や地方交付金など日本政府は多額のお金を地方創生にかけています。
それでもなぜ地方が潤わないのでしょうか。
上記に述べたように地方では移住者を呼び込むような活動をしたり、ふるさと納税や地域の特産品や伝統文化への関心の高まりとともに東京にアンテナショップを出したりと「町おこし」「村おこし」と地域活性化に尽力しています。ただ、地域単位でみると地域活性化に繋がっているのかもしれないが県単位で見ると県全体のGDPを底上げをさせるほどの爆発力を持っているわけではなく、地方のπ、つまり、利益をもたらすほどの影響力はないのです。
だから、
「地域活性化はしているが、地方創生には至っていない」
という見方をせざるを得ないです。
3.地方創生の黄金の方程式!?

今までの日本は地域単位までの活性化しか、さらに、分母を考えるとそれほど多くない地域でしか活性化の事例がない。この要因としては地域活性化の成功例やふるさと納税などの施策を含めて、フォーカスされているのが日本国内であるというところです。ここから世界にどう目を向けていくかが重要になってきます。地場産品を国内で販売するだけでなく、海外に輸出して海外資本を日本資本に変換し、観光客や企業、ビジネスマンや技術者、つまり人・モノ・カネが海外から入ってくる仕組みを作ることが必要です。日本の都市部・地方格差の元凶とも言える中央・東京依存型の経済から脱し、地域が直接海外経済とつながるというシステムに転換していくことが地方創生につながるといえます。
ではその仕組みとは一体、何なのでしょうか?
まず、地方創生には3つのパターンがあるといわれています。
①地産地消の徹底
この地産地消は自給自足経済のことを意味しており、日本の江戸時代で行われていた経済形態であります。それぞれの藩で産業が活発になっていてそれぞれの藩の物や金が藩の中で流通、消費がされていたために経済が潤っていました。
②アメリカ型の道州制
アメリカでは州制度であり、それぞれの州に司法権、立法権、行政権の三権を持っています。これは日本と比較するとアメリカの州は自治体なので権限が多く、道州制では州ごとに成長を競う仕組みがある一方で、日本は自治体ではないので権限が少なく、できることの範囲に大きな差が生まれ、行動に移そうと思っても権限がないために策を講ずることができなくなっています。
③イタリア型の地方独立
イタリアの国民は国家を信用しておらず、イタリア国家経済は破綻しています。それでも地方の経済が潤っているのは地方ならではの産業を興して、高い値段で高いシェアをとるという都市国家モデルを実現しているからです。
そして、相手にしているのは世界のマーケットで、イタリアには1500の都市が世界マーケットと戦っています。イタリアは国単位でみると世界経済に遅れを取っていますが、地方都市は生き生きしています。途上国の勢いに押されて苦しいとき、生産基地を他国に移すことになっても、ブランドとデザインだけは絶対に手放すことはなく、自分たちの製品がなぜこれほどの高値で世界に売れるのかという強みをよく理解して世界と勝負をしています。
この中で日本がモデルとすべきなのは③のイタリアのモデルです。イタリアのモノですぐに思い付くものといえば、イタリアのパルマ産ハムがあると思います。実際、パルマ産ハムは日本のスーパーや飲食店でよく見かけるほど世界中で売られていています。他にも食品でいうとパルメザンチーズ、車ではフェラーリなどイタリアの多くのものが世界で売られ、ほぼ全てが1000億円以上の規模であります。イタリアではこのように地方ごとに世界で戦える製品があります。一方、日本では1800の市町村に1000億円を配る施策が考えられていたが、各市町村あたり1億円もいき渡らないです。これでは日本政府が行なっていることは意味を持っているのか疑問が残ります。
日本の商品ではどうでしょうか?
日本の有名な製品といえば福井県鯖江市の鯖江メガネがあり、アルマーニのメガネを作っていて技術、品質ともに世界に誇れるレベルであることは間違いないです。しかし、鯖江メガネはアルマーニのブランド力を借りている製品、つまり、OEM製品というものです。
そこで、日本の商品がイタリアの製品と違うものは何なのかというと、
このブランド力です。
だからこそ、いかに日本の地方の製品、観光資源、伝統文化を世界に発信するのかが地方創生の鍵を握るのです。
そして、都市部だけでなく、地域単位から地方単位までの経済が潤えば、地方にも人が増えることでコンビニをはじめとする商業施設や医療施設ができることで人々の暮らしが充実しするのではないでしょうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
