
選考官視点で伝える就職活動のポイント
はじめまして。ディップ株式会社にて新卒採用を担当している片沼です。
採用業務に携わって数年、就職活動を選考官や採用設計をする立場で就職活動で押さえておくと良いんじゃないかという点を、学生に伝えられたらと思い、一部ですがまとめてみました。
これが正解という訳ではないので、ここからヒントを掴み、自分らしい意思決定に繋がると嬉しいなと思います。
1.自己分析について

・抽象度高くてもいいから、未来を考える
就活のための自分の夢を考えるのではなく、自分にとって本当に大事なことを考える。どんな生活をしていたいか。どんな人間性になっていたいか。どんな力をつけていたいか。どんな評価や立場を得ていたいか。漠然としていてもいいから、追っかける先を考えてみる。先があるから進む道の根拠を持てるようになる。
・成長のプロセスを線で考える
今の自分は点ではなく線で形成されている。今の自分の性格や価値観がどう醸成されてきたのか。影響度の大きかった人、環境、コミュニティ、時期、事象、今の自分に至った背景を具体的に抑えておくと、自己理解を深くできるようになり、選考時の会話も広がる。自分を時系列の線で深める。
・強みの裏返しを具体的に捉える
強み弱みを選考で聞かれることは多いと思うけど、その言葉まんまを受け取るケースは決して多くない。その強みや弱みの先(裏側)に隠れている"その学生らしさ"を見て、自社の仕事での活躍やカルチャーとのフィットを想像します(例:思考力は高いけど、考えすぎて行動に移せない)。自分の強み弱み整理で終えず、その先のイメージを広げてみよう。
・自分の伸びしろの根拠を整理する
新卒採用はポテンシャル採用。企業は伸びる人材を採用したい。学生に対して成長の可能性を知りたいと思っています。この学生は社会人になってから頑張れるかな?社会に出てからも成長し続けられる人材(伸びしろのある人材)なのかな?を確認するということ。ガクチカ頑張った結果成果を伝えることも大切ではあるけれど、どう頑張ったのか?なぜ頑張ったのか?社会に出てからも仕事を工夫して頑張れるんだ!という事をアピールできることは大切。
・差が出るのは言語化の部分
これまで多くの学生と面接面談してきて感じることは皆何かしら頑張っていい経験を沢山している。が、その経験を自分の言葉に落とし込みきれていないこが多い。選考官が広げて深めてくれたら良さは見えるんだけど、必ずしもそんな選考官だけではなく「良く分からんな」と終わってしまうケースもある。相手に伝える、という視点で言語化にエネルギーを割いてみる。心配だったら壁打ちをしてその制度を高める。この努力が差になる気がする。
2.業界・企業研究について

・IR情報、企業沿革、事業仕事理解は抑える
選考では最終的に、「なんでうちの会社で働きたいの?」とほとんどの企業で問われます。私にとってあなたが良いんです。を根拠を持って伝えるため、相手を知ることは欠かせません。就活で問われるのは「主張⇔根拠」。会社のVISIONや成長戦略は決算説明資料から、文化やカルチャーは沿革から(人事の言葉ではなく歴史から見る)、競合との違いは仕事まで落とし込んで語れると説得力があると思います。
・求める人材を把握する
相手が何を求めているのかを知ることで、自分は合っているのかが判断できる。企業は誰が欲しいのか?何故欲しいのか?具体的に知ることで、自分が入社することで得られる自分のメリットも見えてくる。求める人材を演じて、お互い幸せになれるケースはあまりないんじゃないかな。自分“らしさ”と企業の求める人材が合わないなら、その業界会社に入っても幸せになれない可能性が高いと捉えてもいいかも。
・沢山の社員に会ってみよう
企業側は学生に「いい会社!」「素敵な人が働いている!」というポジティブな印象を持ってほしいから、企業経由で会わせてもらえる社員はだいたいイケてる社員。イケテルトップ層に会うのもいいが、リアルを知るためなら中堅層に会うこともお勧め。リアルが見えます。今は会いに行ける手段がある(OBOG訪問の一般サービス)ので、社員の声を通して自分なりの企業に対する評価をしていってほしい。
3.ES・履歴書について
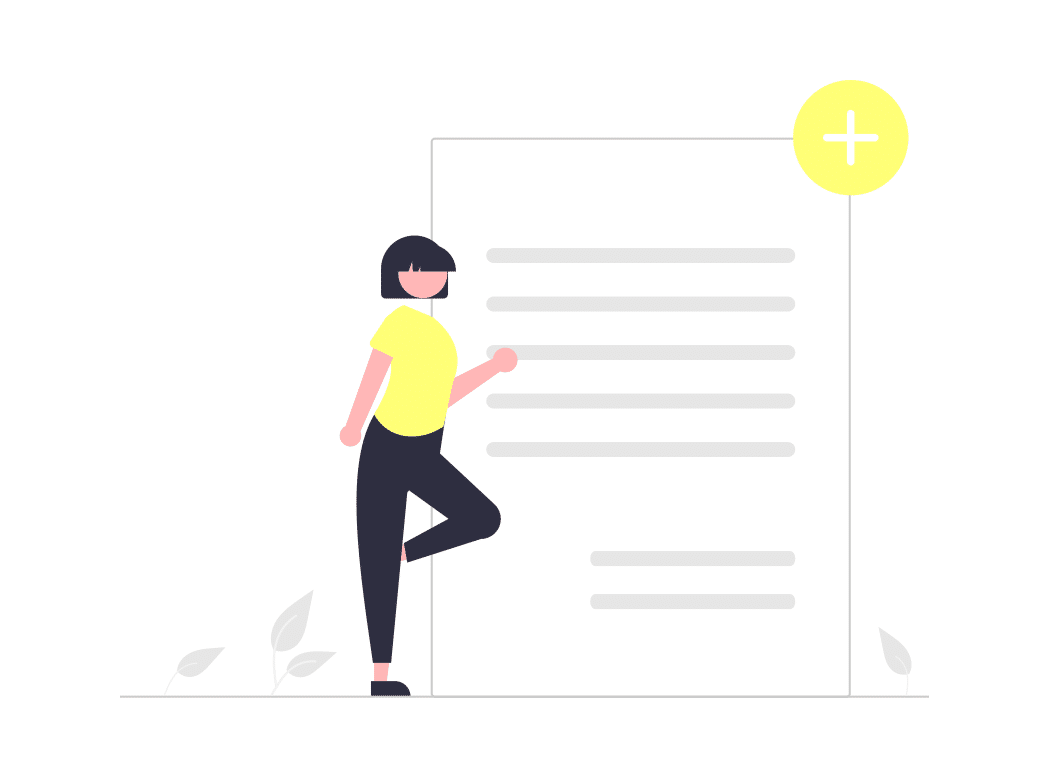
・バイト、サークルネタはレッドオーシャン
この2つは多くの学生がピックアップするので、選考官に対して抜けた良さを与えにくいが、自分の良さを相手に伝えるために自分が頑張った事ならその頑張りを伝えられるように工夫をすべき。良くある話でも自分ならではの頑張りがアピールできれば、選考官に良さは伝わります。(あくまで個人的な視点ですが)私は「自分が変えた事」より「自分が変わった事」を知りたいかも。
・志望動機を求められた場合、企業の魅力にならないように
ありがちなのは御社のここがいいんです。という内容。これは企業に対して魅力を感じた点をまとめただけであって、動機ではないのでお勧めできないです。何故良いと思ったのか?が動機。要は自分はとってのメリット。自分にとって良い理由をはっきりさせよう。
・写真は強みの象徴なら尚良し
求めない企業も増えていますが、自分が損しない程度のもので個人的には良いと思ってます。雑だなー、清潔感ないなー、険しいなー。がなければ。もちろん笑顔で自分の良さが伝わる写真なら尚良いのかも。
4.選考・面接について

・志望動機は自分の理由に
ESと同様。企業は学生が自社を選択したい理由の根拠を求めているので、自分の理由である事が重要。自分のwill(こうありたい、こうなりたい、こうしたい)とその企業で働く事がどう接合するのか。働くことに目的を持てると説得力のあるプレゼンになると思います。
・面接も会話、コミュニケーション
緊張はしてしまうもの。少しでも、話しやすい場にするため緊張してるならしてますと自己紹介で言ってしまえば良いです。自分が話しやすい土俵に持ってくる。緊張してますって言われて「は?」って思う選考官いないです(いたらその会社辞めたほうがいい)。オンラインでカメラ意識しがちだけど、あくまで大事なのは会話の内容なので、そこまで気にしなくても良いです。
・逆質問の目的が「質問すること」にならないように
質問する事が「目的」になってしまっているケースが多いです。「答えるけど、それ聞いてどうすんの…」って思われないように。ポイントは質問と知りたい理由のセットで聞くこと+具体的であること。自分の知りたいことを率直に聞いて欲しいです。質問してもらう目的は、学生の不安や疑問を払拭したいから。
・「何を話すか」と「誰が話すか」の視点
twitterでもよくある話だと思いますが、同じ方の発信でも、フォロワーが多くなると、エンゲージメント率が良くなるという視点ありますよね。面接で言うと、自己紹介や本題に入る前に自分を少しでも理解して置いてもらえると、話が効果的に選考官に入りやすい。ガクチカで大学の話をするなら、自己紹介で高校までに触れておいたり、自分の背景を端的にオープンにすることは地味に効果的。「何を話すか」が大事なのは変わらないが、「誰が話すか」というちょっとした工夫。
・具体性を意識し相手のイメージを広げる
選考官にイメージを広げさせることで、自分の話しやすい場を作る。カフェでアルバイトしていて、よりも、渋谷のスタバで、という方がイメージが膨らむため、選考官の質問も具体的になり、学生側も具体で実際のエピソードを語れるから、一石二鳥。イメージができない話を広げて深堀りすることは選考官も結構大変。
5.グループディスカッション(GD)について

・自分の何をアピールしたいのか意識する
上記「相手を知る」の続きになりますが、相手が求めることに対して、自分の「どんな魅力をアピールするか」を考えて挑もう。GDの決して長くない時間で、自分を効果的に売り込もう(※自分自分!となると逆効果になりがちなので要注意ですが)。なんとなく参加しないように。
・大事なのはチームの結論であるということ
チームとしてどうやって結論を出すのかな?その中で個人の光る分はどこかな?という視点で選考官は見ています。私は、主張と根拠の関係性が明確で、説得力のある結論であればGOODだと思っています。チームとして結論を自信もって出そうぜ!です。その為に定義や、論点の目線合わせ、ゴール設定が必要になるという事です。上手にGDやろうとする事で、目的を見失わないように。
・自分を客観視してみよう
どんなメンバーが同じチームにいたら嫌な気持ちになる?どんなメンバーと一緒にディスカッションしたくない?企業の選考官も、皆さんが嫌だな、と思う相手に対して近しい気持ちになっていることは多いと思います。そうならないような自分の振る舞いや気配りできるといいですね。オンラインだとタイムラグが出てしまうため、頷きや相槌や意図的に大きめに、「わかる!」や「たしかに!」という一言は、チームで議論していく上で効果的。
こうまとめると事前準備がやっぱり大切ですね。
今後の就活の参考になったら何よりです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
