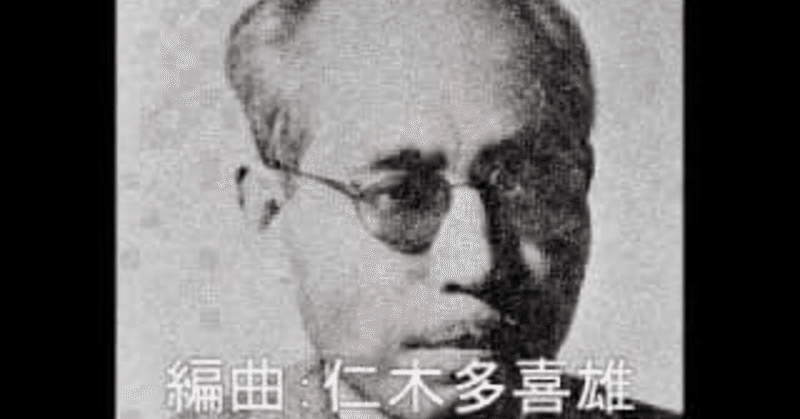
#1 仁木他喜雄
レコードの仕事のうちで一番目立つポジションなのに最も地味な仕事と言えば編曲で有ろう。
よくこの曲は誰それの作曲…などと曲の善し悪しを論ずるときに作曲者が遡上に上りがちだが、実際にレコード録音の為にスタジオで楽器の配置をしたり…ここでサックスにフェイクさせようと録音上の音の"隙間"を埋めたり、そもそも作曲者は曲は書いてもレコーディングで采配をするのは編曲者の仕事なのである。
曲を書くのとレコード録音は別の仕事なのであった。
小生のコラム「ハットリハウス」の主人公服部良一はその概念を打ち破り、作曲者でありながら編曲の知識も有していたことから自分の曲は殆ど全て自身で編曲した。
それに留まらず、作曲者達が自分で書いた曲は自分で編曲しよう!と響友会なる私塾を開き作編曲家の育成にも寄与した。
仁木他喜雄や奥山貞吉と言った服部良一と同じコロムビアレコードで長年に渡り編曲を生業とした先輩達はこの取り組みにどんな想いだったのだろう。
今回はその一人、仁木他喜雄にスポットを当てる。
仁木は明治34年1901年北海道生まれ。
少年時代から音楽に憧れ、横浜に出て外人オーケストラの見習いをしながら打楽器を学んだ。
その後、日本ジャズ史に残るハタノオーケストラに参加、ドラムスであった。
大正14年1925年、24歳のとき山田耕作が日本交響楽団を結成し、そちらに参加 その余暇を割いてジャズを研究、編曲法を学んだ。
やがて、日本交響楽団から分裂した新交響楽団(後のNHK交響楽団)に移り自学研鑽に励みながら、コロムビアレコードにも所属して編曲法の実践活動を開始した。
最も古い仁木のレコードは昭和5年リリースの♫銀座モダーンガール であり、珍しく仁木が作詞作曲迄こなしている。
早速聴いてみよう。
1.銀座モダンガール : 河上喜久代(河原喜久恵)
https://youtu.be/WSiajJfAzHs

二番の歌詞の歌い出し♫…銀座銀座と 通う奴ぁ
馬鹿よ というのは2年前の西條八十が作詞した♫当世銀座節 のそのまんま、頂きである。
種々の粗が見え破綻も来しているが、打楽器奏者の仁木らしいドラムスのアクセントが強烈である。
銀座が好きだった仁木の真骨頂と言った作品である。
2. 春の夜の唄 : 丸山和歌子
https://youtu.be/HADdtQuAbeI

戦前コロムビアレコードでは演歌系の編曲を奥山貞吉が、そして洋楽系の編曲を仁木が手掛けていた。
つまり仁木のジャズセンスが日本流行歌のメインストリームとなっていったのだ。
二曲目は外国曲を仁木が編曲したレコードだが最新式の鍵盤式アコーディオンを仁木自身が弾いたという。
楽器店から借りて来たものだったそうだが仁木の器用な演奏をご堪能いただきたい。
シンガー丸山和歌子は東洋音楽学校卒で淡谷のり子の先輩に当たる人だが、高音Gを易々と出している辺りは見事と言うしか無い。
3. 来る来るサーカス : 淡谷のり子
https://youtu.be/m8TsN4VY6o8
昭和8年春に東京 芝浦で産業大博覧会が開催されるに当たりドイツのハーゲンベックサーカス団が来日することが決まりそのPRの一環として作られたのが♫サーカスの唄 でありそのB面に収められたのが3曲目で、A B面両方とも西條八十の作詞 古賀政男の曲であり仁木は B面のみ担当している。
A面の♫サーカスの唄 はギター伴奏が主体の小編成のアンサンブルであり、管楽器はクラリネットのみと比較的易しい編成だったろうが、こちら B面は華やかなオープニングとエンディングの管編成のメジャーメロディは如何にも仁木の創作っぽい。
https://youtu.be/xPrbPPHV2zQ
新人作曲家 古関裕而の最も初期の作品である。
和製スーザこと古関は来年の朝ドラのモデルと言うリリースが以前発表があり今から楽しみだが、1964東京オリンピックの入場行進の際に流されたオリンピックマーチの作曲者であり、それに因んだ人選と言う訳である。
古関は現在でも人々が口ずさむ曲を数多く作曲しており、最初のリスト曲も早稲田大学の第一応援歌である♫紺碧の空 に始まり現在開催中の高校野球の大会歌♫栄冠は君に輝く もそうだし、プロ野球が最初に発足した時のチーム即ち巨人、大阪(後の阪神)、名古屋軍(後の中日)の全ての球団歌も彼が手掛けた。
兎に角ヒット曲…と言うか人々の記憶に残る数多の曲を量産しているが、この歌を歌う米倉俊英も当時の東京市の市歌をレコードに吹き込んでいる新人歌手であり、将来を嘱望されていたのだがこの翌年、肺炎で呆気なく逝去してしまう。
レコードでは仁木得意の鍵盤式アコーディオンが活躍する。
戦前のある種のんびりとした山の情景を少しコミカルに表現した…ホイホーイ ホーイホーイ
と言うフレーズはやはりこの時がデビューだった松坂直美の作詞である。
5. 青い小径 : 淡谷のり子
https://youtu.be/9hnrXlbJxDw
作曲はいつかも小稿で紹介した原野為二こと池田不二男である。
惜しむらくはこの天才作曲家も昭和18年に肺炎で亡くしている。
肺炎は現在でも毎年1000人以上の死亡者を出している恐ろしい病気であると言うことである。
この人のペンネームが原野為二なのは「腹の為にレコードの仕事をしている」という医者で訳詞家の奥山靉のアイデアを本気で面白がって使用したところに池田の行動派な面が伺い知れる。
別のペンネーム金子史郎に至っては"金こしらう"から来ていると言う、今でも十分通用する洒落ごころだったが、自分の曲をレコード化するに当たり大抵の編曲は仁木に依頼していたようで、2年後にブレイクする♫花言葉の唄 も仁木である。
この傑作タンゴの抒情的かつ恋情性の清廉さは他の追随を許さない。
又、メタルマスターが残っていたのだろうか?ヤケに綺麗な音質で復刻されているが、この曲に関してこの様な高音質で復元されたことを我々は天の配剤に感謝せねばならない。
6. アイラヴユー : バートンクレーン&淡谷のり子
7. バナナは如何が? : バートンクレーン
https://youtu.be/3RZR2lWLX7g
6.は昭和8年8月の新譜で淡谷がメインボーカルでグイグイ引っ張る。
誠にもって堂に入ったもので、淡谷の姐御気質がそのまま仁木の編曲にアイデアをもたらしたので有ろう。
淡谷の提示する様々な事象にバートンがそれに対する言葉を英語で応答すると言う凝ったコミックソングである。
7. は昭和9年2月の新譜でバートン最後のコロムビアレコード録音の内の一曲。
ラヂヲ放送をモジった内容である。
バートンのレコードは外国人から見た日本の風俗をライトタッチに風刺した内容が殆どで後の東宝重役になる森岩雄の傑作な詞は笑いとエロとペーソスに満ちており、バートンクレーンや同時期に来日してアイドルになった川畑"イボンヌ"文子らに提供した一連の作詞は、今聴いても胸に迫るが独特の軽みが、現在でも通用するエッジを秘めているようで聴いていても、とても自然だ。
8. ミルク色だよ : 中野忠晴&コロムビアナカノリズムボーイズ
https://youtu.be/KU8RQaBnvxU
中野忠晴はディレクター的資質を秘めたシンガーで自らプロデュースしたコーラスグループナカノリズムボーイズをアメリカのリズムボーイズ並みの感性で実力を付けさせた。
戦後はレコード会社をキングに移籍して戦前の人気シンガーとしてのキャリアをあっさり捨てて、一転作曲家として独自の活躍のフィールドを巧みに替えて長く流行歌の世界に貢献した。
中野のハイトーンボイスはえも云われぬストーリーテーリングを秘めていて、ここでも自ら作詞した詩を淡々と語る。
♫…ミルク色だよ 波止場の霧は
パイプの煙に ほんのり暮れて
こうした伴奏と詞が一体化した独自の世界はこの直後にコロムビアに入社してきた服部良一と組むことにより、更にハイブロウな世界観を展開して昭和14年の♫チャイナタンゴ でハイライトを迎えることになる。
9. 別れ来て : 伊藤久男
https://youtu.be/eDFLzn9Nsq0
小稿のタイトルが「演歌の源流」だからこうしたものも出さなければ、と探した中から程よくマッチした作品があったのでラストに添えてみた。
№5の♫青い小径 のコンビが作ったものとは思われない短音階の演歌調メロディだが、以前小稿で池田不二男を紹介した際に取り上げた♫片瀬波 から連なる和モノ流行歌の傑作である。
仁木のアレンジも演歌調だからといって、決して流されずにリズムを強調した早いテンポの調子の良い演歌であり、正に現代演歌のお手本のような作品である。
仁木の特集はPART2につづく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
