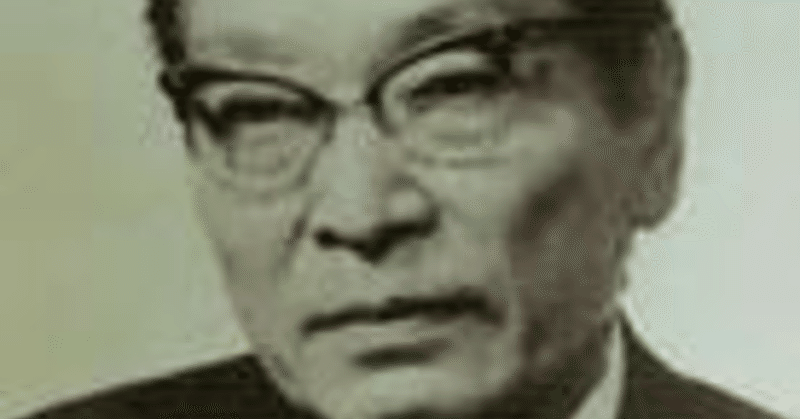
演歌の源流 # 3
☆旅の夜風 : 霧島 昇 ・ ミスコロムビア '38
現在に至る演歌の源流、この我が国独自の節回しの源流を探る流行歌にスポットを当てる小稿。
本日は作曲家万城目正を紹介する。
先づは彼の代表作♫旅の夜風 をお聴き下さい。
https://youtu.be/Fb91k68Ch5c
演奏は↑ココをタップする

如何ですか?
正直、小生と同世代でも既に懐メロと化していた曲ですが何となく聞いたことはある…そんな程度の認識だと思う。
爺さん婆さんには丁度いい昔の流行歌…と言った塩梅で有ろう。
昔内海桂子好江(ウッチャンナンチャンの師匠)懐メロ番組で、この曲を紹介するときに「これ掛かるとパチンコよくでるのよね〜」と確か先に亡くなった好江さんが言って会場の笑いを誘っていたのを記憶している。
確かに駅前のパチンコ屋でこの唄を聞いた覚えがある!
その位この曲は流行ったのだ。
この曲は、昭和13年封切の松竹映画「愛染かつら」の主題歌で有る。
戦前の恋愛映画で当時若手の筆頭俳優だった上原謙(加山雄三の父)と既にベテランだった田中絹代の共演で、…このかつらは、愛染かつらと言ってこの木に触れると思いが通じると言われているのです…さあ、あなたも触って…
顔から火の出るような台詞を淡々と細面な二枚目の上原が言うと辛うじて若さを保っていた田中も恥じらい乍ら…
何ともラヴなやりとりだが、戦前の日本映画ではキスシーンは御法度だった(と言うか、段々厳しくなっていった、昭和初期はOKだった)から濃厚な性描写があるわけでもないが、恋をする男女が2人で両手を合わせて愛染かつらに手を触れ合う、と言うのはかなり極どいシーンだった筈である。
因みにユーチューブ画像にある2人の写真はスチール写真なので宣伝用である。本編にはこうしたシーンはない。

この映画そのものは公開当時大当たりしたので🎯映画はシリーズ化され「愛染夜曲」「愛染草紙」と主題歌も全て万城目が手掛けた。
万城目は元々は北海道出身で劇伴や映画音楽を書いていた人で流行歌の作曲家と言う一面と主に松竹映画の主題歌、挿入歌を多く手掛けている。
だから、この人のヒット曲は大抵映画主題歌なのだ。
有名なところでは終戦直後の松竹映画「そよかぜ」の主題歌♫リンゴの唄 は当時の象徴的な流行歌となり今の世でもたまに耳にする。
このレコードの優れた点は前奏が無茶苦茶明るいメジャーコードなのに、主音階になると一気に哀調を帯びたマイナーコードにチェンジする所だと思う。
日本人はどちらかといえば、マイナーキーを好むのでこの落とし方は、壺を得ている共言えるし作曲者万城目正の発想でなければなし得なかった荒技だと思う。
その辺の話は後で触れる。
余りにヒットし、懐メロファンからリクエストが絶えないのでこの曲を唄った並木路子(凄い名前だ)は終生懐メロ番組でこの唄を歌わされる羽目に…。
戦争の余燼が残る昭和24年には美空ひばりがデビューしてデビュー曲♫悲しき口笛 やそれに続く♫東京キッド 辺りの初期美空ひばりのシングルの多数を手掛けたのもこの人だったし、もう亡くなってしまったが島倉千代子のデビュー曲♫この世の花 も万城目が書いて見事ヒットさせた。
多年に亘り売れる流行歌を量産した万城目正は多分古賀政男に次ぐヒットメーカーではなかろうか?
万城目と古賀の違いは万城目は編曲もこなせるが古賀は出来なくはないが余り得意ではなかった。
この違いは無いようで、あると思う。
レコードと言うのは最終的に編曲家の音になる。
リスナーの耳に届くのは編曲家が編成した音なのだ。
これはいくら作曲者が曲を書いたとしても例えば前奏、間奏、後奏迄記譜すれば別だが大抵の場合は編曲者に委ねられる。
万城目の所属したコロムビアレコードには編曲者の大家が少なくとも2人いた。
奥山貞吉と仁木多喜雄である。
古賀の曲などは大抵は仁木多喜雄が編曲していた。
このオーケストレーションが出来る出来ないは例えば服部良一などは素養もあり、マイナーだが他のレコード会社での実績もあったから♫山寺の和尚さん の様な型破りなジャズコーラスが実現したのだ。
和製ジャズは明らかに服部良一が開花させたものだ。
結局、服部良一の話になってしまった💦
万城目正の場合はやはり自分自身で編曲したのでこうした素晴らしい前奏が出来上がったのだと思う。
このイントロのメロディは♫花も嵐も踏み越えて〜の主音と共に人々の記憶に残る名曲の一部となっていった。
最後までお読みいただきありがとうございます
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
