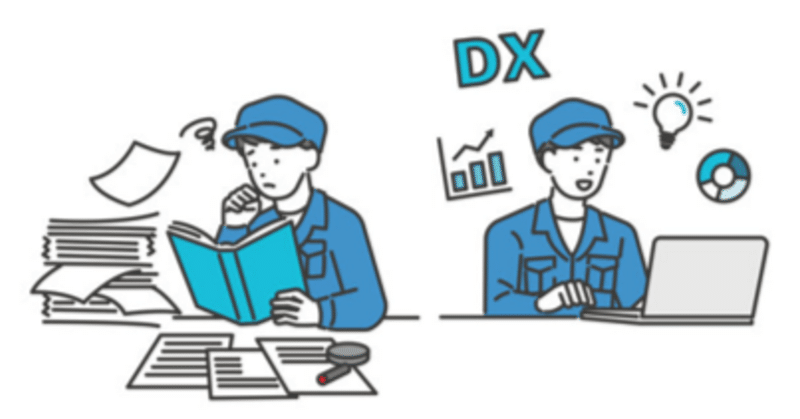
人不足、コロナ、インボイス、キュッシュレス… 院内改革における「引き算」のポイントとは
社会情勢や環境変化、制度改正など将来の予測が難しい現代社会。急激な変化が起き続けている中で、既存の院内ルールとの「ズレ」をどのように見直すべきか。また、院内改革を行う上で必要な「引き算」のポイントについて深堀していく。

突然だが、近年起こった社会変化をいくつ挙げられるだろうか。新型コロナウイルス感染症の影響は言うまでもないが、自動精算機やキャッシュレス決済サービスの導入といったデジタル化をはじめ、インボイス制度やオンライン資格確認の原則義務化で導入を行った施設もあるだろう。その背景には、少子高齢化や感染症による「人材不足」が要因としてあげられ、皆様のご施設でも課題のひとつではないだろうか。このように、医療は不変的なものに見えるが実は、少なからず社会変化に影響を受けていることが分かる。これら多数の変化の中で皆様のご施設では、どのような「院内改革」を行っているだろうか。

慢性的な人材不足は、どの業種においても深刻化しているが、医療業界ではどうだろうか。沖縄県医療福祉労働組合連合会が2022年に加盟労組の看護職員に実施した労働実態調査にて、仕事を辞めたいと思う人は72.2%だったと発表した。その理由には、「慢性的な人手不足による過重労働」をあげる人が半数を占めるほか、同様の理由で約8割の人は医療・看護事故が続く原因としてあげている。

去った9月、弊社主催で接遇セミナーを行った。接遇では、患者の不安な気持ちを労り・癒すことを重要視しているが、参加された方からは「コロナ禍で職員の離職率が加速したことや職員教育の機会が減ったことで、接遇の意識が疎かになっていた」という声があがった。
以上のことから、弊社では接遇セミナーで職員の意識やモチベーションを向上させると共に、職員がやらない仕事を棚卸し、業務を「引き算すること」を推奨している。

では、時代に沿った求められる院内ルールはどのように見直すべきか。ポイントは3つある。まず「①現在の院内にあるルールを顕在化させること」だ。就業規則や業務マニュアル、日々のミーティングから院内セミナー・イベントに至るまで、ルールをあげ、その上で、今の時代には何が必要で不必要なものかを「②取捨選択(棚卸)」するのだ。この棚卸の過程では、さまざまな「抜け」も見つかり、ついついルールの足し算になってしまいがちだが、上述した人材不足の現状では、積極的に「やらないこと」や「アウトソースすること」を探し、引き算していく活動が、特に重要である。さらに激変する社会の中で、地域に根付いた施設になるために最も重要なことは、組織として「③個性が発揮されているか」という点である。例えば「業務を一部アウトソースする」という対策を取るのであれば、その空いた時間に勉強会の開催や業務改善報告会など職員教育の時間を充分確保することで職場環境、ひいては接遇といった患者への対応にも影響を及ぼすことだろう。その上で、変化させる部分と不変的な部分を組み合わせる、それこそが「組織の個性」となり、変化させるルールに対してどれだけの時間と労力をかけらるかが「他施設との差別化」を創ることにも繋がるのだ。
様々な社会変化と既存の院内ルールとの間にできる「ズレ」。それを把握した上で、やらない業務を引き算し、必要なものに時間をかけるといった考えを取り入れてみてはいかがだろうか。

※この記事に関するお問い合わせは、以下の公式LINEまで
弊社公式ホームページはこちらから
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
