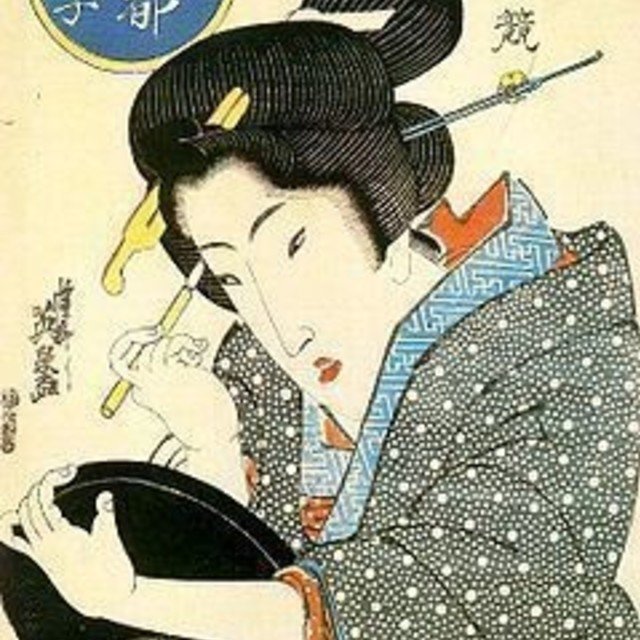
都節音階(陰旋法)E
replay3_3
00:00 | 00:00
ミ・ファ・ラ・シ・ド・ミの音階。左手はミ・シ。A(ラ)の「ヨナ抜き短調音階」の主音をE(ミ)にかえて弾いたもの。これにより日本伝統音階とされる「都節音階」となる。ヨナ抜き短調に比べて、より「江戸もの」っぽさが増す。琴や三味線で聴きたい感じ。
これは5音階(ペンタトニック)の一種だが、半音を二つ含んでいる(ミ・ファとシ・ド)。社会学者のM.ヴェーバーによれば、半音を含む5音階は世界的にも避けられる傾向が強いとのことで、その珍しい例の一つとして日本が挙げられている(『音楽社会学』より)。
上原六四郎は、八木節のような半音を含まない音階(ミを主音にするとミ・ソ・ラ・シ・レ)を田舎音階および陽旋と呼び、都節・陰旋と対比させた。たしかに田舎節は非常に素朴な響きがあるのに対して、都節は艶っぽく、大人の密やかな情の交わりのような雰囲気がある。不思議なことだが、「半音」(註)にはどこか人間の割り切れない情念や心意のようなものを表現する力があるのかもしれない。
註:この「半音」という表現自体、西洋音楽の表現なのだけれども、逆に12分割したとなり合う音を「半音」とした上で、それを和声的かつ旋律的に利用可能にした点にこそ、西洋機能和声法の真骨頂があるともいえるだろう。
これは5音階(ペンタトニック)の一種だが、半音を二つ含んでいる(ミ・ファとシ・ド)。社会学者のM.ヴェーバーによれば、半音を含む5音階は世界的にも避けられる傾向が強いとのことで、その珍しい例の一つとして日本が挙げられている(『音楽社会学』より)。
上原六四郎は、八木節のような半音を含まない音階(ミを主音にするとミ・ソ・ラ・シ・レ)を田舎音階および陽旋と呼び、都節・陰旋と対比させた。たしかに田舎節は非常に素朴な響きがあるのに対して、都節は艶っぽく、大人の密やかな情の交わりのような雰囲気がある。不思議なことだが、「半音」(註)にはどこか人間の割り切れない情念や心意のようなものを表現する力があるのかもしれない。
註:この「半音」という表現自体、西洋音楽の表現なのだけれども、逆に12分割したとなり合う音を「半音」とした上で、それを和声的かつ旋律的に利用可能にした点にこそ、西洋機能和声法の真骨頂があるともいえるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
