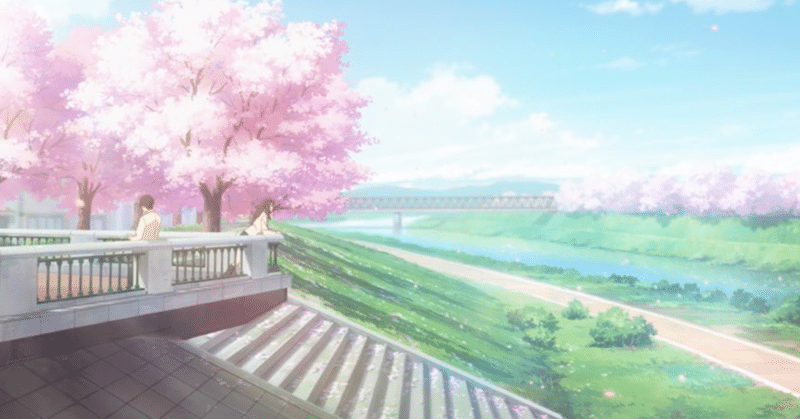
桜の木の下【短編小説/後編】
この小説は、kesun4さんの詩
「桜の木の下」
をイメージしています
言葉がずるずると溢れて止めることができない。
「葬式が終わってから、引き出しの中にあるのを見つけて。彼女が自分の名前を書いていて……書類の表面に濡れた跡があった。多分、涙だと思う……泣きながら書いたんだ。彼女の友人に言われました。僕が彼女を苦しめていたって。知ったのは、彼女を失ってからだ。もっと早くに気づいていれば……」
それまで黙っていた、トメと呼ばれた女の子が、口を開いた。
「会ってどうする」
皆は同時にトメの方を見た。トメは無表情な顔の中に、強い眼の光をたたえ、視線をひたと僕にあてた。
「女は既に死んでいる。もうお前にはなにもできない。今さら会って、どうしようというのか」
僕は目を見開いて、トメを見つめた。
「僕は……ぼ、ぼくは……」
「♫あなたがいた頃は〜笑いさざめき〜、誰もが幸せに見えていたけど〜♫」
突然、音楽と歌声が聞こえてきた。音が届く範囲のモノノケ達は、一斉にそちらを見た。地面の傾斜が少し高いところに立ち、マイクを持って歌う人影がある。いや、よく見ると人じゃない。洋服を着ている一つ目の妖怪だ。誰かが持ち込んだものか、重箱を積んだ上に屋外用のポータブルカラオケセットが載っていて、大きなスピーカーから音楽が鳴っている。
妖怪は、杉田か○るの「鳥の詩」を歌っている。なかなか達者な歌声で、周りのギャラリーは手拍子とともに声援を送っていて、盛り上がりを見せている。僕は、妖怪もカラオケで歌謡曲を歌うんだな。と妙な感心をした。
やがて「♫鳥よ、鳥よ〜鳥のうたぁ〜♫」と歌が終わり、拍手とともに群衆の中から、次のものが立ち上がって、歌い手は交代した。マイクを受け取ったのはなんと逝上だ。
「逝上さん」
僕は呆然として呟いた。剥き出しの丸い頭にグラサンをかけている。逝上の顔は真っ赤で、明らかに酔っている様子だった。彼がわずかにフラフラしながら位置に着くと、音楽が始まった。
「♫雨を避けたロッカールームで〜君はすこし俯いて〜もう戻れはしないだろうといったね〜♫」
お世辞にも上手いとは言えない。本人はすっかり入り込んで、身振り手振りを交えて熱唱しているのだが、周りからはたちまち野次が飛んだ。「おいおい、似てるのは見た目だけか」「知ってるぞ、あれだ爆福スランプ……」「……これって上手いの?下手なの?」
それでもサビの「♫走る走る〜俺たち♫」のところは、周りも盛り上がって一緒に歌ったり踊ったりしている。
振り返ると、トメの姿が見えなくなっていた。僕は目でおばさんを探したが、おばさんは「マイクを貸してみなぁー」と喚きながら、群衆をかき分けて、カラオケの方に向かって歩き出したところだった。ワンピース女と壮年男が呆れ顔で「おときさん、いつもの奴か」「『また君に恋してる』好きだよねぇ」と話している。
「歌は、生者だけでなく死者をも慰める」
ふいに、至近距離で剃髪の美青年に囁かれ、僕は思わず身を引いた。近くで見ると喉元と両手首に、包帯のような細長い布を巻きつけている。
「西洋では、歌は礼拝に欠かせないものだ。仏教にも賛歌はあるのだが、あまり一般の人は知らない。私は歌が好きなんだ。生前は歌うどころか話すこともできなかったがね……」
青年は話すときに口を開けていない。なのに、声が聴こえるのが不思議だ。彼は喉元に巻かれた包帯のような布を指でずらして見せてくれた。そこには、切り開かれた後に乱暴に縫い合わせたような、大きな傷跡があった。僕は息を呑み、おそるおそる尋ねてみた。
「死んでも、傷は消えないのですか」
「いいや。死者は肉体の枷から自由になるものだ、大抵は。これが消えないのは、私の肉体以上に、心についた傷が深かったことの証のようなもの……だが時が経つほど無念の想いは薄れて、この世に留まり続けることが難しくなる」
穏やかな佇まいの中に壮絶な過去が垣間見えて、僕は言葉を失った。おばさんは“自分と同じくらい古い死者たち”と言っていた。この世に留まる長さは、生前に抱えていた無念の深さに比例するのかもしれない。逝上を眺めて笑っている、ワンピース女と壮年男を見て、僕は複雑な気持ちになった。青年も逝上を眺め、少し笑った。
「何が言いたいのかというと、其方の妻女のことだ。思い入れがある歌を知っていれば、ここで歌ってみるのも手だ。届くかもしれぬよ」
「……!」
僕は、深々と頭を下げた。
「ありがとうございます!」
僕は群衆をかき分けて、カラオケ場の方へ向かった。逝上とおばさんが、次はどちらが歌うかとマイクの取り合いをしていて、周りはその様子を面白がっている。
僕はそこまでたどり着くと、二人に向かって勢いよく頭を下げた。
「お取り込み中すみません。どうか次は、僕に歌わせて下さい。春香が好きだった歌があるんです……桜の歌です。今ここで歌えば、彼女に聞こえるかもしれない。どうか、お願いします」
逝上とおばさんは顔を見合わせた。逝上はいくらか酔いの醒めた顔で
「もちろんっす。川井さん、思い切りぶちかましちゃってください」と言い、おばさんも「これで出てこなかったら、諦めるんだよ」と、マイクを渡してくれた。
僕はポータブルカラオケに曲名を入力した。小さな画面に歌のタイトル「桜の木の下 /唄 kesun4」が表示される。僕は群衆に向き直った。昏い空間の中、光る花びらが舞う宴席では、向こうの彼方まで、たくさんの死者とモノノケ達が見える。まるで舞台の上から客席を眺めているような気分だ。
前奏が終わり、僕は思い切り息を吸い込んだ。
♫ 桜の木の下には死体が埋まっているそうで……
何も戦争の事を嘆いてそんな事を言った訳でも
流行り病を嘆いてそんな事を言った訳でも♫
営業職では、接待でカラオケに行く場面もある。そんな時、僕はこの曲だけは歌わない。僕にとっては、春香のためだけの歌なんだ。初めて死ぬほど練習した歌。
♫ただ、満開の桜に目を奪われて
こんなに狂ったように咲くのなら
足元の事など、いっさい忘れて
この匂いと淡い桃色に飲み込まれるのも
決して悪くはない訳で♫
目の前で好き勝手にざわめいていたモノノケ達、死者たちが、話をやめて、僕に視線を向け始める。
♫自分もどうせいつかは死んで
土へと生まれ変わるならこんな桜の木の下で…
きっとそんな風に思った人が♫
……いるんだろ、ここに。この、どこかに。
出て来てくれ春香。お願いだから。ああ、この歌を歌ったのは……いつぶりだろうか。
♫ 死んだら桜の木の下にと
残された者に頼んだのかも知れないなと
桃色の花弁の隙間から見える青い空を見ながら
ふっと思った訳で♫
宴席の人の波が次第に鎮まり、その静けさは……
水に投げ入れた石が波紋を広げてゆくように……僕から近いところから次第に遠くへと……
♫今日もあの日と同じ様に
桜は綺麗に咲いていました
きっとこの先も♫
群衆の中を次第に近づいてくる……ちらちらと見えるのは、トメの姿。トメは白い布を頭から被った人物の手を引いている。それに気づいたモノノケ達が、彼らに道を譲る。割れてゆく人がきの先端が、僕に近づく。
♫何度も何度でも
桜は綺麗に咲くのでしょう
世界に何があったとしても
私が土に還ったと……♫
「ゆういち!」
人がきの先頭から飛び出して来た白い布の人物は、顔の左側だけわずかに布から覗かせて僕の前に立った。
「はるかっ」
僕はマイクを放り出すと、彼女に駆け寄って抱きしめた。彼女の身体は冷たい。でも、この感じは間違いなく春香だ。
「本当に雄一? なんでここに、どうやって……ううんそれより、早く逃げて! ここは、生きてる人は危ないから」
僕は僅かに体を離して、彼女の左半分側の顔を見つめた。布に隠れている側は……まだ、傷ついたままなのだろうか?そう考えると、胸が締め付けられるように、苦しくなる。
「……うん、分かってる。ここに来るまで、沢山の人たちに助けて貰った。僕はただ必死で。もう一度、君に会わなきゃって。分かったんだ、自分が何をしたのか。僕は君に……ずうっと長い間、酷いことを……」
ああ、春香が目の前に居るのに。焦りすぎて、頭が回らない。上手く喋れなくて、ますます焦りが募る。
子供たちの姿が脳裏をよぎった。あの、驚きに満ちた一日のことが思い浮かんだ。
「……こども……食堂に行った。はじめて。夏木さんと会って、他の人たちとも話をして。春香がここで、どんなだったか聞いた。どんな風に働いて……どんな風にご飯を作って、子供と触れ合って……」
言葉が喉でつかえて、涙が溢れてくる。
「から、唐揚げを、作る、手伝いをさせて貰って……大変なんだね唐揚げって。肉に衣を付けるのも、油で揚げるのも……でも、子供はやっぱり、唐揚げが好きなんだよな……僕が作った揚げすぎの、焦げついた唐揚げを……おいしいおいしいって、食べてくれてさ……」
春香は、優しく僕を引き寄せて、ゆるく抱きしめた。僕は縋るように彼女に捕まって、話つづけた。
「たくさんの……子供と、その親と、いろんな話をして……これが春香の見ていた光景か。僕はなんて狭い世界しか見えてなかったんだ、そう思って……一番、身近な君のことも、見ているつもりで、全然見えてなかった……気がついたのに。やっと気がついたのに……君はもういない」
こんどこそ、春香とちゃんと向き合って話をしよう。そう思っていたのに、僕だけが一方的に喋って、彼女に縋りついて泣いた。遺体を確認した時も、葬儀の手続きをしている時も、ずっと出なかった涙が、びっくりするほどやすやすと、とめどなく出て来る。
「雄一」──春香の声が聞こえる。
「ねえ私たち、いつの間にか、一緒にいても話ができなくなってたよね。私も、諦める前に、もっと闘えばよかったね。結局、いちばん酷い形であなたのことを傷つけた……雄一、ありがとう、伝えに来てくれて。嬉しい。ものすごく嬉しいよ」
辺りのざわめきが急に大きくなった。
「……場が……」「……移動する……」
トメとおばさんが、僕の方を見て何か言っている。
「お・さ・ら・ば」
二人の死者は、後ろを向くと群衆の方へと歩み入り、姿が見えなくなった。桜並木の間を強い風が吹き抜け、死者やモノノケ達の服をはためかせ、花びらが渦を巻く。急速に群衆の輪郭がぼやけて歪み、宴席の端の方から、まくれ上がるように闇へと溶けてゆく。
春香は僕の身体を離した。そして、ゆっくりと後ろへ下がってゆく。僕はなおも、彼女に縋ろうとしたが、側に来ていた逝上が、僕を押さえた。
「春香っ」
「私の分も、生きてね、雄一。それから、できる範囲でいいから、困っている子供達を助けてあげて。ああよかった。伝えられた……」
風が渦を巻いて、彼女の服と髪の毛を吹き乱した。彼女の顔の半分を覆っていた白い布が風で引っ張られて、滑り落ちた。
損なわれる前の顔が、そこにあった。久しぶりに見た、そして最後の、晴れやかな微笑み。
「はるかーーっ」
墨のような闇が辺りの風景を塗りつぶしてゆき、彼女の微笑みが滲んで、闇に溶け込むように消えていった。
***
地平線に薄く、暗い赤が現れて、辺りはいくらか明るくなった。
気がつくと、僕らは夜明けの原っぱに二人でぼんやりと立ち尽くしていた。逝上は僕の手首から赤い糸を解くと、腕を離し、僕はその場に跪いた。原っぱの向こうには、長い一本道が左右に伸びている。見覚えのある風景だ。
「……あの道を通って……学校に行ってました。僕たちは。僕と、春香は……」僕はうつむいた。「あの頃は、並んで歩くだけで、死ぬほど幸せだったのに……なんで……僕は」
逝上はぼんやりとした調子で言った。
「人って、近すぎると見失いがち、らしいっす」
「誰の台詞ですか」
「姉です」
僕は後ろに立つ彼を見上げた。
「恋人はいないんですか」
逝上は、懐に手を入れて、紺色のバンダナを引っ張り出すと頭を覆った。
「まあ、俺は生きてる人より死人の方が、話す機会が多いような奴なんで。こんな怪しげな坊主、付き合わないに越したことないっすよ」
僕はポケットを探り、指輪を取り出した。逝上はそれを見て
「奥さんのですか。あーだから、モノノケ道に入っちゃったんすね。故人の身近なものを持ってると、たまに引き寄せられるんです」
「これを持っていれば、また会えるんですか?」
逝上は首を振った。
「彼女、綺麗になってましたから。あ、綺麗ってのは、霊的な意味ですよ。だからね、奥さんが”場”に居る時間は長くないと思います。もしかしたら、もう”還った”かも」
「還る……」僕は立ち上がりながら呟いた。「どこに……」
「知り合いは『生まれいずる前』って言ってました」
「生まれいずる……その知り合いって何者ですか」
「さて、爺さんの頃からの付き合いらしいんすけど。人間じゃないことは確かです。鬼か、悪魔か」
僕は驚いた。
「悪魔?」
逝上は肩をすくめ、苦笑した。
「ひとの姿をしたひと以外のナニカって、意外と多いっすよ、世の中には」
***
「あのさ! これっ」
突然の声に、私はビックリして振り返った。まだ時間が早いせいで、通学路には誰もいないと思い込んでいたから。
声をかけてきたのは、高校生の男の子だった。彼は私に何かを差し出した。よく見ると、手にモケモンのキャラクターキーホルダーが握られている。
「落としたよ」
私はようやく、そのキーホルダーは、いま私が落としたもので、彼はそれを拾ってくれたんだ、と気がついて慌てた。
「あっ、ありがとうございます! ごめんなさい気がつかなくて」
私はキーホルダーを受け取った。一番くじで手に入れた、激レアなキーホルダーだ。失くしたら大変だった。
彼は、小走りで後ろに戻ると、停めていた自転車のスタンドを足で外した。キーホルダーを拾うために、咄嗟に自転車をその場に停めて、走ってくれたんだ。私は申し訳ない気持ちになって、彼が側に追いつくまで、何となくその場に留まった。
彼は自転車に乗らずに、それを押して歩いて、私の側まで歩いて来た。制服で、桜坂高だと分かる。この辺りではそこそこ名の知れた進学校だった。
私たちがいる道は、まっすぐな一本道で、道の終点で左右に分かれる。彼が自転車に乗らずに歩いているので、私も並んで歩き始めた。妙なことになったな、と思う。だって、知らない男子と一緒に登校するなんて。
沈黙が続き、次第に気まずさが増してゆく。変に気を使わなくていいから、とっとと先に行ってくれないかなぁ……。
その時、彼が口を開いた。
「ぼ……おれの事、覚えてる?」
「えっ? ごめんなさい……えっと、どなたでしたっけ?」
向こうは私を知ってるらしい。必死に思い出そうとするけど、歳上の男子の知り合いなんていないはず。人違いじゃないかな?彼はがっかりした様子で
「まあ、そうだよな。前に、笹川公園でさ。女の子の落としもの、探すの手伝ったことあるんだけど」
「あっ、あー! 思い出したっ。ゆっこのビーズの指輪、一緒に探してくれたひと。そっか、あの時も見つけてもらって。それに今も拾ってもらって。えーなんかすごい、すごい偶然」
思い出すことができてホッとした。こんな所で、恩人に再会するなんて。知り合いと分かってグッと気が楽になり、私は彼の様子をまじまじと観察した。
「桜坂、ですよね、その制服。全然変わっててわかんなかった、やっぱ高校生って大人っぽいです」
彼はこちらをチラチラ見ながら
「そう? おれは、すぐ分かったけど。お前、ぜんっぜん変わってないから。この時間に学校行くって朝練? 何部?」
私はその言葉に少しモヤモヤしながら「……ソフトテニス部です」と答えた。また話が途切れて、私たちは無言のまま、歩き続けた。
小学校の頃から変わってないとか……要するにガキっぽいってことだよね。
小学四年生くらいから、友達の話題はファッション雑誌とか、服の流行とかになってきて、新しい服だのアクセだのを自慢したりLINEで陰口言ったりするようになって、私はそういうのは何だかなぁ、と思っていた。アクセサリーより好きなアニメの話の方が楽しいし、みんなと仲良く盛り上がれるのに。でも今になって、それがガキっぽいってことなのかな、という気がしてテンションが急降下する。次第にモヤモヤを通り越して、少し悲しくなってくる。
一本道の終点、別れ道のところまで来た。彼の高校は右方向、私は左だ。何なんだろ、すごく心が複雑な感じ。気まずさから解放されてホッとした、もう会うこともないと思うとちょっとだけ名残惜しい、ガキっぽいと思われて何だか悲しい、そもそも何で関係ない人の言葉にこんなにモヤモヤしないといけないんだ、と腹が立つ……こういう全部の気持ち。
男の子は別れ道で立ち止まり、私を初めて正面から見た。
「顔は覚えてたけど、名前は忘れた。おれは川井雄一。お前さ、えっと名前……その……」
「筒井です。筒井春香」
「分かった。筒井。また会うかもね。おれ朝ベンでこの時間に行くから」
「朝から早弁? 朝ごはん食べてないんですか?」
彼は吹き出した。
「ベンは弁当のベンじゃなくて、勉強のベン」
私も笑った。
「ですよね。朝から弁当は早すぎますよね」
笑ったことで空気が柔らかくなった。私は左方向に歩み出しながら彼の方を振り返り「じゃあ……」と言った。
彼は自転車の脇に立って「あのさあ、さっき言ったこと、嘘だから」と声を張り上げたので、私は足を止めた。彼は続けて
「全然変わってないとか、嘘だから。すごい変わったわ、お前」
と言うと自転車に跨った。私は慌てて呼びかけた。
「え、どこが? どこが変わったんですか」
「だからあ……かわいくなったっ、てことっ!」
彼は怒ったように言うと、こっちを見ずに自転車を漕ぎ出した。
私はポカンとしてその場に立ちつくし、彼の後ろ姿を見つめた。遠ざかっていく彼の耳たぶが真っ赤になっているのが、ここからでもよく見える。
さっきまでのモヤモヤがいっぺんに吹っ飛んで、お腹の底がポカポカしてきた。ポカポカは、嬉しい嬉しい嬉しいって気持ちになって、私はその場でぴょんぴょん飛び跳ねたくなる。
──私の人生に、なにかがはじまったんだ。
とてつもなく素敵な、なにかが。
(完)
***
kesun4さんとのコラボ小説、第二弾!
遅くなっちゃってすみません💦
詩の内容をうまく絡ませられたか、少々疑問も残りますが……
逝上シリーズ(?)三作目、大好きなモノノケ&死者たちを書けて楽しかったです。
kesun4さん、読んでくださることと、たくさんのコメントと、おすすめと。
感謝感激であります。ありがとうございました😊
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
