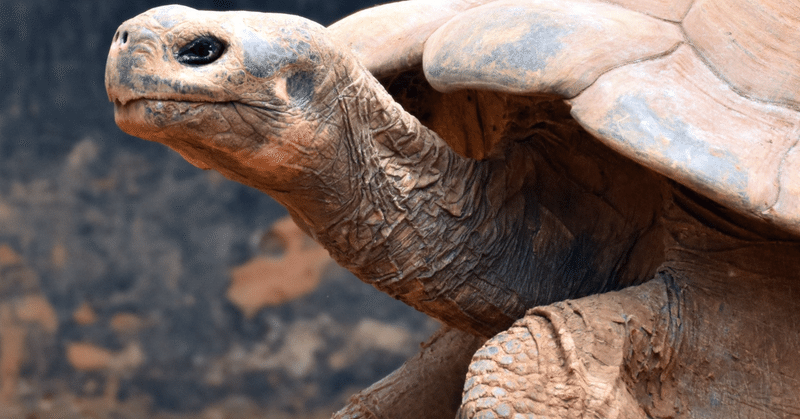
ガラパゴスとマクドナルド~文化的多様性と均一性について~
ユニークさについて
島によってくちばしの形が異なる。どうも食べ物に依存しているらしい。食べやすい、獲りやすい形状に適応しているようだ。
ダーウィンフィンチが示す形態の特殊性は、絶海の孤島という外的要因が少ない環境で生まれた。
ガラパゴス諸島におけるニッチのユニークさは、進化論によって人口に膾炙している。
ここで問いたい。ガラパゴスを「ユニーク」だと感じるのはなぜなのか?
もちろん、自分がマジョリティだと思っているからだ。ユニークというのはおおよそいい印象を与える言葉だが、自分とは違う、という前提に立っている。悪い言い方をすれば「変わっている」「変」になるだろう。
では、もし、ガラパゴスから外を眺めたらどのような景色が見えるのか?
自分たちはマイノリティだと思うのか?
違う。
外の世界は「ユニーク」だ。
そう思うに違いない。外の世界とのコミュニケーションもないのだから、自分たちが少数派だということもわからない。
大航海時代等を経て、文化的生物的グローバリゼーションが引き起こされつつあることを知らない。
マスメディアが登場するまでは、それが普通の感覚だったと考えられる。
ネット社会の功罪は、どうやら自分たちはマイノリティらしい、と気づく、もしくは「勘違いする」ことにある。
人々はその場合、どういう行動をとるだろうか。
文化の差異が生まれる背景
現在、ニューヨーク、ロンドン、東京で道行く人々のファッションをそれぞれ眺めたとしても、違和感はあまりないだろう。
100年前だったらどうだろう? 200年前だったらどうだろう?
時間を巻き戻すごとに、それぞれの国で異なる文化がはぐくまれていることが一目でわかるはずだ。ちょんまげをつけながらテンガロンハットをかぶっていたロンドンっ子はいないし、どの街角でもナイキのシューズを見かけることもない。
逆に、時間の針を先に進めてみればどうなるだろう?
未来のことは誰にもわからないが、均一化が進んでいると予測する人が多いのではないだろうか。
人は他人に影響される。研究結果もあるし、朱に交われば赤くなる、といった経験則もたくさん残されている。
アレクサンドロスの遠征で何が起きたか?
東西文化が融合したヘレニズム文化が拓けた。
遣唐使を廃止して何が起きたか?
日本独自の国風文化が花開いた。
文化も生物も、クローズであればあるほど、周りとは異なった独特の進化を遂げる。
オープンになればなるほど、周りに影響されあった折衷的なところに落ち着く。
マクドナルド化する社会
本文におけるマクドナルド化というのは、どこでも均一のサービスが受けられることから派生した、文化的均一化が進むという定義で使用する。
当たり前だが、マクドナルド化は有益な面もあるし、不利益をもたらすこともある。
不利益の側面に注目する。均一化が生じると、いざというときにすべてがダメになるという現象が起こる。
東日本大震災でのサプライチェーン然り、発展途上国でのプランテーション農業然り。一つのものに依存すると、ダメになったときの被害が大きい。
トレーダはポートフォリオを組むし、プログラムはフェイルセーフの考え方を取り入れている。
選択肢を増やすことは、不確定な未来に対する唯一の答えだ。恋愛においても、ずぶずぶの共依存が健康的ではないことは一目瞭然。児童でも、学校以外の社会を持っている(習い事でも宗教でもなんでも)子はレジリエンスがあると言われている。
多様性のメリットはたくさん喧伝され、均一化のデメリットも指摘されているものの、マクドナルド化は多国籍企業やネットによってどんどん進んでいる状態だ。
音楽的な話をようやく始めよう
※以前もどこかで断ったが、音楽性が良いとか悪いとか、そういう話は一切しない。
おそらく、現代日本においては、ワールドミュージックを聴けば、「こんな音楽があるんだ!」と思う人がほとんどだろう。
しかし、明治時代初期に西洋音楽が入ってきたときにも同じことを思ったはずだ。「雅楽とは全然違う!」と。
今は、西洋音楽と雅楽が折衷された世界に住んでいるので、西洋音楽に対しての違和感があまりない。垣根が低くなっている。
なので、逆にJ-popはアメリカの人が聴いても楽しめるはずだ。どの程度本当かは知らないが、シティポップが再燃しているのは海外からの逆輸入というニュースをみた。
現代社会の音楽分野においては、西洋音楽が圧倒的なマクドナルドであることには異論がないだろう。
逆にワールドミュージックはガラパゴス化され、ユニークな体系になっている。
この事実を敷衍すれば、少しミクロな世界に潜っても同じ景色が見えるのではないだろうか。
小さなコミュニティというガラパゴス
世にはばたく音楽バンドというのは、結成し、曲を作り、ファンを集めて、デビュする、という流れを経ている。
ここで考えたいのはコミュニティの大きさだ。
ファンを獲得する段階において、コミュニティが小さいほうが、ユニークなものが進化しやすいと考えられないだろうか。
つまりは、クローズなガラパゴスだ。
小さいコミュニティの場合、なんらかの要因で特定の好みを持ちやすいし、進化のたこつぼに入り込みやすい。
ものすごく卑近で単純な例を出せば、ボーカルがその学校一番のイケメンだったとか。
そして、そのコミュニティ内バンドのニッチの頂点に立ったとしよう。
そうなると、あまり周りを気にせず自分の音楽を貫きやすい。横のつながりもそこまで広くないので、影響されにくい。世の中の情報は入ってくるだろうけれども、まず戦う相手は対バンする相手なのだから、大きな流行りはあまり関係ない。
人は集団の意向から外れることを極端に嫌う性質があるので(研究結果あり)、ある程度のファンがついているものは無視できなくなり、バンドワゴン効果が働きはじめる。
そう考えると、日本各地のライブハウスから出てくるたたき上げのバンドは、当地のコミュニティの意向を踏まえていると考えられる。つまり、ガラパゴス化された多様性の中成長してきたのだ。
大きなコミュニティのマクドナルド
では、ここでネット上の活動を考えてみる。
ネットは広く繋がった大きなオープンコミュニティだ。
横のつながりでお互いが影響を与えあう可能性が高くなる。あの曲が伸びている、という情報が嫌でも入り(しかもたくさん)、意識的無意識になんらかの影響が与えられる。また、曲を発表するという側面でも、隣町のあのバンド、ではなく、ネットコミュニティが相手になるため、大きな流れが無視しづらい。
つまり、マクドナルド化しやすい状態になっているのではないだろうか。
もちろん、コミュニティ内での分派は存在するが、ガラパゴス化された世界が異教徒の集まりだとすると、マクドナルド化された世界のそれは同じ宗教内の異端の集まりだ。神の数や世界観は同じで解釈が異なる。
比較しやすい一定の秩序がもたらされるため、内部では明確なヒエラルキ構造が生まれやすい。
今後の世界
AIが猛威をふるっている。
文章、絵、音楽、プログラミング。
どんな分野でもどんとこい。
AIは過去から何かを紡ぎ出す。
青と赤を取り入れて紫を生み出す。
つまり、マクドナルド化だ。
混色を重ね、行きつく先は何か?
どれも黒。
フォーマルでもカジュアルでも使える万能な色。
誰も困らないし喜びもしない。
私はAIに席巻された世界の後に、本当の人間の時代がやってくると思っている。過去を均質化したような無難な答えがあふれる社会に求められるのは、人間にしか生み出せないアイデアだろう。
私は天才を「様式を破壊するもの」と定義している。
写実的だった絵画は印象派によって破壊された。
印象派はキュビズム等の抽象的な一派によって破壊された。
停滞する流れを変えることができる人が、天才だと思う。
音楽の歴史も破壊されてきた。
クラシックはジャズに、ジャズはロックにメインストリームを明け渡してきた。
皮肉な話になるが、現状を打破した創造的な破壊者は、その後フォロワが増えてしまうため、破壊される対象であるマジョリティとなってしまう。
終わりに
声の大きな人がいる。
何か意見を言っている。
少し自分の意見と似ている。
やはり、自分の意見は正しいと確信する。
声の大きな人がいる。
何か意見を言っている。
自分の意見とは少し違う。
自分の意見を修正し、信じ込む。
人は流されやすい。
他人を誤解しやすい。
その結果、「多くの人がそう思っているだろう」という幻想に操られ、自分の意見を行動を変える。周りの人も同じように思い、自分の意見を封じ込めながら、みんながこう思ってると思う意見に合わせていく。幻想上の多数派が誕生する(昔からの因習は大体そうだ。ほとんどの人が無意味だと思いながらも、他の村民は大事だと思ってるんだろうと勘違いし、自分も合わせている)。
チリだらけだった太陽系。チリの初期分布の少しのゆらぎが、特定の場所に集まる力を加速させ、惑星が誕生した。
意見も同じ。強い意見の周りの少し異なる意見は、流されやすい人の性質から集約されていく。
マクドナルド化する世界で生きていくには、このような認知的不協和を避けることが大事だ。
自分を曲げ、他人の評価基準に合わせた行動をとるとき、人はストレスを感じる。
自分の信念に沿った行動をとるとき、他人評価ではなく自分の価値基準で動くとき、人はストレスが減り幸せを感じる。
自分を信じて生きていきたいと、改めてつよく思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
