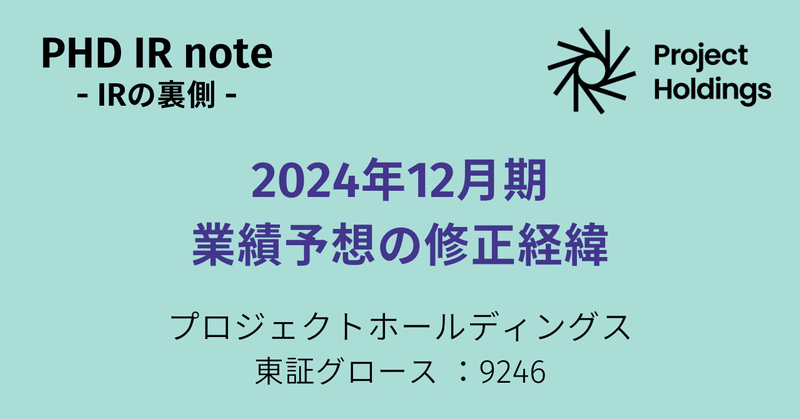
2024年12月期 業績予想の修正経緯|PHD IR note
(株)プロジェクトホールディングス 経営企画ユニット長の三科(みしな)です。
応援・ご期待いただいていた株主の皆さまには大変申し訳ないながら、当社は5月15日に2024年12月期 第1四半期決算の公表と併せて通期の業績予想を下方修正いたしました。
第1四半期の業績は計画対比では上振れにて着地した中、通期業績予想をこのタイミングで下方修正するに至った経緯をご説明できればと考えております。
業績予想修正の全体像
今回、業績予想を修正せざるを得ない状況となった要因が複数あり、大きく以下の3区分となります。
地代家賃の計上方法を予算策定時の想定から変更したこと
専門家等との協議も踏まえ、今期に実際の支払額を上回る地代家賃を費用計上することとなりました
(逆に、来期以降は当初想定より計上額が少なくなります)連結子会社であるプロジェクトHRソリューションズ社の株式譲渡
5月15日に決議した株式譲渡に伴い同社が連結対象でなくなるため、同社が今期計画していた売上・利益を控除する必要がありますその他の要因
一部費用の計上科目を前回予想時から修正したこと、デジタルトランスフォーメーション事業における従業員育成の優先、株主優待費用、など

このうち、要因①・要因②が年間で▲2.6億円の利益インパクトと大きく、決算説明資料中(p.24、p.25)でもご説明している通りです。
以下では「その他の要因」として織り込んだ修正要因のうち、特にデジタルトランスフォーメーション事業における従業員育成の強化について、背景・経緯を詳述できればと思います。
従業員育成の強化と業績予想修正との関係
今回の業績予想修正の理由として、「従業員育成の強化」がどのように関係しているのか、ここには過去、当社が成長してきたトラックレコードが大きく関連してきますので、順を追って説明してみたいと思います。
ベンチャー企業としての成長期(~2022年)
私たちが目指すのは「プロジェクト型社会」。次世代の日本を創り出すべく、ビジネスを成功に導ける人材を輩出し日本社会を変革することを目指しています。
そのため、主軸のデジタルトランスフォーメーション事業で顧客の事業をグロースする支援サービスを展開し、その中でキャッチした顧客企業の共通的な課題やニーズを解決するソリューションをサービス化・プロダクト化していくことで、事業領域を広げていくというビジネスモデルを考えています。
【参考】2024年3月1日「事業計画及び成長可能性に関する事項」 p.18-20
このミッション/ビジョンの達成に向けて、いわゆる”ベンチャー企業”として、次のような点を重視することで、主軸となるデジタルトランスフォーメーション事業を急速に拡大してきました。
トップダウンの徹底による、迅速な意思決定
若手/ポテンシャル人材の早期抜擢による育成
「量質転化」の考え方に基づき、貢献売上・利益を重視する評価体系
これらの徹底によって、成長志向のベンチャー企業がまずぶつかると言われる「30人の壁」「50人の壁」も早期に突破、複数の20代執行役員が誕生するなど目に見える功績もありました。
【参考】30人の壁、50人の壁について、分かりやすく書かれています
ひずみが生じた2023年
デジタルトランスフォーメーション事業のみで100名を超え、M&Aでグループジョインした会社も含めると250名規模となった2023年、トップダウンによる意思決定が徐々に組織浸透しづらくなり、バランスが崩れ始めます。

(2023年8月15日「2023年12月期 第2四半期 決算説明資料」 p.24)
専ら、若手期待人材の早期抜擢による組織構築に依存していたため、マネージャー層の数・質ともに万全な状態ではなく、一部マネージャーに負荷が偏る、十分に面倒を見てもらえないメンバーが発生するなどに伴って離職者が増え始めました。
そこに被せて、不祥事が発生します。その後は組織に対する不信感から離職者がさらに増加、不祥事自体の対応も相まって、事業成長のドライバーである採用もままならぬ状態で年末を迎えました。
オフィス移転から始まった2024年
2024年1月、オフィスを移転し商号も「プロジェクトホールディングス」と改めて、心機一転スタートを切りました。
このタイミングで、大きく会社のカルチャー・方針を転換しています。大きなところでは:
(これまで)上→下への一方通行を中心とするコミュニケーション
→ 人事企画部門を新設し、社長座談会や従業員サーベイなどを導入することで双方向のコミュニケーションの基盤を整備(これまで)とにかく抜擢による自己成長
→ 人材育成をミッションとする組織を組成し、ポテンシャル人材の仕組みとしての育成を強化(これまで)「量質転化」に基づく短期業績重視
→ 業績貢献に加え、個人の能力成長や他者育成の観点を評価体系に組み込み
細かな施策レベルでは成功・失敗とあったものの、全体としては概ねうまく進んでいるものと捉えており、実際に2023年12月に15名、2024年1月に10名となっていたデジタルトランスフォーメーション事業における離職者数は、2月に1名、3月は4名と落ち着きを見せています。
【参考】2024年5月15日「2024年12月期 第1四半期決算説明資料」 p.20
さらに注力すべきことが見えてきた
2024年1月から3月にかけての上記取り組みを振り返ると、プロジェクトカンパニー社において、さらに強化したい・すべきことが見えてきました。
プロフェッショナルが働きやすい環境の整備
コミュニケーション基盤や評価体系の刷新に留まらず、プロフェッショナルが生産性高く働くための制度を継続的に企画・運営していく必要性、そのための体制を増強する必要性が見えてきました。
直近では、業務状況に応じたフレキシブルな勤務制度や、一人ひとりの希望に応じたキャリア選択のための社内公募制度をリリースしています。育成にフォーカスした組織体制への移行
人材育成をミッションとする組織を切り出して運用していましたが、さらに深化させて各チームのトップが育成にミッションを持つべきではないかという議論がありました。
これを受けて下図のような並列本部制に改組し、各本部長が明確に配下のマネージャーやメンバーの育成に対してミッションを負うこととしました。
その中で、各種研修や勉強会の開催も活発になってきています。

上記2点を中心に、事業のリソース(社員の工数)を一部、人事企画部門や育成施策に回すことになり、これが短期的には業績に対してネガティブな影響を与えてしまうこととなりました。
来期以降に向けて
このような経緯と、固定費の負担増などを背景に今期の業績予想を下方修正し、通期で赤字の予想とさせていただきました。
一従業員としても非常に残念ではありますが、一方で、しっかりと上記のような仕組みを整備し組織を作り変えることで今後の成長力の源泉となる、即ち今期この従業員育成の強化(仕組化)にフォーカスすることでしか、来期以降に改めて成長軌道に戻すことが見通せないという経営判断となります。
これまでの方針下でも昨年水準の業績を出し続けることは可能ではあろうかと思いますが、当社が目指す世界は決して現状維持ではなく「100億×100社」です。
実際、来期に向けて新たな領域での支援メニュー拡充等の検討・仕込みを進めており、これらをしっかりと立ち上げていくためにも、今期は人材を集め、育成する期間として、株主や応援いただいている皆さまにも是非、長い目でご理解をいただけますと幸いです。
執筆: コーポレート本部 経営企画ユニット長 三科 朋大
注意事項
本記事は、情報提供のみを目的として作成しており、有価証券の販売の勧誘や購入の勧誘を目的としたものではありませんのでご留意ください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
