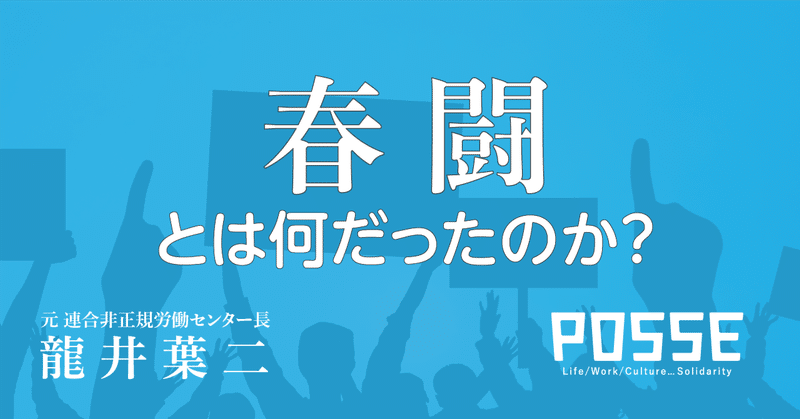
春闘とは何だったのか?──元 連合非正規労働センター長 龍井葉二
急激な物価上昇のなか、今年の春闘の賃上げは、いっそう注目が高まっています。連日、大企業の回答結果が報じられている一方、今年は非正規雇用の賃上げや改善を求める「非正規春闘」も盛り上がっています。
そもそも「春闘」とはどのように始まり、どのような問題点や限界を抱えてきたのでしょうか。このように春闘が注目を集めているときだからこそ、意外と知らないその歴史と構造、問題点について掘り下げていきたいと思います。
連合の春闘の現場にも長年関わった経験を持つ、元非正規労働センター長の龍井葉二さんにご寄稿いただきました。
本記事は、3月下旬刊行予定の『POSSE vol.56』の特集「春闘をアップデートせよ! 非正規×インフレ危機」に基調論文として掲載される予定です。
本誌では、この論文をもとに、木下武男さん(労働社会学者)、今野晴貴(POSSE代表)と龍井さんの鼎談も掲載。ほかにも、全労連事務局長の黒澤幸一さん、非正規春闘に取り組む総合サポートユニオンの青木耕太郎さんなどがご登場予定です。ぜひ本誌もご覧ください。
▼ただいまご予約受付中です▼
春闘とは何だったのか?──龍井葉二
2024年1月、春闘をめぐる政労使会議が開催された。出席した経営側の代表は、春闘の「闘」について、「デフレと闘うことを(三者で)確認した」という趣旨のコメントをした。
2009年秋まで連合本部に在籍し、春闘を担当したこともある私にとっても実に異様な光景であった。
果たして春闘とは何だったのか──それを考えるためにいくつかの論点を検討してみよう。
1 春闘メカニズムの成立
労働組合運動の二面性
労働組合の本分は賃金を中心とする労働条件の維持・向上であり、労働市場を規制するためには職業別・産業別の形態が望ましい──これは労働組合の説明としてお馴染みのものだが、実はそう単純ではない。
この説明には、労働力が商品化され、その商品の価格が集団取引(団体交渉)の対象となるということが前提とされているのだが、その「商品化」自体が大モンダイなのだ。
農地の囲い込みによって生産手段を失った労働者がその労働力を売る以外になくなったからといって、直ちに雇用関係に入るというわけではない。決められた時間に決められた場所に出向き、見ず知らずの他人の指揮命令に従い、機械の一部となる──これは堪え難いことであり、尊厳に関わる問題に他ならない。
つまり、労働をめぐる対立は、二つの軸によって展開されることになる。
(a)労働の商品化自体をめぐるせめぎ合い(解放)
(b)労働力商品の価格をめぐるせめぎ合い(改善)
これは、歴史の進歩や運動の成熟によって(b)から(a)に移行するのではなく、絶えず両方の軸を孕んでいて、ただ、時代の変化に伴ってどちらかがより前面に出てくると考えられる。
春闘スタートの背景にあるもの
では、日本の労働組合運動はどのように推移してきたのか?
ここで想起すべきなのは、日本最初の労働組合である友愛会が、結成8年目となる1919年に決定した方針のなかで、「労働非商品の原則」を掲げていたことである。
当時は農村に足場を残したままの労働者も多く、重工業化・都市化が進行していたとはいえ社会全体としては労働力が商品化の渦中にあったといえる。
その後1930年代に展開される労働運動の高揚は反ファッショの社会運動・農民運動・政治運動と一体のものとして闘われていた。
そして戦後、生産活動においても労働運動においても、その中軸を担ったのは、この1930年代を生き抜いた世代であり、労働運動もその当時のスタイルが引き継がれていた。賃金引き上げの闘いも果敢におこなわれていたが、インフレ下で時期を限ることはできず、「春夏秋闘」の様相を呈する一方、政治闘争や国民運動と一体のものとして展開されていた。
変化が起こるのは、1953年以降である。
一つは、後に総評リーダーとなる太田薫や岩井章らが当時の総評の活動について、「政治偏向」と批判し始めたことである。
もう一つは、1955年に、大河内一男(東大教授)が総評を批判し、総評は労働組合本来の姿に立ち返るべきだという趣旨の主張をおこなったことである。
こうした事情を背景に、1955年にスタートしたのが「春闘」だった。
太田薫が提起した八単産共闘は「暗い夜道にお手てつないで」という産別の共闘の提起であったが、それは単なる賃上げ共闘にとどまらず、労働運動そのものの方向性に関わる方針提起でもあった。
この(a)と(b)との確執は、戦前世代がなお健在だったこともあり、1950年代末まで続いたが、総評における方針転換が明確になるのは、1960年の太田・岩井らによる「日本的労働組合主義」の提唱で、ここで労働組合は「ほんらい」の「身近な要求の実現」に、政治活動は選挙活動に、という一種の分業が提起されていた。
春闘方式の確立
こうして1960年代以降になって、いわゆる「春闘方式」が確立する(同盟では「賃闘」という)。
そこで実現された大幅賃上げは「総評=社会党ブロック」の高揚期をもたらしたわけだが、他方で、民間大企業において同盟の組合員が増加し(その背景には経営側の労組分裂策もあった)、民間企業においては1966年以降、同盟が総評を上回るという事態も起きている。
春闘方式は、主要労組が要求提出と交渉の時期を揃えるだけでなく、その妥結結果が「相場」となって「波及」していった点に大きな特徴がある。
それは、後続の中堅・中小労組にとどまらず、労組が組織されていない企業にも影響を及ぼした。また、労働基本権が制約されている公共企業体の労働者等の賃金についても、1964年の池田首相と太田総評議長の会談によって民間に準拠して改定されることになり、さらにその後、法定最低賃金の目安改定も、中小企業の賃金改定調査の結果を反映することになった。こうして、先行組合(主として大手)による「相場」が結果的に国民経済レベルにまで「波及」するメカニズムが形成されることになった。
つまり、日本の労働組合は、企業別のまま、低い組織率のままで、社会的な影響力を持つ存在となったのである。
このメカニズムは、労働協約の拡張適用によるものでもなく、厳密には解明し切れない性格のものといえるが、背景にあったものはいくつか指摘できるかもしれない。
一つは、職場における争議・ストライキの広がりであり、地域における共闘である。最盛期の春闘の風景といえば職場や地域に林立する赤い組合旗やデモの姿であり、交通機関が止まるのは当たり前のことだった(ストライキ自体は、労働力商品の売り止めであり前記の(a)のように見えるが、実際は(b)のための手段という色彩が強かった)。つまり、春闘は報道されるまでもなく誰の目にも可視化されていた「祭り」だった。
もう一つは、大幅賃上げが、消費拡大→利益拡大→投資拡大という日本経済・企業の成長メカニズムに組み込まれていたことで、こうした中長期的な見通しの下では、人件費は人材投資として将来的に回収可能なものとされていた。賃金引き上げを導いた大きな要因の一つは、人手不足の状況下での初任給引き上げだった。
もちろん、問題点も少なくなかった。
この春闘メカニズムで波及していたのは賃金の引き上げ率であって、賃金の絶対水準ではなかった。大手から中小への波及は、賃金格差の解消には結びつかなかったのだ。
また、労働組合の賃上げ要求は、インフレ経済を前提として、過年度の物価上昇率をその根拠の一つとしていた。低成長経済に移行しても、物価が上昇する限りこの要求根拠は有効だったが、デフレ経済に転ずると、むしろ悪循環を促進することになってしまうことになる(連合で春闘を担当していたときに、この要求根拠を見直すことを検討しかかったが、道半ばで終わってしまった)。
さらに、春闘というメカニズムは、いわば結果的に波及していったものであり、これを通じた労働組合組織の根本的な見直しや組織拡大が進んだわけではなく、むしろ日本固有の企業主義は強化されていったことも指摘できるだろう。
2 春闘の変貌と連合の結成
低成長下の春闘
春闘に転機をもたらすのは、いうまでもなく1973年のオイル・ショックに端を発する低成長への移行である。八単産共闘を提起した太田薫は、「春闘の終焉」を宣言した。労組の中からも経済整合性論など、賃上げ抑制の動きが出てくる。
ところが、春闘メカニズムは、「大幅」とはいかなかったものの、その後も機能し続けた。各企業は、世間相場よりも自社の支払い能力を重視する傾向が強まったが、それでも相場→波及のメカニズムが消え去ることはなかった。
ここで相場形成役としての地位を確立したのが、JC(金属労協)であった。1975年のスト権ストと、1976年のJC同時同額決着は、労働運動における主導権の変化を告げる象徴的な一コマであった。
JCの中心は、鉄鋼労連、造船重機労連、自動車総連、電機労連の四単産だったが、賃金決定は、各産業の主要二企業の労担役員で構成される八社懇でおこなわれていた。この結果をベースとして、後続の労組の交渉はそれに横並び、あるいは上積みを図ることになる。鉄鋼労連がこれを“タダ乗り”として後続組合を批判したように、相場形成役は自ら進んで買って出たわけではなかった。
他方、この不況期に広がった企業の減量経営は、その影響を受けなかった官公セクターに対する反発を呼び起こすことになり、官民分断にとどまらず、行政改革や民営化を支持する動きが民間労組の中にも芽生えはじめていた。
JCは、総評、同盟、中立労連、純中立にまたがる産別で構成されており、春闘の相場形成役がJCになったということは、少なくとも相場形成に関する限り各ナショナルセンターの役割が大幅に後退することを意味していた。逆に言えば、民間大手単産・単組からすれば、賃金決定は各産別の任務であり、ナショナルセンターは政策分野に特化してほしいということになる。ここから生まれたのが1980年頃にスタートした新たな労働戦線統一の動きであった。
春闘における連合の役割
この労働戦線統一の動きの特徴は、ナショナルセンター間の協議ではなく、民間の有志六単産による統一準備会からスタートし、そこでまとめられた基本構想に賛同する産別がまず民間先行統一を実現するという手順をとったことである。
こうして1989年に新たなナショナルセンターとして誕生した連合のメインスローガンは「力と政策」。つまり、連合は政策課題を担い、賃金を中心とする労働条件は「産別自決」とするというものであった。
しかし、実際に「自決」が可能な産別は限られており、春闘における連合の役割が改めて議論の焦点となった。その結果、連合として賃上げ要求の目安を提示する一方、中小労働委員会では、3月中旬以降に中小労組の山場にむけた様々な行動配置や、各地方連合会における地場組合の賃上げ集計などを行い、その後、中小労組を対象とした妥結基準や地域ミニマムを設定するなど、かつてのナショナルセンターもおこなっていなかった活動を展開するに至った。だが、こうした試みも春闘全体に与えるインパクトは限られており、基本的にはそれまでのJC主導のパターンが引き継がれていった。
3 経済・経営システムの転換と春闘
1997年前後の大変動
1990年代半ばになると、産業競争力を失った鉄鋼に代わって、自動車と電機が相場形成役の中心となったが、その後さらに大きな変動が経済と経営を襲った。
それは一言で言えば、金融主導のグローバル経済への転換であった。
我々は、1999年の『連合白書』のなかで、この変動について「長期→短期、人事労務→財務、従業員利益→株主営利」と指摘した。これは景気循環とは異質な地殻変動というべきものであった。
賃金は、人材投資として事後に回収するものではなく、短期的視点に立ったコストと見なされ、非正規雇用への代替が急速に進められた。当時、人事労務の中心だった日経連の「新時代の日本的経営」(1995年)が話題になっていたが、その日経連がほどなく経団連に吸収されてしまうほどの急変だったといえる。
グローバル化した企業にとって、投資、労働力調達、製品販売といった活動は国境という枠を越え、かつてのような国民経済を単位とした「賃上げ→消費拡大→利益拡大→投資拡大」といった好循環が崩れ、その一環を形成していた春闘も転換を余儀なくされることになる。誤解を恐れずに言えば、日経連とは意見も利害も対立するが同じ土俵だったのに対し、経団連とは土俵そのものが異なるのだ。
こうした変化の中で、2002年春闘において「トヨタ・ベアゼロ」という事件が起きる。トヨタのベアゼロは好業績の下でその後も何回か起きるが、トヨタに限らず、多くの企業が膨大な企業貯蓄を抱えながら、株主配当は増大させる一方で賃金はいっこうに上がらない、という歪んだ傾向が続いた。
産別自決・単組自決の下では如何(いかん)ともし難い事態であったが、それにとどまらず、一部の産別からは、連合は春闘から撤退すべきだという趣旨の主張がなされた。連合結成の“初心”に帰った主張である。これに対して、連合の労働条件担当者会議は、三つの「ミニマム運動課題」(賃金カーブ維持、サービス残業撲滅、企業内最賃協定締結)を掲げて、春闘という共闘の継続を図った。
そして、連合が2003年春闘の前段で掲げたのが「引き上げから底上げへ」という方針であった。
これは、「かつてはバケツの把手を持ち上げればバケツ全体が持ち上がったが、今は把手が上がらない、もしくは外れているので、バケツの底を両手で支えて持ち上げるしかない」という趣旨だったが、JC回答に先行する組合の組織に加えて、中心となるのは、すでに始まっていた「中小共闘」の強化と、「パート共闘」の開始であった。この方針は、地場の中小労組や正社員中心の労組にスンナリ受け容れられたわけではなかったが、徐々に広がりを見せていった。また、最低賃金引き上げに向けて、マーケット・バスケット方式によって地域ごとの「リビング・ウェイジ」(生活賃金)の試算をおこなったのもこの時期である。
非正規雇用の社会問題化
経済・経営システムの地殻変動が引き起こしたのは、“ベアゼロ”だけではなかった。
小泉内閣の下で進められた様々な分野での規制緩和、民営化、公共投資削減などは、非正規雇用の拡大、個人事業主の減少、地域経済の疲弊などをもたらし、これまでの社会基盤、すなわち保守基盤に大きな打撃を与えることになった。
こうして政治問題と化した「格差と貧困」の問題は、二つの動き呼び起こすことになった。
一つは、政府側の対応である。
小泉内閣に続いて登場した安倍内閣(第一次)は、軌道修正を余儀なくされ、自民党労働部会の後藤田会長の「連合、民主党に代わって自民党が非正規雇用労働者を代弁する」との掛け声の下、パート労働法と最低賃金法の改正に着手した。
これによって、最低賃金は、従来の春闘メカニズムの一環としての改定から抜け出すことになる。第一には、改正法に生活保護水準が新たに加えられたことから、最賃改定論議も、上げ幅だけでなく水準を問題にするようになった。これは長く続いてきた最賃改定において初めてのことだったといえる。もう一つは、それに連動して、最賃改定は、中小企業の賃金改定調査結果の数字から離れて、独自に決められることになった。そしてその後、最賃改定は相場の波及を待つことなく、それを上回る改定が続いていく。これは、まさしく「政治判断」として遂行されたものだった。
社会運動の広がり
もう一つは新たな社会運動の展開である。
すでに各地の市民グループやNPOがさまざまな活動を展開していたが、2007年には反貧困ネットワークが結成され、課題や地域を超えた運動の連携が強化されていった。
また、労福協も全国各地で独自の支援活動をくり広げていった。
一方、春闘においては、2005年頃から、派遣ユニオンのグッドウィルやフルキャストとの闘い、首都圏青年ユニオンのすき家との闘い、さらにプレカリアートユニオンの自由と生存のメーデーなど、当事者たちによる行動が展開された。
こうして2007年には、連合、そして全労連で非正規労働センターが設置され、労働組合運動も労働者全体を視野に入れた運動に向かうことになる。
4 リーマン・ショックから政権交代へ
「商品化」をめぐるせめぎ合い
2008年秋のリーマン・ショックと派遣切り、そして年末の「年越し派遣村」の取り組みは、この時期の社会状況を象徴するものであった。
それはK・ポラニーの『大転換』が本来ありえないものと指摘していた「貨幣の商品化」「労働の商品化」が引き起こした事態であり、前述の「商品化そのものをめぐるせめぎ合い」(ポラニーのいう商品化に対する「社会の防衛」)の時代に入っていたことを示していた。
つまり、相場→波及としての春闘が低迷していたというよりは、運動が(b)から(a)に転換していたことを意味していたといえる。
連合総研が後におこなったワーキングプアのヒアリング調査のなかで、ある労働者は「使い捨てではなく必要とされる存在になりたい」と語っているが、貧困が経済的貧困にとどまらないこと、仕事が単なる食い扶持ではないことを物語っている。
政権交代と連合の対応
「格差と貧困」の政治問題化と社会運動の広がりは、保守層の自民党離れにもつながり、2009年に歴史的な政権交代が実現した。
ここで一つ問題となるのが、その間の連合の対応である。
連合は2009年末から、1999年以来掲げてきた「力と行動」に代わって「要求型から協議型へ」のスローガンに転じた。これによって、政策実現に向けた取り組みは政府との協議を中心におこなわれ、それまで地方連合会を含めてくり広げてきたさまざまな行動が鳴りを潜めることになる。
これは、支持政党が政権の座にあるあいだの特殊事情のようにも思われたが、2012年の自公政権復帰後もこのスタンスは基本的に変わることはなかった。
2014年、第二次安倍内閣は、デフレからの脱却に向けて賃金引き上げの必要性を唱え、経営側にも働きかけをおこなった。いわゆる「官製春闘」である。
これは目に見える成果に結び着いたわけではないが、この試みはその後も続いた。ある年の『朝日新聞』のインタビュー記事において、労使代表に官製春闘について問うと、経営側は(政府の介入を拒否する意味もあってか)賃金は労使で、という原則を強調したのに対して、神津連合会長(当時)は、「官製春闘ではなく政労使春闘だ」と答えている。
もちろん政労使の三者構成はどんな場合にもありえることだが、問題は、その場の設定が、労働側あるいは労使の主導権によるものなのか、という点だろう。
かくして、春闘報道は、社会面から経済面へ、そして昨今は政治面へと移りつつあるかのようだ。
春闘の再生に向けて
これからの春闘の可能性について、連合本部を離れて久しい老兵がとやかく言うことではないと思うが、連合総研在籍中に気になっていたことがいくつかある。
一つは、「要求型から協議型へ」が連合本部にとどまらず、各単組においても、労使協議と団体交渉の区分けがあいまいになっているのでは、という懸念である。私はストライキ至上主義者ではないが、労使交渉は争議権(スト権)を背景にした団体交渉だという、基本中の基本を再確認すべき状況になっているように思えてならない。
もう一つは、すでに触れたように、春闘は単なる時期合わせではなく、他の労働組合との共闘、相互支援であり、日常とは一線を画した非日常(祭り)だということも、想起されるべきだろう。
ポスト・コロナの人材確保でバケツの把手が上がったとしてもバケツ全体が上がる保証はないとすれば、底上げする手の数をもっともっと増やすしかない。
やはり出発点は改めて強調するまでもなく、当事者たちによる切実な要求と行動である。それがあって初めて底上げの手が増え、社会運動となる。
私自身がかつて挑戦しようとして企画倒れに終わった課題の一つが、ベーシックワーカーを軸とした春闘である。ベーシックワーカーという言葉(今風にいえばエッセンシャルワーカー)は、2000年前後に議論となったベーシックインカムに対置するために用いていたものだが、今やかつての相場形成役に引けをとらない“基幹産業”となっている。この分野における賃金・労働時間の改善、人材の確保、そしてやりがいのある仕事を通じた仲間づくりは、労働問題を超えた日本社会の基盤づくり、地域づくりそのものであり、サービスの利用者や住民と一体となって取り組みえる、取り組むべき課題だろう。つまり、春闘(“非正規春闘”を含めて)と社会運動は、相互に作用するものとして展開されていくはずである。そこで目指されるのは、単なる政権交代や新たな国家の建設ではなく、新たな社会そのものの建設ということになるだろう。
いま我々が直面している春闘の困難さは、そうした運動展開の産みの苦しみなのかもしれない。
▼予約受付中▼
POSSEの編集は、大学生を中心としたボランティアで運営されています。よりよい誌面を製作するため、サポートをお願いします。
