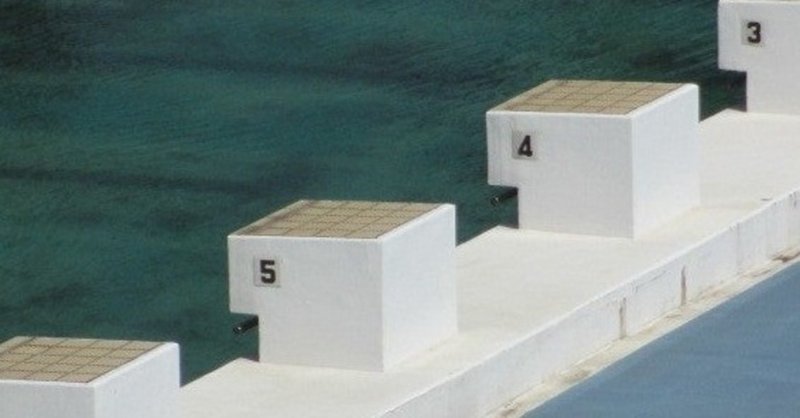
国民皆泳の日
1953年から8月14日に制定されていた国民皆泳の日を引き継いだかたちで、日本水泳連盟が記念日に制定。
ちょっと古い話になるが、平泳ぎ金メダリストの北島康介はクロールの泳ぎ方があまり綺麗ではなかったという。けれどもちゃんと練習すればクロールだって綺麗なフォームで泳げると言い張る。この負けん気の強さが清々しい。世界一を出したときは、北島自身が一番ビックリしていたと語る。体調も悪かったし、全然いいと思ってなかった。だからこそ二度めは、なんで世界新がとれたのかきちんと分析したかったという。
イアン・ソープもフェルブスも練習で世界新の泳ぎなんてしていない。試合当日に自分の力を出し切れるようにコンディションを整える。試合では何が起こるかわからないと寺川綾も語る。だからこそ、本番ではなにか無心になれるものが必要。北島は自分のストロークを数えることで、リズムを作るという。

落語の名人の話を思い出した。志らく師匠が語ってくれたのだが、名人の落語は眠れるくらい心地よい。そういう落語のリズムなり芸の音の形みたいなものがある。その音を聴き分ける耳をまず持たなくちゃいけないという。
たとえ会場が湧いていても、音の形ができていないと真打にはなれない。
新米の落語家は上下に揺れるという、すべてのセリフを力いっぱいやってしまう。下手な役者ほどやたらと表情をつくり、そして身振り手振りが大げさになるのと似ている。名人ほど、たとえば小さんはほとんど動かない。それでいて話は立体的になると。
水泳のフォーム、話のリズム抑揚強弱、どんなものにも筋(すじ)という骨格がある。ときにはそれを崩す名人もいるが、芸になるまでいく人は少ない。肝心要は自分のものにしているかどうかであろう。
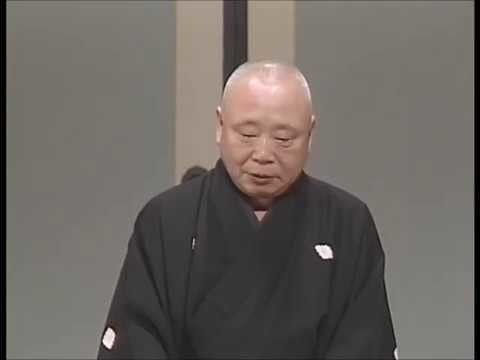
実は文章も同じであろうと思う。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
「冬の時代」という舞台が今年の3月にかかった。感染症の影響で全日程を走り切ることなく中止となったのは残念だ。この舞台は、社会主義活動に身を投じた若者たちの物語である。大河(NHKのドラマ番組)ではまず取り上げられないし、歴史の中でも日陰の立ち位置なのだが、彼らの政治、そして文化にかけた情熱は、明治維新を駆け抜けた志士と匹敵するドラマをもっている。
日本社会主義やアナーキストの中に荒畑寒村という文の名手がいる。彼の筆がなければ、彼らの行動なりドラマが今日に蘇ったか怪しい。
8月14日は荒畑寒村の誕生日(1887)である。
私が荒畑寒村の自伝を読んだのは、受験を控えたときである。受験テクニックからいうと、こんな本を読んでいる場合ではない。後ろめたさも手伝ってスリリングに読んだものである。彼らの自伝の中に日本社会主義の伴走者である幸徳秋水、堺利彦、大杉栄、伊藤野枝、管野スガといった面々が鮮やかに描かれる。実際の交流なのだから、生生しさももちろんあるのだが、寒村自身が歌舞伎や浄瑠璃など日本の文芸に造詣が深く、そういった格調高さをも伴って読ませるのであるから、面白くないわけがない。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
今日も頭出しの記事となる。
この荒畑寒村自伝を再読するのが来年以降の課題だ。
その前に思想的な部分を振り返ってみよう。
まずは無政府主義者とはなんだろう。
無政府主義には
プルードン → バクーニン → クロポトキン
という流れがある。
プルードンは無政府主義者の父とされるが、もっと前からその思想の源流を見る人もいる。老子とかソクラテスまで遡る。
国家のどういう点が気に食わなかったのだろう。プルードンの前にちょっと考えてみる。法律は国家に正当と認められた暴力であると習う。この暴力という”悪”を示す言葉にある種の恣意性がみられる。だから、まぁ、それだけでも国家は悪なのであるといってもよい。しかし法律がなくてどうやって世の中がなりたつのだろう。無政府主義はなにも混沌(カオス)がよいと言っているわけではない。簡単にいえば、戦争は悪である(必要悪も含めて)そして資本主義の矛盾や緊張が激化すると、戦争という手段をとるのが国家だ。これへのアンチテーゼが思想の根っことしてある。畢竟、資本主義は行き詰まると植民地を必要とする。植民地の確保には戦争が必要になってしまう。戦争は、資本主義の緊張状態が直接原因なのだが、根本原因は資本主義を支えている経済的階級がある。資本家と労働者だ。この階級闘争を根こそぎ消滅させればよい。その受け皿というか代わりの生活基盤として、無政府主義は理想郷を求める。
プルードンは、この階級闘争の根本である財産に目をむけた。そもそも財産ってなんだっていう単純な疑問だ。それに対するプルードン自身が出した回答が、”私有財産とは泥棒だ”である。
L’œuvre commence par cette réponse célèbre : « Si j’avais à répondre à la question suivante : Qu’est-ce que l’esclavage ? et que d’un seul mot je répondisse : c’est l’assassinat, ma pensée serait d’abord comprise. Je n’aurais pas besoin d’un long discours pour montrer que le pouvoir d’ôter à l’homme la pensée, la volonté, la personnalité, est un pouvoir de vie et de mort, et que faire un homme esclave, c’est l’assassinat. Pourquoi donc à cette autre demande : Qu’est-ce que la propriété ? ne puis-je répondre de même : c’est le vol, sans avoir la certitude de n’être pas entendu, bien que cette seconde proposition ne soit que la première transformée ? »
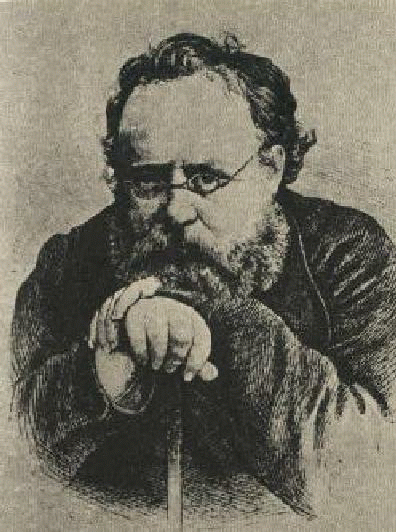
じゃあ財産なしにどうやって食べていくの?ということだが、それを「貧困の哲学」で記した。原理的なことから書いてあるので分厚い・・・笑
ごく簡単にまとめると、資本家のためでなく、国家のためでもなく、自分のために働けばよい。それで貨幣によらない物々交換から始めるのであるが、そもそもが、世界の経済はそこからはじめたのであって、そのままでは同じ矛盾に陥る。その矛盾を取り除きながら、共同体を成り立たせるためにはどんなことが必要か、同じ轍は踏まないように注意しながら理想郷を作らねばならぬ、難題である。いたらないところが多々あるのはいたしかたのないところだと思うのであるが、痛烈な批判を浴びる。マルクスだ。「貧困の哲学」を皮肉るように「哲学の貧困」という本を書く(なんとフランス語で書いた)。だが、その内容は原理の批判というより、(これも約めていえば)”揚げ足取り”のような批判である。原理自体はマルクスも同じであって、プルードンから「いいたいことを先にいわれて地団駄ふんでいる本」と評され、事実この本の売れ行きもさっぱりであった。ただ、マルクスはプルードンが政治闘争を避けていることをどうしても批判しなければならなかった。政治的な闘争は理想郷の実現のためには、絶対に避けることはできないのだと。
このように理想郷への道筋をめぐって、プルードンとマルクスは対立するわけだが、手段は違っても目的というか根は一緒だと言える。”根とは国家は不要である”というものだ。マルクスがこのように言う理由は中学校で習ったとおり、エンゲルスである。「反デューリング論」の中でエンゲルスは次のようにいう。
« L'intervention du pouvoir d'État dans les relations sociales devient superflue dans un domaine après l'autre, et s'assoupit ensuite d'elle-même. Au gouvernement des personnes se substituent l'administration des choses et la direction du processus de production. L'État n'est pas « aboli » ; il dépérit. »
●superflue ... 余計なもの
私訳)
国家の社会への介入は、ことごく不必要になり、次第に薄らいでいくであろう。人間を必要とする政府は、生産プロセスと物資の管理に取って代わるだろう。国家は”廃止”されるのではなく、消滅するのである。
これはあのフリードマンの息子(D・フリードマン)がいうところの”アナルコ・キャピタリズム”とか、リベラルが標榜するスモール政府とかという考え方に非常に近しいものを感じる。また、エンゲルスは次のようにいう。
« Ces classes [sociales] tomberont aussi inévitablement qu’elles ont surgi autrefois. L’État tombe inévitablement avec elles. La société, qui réorganisera la production sur la base d’une association libre et égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de l’État là où sera dorénavant sa place au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. »
私訳)
社会階級はそれが現れたときと同様に必然的に消えゆく。国家もそれとともに消えゆくのである。社会は自由で平等な共同体をベースにして生産物を再構築し、国家のすべての機構を追いやるだろう、どこへ追いやるのか、それは昔の紡ぎ車や、青銅器とともに考古博物館に安置されるだろう。
バクーニンはプルードンともマルクスとも交流があった。バクーニンとマルクスとは、強く対立していく。
第一インターナショナルの第4大会でマルクスはバクーニンを除名する。この頃にはマルクスは思想家として人気が出ておりプルードンにけなされたような存在ではなく、当時の多数派はマルクスを支持していた。除名の原因は「相続税の廃止」をバクーニンが提案したことを危惧したからなのだが、この二人の持つ根本的な思想的違いは、国家観をめぐるものだ。マルクスが自然に消滅するのだから、一旦は国家を利用しようといったのに対し、バクーニンはあくまでも国家は悪であるから無に帰すべきだとした。マルクスが一時的な形としてプロレタリアートによる国家の建設を目指したのに対し、バクーニンはそれでは新たな国家権力を作ってしまうことになると主張し譲らなかったのだ。
バクーニンは相続税の廃止を訴えるわりに、その実、自らは遺産を食いつぶして生き延びて活動を続けていた。このあたり、バクーニンの人間的な面白さもある。
ところで第一インターナショナルはスイスで開催されているのだが、スイスがどうして出てくるのかといえば、時計職人たちが、自らの技術で自立した生活を送っていた背景がある。繰り返すが無政府主義は無政府状態(混沌)を目指しているのでなく、国家に頼らないで生活を築かなくてはならない。その実現のためには、自律・自立が必要なのである。無政府主義者らの求める理想郷の一つの体現をしていた時計職人たち(ジュラ連合)に依拠しようとしたのである。バクーニンはアナルコ・コレクティビズム(集産主義的無政府主義)を標榜したがジュラ連合がモデルとなり、それを推し進めたものだった。でも、そのバクニーンの主義は、どことなく歪なものであった。それはマルクスが唱えた共産主義(コミンテルン)に対抗して用意したものだったからなのかしれない。バクーニンが目指す共同体は個人主義的で理念的でありすぎた。活動はするけど遊ぶときは遊ぶから、そこに共同体は関係ないよね・・・みたいな。これに対し、実際に日常生活でも仕事でも共同体で過ごしたほうがよいのではないかといったのがクロポトキンである。
クロポトキンはダーウインの進化論の誤解した流行が弱肉強食を煽るの批判して、人類が進化してきたのは相互扶助があればこそだと主張し「相互扶助論」を唱えた。その社会的基盤を共同体に置こうとしたのである。
すぐれた思想でも正しく流布するとは限らない。進化論の進化は改良とか進歩を意味していない。ダーウィンの唱えたのは中立的な変化である。
クロポトキンは大衆の進化論の受容は間違えているとした上で、適者生存で取捨選択的に人類が進歩したはずがなく、共同体でみんなが知恵を絞って、創意工夫したからこそ進歩したのだと主張した。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
クロポトキンの「相互扶助論」を日本語に訳したのが、大杉栄である。
幸徳秋水も大杉栄もともにクロポトキンの思想に大きな衝撃を受けた。そのロシア行に荒畑寒村も同行している。当時のロシアがどんな状況だったのか、当時の”生の”幸徳秋水や、大杉栄を荒畑寒村の筆はどう描いているのか
それを再読しながらここに書いてみようと思う。
今日から見て、明治維新がゴールなはずはない。その後の日本は日露戦争をはじめ昭和の第二次世界大戦にいたるまで、さまざまな過ちを繰り返す。さらに、そこには思想的弾圧があった。したがって、明治維新を成し遂げた志士ばかりを大河ドラマで描くのは、いささか片手落ちとしかいいようがない。幸徳秋水は愛国心溢れた思想家であったという見方もある。その秋水に罪を無理やりなすりつけて殺害するにいたったのは非常に残念な歴史だと思う。逆から見ると、当時の日本が、どうして無政府主義を唱えなければならない状況だったのか。国家の持つ負の要素、(冤罪で無理やり人殺しをするんだからこれが負の要素でなくてなんであろう。)その負の要素がどんなふうに当時の人々に影響をあたえていたのか、寒村の自伝を通して考察してみたいと思う。
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
世界水泳や、オリンピックで活躍する選手たちは、
国家がどのような状態だろうと、試合のプレッシャーと戦う。
北島康介がストロークの数を拠り所としたように、自分を信じて。。。
選手の姿は実に凛々しく思う。
そこに国家の負の要素を気にして、日の丸の重みも加わっているように心配したのだが、杞憂なのかもしれない。
GAFAのような国際的巨大企業がタックスヘイブン(税金を免除されている国)に本拠地を置き、国家に税金を収めず、国の扶助を必要とせず躍動的に活動している。そういう意味では国際的というより無国籍的な世界企業だ。そんなアナルコ・キャピタリズムの波はこれからも大きくなっていくだろう。ブロックチェーン技術も小さな政府を実現できそうで、国家権力と、今後どのように対峙していくのか動向に目が離せない状況であるともいえる。しかしナチスが蹂躙した混乱の状態があっても物理学は飛躍的に発展したのだ。研究者達は研究をやめることはしなかった。
激動や変化をただ眺めるでなく、自分はこの変革の中でどのように自律を考え、どんなストロークを数えていけばいいのか、さっさと覚悟を決めて自立していきたいと思う。
------------------------------------------------
<来年の宿題>
・荒畑寒村自伝を再読
------------------------------------------------
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
