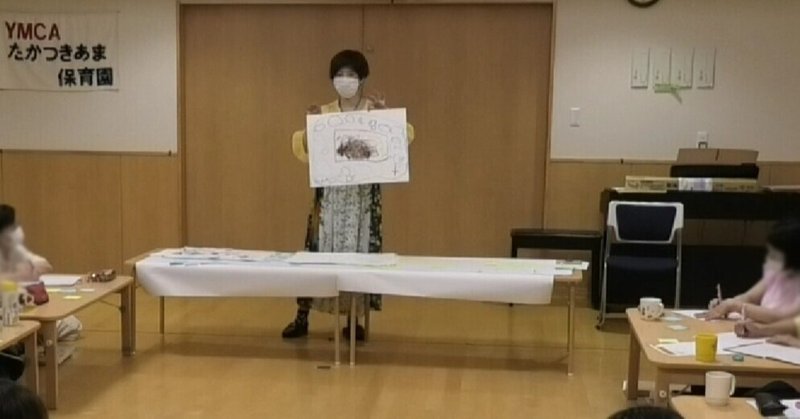
造形活動について園内研修に伺いました
YMCAたかつきあま保育園様に造形活動の研修に伺ってまいりました。
そもそものお悩みは、日々行っている造形活動の中で、どのように提供したらいいのか、子どもの絵の特徴は?というお話でしたので、園で最近描かれた作品などをご用意いただき、座学と交えながら実際の絵を見ながら色々お話をさせていただきました。
お悩みがとても明確でしたので、大好きな松岡先生の書籍から、子どもの絵の発達段階の言葉を引用させていただきながら、ピカソプロジェクトで生まれたカワイイ作品例を参考資料としてご提示しながらお話させていただきました。
2歳児さんは、丸が閉じた子もいれば、線のレパートリーが増えてきた子、力強い線が描けるようになった子、なが~い大きな線を描き続ける子、色々あって、のびのび描けているのが印象的。
もっと教えるべきか、見守るだけで良いのか。とお悩みもありましたが、たくさん経験をさせてあげて、お話をして、その中で何を感じてどう動いたのか、先生の働きかけのどこに反応して、どんな行動をしたのか、きっとそれが絵に表れているのではないですか?とお話すると(実際のお話の中ではもっと具体的でしたが)「すごい!ほんとだ!そうだわ!」と担任の先生同士で盛り上がる
4・5歳児さんは、ちょうど数日前に遠足があって、お芋ほりをしてきたそうです。
「茶色真ん中にぐりぐり~っと書いて、私は泥んこあそびが印象だったんだっと思うし、いいんじゃないか…と思うんですけど、それでいいのでしょうか…」
とっても素敵。そう思ってくれた先生が素敵! 自信もってください。きっとその子は泥が楽しかったのか憎かったのか(笑)は知らないですが、本当に泥が印象的だったのでしょうね~(よく見ると、中に黒い丸…)「もしかすると、泥に入りましたかね(笑)」っと言うと
「なんでわかったんですか(笑)」と。ちゃんと感じたことが絵になっている。素晴らしい保育をされていると感じました。
他にもたくさん素敵なエピソードをお聞きしましたが、どれも、先生の視点や「こうかな?」と思われるポイントは全部素敵でした。
ただ、最初に「何に悩みますか?」と聞いたところ、
一番多かったのが「子どもの絵をどう見て、どう言葉がけすれば良いのかわからない」という系統。
次に多かったのが「自分がセンス、表現力がないから子どもに教える自信がない」という系統。
これは、どこの園でもあるお悩みです。そして、かなりあるお悩みです。
でも、大概の先生は”わかっている”のです。
分かっているけれど、自信がない(だって、その正体を習ってこなかったから)気付いているけれど、言葉にできていない(曖昧なことはなかなか言語化難しいですよね)だけ。なのです。
たったそれだけだから、これだけ子どもを愛して、のびのびと製作させてあげられているんだから、少し知って、少し実感がわけば、誰だって子どもの絵の鑑賞のプロになれる。
今回の研修ではそんなお話をさせていただきました。
実際、園に入った瞬間から、先生が保護者の方とお話をされている時の子どもの様子の伝え方や、子どもが先生に対するときの落ち着いた様子に、きちんと関わっていらっしゃることは充分伝わりました。
この研修を受けて、次に先生方にお会いするとき、どんな風に感じられるんだろう。どんな発見をしていかれるんだろう。
わくわくとした気持ちでお別れしました。
「私の前にいた園でもやってほしいです!!みんな悩んでた!!」と言ってくださる先生もいらっしゃいました。
「画材研究したいです(><)どうしたらいいですか」という嬉しいリクエストもありました!
いつでも、喜んでお伺いしますね。
YMCAたかつきあま保育園の皆様、研修の許可をくださった理事長様、本当にありがとうございました。
今回の絵の見つけ方として参考にさせていただいた内容は、こちらの書籍で分かりやすく紹介されています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
