第11回〈学問とは何かを考える〉-ウェーバー4『職業としての学問』を読む
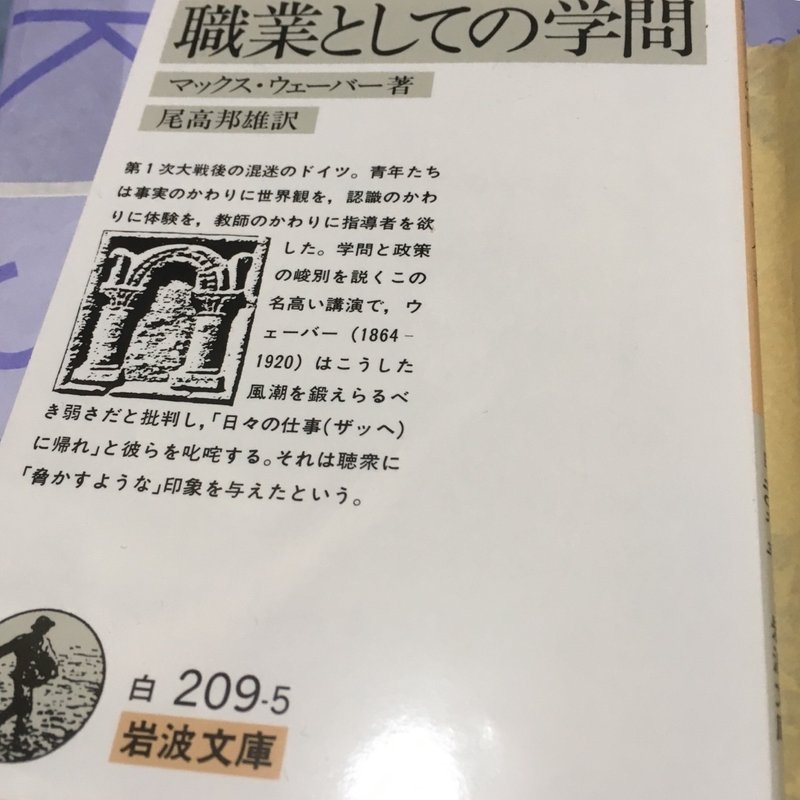
教師とは何か、学問は何に寄与しているのか。
よく、院生にも自分の専門分野の意義や重要性を主張しようとする人がいたけれど、物事はすべて、前提があってはじめて、問題提起として現れる。今回は、このことを考えながらマックス・ウェーバーの『職業としての学問』(尾高邦雄訳.東京:岩波書店.1936年第1版. 2016年第96版)をよみたい。(私はウェーバーに関しては専門外なので読みながら考えました)
本書は、ウェーバーが1919年1月にミュンヘンで行なった講演“Wissenschaft als Beruf”の邦訳である。(Wissenschaft=学問、Beruf=職業、使命)この講演をまとめると、①経済的意味の職業、つまり生計の資を得るための学問の現状について、ドイツの私講師とアメリカの助手の境遇の違いを用いて説明しながら、ドイツのアメリカ化とその一方で教員の就職や昇任には古くからの慣習である僥倖が支配していることを明らかにしている。さらに②職業としての学問(つまり学者)に対して人々がとるべき心構えとして、専門への自己閉塞性と仕事への専心を説き(後述)、③学問と政策の区別を強調して教師は一切の政治的立場ら価値判断から自由でなくてはならないことを主張している。ウェーバーの講演の聴者であった当時の青年たちは、現実の代わりに理想を、事実の代わりに世界観を、認識の代わりに体験を、専門家の代わりに全人を、教師の代わりに指導者を欲していた。こうしたことは、ウェーバーの時代のことだけではなく、他の宗教でも(オウム真理教の信者たちもこうしたことを求めていた人たちだったのではないか)、また我々にも当てはまると思う。ただ、ウェーバー自身は、こうした青年たちに日々の自己の仕事に回帰せよと叱咤している。
さて、講演のはじめにウェーバーは、学問を自分の天職と考える青年は、学者としての資格だけではなく教師としての資格も必要だと述べている。つまり、大学は研究と教授という2つの課題を等しく尊重すべきであると。ただ、この2つの才能を兼ね備えた学者の出現はまさに、僥倖を待つほかなく、その上でウェーバーは、学問を職業とする者の心得として「学問上の仕事を完成したという誇りは、ひとり自己の専門の殻に閉じこもってのみ得られるもの」で、隣接領域に手を出すことには一種の諦めが必要であり、学問に生きるものはひとり自己の専門の殻に閉じこもることで“自分にとって”後々まで残る仕事をした、という深い喜びを得られるのだと述べている。そうした、学問を職業とする者に向いているのは、ある写本のある箇所の正しい解釈を得ることに、何事も忘れて熱中できるような人で、これができない人には学問は向いてないという。ウェーバーの研究者としてのこの考えは、時代の変化とともに学問分野の垣根が曖昧になっている今も変わらぬ心構えだと思う。とはいえ、情熱だけで結果を得ることができないのだが、情熱こそがいわゆる「霊感(serendipityのようなものと解釈)」(これはシュタイナーの考えとも通じてくる)を生み出す地盤であり、この霊感こそが、学者にとって決定的なものであり、学問は実験室で扱う計算問題のようなものではないと述べている。
この霊感は、〈ウェーバー1〉で記載した京都大学の本庶先生のおっしゃる“curiosity”につながってゆくと思う。霊感は机に向かっている時よりむしろ、人が期待していなかった時に突如として現れるいわば運次第のもので、そこには「趣向」、つまり想像力と、この想像力をもってそれをかたちにしていく「創造力」が必要である。(これが私の研究でした)ウェーバーの話は、彼の時代の文脈の中で書かれたものではあるけれど、このように解釈していくと現代の文脈にも当てはめられる。
またウェーバーは講演で、若者は特に「個性」と「体験」こそが重要だと思っており、何かを体験することでそれが自分の個性になると思い込んでいる。そして、それは人とは異なる体験をすることだ、と思っているという。しかし学問の領域において「個性を持っている」というのは、ここまでの話でその仕事につかえ、自分の専門にのみ夢中になれる人のことだ、と解釈できる。ウェーバーの考えでいえば、学問に向いている人は“自分探し”や“自分の価値付け”のため、または富や名声を得るために学問をするのではなく、ただ純粋に、その自己の専門分野に没頭しのめり込める人だ。私は、これが専門家だけでなく、大学院生や学問をする者の姿勢であるべきだと思う。そして、自分の研究は常に進化すべく運命づけられていて、未来の研究によって塗り替えられていく、つまり学問上の「達成」は常に新しい問題提起を意味している。ここで、学問の意義はどこにあるのか、という問題に直面するのだ。学問は○○をよくするために、○○を変えるために、ではなくその学問をすることそれ自体、その学問それ自身のためになされるものだ。
ここまでが一文目に記載した命題の内容だ。
そして、教師という立場にいる者の仕事は①事実の確定と裏付けを示した上で、②その確定した先の文化共同体で人がいかに行動すべきかに答えること、となる。ただし、教室という空間には、街頭演説をする政治家とは違って彼の批判者はおらず、教師が主張し、生徒が聞くという(一種のマンスプレイニング)立場に強いられる。よって、彼の政治的見解や思惑を聴講者に一方的に語るのは無責任だと言える。(一般的に教員が、宗教や政治的見解を述べることを良しとされないのはこれが理由だ)学問の歴史に徴して主観的価値判断を事とする学者がいる場合、必ず真実の真の認識は歪む。(ウェーバー3の話を参照)教員の仕事は、学生たちにいかにして学問をするかを教えることであり、学問をする場合に自分の意見に相反するものを排除せず受容することが大切だと伝えることなのだ。学問が規定しているのは前提と定義付けのみで、どれが良い悪いという評価はなく、また教員の仕事もこの前提と定義付けを学習者に理解させることができたら完了する。青年たちは往々にして先導してくれる人(や答え)を求めがちだが教師が教壇に立つのは教師としてのみであり、先導する指導者ではない。つまり、教師と指導者は別物である、これがウェーバーの見解だ。教壇に立つものは自分が指導者であることは証明できない。指導者を指導者たらしめるのは聴き手の側で、従って聴き手が沈黙を余儀なくされるような場で自分の意見を発表するのはあまりに勝手なことだ。だから、ウェーバーは官僚制的非人格化が必要である、と考えているのかもしれない。
さて、学問は何に寄与しているのか、という問いにたちかえると、教師が学問とはなんぞやかを教える場合、Aという立場を立証するためにBという前提が必要であることに、“気づかせる”指導をしなくてはならない。そして、ある立場(A)を貫徹するためには「そうではない立場」を一貫して退けなければならない。そのためには「そうでない立場」についてすべて理解していなければならない。要約すれば、いかなる学問も絶対的に無前提では成り立たず、またいかなる学問もその前提を否定する事柄(立場)に対して、自己の基本的価値を証拠だてることはできない、絶対的なものではなく、相対的なものである。
ここまでが本書の理解です。マックス・ウェーバーの官僚制は、こうした専門性の原則の観点で、分業という近代官僚制の特徴を捉えると同時に官僚制の限界について検討し、官僚制的組織はイノベーションにおいては無力だと述べています。近年、ティール組織(進化型組織)という考えが受容されてきたのは、急速に変化する社会におけるイノベーションの速さに、ウェーバーの予測通りもはや官僚制組織では限界が見えているからかもしれない。
いずれにせよ、今回はウェーバーの『職業としての学問』、つまり研究者、学者、教師はどうあるべきかを本書を読みながら検討してきたが、「グローバル化」、「資本主義社会、資本主義経済」が新しいフェーズに移行しつつある今、もう一度資本主義経済完成後のウェーバーの時代の話に立ち返って、そこから再考する事も大切だと思う。
【語彙補足】
①ウェーバーの官僚制(近代官僚制)は、家父長制支配に基づく血縁重視の家族型官僚制に対するものである
②Max Weberの本名は、Karl Emil Maximilian Weber(1864.4.21〜1920.6.14)で、社会学者であり経済学者のアルフレッド・ウェーバーの兄。
③ウェーバーの批判をした人で有名なのは、R.K.マートン
④史上最古の成文法であるハンムラビ法典がのちの法制度に与えた点は大きい。ハンムラビ法典そのものは、現代の感覚からすると非常に残酷だが、それまでの為政者の一時の感情で統治していたやり方を否定し、個人の感情を棚上げして明文化された法に従ってすべての人に等しく適用する法の支配の尊重と国の法をつくったことで近代国家の幕開けと考えられている。
ありがとうございます😊サポートしていただいたお金は、勉強のための書籍費、「教育から社会を変える」を実現するための資金に使わせていただきます。
