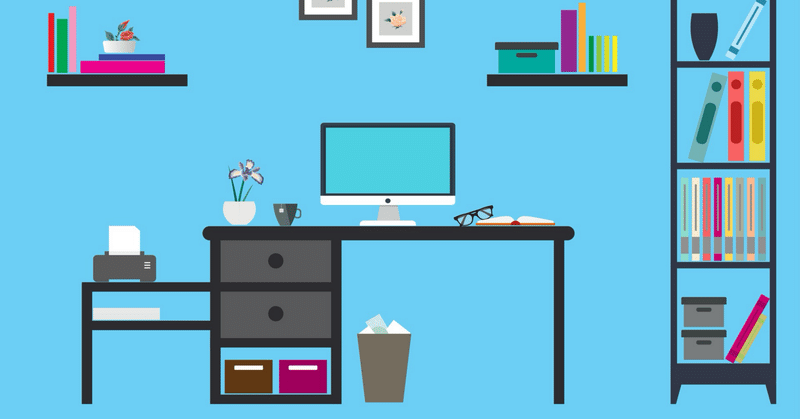
FP1級実技|直前対策ラスパーlog集②(2024年6月受検用)
前回試験向けの直前対策記事(ラスパーlog)の主要部分について、6月度試験向けに加筆・修正した4回シリーズの2回目です。
Image by Mudassar Iqbal via Pixabay
ざっと頭の中で計算して、判断する
実技面接では、次のような質問が出ることがあります。
「X社が甲土地の隣地を相場よりも高い値段で欲しがる理由は何か?」
「甲土地の前面道路の路線価と側道の路線価が大きく異なる理由は何か?」
目のつけどころは「容積率」です。
いずれも道路の幅員の違いで、容積率に差が出ます。(前者では隣地が角地だった場合、建蔽率も上がります)
実技面接のPartⅡでは、容積率の一連の計算(前面道路の幅員が12m未満の場合は指定容積率と前面道路の幅員×法定乗数のいずれか小さいほう、12m以上の場合は指定容積率をその建物の容積率とする)を頭の中でざっと行って、判断を下さなければならない場面が時々あります。
また、居住用財産の買換え特例か、3,000万円特別控除+軽減税率か、どちらが有利かを、ざっくりと試算して、判断しなければならないケースもあります。
「マイ♡ナンバーズ Season2」のQ12~15には、このような問題を並べてあります。
「金庫株」とは?
「金庫株」とは、会社が自社の株式(自己株式)を取得して、それを消却したり譲渡したりせずに、まさに金庫に保管するようにして、自社で保有している状態のものを言います。
会社が、特定の株主から自己株式を買い取る場合は、
株主総会の特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)が必要
譲渡価額のうち当該株式に対応する資本金等の額を超える部分は配当所得とみなされ、総合課税の対象となる(みなし配当課税)
などの点に留意しましょう。
また、自己株式を承継した相続人に対して、会社が売渡請求を行う場合は、
定款にその旨を定める
株主総会の特別決議(出席株主の3分の2以上の賛成)が必要
売渡請求は相続があったことを知った日から1年以内に行う
などの点に留意しましょう。
また、相続開始から3年10か月以内(相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間)に、相続人が自己株式を会社に譲渡した場合は、上記の「みなし配当課税」は適用されず、譲渡益は申告分離課税となります。
またこの場合、「相続税の取得費加算」も併用できる点を押さえておきましょう。
事業承継における「金庫株」の活用シーン
以上の自己株式の取得・保有(金庫株)に係る論点はFP1級学科で時々出題されますが、実技面接では事業承継における「金庫株」の活用シーンによく焦点が当てられます。
自己株式には議決権がありませんから、一部の株式を会社が取得して「金庫株」にした場合、他の株主の「議決権割合」が変化するという効果があります。
例えば、
Aさんが500株(議決権割合50%)、Eさんが300株(30%)、Fさんが200株(20%)を所有している状況で、
Aさん所有の300株、Fさん所有の100株を会社が買い取って金庫株とした場合、
この金庫株400株には議決権がありませんから、残り600株の所有株式数と議決権割合は、Aさん200株(議決権割合33.3%)、Eさん300株(50%)、Fさん100株(16.6%)と変化することになります。
このように事業承継において「金庫株」は、後継者に株式自体を移転しなくても、後継者の「議決権割合を高める」効果があり、実質的に支配権を確立する手段として活用できることになります。
「金庫株の活用」については、「伏線回収シリーズ」Season3の(2)社内承継の問題に登場します。
金庫株の活用のほか、基準となる売買価額の決定(同族株主か、そうでないかで変わってくる)、株式の評価額引き下げ(役員退職金の支給や役員報酬の増額)、買取資金の確保(MBO)などの論点についても、よく確認しておきましょう。
また、事業承継の様々な形については、以下の記事の「弟や甥などへの承継と社内承継」の章で、過去の設例を挙げて解説しています。
株主構成が異なる様々なケースで、どの手法を使うのが適切なのかを整理しておきましょう。
相続人等に対する株式売渡し請求のリスク
上述したように、相続人等に対する株式売渡請求については、定款にその旨を規定し、株主総会の特別決議を経る必要がありますが、注意したいのは、売渡請求される相続人等はその特別決議で議決権の行使ができない点です。
もしオーナー株主に相続が発生した場合は、これに乗じて少数株主に会社を乗っ取られるリスクが生じることがあります。
以下のサイトの「注意点2.相続クーデター」に具体例が示されています。
そもそも相続等による株式の分散を防止する目的で定款に定めた売渡請求権が、逆手に取られた形です。
こうしたリスクを避けるには、売渡請求権を少数株主に相続が発生した都度、定款に記載する方法や、種類株式(黄金株、議決権制限株式、取得条項付株式)を利用する方法などがあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
