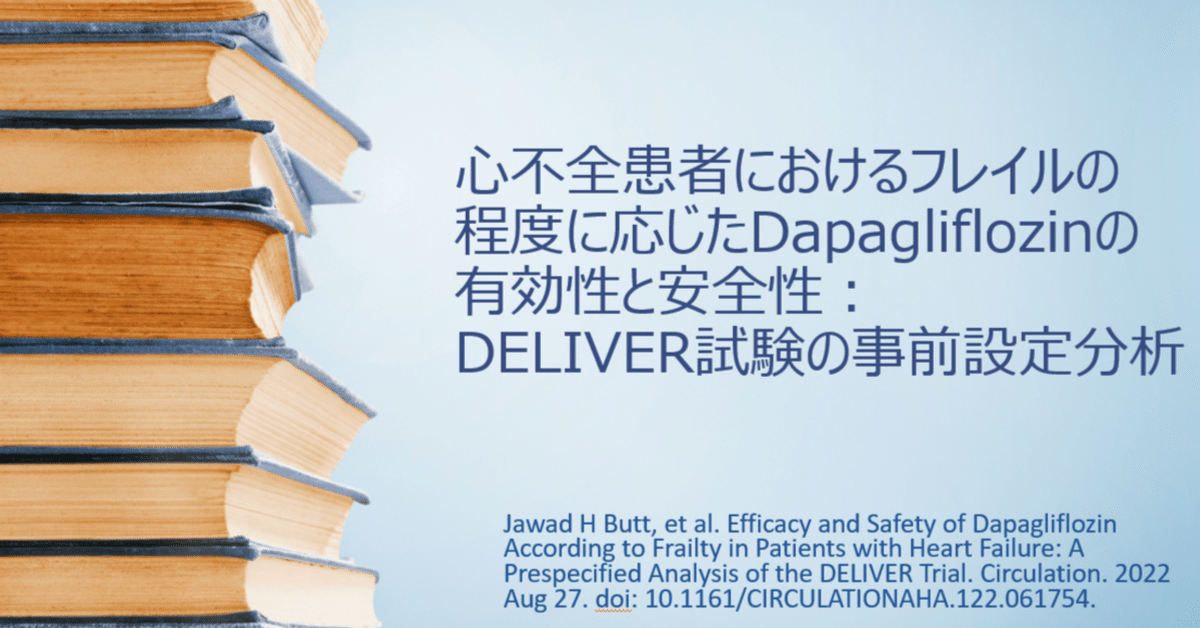
心不全患者におけるフレイルの程度に応じたDapagliflozinの有効性と安全性:DELIVER試験の事前設定分析
はじめに
尿中に排泄されたグルコースは、通常、近位尿細管という部位でナトリウム・グルコース共役輸送体「SGLT」を介してほぼ100%再吸収されます。
近位尿細管での再吸収率は、SGLT2が90%、SGLT1が約10%で、SGLT2阻害薬はSGLT2を阻害することでグルコースの尿細管からの吸収を阻害します。
SGLT2阻害薬の中でもダパグリフロジン(フォシーガ®)は2型糖尿病、1型糖尿病の他にも慢性腎臓病、慢性心不全にも適応が通っており、特に循環器内科での使用が増えている印象です。
ただし、
75歳以上の高齢者、あるいは65歳から74歳で老年症候群(サルコペニア、認知機能低下、ADL低下など)のある場合には慎重に投与する
とあるように、SGLT2阻害薬は廃用症候群のリスクにもなり得るため、高齢痩せ型の患者には慎重投与という位置付けです。
今回の論文は、心不全患者におけるフレイルの程度に応じたDapagliflozinの有効性と安全性を検討した論文です。
目的
フレイル患者は増加しており、このような患者は薬理学的治療のベネフィットが乏しく、リスク面からも新規薬剤による治療が躊躇される場合が多い。
この論文では、フレイルを認めるHFmrEFおよびHFpEF患者の心不全患者において、ダパグリフロジンの有効性および忍容性を検討した。
*HFmrEF=左室駆出率(EF)がわずかな低下(40%≦EF<50%)に留まるもの
*HFpEF=EFの保持された(≧50%)心不全
方法
DELIVER試験:二重盲検無作為化比較試験
対象
・年齢≧40歳
・HFと診断されて6週間以上で利尿剤使用歴あり
・NYHA機能分類II-IV
・LVEF>40%
・左房拡大または左室肥大所見、NT-proBNP≧300pg/mL
<除外基準>
・1型糖尿病
・eGFR<25 mL/min/1.73m2
・収縮期血圧<95 mmHg
Frailty Index(FI):欠損累積モデルのフレイル評価
症状、兆候、疾病、障害、検査値など多面的な項目を30項目以上検討し、検討した項目数に占める該当数の割合を計算し0-1の実数で表したもの。
FIに従って患者を以下の3つのサブグループに分類。
FI ≦0.210(FI クラス 1):not frail
FI 0.211-0.310(FI クラス 2):more frail
FI >0.311(FI クラス 3):most frail
評価項目
心不全の増悪または心血管死亡までの期間
結果
Frailty Indexに基づく転帰
FI クラス 1の患者と比較してFI クラス 3の患者は、すべての主要評価において高いリスクを有した
ダパグリフロジンのFIに基づく臨床転帰への影響
ダパグリフロジンはプラセボと比較して、FIクラス全体において心不全の悪化または心血管死のリスクを減少させた。
ダパグリフロジンによる心不全の悪化・心血管死の抑制はFIクラスの程度に影響を受けなかった。
また、KCCQはよりFIが高い患者において、ダパグリフロジンはプラセボと比較して4カ月および8カ月で大きな増加(改善)を認めた。
*KCCQ(The Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire):心不全患者のQOLを評価する質問票。23項目で、身体的制限、症状(頻度、重症度および経時変化) 、自己効力感、 社会的制限、QOLの5つのドメインから構成される。スコアが高いほど健康状態が良好。

研究の限界
①DELIVER試験の対象・除外基準により最重度のフレイル患者が登録されず、一般的なHFmrEFおよびHFpEFの患者よりもフレイルの程度が軽い患者が対象の試験であったと考えられる。
→今回の結果はすべての心不全患者に一般化できるものではなく、最重度のフレイル患者ではダパグリフロジンによる効果が減弱する可能性がある。
②筋力や機能的能力の評価を含む他のフレイルスコアの測定が行われていなかったため、これらのスコアを検証することはできなかった。
③FIと臨床転帰の関連についての解析が観察的であることから、残存交絡の可能性を完全に排除することはできない。
結論
DELIVER試験において、フレイルは健康状態の悪化および臨床転帰の悪化と関連していた。ダパグリフロジンはフレイルの程度に関係なく臨床イベントの相対リスクを減らすが、健康関連QOLの改善はフレイルの程度が重い患者ほど顕著であった。有害事象は、フレイルの程度にかかわらず、プラセボ群とダパグリフロジン群で差はなかった。
これらの知見は、フレイル患者にSGLT2阻害薬を導入することに対する臨床上の消極的な姿勢を改めるものである。
My Comment
ESC Congress 2022から引っ張ってきた論文でした(ツイッターで紹介されているのをみて自分でも読んでみようと思いました)
フレイルの程度に関係なく、ダパグリフロジンの有効性が報告され、有害事象もプラセボ群と差がなかったことから、むしろSGLT2阻害薬を入れるメリットの方が上回る結果となりました。
ただ、やっぱり廃用以外に関する問題点、例えば尿路感染だったり、ケトアシドーシスのリスクを考えると、フレイル患者では個々でリスクとベネフィットを考えて導入するかを検討しなければならないなと思いました。(DELIVER試験では最重度のフレイル患者は除外されていそうなので)
優先度として高いのは慢性心不全のあるフレイル患者(軽度)なのでしょうか?
よろしければサポートお願いします!いただいたサポートは養育費の足しに使わせていただきます(*´ω`)
