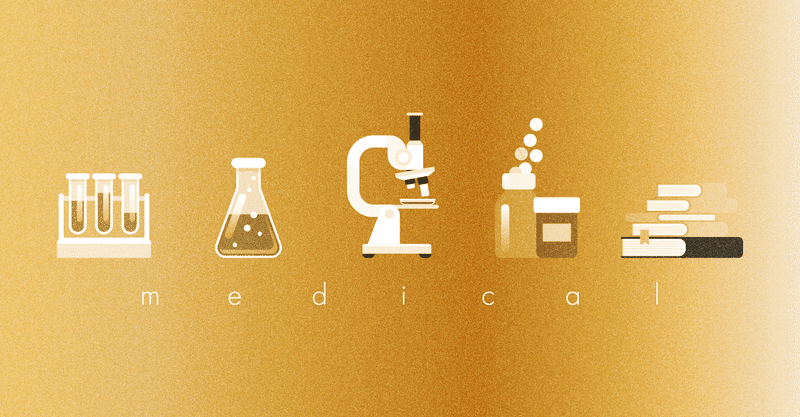
一般集団におけるポリエチレングリコール(PEG)に対する既存のIgGおよびIgM抗体の分析【論文要約/解説/和訳】
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6512330/
Analysis of Pre-existing IgG and IgM Antibodies against Polyethylene Glycol (PEG) in the General Populationより引用
概要:ポリエチレングリコールとは…
その作用について
タンパク質およびナノ粒子治療で日常的に使用される生体適合性ポリマーであるポリエチレングリコール(Polyethylene Glycol =PEG)に特異的に結合する抗体(Antibody=Ab)は、PEGで修飾または含有する治療薬の有効性の低下および/または副作用に関連しています。
最初の一文の時点で意味が分からないくらい難しいのだが…w
まず、この一文がどのようなことを言っているのかの理解からしていこう。
ポリエチレングリコール(PEG)とは
①毒性が低い
②優れた潤滑性を有する。
③異なる分子量のものを任意に混合することができる。
④水や多くの有機溶剤に優れた溶解性を示す。
このような特長から医薬品・医薬品添加物、ヘアケア・スキンケア製品、洗剤、顔料分散剤、潤滑剤、バインダーなど、
さまざまな用途に使用されている。特に医薬品に用いられる場合においては、タンパク質の分解を抑制する効果(“ステルス化”)により、効力を延長したり副作用を軽減することを目的として基剤として使われることが多い。
タンパク質とはこれくらいの大きさの物質であり、これらのタンパク質が紐が解けるように消化酵素で分解されることにより、私達はタンパク質を栄養へと変えていきます。このタンパク質の分解…つまりは酵素の働きを阻害してしまうということです。
生体適合性とは…
「医療器具に用いられ、生体との相互作用を意図された材料」のことを総称して生体材料(biomaterial)と呼びます。生体は体内に異物が混入すると、異物反応(アナフィラキシーもこの一種)と呼ばれる反応を起こし、混入した異物を除去するよう応答します。また、「ある材料を装着あるいは移植した際に、生体に異物として認識され、排除されることなく馴染む性質」のことを生体適合性(biocompatibility)と呼びます。
様々な用途で用いられる、「生体適合性樹脂」「吸水性樹脂」「ガスバリア性樹脂」 | みんなの試作広場 より引用

つまり、生体適合性ポリマーとは…CH²が分子レベルの単一の物質=モノマーだとして、複数の分子が手を繋いで1つの物質となっている状態をポリマーと言う。その状態で生体適合…つまりは身体からの拒絶反応が起きにくいものが生体適合性ポリマーということだ。


ポリエチレングリコールと結合する細胞にある抗体(Antibody)は、PEGで修飾または含有する治療薬の有効性の低下および/または副作用に関連しているというのは…
つまりは、生体適合性ポリマーであっても身体から拒絶反応は出ていて、副作用もあるし、治療薬の基剤にはなるけど有効性の低下にも関連していると思いますよというのが最初の一文で説明されています。
概要:ポリエチレングリコールの
抗体の発生と分量の問題について
最初の薬物投与後に誘導されるほとんどの抗薬物抗体とは異なり、抗PEG Abは、治療歴のない個人(つまり、PEG化薬物による治療を受けたことがないが、他の手段でPEGに曝露された可能性が高い個人)に見られます。残念ながら、既存の抗PEG Abの真の有病率、定量的レベル、およびAbアイソタイプは十分に理解されていないままです。
簡易に説明すると、ポリエチレングリコールに対する抗体というのは、薬物投与した時に発生しているのではなく。その人が日常生活の中でポリエチレングリコールを曝露して抗体を持っている可能性が高く…。
PEGの抗体に関する有病率、その分量や、PEGの抗体の形についての理解は十分にされていないということを言っています。
抗体のアイソタイプとはIgM、IgD、IgG、IgA、IgEと言ったようなもので、この形によっても、その役割は異なるということです。
簡易な実験法の説明
ここでは、厳密に検証されたELISA-競合法と、操作されたキメラ抗PEGモノクローナル抗体標準を使用して、現代および過去のヒトサンプルの両方で、抗PEGIgMおよび抗PEGIgGのさまざまなサブクラス(IgG1-4)のレベルを定量化しました。
ELISA法(Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay)という試験方法があり、この方法では試料溶液中に含まれる目的の抗原あるいは抗体を、特異抗体あるいは抗原で捕捉するとともに、酵素反応を利用して検出・定量する方法です。https://ruo.mbl.co.jp/bio/support/method/elisa.html
簡単に言うと、抗体や抗原を調べてますよ~ということです。
モノクローナル抗体とは…
例えば今回の場合はポリエチレングリコールに対する抗体というのが人間の細胞に存在しています。これに対して、ポリエチレングリコール(抗原)のみを取り除こうと考えた時にポリエチレングリコールに反応する抗体(クローナル)が身体の中にあれば、それが反応してクローナルと抗原が合体することで、細胞の抗体に取り込まれることを防いでくれるわけです。
キメラとは人間の抗体とマウスの抗体を合体させたものであり、完全な人間の抗体では無い為、拒絶反応は考えられるがポリエチレングリコールに対する抗体反応を試すことはできます。
ちょっとここの内容は難しいかもしれません…(´-ω-`)
そして、今回の研究ではその抗体の量として、ポリエチレングリコールに対するIgMおよびIgGのサブクラス(細かい分類)の量まで見ましたよということです。
実験結果
予想外に、90%の信頼度で、現代の検体の約72%(18%IgG、25%IgM、30%IgGとIgMの両方)で検出可能なレベルの抗PEGAbが見つかりました。これらのサンプルの大部分には低レベルの抗PEGAbが含まれており、すべての検体の約7%と約1%がそれぞれ500 ng / mLを超える抗PEGIgGとIgMを持っていました。
抗体の72%でポリエチレングリコールに反応した抗体が見られて、そのアイソタイプの中でIgGとIgMに関しては以下の割合で見られたということです。
①IgG 18% /IgG 30%
②IgM 25%/IgM 30%
全体の1~7%の抗体が抗PEGのIgGとIgMを持っていました。
IgG2は主要な抗PEGIgGサブクラスでした。1970年から1999年の間に収集された血清サンプルの約56%(20%IgG、19%IgM、および16%IgGとIgMの両方)でも抗PEG Abが観察され、PEG特異的抗体の存在が長期にわたる可能性があることを示唆しています。現象。抗PEGIgGレベルは、患者の年齢との相関を示しましたが、性別や人種との相関は示していません。
その抗体の中でもサブクラスとしてIgG-2は主要な抗原だったということです。1970年から1999年の間に収集された血清サンプルでもPEG抗体は観察されており、抗体の存在が長期に渡る可能性がある。
また、年齢との相関があると結論づけています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?







