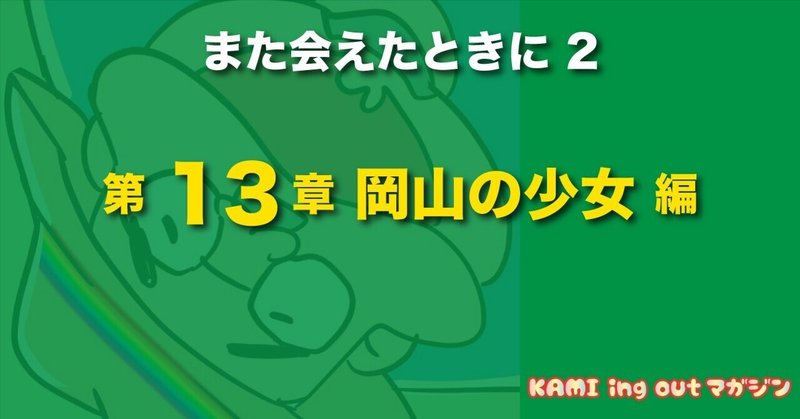
ロードムービー原作 「また会えたときに 2」 第13章 (岡山の少女 編)
僕:「いよいよ今回が実質の最終章ですか。ちょっとドキドキしてきました・・・。」
八幡様:「ここで、物語全体の時系列を説明しておきたいと思います。
今回のロードムービー『また会えたときに 2』が、青年の最初のバイク旅になります。
その後、青年はまた新しい旅に出たのですが、その物語が、古川さんがまとめてくださった『パート1(Youtubeの音声ドラマ)』になります。」
僕:「そうなんです。時系列でいうと、逆なんですよね。」
八幡様:「はい。しかし、この2つは密接に関係しています。」
僕:「密接どころか、僕にとったらもう、ひとつの物語というか。」
八幡様:「よくわかりましたね。」
僕:「は?」
八幡様:「ふたつで、ひとつです。」
僕:「ああっ!!! 僧形の!!!」
八幡様:「時系列的に混乱すると申し訳ないので、最初にご説明をさせていただきました。」
僕:「でもこれ、スターウォーズの映画と同じ感じ、ですね。」
八幡様:「ハリウッド風ということでお許しください。ではアニキ、ここでも音声ドラマの動画を貼っておきましょう。」
僕:「ここで、ですか?」
八幡様:「はい、ふたつでひとつ、です。まだの方は『パート1(Youtubeの音声ドラマ)』もご覧いただきたいと思います。」
僕:「2時間半と長いドラマで恐縮なのですが、ぜひ。」
※広告表示もナシにするよう、運営様にお願いしています
八幡様:「さて、今から書いていくこの13章は、ロードムービー最後のエピソードであり、最初の物語でもあります。
僕:「・・・はい? この章が最後のエピソードなのはわかります。でも、最初の物語でもあるって、どういうことでしょう?
第1章の瀬戸内フェリー編が最初にはなるのですが・・・?」
八幡様:「フェリーの男の子、リョータくんが成長した姿は、14章のエンディングで少し見ることができます。」
僕:「え? 少し、ってことは、あれ? それがラストのメインではなかったのですね?」
八幡様:「はい。アニキはフェリーに始まり、フェリーに終わると思っていましたか?」
僕:「ええ、僕は完璧にそう思ってましたが・・・違うんですね?」
八幡様:「ところで、アニキはまだ思い出しませんか?」
僕:「げ。また、そうやって、いきなり・・・。」
八幡様:「岡山で出会った少女のことです。」
僕:「少女? 岡山で?」
八幡様:「ヒントはお人形です。」
僕:「お人形!? あれ。うーん。ちょっと待ってください・・・。」
八幡様:「覚えていませんか?」
僕:「おぼろげに・・・。なんだか僕、岡山に着いたあたりの記憶がどうも薄いんです。」
八幡様:「あの日は相当な長距離を走り、そのうえ山登りまでしたのですから、さすがに疲れていたのかもしれませんね。」
僕:「そうかもしれません・・・。でもきっと、触りを聞くと、思い出してくると思います。
お手数ですが、きっかけの書き出しをお願いして良いでしょうか?」
八幡様:「わかりました。それでは始めましょう。」
「また会えたときに 2 」 第13章
問いかけ
広島から岡山へと続く、深夜の国道2号線。
日中と比べると、交通量はガクンと減る。
真っ暗な道を、ダックス号のヘッドライトをハイビームにしたまま、ただ走る。
青年はこの長い移動時間を使い、ずっと考えている。
脳が興奮状態で、意識の深部が覚醒しているのだ。
いつもと違う時間帯に漂っている空気感は、精神の浮力を生み出すのかもしれない。
自分は一体何がしたいのか。
こうして旅をすることで、何を求めていたのか。
本来なら、こんなことを真剣に考える必要などないかもしれない。
ただ何も考えずに走っているだけで、じゅうぶんに楽しい。
人に出会って、ドラマが起きるのもたまらないほど面白い。
しかし、それはあくまで一過性のものだ。
全て流れていってしまう出来事に過ぎないことを青年は感じていた。
いま、こうやって暗闇を走る時は、ライトがなければ先へ進むことはできない。
では、僕にとって、そのライトとは、なんだ?
ライトが勝手に明るくしてくれているのか?
違う。
自分が進みたいからこそ、ライトを点けている。
であれば、僕自身が、ライトなんだ。
ただただ、進み続けたくて、走る。
その先に何があるのかを見つけたいから。
つまり、結論を探すために動いている。
では、その結論とはなんだ?
自分は何がしたいんだ?
本当に、学校の先生になりたいのか?
子どもと一緒にいたいから?
待てよ。
子どもと一緒に過ごせる仕事なら、学校の先生じゃなくてもいいんじゃないか?
そこで青年の脳裏に、小野村先生にかけてもらった言葉が響く。
小野村先生:「あなたは小さな学校に収まるかねえ。よほど大きな学校か、何か違う先生になってもええんと違うかなあ?」
そうか。
今、大学で学んでいる人形劇。
それだけで、全国の子どもたちに会いに行けるじゃないか。
旅をしながら、人形劇をすることもできる。
さらに、テレビはどうだ。
映像を使った人形劇で、世界中の子どもたちを喜ばせることができるぞ。
しかしそのためには、最高の技術と、最高のシナリオが必要だし、人形劇のプロフェッショナルにならねば、誰も取り上げようとはしないだろう。
本当のプロになるのは甘くない。
きっと30年はかかるだろう。
自分にできるのか。
できないだろうな。
いやできる。
できるかもしれない。
いや、できないかも・・・。
ふたつの気持ちが交錯して、揺れて、なかなか結論までは行き着かない。
こうやって、誰とも会わずひとりで行動している時は、どこかから、
「考え、動け。それを継続せよ。」
と声が聞こえてくる気がしてくる。
青年は、考えて、悩んで、葛藤もする。
しかし、それをマイナス方向に持っていくのではなく、全て「やる」結論に持っていく。
それができるのは、この旅の中で全て「やる」選択をしてこれたからだ。
行き当たりばっ旅は、ちゃんと行き当たれたのだ。
それも全て「やる」と決めたから。
やってみれば、ちゃんと結果が生まれていく。
そんな経験が、青年の思考の背中を後押しする。
そうか。
これがもしかすると、未来の自分への大きなプレゼントだったのかもしれない。
そのことに気がついた瞬間、この旅で見てきた映像が断片的に流れ始める。
そしてそれが有機的に動き出し、ひとつにまとまり始めた。
赤い2体の仁王像に出迎えられた青年。
仁王様は何か物言いたげなお顔をしていることに気づく。
青年はそれを見て思う。
「このお仁王様が真っ赤な顔をして怒り、夜な夜な悪者たちを退治しに動き出したら面白いなあ。しかも、この大きさで歩き回るから、かなりの迫力になる。
そうだ。いずれ僕も大きな人形を作って、物語を作って、動かしてみたら面白いかもしれない。
性格も、怖い顔はしているんだけど、心は優しくて、赤ちゃんを見るとすぐに抱っこしたくなる。
でも、人は恐れ慄き、敵とみなす人も出てきて、葛藤する。」
そうだ。岡山といえば、桃太郎。鬼ヶ島の伝説がある。
鬼。
鬼。
鬼。
青年は「あっ!」と声が出た。
広島で出会ったのは、鬼瓦。
青年:「だって、このお店の中にいる人たちは、みんな、本当に幸せそうに食べてます。何の邪念もなく、お好み焼きがおいしい、お酒がおいしい、喋るのが楽しい、ここにいるのは嬉しい。
そうやって幸せいっぱいな顔してます。
そうなるには、大将と奥さんの店お客様を大切にする積み重ねがあったことと思うんですが、それよりも何よりも、この瓦の神様に、きっと助けてもらっていると思ってるんだと思うんです。」
大将:「ほう。そんで?」
青年:「来てくれるお客様の嫌なことや、辛いことや、魔に流されないよう、邪(よこしま)な気持ちにならないよう、この鬼瓦がそういうものをきれいに取りとってくれるようにと、祈願してるんじゃないでしょうか。
ただ、おいしいお好み焼きを食べさせたいんだけどではなくて、来てくれるお客様みんなが、幸せになってもらいたい。
そう思って、いつもお祈りしてるんじゃないですか?」
大将と女将は目を丸くして顔を見合わせている。
奥さん:「あんた。鬼さん?」
青年:「鬼? いえいえ、お兄さんです。」
人間にとっての鬼は、怖い存在ではなく、人間を守ってくれる存在なのだ。
怖くて、強くて、情け深くて涙もろくて、人間からの差別に苦しみつつ、それでも弱き人間を守ろうと生きる存在。
その時、朝日が右の海から顔を出した。
青年のビジョンの中で、鬼のキャラクターに後光が差す。
僕は、これをやりたいんだ。
僕は、本気で人形劇がしたいんだ。
そのために、僕が作りたい人形を作る。
それは、鬼だ。
真っ赤な鬼の、大きな人形を作りたい。
だけど、その鬼は怖くない。
青年の見る風景は、太陽の光で一変していく。
まるで魔法の粉をかけられたように、世界が今までとは違って見える。
そこで見えてきたのは不思議な看板。
< ← 鬼ノ城山 >
オニのシロの山か。
看板といえば、あれも鬼だった。
しばらく進むと、手書きの看板が見えた。
「伊予 鬼近→」
と白地に赤字で書きなぐられている。
伊予といえば愛媛のことだが、鬼近・・・? そうか!
当時の流行り言葉で、「めっちゃすごい」の進化系で、「鬼のようにすごい」というものがあった。
青年:「こっちの道を行けば鬼のように近くなる、ってことだな!」
青年はこう理解した。
迷わず四万十川に別れを告げ、支流の川沿いの狭い道へと突入する。
おそらく、その道は本当に近道だったのだろう。しかし、その看板はできれば「鬼道」と書くべきだったのかもしれない。
その抜け道は愛媛に繋がってはいるが、いわゆる旧道。古いトンネルが多く、道路は細く、なかなか大変な山道。一言でいうと、悪路なのだ。
しかし青年はそんなことは知らず、ワクワクしながら鬼道を進んでいく。
青年は、このタイミングで目に飛び込んできた小さな看板に強く惹かれた。
よし!
鬼ノ城山へ行ってみよう。
鬼ノ城
鬼ノ城と書いて、「きのじょう」と読む。
今では整備も進み、発掘もされ、復元もされ、観光地としては有名だが、当時はまだ発掘途中の研究途中だった。
登山道の入り口にある駐車場にバイクを止める。
そこから青年はいつものごとく、なんの情報もないまま、山道をズンズン登って行く。
バイクで走っている途中で、山肌に一瞬見えた、岩の集まっている場所が気になったので、そこへ向かうことにする。
朝の空気と、朝日の木漏れ日が、一枚の絵画のように胸に迫る。
この城に昔、鬼が住んでいたとしたら、何を思ってここにいたのか、と思いを馳せる青年。
ここはただの山ではない。
鬼と名前がついているだけあって、桃太郎伝説に関わりがあるのかもしれない。
いやむしろ、鬼ヶ島のルーツはここかもしれない。
てっきり海の上に浮かんでいるものと思っていたが、雲海の上にある城のイメージが人々に植え付けられていたなら、ここが鬼ヶ島だということもありうる。
伝説に思いを巡らせながら、青年は力強く歩いた。
しかし残念ながら、途中で通行止めだった。
ここから先は進めません。とある。
仕方がない。
目的地には行けなかったが、ここまで来れたことが青年にとっては満足だった。歩いているうちに、考えがさらにまとまっていったからだ。
少し疲れた青年は、木陰に30センチくらいの高さの丸太が並んでいることに気が付く。
3本の列と2本の列。合計5本がぴったりとくっついている。
真上から見ると台形で、ちょうど大人一人分が寝れる大きさだ。
高さも均一なので、青年は丸太の上に迷わず横になる。
梢がゆっくりと揺れている。風が心地いい。蝉の声がだんだん遠くに聞こえてくる。
青年は、丸太の上で眠り込んでしまった。1時間ほどまどろんだであろうか。人の気配がして起きた。
3人の作業員らしき人と、2人の学生さんらしき女性が、手にカメラと大きなファイルと、小さな黒板を持って、青年の横を会釈して通り過ぎていった。
おそらく、発掘のお手伝いをしている方々なのだろう。
青年は、少し睡眠を取れたことによって体が軽くなり、心はますます弾んできた。
人形だ。早く人形を作りたい。
帰ってからゆっくり作るより、今頭に浮かんでいるものを、熱いまま、その場で作ってみたい。
後回しにすると、結局はやらなくなってしまう自分の性格を把握している青年は、最寄りの手芸用品店を探すことにした。
山を下りる道すがらも、青年のイメージはとめどなく溢れて止まらない。
鬼は、おそらく日本人ではなかったのだ。
もしかすると宇宙人だったのかもしれない。それとも大陸から渡ってきた野心をもつ有力者だったか。
いずれにしても異端の人として、やむを得ず人里離れて暮らさなければならなかった。
そして、結果、人に滅ぼされた。
その理由は、「みんなと同じではなかった」から。
滅ぼした桃太郎側も、きっと悩んだはずだ。
鬼たちをうまく活用することができれば、縁を切らなくてもよかったのにと、後々、未来の繁栄を自ら途絶えさせたことに気づく。
当時の庶民はこう思っていた。
高い知能はいらない。背の高さも必要ない。権力に反発するなんてもってのほか。力なんてものはいらない。
そんな時代だ。
とにかく、長いものに巻かれながら平和に生活できればよかった人々にとっては、鬼は恐ろしい存在だったのだ。
そんな近寄り難かった鬼に対して、子どもだけは違った。
素直な気持ちで、損得勘定なしで、その能力を尊敬し、褒めた。
その知恵を称えた。その行動を認めた。
鬼の発する真摯な言葉を受け止めた。
そんな文化も、ここ岡山には残っているはずだ。
青年は、ここにきてようやく、旅の目標が決まりつつある。
さまざまな出会いの中でいただいた情熱を、自らの中に蓄えること。
そのパッションを、人形劇という表現方法を使って放出させること。
そして、愛をもって、子どもたちの心の成長を見守っていくこと。
それを自分が最高に楽しめる仕事として継続すること。
間違いない。
それがこの世で、僕が一番ワクワクすることなんだ!
山を早足で下りながら、青年はとうとう自分なりの答えを導き出していた。
木漏れ日のトンネルも抜けて、日差しも強くなってきた。
ダックス号が待つ駐車場につく。
自動販売機でスポーツドリンクを買って一気飲みをすると、さあ出発だ。
しかし、この近くに手芸店は果たしてあるだろうか。
とにかく、目の前にある道を真っ直ぐ進んでみよう。
僕はいつだって、真っ直ぐに行くのだ。
手芸のナカノ
倉敷の近く、信号待ちで日傘をさしているマダムに青年は尋ねた。
青年:「すみません。お嬢さん。お嬢さん!」
マダム:(キョロキョロして)「わ、私のこと?」
青年:「すみません。ついついお声をかけてしまいました、お嬢さん。」
マダム:(照れて)「なにか?」
青年:「この近くに手芸洋品店とか、生地屋さんってありませんか?」
マダム:「手芸のナカノ? でいいかしら?」
青年:「やったー!(信号が変わる)あ、あ、どっちでしょう!」
バルルル、と動き始めたバイク。
マダムは道を指さして叫んだ。
マダム:「こっちを真っ直ぐ! たこ焼き屋さんのお隣よっ!」
青年:「お嬢さん、ありがとう〜っ!」
青年は走りながら礼を言った。
1キロほど走って見つけることができた手芸店。
店構えは意外と大きく、駐車場にも車が多い。
お昼前の時間帯なのに、すごい人気だ。
期待いっぱいで店の玄関に立つ青年。
心が激しく燃えている青年は、自分のイメージする人形に使う布をすでに決めている。
しかし、その布が果たしてここにあるだろうか。
店内に入っていくと、当然ながら女性ばかりだ。青年のような伸び放題の無精ヒゲと中途半端な長さの髪の男は1人もいない。
青年は、広い店内に繰り広げられた、さまざまな布の束をみるだけで、ますます情熱の炎がゆらめく。
青年:「ふんっむ! さあー、あるかなあー! あってくれ〜!」
と、もみ手をしながら、気合たっぷりにサーチを開始する。
そのとき、店内左奥の一角から女性たちの大きな笑い声が起こった。
青年が目を凝らすと、そこでは女性たちが皆お揃いのスモックを着て、ミシンを扱う先生らしき人を取り囲んでいる。
どうやらミシン教室らしい。
なるほど、このお店の雰囲気がいいのは、あの教室があるおかげだ。
店内はどこも清潔で、入口右手の広場に手作りぬいぐるみコーナーもあって、そこは椅子と、小さな机と、絵本の棚が置いてある。
子どもを一時的に遊ばせておけて、予約すれば預けられるようになっているのだ。
素晴らしい。そして珍しい。これはお客様に喜ばれるはずだ。
主婦の気持ちをよくわかっているお店で、好感しかない。
ああ、わかった。あの教室の先生が、この手芸店のオーナーなんだな。
青年はひとり感心しながら、一通り手芸用品を見て周り、お目当ての布を3つ見つけた。
それらを机に並べて比べてみようと思い、近道に見えた糸コーナーを抜けてるつもりで通路に入った瞬間、ひとりの少女と鉢合わせになった。
少女:「あっ!」
と、その子は驚いて、手に持っていたミシン糸を床に転がしてしまった。
落とした糸をすぐに拾った青年は、それを返しがてら、少女に言う。
青年:「驚かせてごめん! でも、すごいね。ミシンかけれるの?」
ノースリーブの水色ワンピを着た少女は、7〜8歳くらいに見える。
青年を見上げ、首を横に振る。
それに合わせて、さらっさらの長い艶髪が美しく揺れる。
青年:「さすがにミシンは難しいか〜。」
少女は、少し背伸びをして、棚の向こうのミシン教室の先生をちらっと見る。きっと、あそこにお母さんがいるのだろう。
青年:「なにかを縫いたいの? スカートかなんか?」
少女はやはり首を振るだけ。
青年:「お母さんが教室に来てるの?」
少女はまだ首を振る。
あ、違うのね?
じゃあ、自分のために糸を探していた?
でも、ミシンを使わないなら、手縫いの糸を探していたのかな?
だったら、この場所じゃなく、もう一つ奥の列だ。
ひょっとして少女は糸を探すも、たくさんあって迷っていて、先生も忙しそうだし、自分で探すしかない。そう思っていたのかな。
それでこの棚に来て、この糸でいいのかどうかを確認していたら、なんだか暑苦しいヒゲをはやし、目の周りだけが青くなっている青年が来て、びっくりして落としてしまった。
青年は、もしそうだとしたら、申し訳ないことをしたと思い、しゃがんで訊いた。
青年:「もしかしてだけど、自分で手で縫ってみたいん? こうやって。」
少女:「うん。」
ようやく声が聞けた。青年は続けた。
青年:「すごいやん! 針と糸で手縫いって、難しいのに〜! やってみたいって、すごいわー! 初めてやんな?」
少女はモジモジして体を振り出した。照れて目は合わせない。少し頷く。
青年:「針はあるん?」
少女:「あるけど、おかあちゃんのやけ、使いとうない。」
どういうことだろう。
お母さんの針は、使いたくない。あまり仲が良くないのかな?
あ、お母さんには内緒で作りたいものがあるのか。
でも、何かを縫いたいのだ。
縫うというよりも、何かを作りたいのか。
縫って作れるものと言えば、ハンカチとか?
ティッシュケース?
それか、もしかして僕と同じく、お人形か?
青年は、この少女が何を作ろうとしているのかを聞き出したかった。
それによって、使う布と、糸の種類と、針の種類と、縫い方が変わるからだ。
それにはまず、自分のことから話さなくてはいけないと思った。
シンクロニシティ
青年:「僕なあ、大阪から来てんけど。」
少女:「大阪?」
青年:「うん。まずな、大阪から岡山まで来たんや。
で、そっからなぜか四国の香川に行ってな。
で、徳島に行って、高知に行って、愛媛から九州に渡って、鹿児島まで行って。
そこから奄美大島に渡ってな。
で、また九州帰ってきてな。
熊本、長崎で、福岡、山口、広島やろ。
そんで今日、やっと岡山に戻ってきてん。」
少女は、目をくるくるさせて、
少女:「ぐるっと?」
青年:「そう。ぐるっと。岡山から出て、岡山にまで帰ってきてん。」
少女:(少し興味を持った顔で)「なにしに行っとったん?」
青年:「それがなあ、さっきやわ! 僕、なにしに行っとったんかわかってん。」
少女:「さっき?」
少女は、この変なおじさんは日本をぐるっと回りながら、さっき目的に気が付いたって、どれだけのんびりしてるんだろうと不思議がっているのであろう。
だから口元は微笑んでいるが、目は笑っていない。
青年:「うん、さっき分かったんや。ここ、岡山といえば、桃太郎やろ。だからなあ、鬼の人形を作ろうと思って。」
少女:「鬼? あはっ! なんで桃太郎やないん?」
少女は素の顔で笑いながら、言った。
少女:「あー、でもな、うちもさっき、ちっさい人形作ろう思うとったんやで。うちがすぐそこやけぇ、だからここに来たんじゃあ。」
青年と少女は、嬉しそうに目を見合わせて、「さっき人形を作ろうと思った」というシンクロに驚き、急速な魂のつながりを感じた。
お互いに、どんな人形を作りたいのか、なぜそれを作りたくなったのか、そしてそれを何に使いたいのか。
2人は、ミシン糸の陳列棚の前でしばらく語り合った。
よく聞くと、少女は、糸の種類も、針の種類も、縫い方の基本も知らない。
玉結びや、玉どめすらも知らないことが分かった。
青年:「よしわかった。じゃあ、一緒にやってみる? 練習用の布を一枚買ってみよう。100円だし。」
少女はワッと喜び、小さな口を目一杯開いて笑った。
ほっぺたの右側に、小さなエクボができている。
少女:「じゃあ、よろしくお願いします。先生。」
青年:「先生! じゃないよ〜。僕は縫い方の基本だけ教えるから、しっかりマスターしましょう。お名前は?」
少女:「みなみ。古川みなみ」
2人は、ミシン教室の横の広いスペースに移動した。ここなら机と椅子がたくさんある。
青年:「みなみちゃん。僕は鈴木です。では、まず玉結びね。針の穴に糸を通すところから。。。えっと、こうして・・・・。」
みなみ:「はい! できました!」
青年:「はや!! ちょっと待ってねえ。。。よしっと! はい入った。みなみちゃん、上手だね!」
みなみちゃんは聡明で、よく笑い、よく喋り、飲み込みも早く、手先も器用だった。あっという間に青年よりも上手くなってしまうほど、針さばきも完璧だった。
みなみちゃんがなぜ、人形を作りたかったのか。
その背景はちょっと複雑だった。
2年前、両親が離婚し、父親は家を出て行った。
母親はもうすぐ再婚しそうで、今お付き合いしている、いずれ自分の父親になる人もいて、それはとてもいい人で、少女のこともとても可愛がってくれている。
すでにお父さんと呼んでいる。
でも、自分はきっと、どこまでいっても、その人の娘にはなれないと感じている。
今まで、一緒に暮らしていなかったし、思い出話もあまりつながらないし。
でも、もしかしたら、私から何かをプレゼントすることで、距離が縮まって、親子じゃないけど、仲良くなれそうな気がしたのだと、話してくれた。
しかし、あまりそれを自分で納得している訳でもなかったのが気になった。
みなみ:「ただの思いつきじゃけ。」
そう言って、人形作りを今にもストップしてしまう空気感を何度も出していた。
それと、お母さんは仕事がとても忙しく、少女のことを振り返ってみてくれる時間もなく、お母さん自身もその忙しさに疲れ果て、毎日何かに怒っている、ともこぼした。
少女は、それを愚痴っぽくは言わない。
ただ、お母さんが辛い思いをしていることが辛いのだ。
それで今日、思いついたらしい。
自分が可愛い人形を作れば、きっとお父さんとお母さん、2人ともが笑顔になる。
2人が笑顔になれば、私も幸せな気持ちになるはずだと。
そして、それを毎日持ち歩いてくれれば、自分のことを忘れないでいてくれるし、ひとりで頑張らなければならない時に、その人形が支えになってくれるのではないかと、幼心に考えていたのだ。
プレゼント
隣の教室スペースからパラパラと拍手が聞こえた。
ミシン教室が終わったようだ。生徒さんたちがお疲れさんと挨拶を始めた。
青年の縫い方レッスンは、まだ続く。
少女は真剣な面持ちで、針と糸と格闘中だ。
すでに縫い合わせと、まつり縫いと、かがり縫いの基本を伝授していて、おそらくこれらをマスターしておけば簡単な人形はできるようになるはず。
あとは、布の種類と、どんな人形を作りたいかでまた変わってくる。
集中している2人に突然、声がかかった。
ミシンの先生:「みぃちゃん! どうもね〜!」
みなみ:「あ、先生! こんにちは。」
ミシンの先生:「はい、こんにちは。あ、こちらさんもこんにちは〜。」
青年:「あ、どうも。こんにちは! お教室、大盛況でしたね!」
ミシンの先生:「お陰さまじゃ〜。みなさん、熱心に通ってくださるけぇここもやっていけとるんよ。
(向き直って)みぃちゃん、今日はお母さんと一緒じゃねえんじゃなぁ。」
少女は嬉しそう笑って、
みなみ:「ふふふ〜ん。今日はの、お母さんじゃのうて新しい兄さん先生に教えてもろうとるけぇ、だいじょぶじゃ〜!」
ミシンの先生:「ほ〜! このお兄さんが先生ね。そりゃあ良かったね〜! これ、ハギレやけどよかったら使うて〜。」
そう言って、先生は大量のハギレ、と言っても十分人形作りに使える量の布を提供してくれた。
そしてうちは後片付けするから〜、とその場を離れながら、
ミシンの先生:「そこ、今日ずっと使うてええけぇなぁ〜。」
と言ってくれたので、存分に2人で人形を作る練習ができた。
青年:「いつ渡すの? お人形。」
みなみ:「お母さんの誕生日かな。」
青年:「それっていつ?」
みなみ:「8月16日。」
青年:「そっか! もうすぐやね!」
みなみ:「でも来年やけえ。」
青年:「え? 来年? どうして来年? 今年でもまだ間に合うよ?」
みなみ:「間に合わん。」
青年は、少女の意志の強い唇を見ながら、みなみちゃんにはちゃんと考えがあると気づく。
ひょっとして、急いで作ってもいいものができないとか、どんなに頑張っても縫うのはやっぱり難しいと思っているとか?
青年:「でもさっきは、何かをプレゼントすることで、距離が縮まって仲良くなれそうな気がするって言ってたけど、気が変わった?」
みなみ:「うん。兄さん先生とお話しょったら、だんだん気持ちが変わってきた。
うち、今度こそ、お母さんにゃあ幸せになってもらいてえの。
次のお父さんが、お母さんのことをちゃーんと見てくれる人かどうかが、まだわからんけぇ、まだやられん。
ちゃんとお母さんと結婚して、お母さんを幸せにしてくれたら、その時作ってお礼として渡すんじゃ。
うん。そうする。もう決めた!」
青年:「そっか。お父さんになる人には、お母さんを幸せにするってわかったら作る。ってことはわかったけど、お母さんの誕生日がもうすぐなんやから、お母さんに最初に渡しても、それはそれで喜ぶんちゃう?」
少女は大人びた顔で、しばらく考える。
そして首を振りながら言った。
みなみ:「今のお母さんにあげても、きっと喜ばない。」
青年:「どうして?」
少女は、黙ってしまった。
なるほど。青年は少し踏み込みすぎたことを反省し、話題を変えた。
青年:「僕の話を聞いてもらってもいい?」
みなみ:「いいよ。」
そう言って、とみちゃんの話をした。
プレゼントしたくて、手紙まで書いて送ろうとしていたけど、心が引っかかって渡せず、そのプレゼントも渡せず、結局十何年経ってから、やっと初めてプレゼントを渡すことになったという経緯を丁寧に伝えた。
もうひとつ。
熊本のせっちゃんが、思いつきで赤ちゃん用の抱っこ布を諫早の奥様にプレゼントした時の話。
この話の共通点は、相手のことを大切に思う気持ちをたっぷり持っている人が渡すプレゼントの中には「すごく素敵な何か」が入り込むってことだ。
つまり、プレゼントは物ではなく、心そのものなんだと、青年は力説した。
特に、今から作る人形には、命が宿る。
その命は、これからお父さんとお母さんにもし、命が削られるほど苦しいことが起きたとしても、それがある限り、大丈夫。
だから今作っておくといいよ。と続けた。
しかしそれでも少女は首を縦に振らなかったのだ。
みなみ:「うん。今は喜ばんかもしれんけど、心を込めりゃあ、伝わるってことじゃなぁ?」
青年:「そう。みなみちゃんの心が人形に入るからね。」
なぜ、お母さんに人形を渡しても今は喜ばないと言ったのか、青年はわかった。
少女は孤独なのだ。
お母さんは今、自分ではなく、お父さんになる人に夢中で、しかも仕事が忙しい。
少女は元夫の子どもであることには間違いないから、どこかにわだかまりが残ってしまっている可能性もある。
それに少女は、人形をプレゼントをしたとしても、今の母親の気持ちを自分に向かせることは難しい、と思い込んでしまっている。
お手紙作戦
青年:「よし。じゃあね、お手紙、書いてみいひん?」
青年は唐突に言った。
みなみ:「おてがみ?」
青年:「そう。お父さんになる人に、もうお父さんって書いちゃう。プレゼントも、お手紙も、渡すのは来年でええから、お手紙を書いておくねん。
そうすれば、これから1年間、絶対に喜んでもらえることがわかってるプレゼントを、誰よりもみなみちゃん自身がワクワクしながら持っておくことができる。」
この提案における青年の意図は、人形を無理して作って、今渡して、ああやっぱり、とガッカリすることがないようにさせることがひとつ。
次に、今の自分の思いを明確にさせ、その気持ちを持続させるために文字(お手紙)に起こしておくこと。
それだけで、自分の心を確定させることができ、母親と新しいお父さん、2人の存在を親と認識することができる。
そして、手渡す時期を、少女の言う通りに1年後に設定する。
そうすれば、その間、相手を思う気持ちと、喜んでもらえる期待感を持ち続けることができて、孤独感も和らぐはずだ。
人形を作る前に、なぜこの人に心を込めた人形をプレゼントしたいのか、を明らかにすることが、制作のモチベーションにもなると考えた。
青年:「どう? お手紙、書いてみる?」
みなみ:「書く。」
すぐ横で後片付けをしていた教室の先生も話を聞いていたようで、
先生:「あらあ、お手紙はええ思うよ〜。お母さんも喜ぶわあ。これ、紙と鉛筆。使うて〜!」
と協力してくれた。
みなみちゃんは、これは下書きじゃから字が汚い、と言い訳しながら、書いた。
筆が進むたびに、真剣な表情になっていく。
お父さんへ
お父さん、お母さんのことを大好きでいてくれてありがとう。
お母さんも、お父さんのことが大好き。
二人が、おたがいのことを大切にしてることがよーくわかるから、わたしも二人をだいじにしなきゃと思います。
お父さんはわたしとは血がつながってないけど、ほんとうのむすめのようにしゃべってくれるね。
それがとってもうれしくて、ドキドキします。
わたしのいいところをたくさん見つけてくれるし、わたしがしっぱいしたことをぜったいにおこらず、なぜしっぱいしたかをせつめいしてくれるし、くやしくて泣いてる時は、ずっとあたまをなぜなぜしてくれるし、おもしろいこと言った時は大笑いしてくれる。
ほんとうにありがとう。
わたし、お父さんに会えてほんとうによかったよ!
もし、お父さんとお母さんがつらいとき、くるしいときがあったら、こんどはわたしがずっとそばにいて、二人をだきしめて、なぜなぜしてあげるからね。
あんしんしてね。
お父さん、わたしのかわいいお母さんを、守ってあげてね。やくそくだからね。
お父さんへの手紙を書き終えると、少女はふーーーっっと大きく息を吐き、満足そうな顔をした。
そして「次はお母さんじゃ」と言って新しい紙を出した。
おかあさんへ
お母さん。おたんじょう日、おめでとう!
わたしのだいすきなお母さん。
いつも、夜おそくまでおきて、お父さんのおしごとのおてつだいをして、朝早くおきて、朝ごはんを作ってくれるお母さん。
おしごとが大変なのに、わたしが学校からかえってくるといつも元気なこえで「おかえりっ」て言ってくれるお母さん。
わたしがけがをすると、もうスピードでしょちしてくれて、ギュッとだきしめてくれて、早くなおりますようにっておいのりしてくれるお母さん。
お母さんが、私のお母さんでいてくれて、わたしは世界いちしあわせ。
ありがとうお母さん。
生まれてきてくれて、ありがとう。
わたしをうんでくれてありがとう。
わたしをそだててくれてありがとう。
ずっとずうっと、だいすきだよ!
集中して書いて、書いて、書きながら、みなみちゃんはその目から大粒の涙がボトボトと落ちていった。
青年も何も喋らず、ただ書き終わるのを待った。
全て書き終わった少女の目は、美しく澄んでいた。
なぜ、自分が人形を作りたいかが、はっきりと見えたようだ。
なんとなく、喜んでくれるだろう。とか、振り向いてほしい。とか、私がどんなに寂しいかをアピールするためとかではなく、自分の本心からのありがとうの気持ちさえ出てくれば、なんのために作るかの目標が見えてくるのだ。
本当の教育
青年は気付いた。
小野村先生! これなんですね。
小野村先生:「本当の教育と言うものは、頭の中をこねくり回して、考えさせて、答えを出させることではないってことじゃ。
子どもの心を熱くさせて、目標を決めさせるだけで良い。うん。それが本当の教育。
強く厳しく教え込むことでは全くない。
しかし、勉強を覚えさせるために一から百までを教え込むことが、今の時代は『良い先生』と言われるようになっている。
そのようにはなってはならん、ということじゃ。」
少女は手紙を書いたことで、自分の存在が見えた。
そして未来も見えた。
このお人形を作ることで、両親はもっと仲良くなれるし、みなみちゃんは2人の子どもとして生涯認められることになる。
青年は、もうこれで大丈夫だと思って言った。
青年:「もし、人形を作ったら、どうやって2人に渡す?」
みなみ:「うっふふ。いい作戦思いついた。ふっふっふ。」
なんだか悪戯じみた笑顔だ。
青年:「どんな作戦?」
みなみ:「親といえば! 兄さん、子育て中、一番嫌なことって何か知っとる?」
青年:「一番嫌なこと? なんやろ。病気になるか、怪我をするかやろか。」
みなみ;「ちゃうわ。学校からの呼・び・出・し。」
青年:「わー、確かに!!」
みなみ:「先生に手伝ってもろうて、呼び出してもらうの。2人できんせーって。」
青年:「いやいや、そりゃあ無茶でしょう! 2人とも忙しいんやから。」
みなみ:「忙しいのに、娘のために時間を作って学校にいくのが、親じゃ!うち、絶対実行するけぇな。」
少女は、よほど寂しかったのだ。
冗談っぽい目で言ってはいるが、半分本気なのだろう。
しかし、これは面白い作戦かもしれない。
親の本気を試すことにもなる。
学校にドキドキで呼ばれ、先生からまさかのお人形プレゼントを渡され、「みなみさん、頑張ってますよ〜!」の一言をいただければ、親としては嬉しくなって娘を抱きしめたくなるだろう。
青年は、成功を祈ると約束し、少女は胸を張って、
みなみ:「大丈夫。成功間違いなしじゃけ。」
そう言って花咲くように笑った可愛い顔が、青年を癒やした。
気がつけば、もう夕方だ。
鬼の人形を作ろうと思って入った手芸店だったが、結局それには手を付けられず、少女の思いに目一杯の力を注ぎ込んでしまった。
しかし、少女の笑顔で、青年はすべてがOKになる。
思い通りに行かなくても、信じる道が2つに分かれていて、間違った道を選んだとしても、ゴールはひとつなんだと確信した。
だから、どの道を進んでも良い。
僕はただただ自分らしく、感謝とともに、生きていけば良いんだ。
行き着く先は、ひとつなんだから。
青年の脳裏に、それまでに旅で出会った人々の笑顔が、溢れるように浮かんでは消えていく。
さあ、帰ろう。大阪に。
青年は、少女と握手をした。
またあえた時に、一緒に人形劇をしよう。
そう約束して。
おわりに
八幡様:「そうです。みなみちゃんは、さちこさんの亡くなった娘さんです。」
僕:「はい・・・。ちょっと衝撃的過ぎて・・・。今回もまた長い時間執筆を中断させてしまい、申し訳ありませんでした。」
八幡様:「アニキの『涙のあがり待ち』にはもう慣れましたよ。」
僕:「僕は・・・会っていたんですね。みなみちゃんが亡くなるちょうど1年前に。」
八幡様:「少女とのやり取りは覚えていましたか?」
僕:「はい。鮮明に思い出しました。
みなみちゃんは、今日紹介した会話よりももっと大人びていて、もっともっと可愛くて賢い女の子でした。
別れ際、僕にウサギのイラストを描いてくれて、それを貰いました。」
八幡様:「みなみちゃんが作ったフェルトのマスコット人形は、完成までに何度も失敗して、学校の先生にも手伝ってもらいながら完成し、1年後の誕生日の前に、先生から古川さん夫妻に渡されています。
その物語が『また会えたときに』のパート1に描かれています。」
僕:「八幡様が最初に言っていたことがようやく理解できました。たしかに今回のエピソードは、”最初の物語”なんですね。」
八幡様:「劇的で不思議なお話は、パート1に集まりました。人間的で、本気で教育に携わろうとする青年の葛藤と気づきはパート2です。」
僕:「はい、僕自身、気づきに満ち満ちています。感謝しかありません。」
八幡様:「しかし、アニキも最後までよく書き抜きましたね。
あとは、エンディング映像のイメージを、映像編集者に向けてわかりやすく書いていく作業です。」
僕:「いいですね。いつか出会えるかもしれない映像編集者さん、よろしくお願いします。」
八幡様:「これは楽しみながら、リラックスして描くことが大切です。」
僕:「はい。おかげさまで、もうすでに楽しんでいます。
次回はまた旅で出会えたみなさんにお会いできるのでしょうか。
いちおう、ハンカチの準備をしておきます。」
それでは皆様、次回がエンディングです。
長い間お付き合いいただき、本当にありがとうございました。
明日も元気いっぱい、お愛しましょう♡
ここから先は

KAMI ing out マガジン
「僕のアニキは神様とお話ができます」「サイン」の著者、アニキ(くまちゃん)が執筆。天性のおりられ体質を活用し、神様からのメッセージを届けま…
ご支援ありがとうございます。このnoteはサポートのお志で成り立っております。メッセージにお名前(ご本名とご住所)も入れていただけると、感謝とサチアレ念をダイレクトに飛ばさせていただきます。
